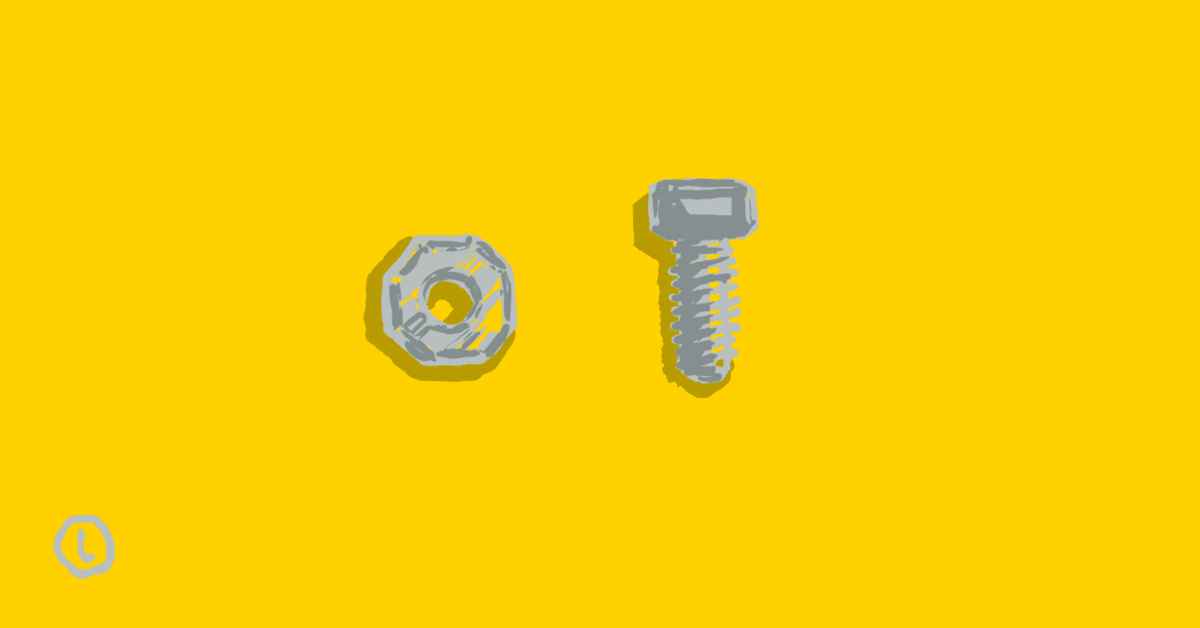
東京に出てきて十年近く経とうとしていた頃、田舎から
東京に出てきて十年近く経とうとしていた頃、田舎から一通の電報が届いた。その時、丁度私は金属部品の研磨をしかける所だった。金の卵として田舎を出た後、私は金属加工の工場で働いていた。十年間、毎日ねじを作りながら、ねじのように働くのは大変素晴らしかった。私は、ねじになりたかった。円柱の金属部品に螺旋状の溝をつける作業をしながら、いつも私はねじと一緒に溶けて同化していくような心地いい気分になった。ねじに、なりたかった。私はねじになりたかった。何も考えず、何も苦しまず、何も辛くない。赤い地獄で生きる事は私には困難で、逃げた。私は、己の運命から、環境から逃げた、のだろうか。逃げる事も運命だったのであればそれはそれで救いだろうか、はたまた苦しみだろうか。わからない。人によっては、こんな風に社会のねじになって働くなんてとんでもない、御免被ると拒む人もいるかもしれない。が、私には至極幸福な環境であった。何も決めなくていい、言われた事だけ、与えられた仕事だけを毎日淡々とこなしていればいいのだ。私はもう考える事ができなかった。考える事を放棄していた。あの日、赤い花が根こそぎ駆逐される光景を見たおぞましい日から。おぞましい記憶として残る、あの日から。ドンチンドンチン、ドドンドドン。かすかに太鼓の音が聞こえたような気がした。
——電報。
息を切らして走ってきた社長の手には「ユキオ キトク スグ カエレ」と書かれた電報が握られていた。
「大変じゃあ、正ちゃん、はよ荷造りせえ」
社長はまん丸な目を赤くして、今にも泣き出しそうな声で言った。事務所から急いで駆けつけたらしく、足元は室内履きの黄色いスリッパのままだった。それは、薄暗く埃っぽい作業場には不釣り合いなほどの、鮮やかな色をしていた。
十六になる弟に一体何があったのだろうか。私が田舎を出てから十年間、弟は事あるごとに何通も手紙を送ってくれた。最初は習いたての文字が拙い可愛らしい手紙だった。が、やがて角ばった四角い字になり、跳ね上げる角度や払いの力の引き方が父親のそれとそっくりになっていった。ああ、やはり二人は血の繋がった親子なんだなと、自分も渦中の人間でありながら他人事のように思った事を覚えている。弟の手紙には一通も返事を出していない。
手紙にはいつも、村での様子が記されていた。学校は楽しい事、新聞配達はほとんど自分がやるようになった事、村の人々は相変わらず優しい事、姉の和子とはたまに喧嘩をする事。そして、村に咲いていた綺麗な赤い花は、全て根こそぎ刈られてしまった事。私はその手紙を読んで、鼻腔の奥をかすかな花の香りが漂ってくるのを感じた。甘く芳醇な香りの中に、どこか爽やかな青臭さが混じったような、あの赤い花独特の香りであった。だがそれは、弟からの手紙によって私の古い海馬が刺激され、蘇っただけの幻だった。かつて赤い花が咲き誇っていた村。満開に咲いた花弁は朝露に濡れ、太陽の光を浴びてキラキラと輝いていた。その光景を一緒に見た少女の名は、何といっただろう。赤く染められた着物を纏い、小さな唇に赤い紅を差していたあの子。
数ヶ月前の春に届いたばかりの手紙には、弟も集団就職で東京に出てきたと書かれていた。印刷所で働き始めた事、ジャズを聴くようになった事、休みの日には多摩川を散歩する事、景子というガールフレンドができた事。その手紙は、いつもより格別に長めだった。上京してからの生活は、彼にとって刺激溢れるものだったのだろう。あんなに小さかった弟が、上京して就職をするような歳になったのかといささか驚いたが、弟が私の元を訪ねて来る事はなかった。
——電報。
電報を受け取った私は社長に急かされ、工場を早引きし、急行列車に乗った。ねじを作っている途中だったのに、と少しだけ後ろ髪を引かれながら。新宿駅から出ている急行に乗れば、夜には田舎に着くだろう。電車の時刻を調べてくれた社長が、軽トラのハンドルを回しながら教えてくれた。
「しっかりな!正ちゃん」
最寄り駅まで送ってくれた社長が、駅舎に入っていく私の背中へ声をかけた。その声は、なんとか私を鼓舞しようと努めて明るく発しようとしたが、それを悟られまいと緊張して結局は裏返った声となって届いた。
正吉は、神妙そうな顔つきの社長に向かって軽く頭を下げた。西から差し込む太陽の光が、彼の影を、長く、濃く伸ばしていた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
