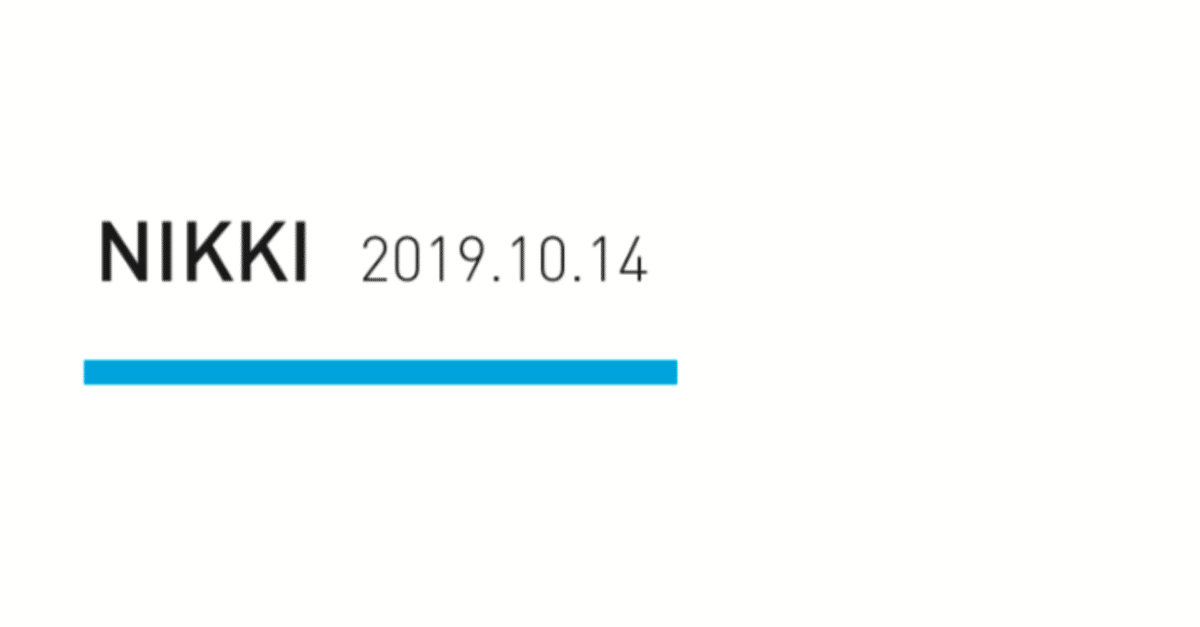
嘘で悪を描くこととその甘美さについて
人を殺したいと思ったことがある、そして人を殺したいと思ったことがない人なんていないだろうと思っている、「私は人を殺したいと思ったことがない」と嘘をつく人のことを信用できないと思っている。
現実とフィクションの違いについて都合よく解釈している、全ては現実、と、レトリックの魔法を使ってみたりして、時々それをフィクションの力を信じるみたいな言い方を頭の中でしてみたりして、「自分」と「フィクションを含んだ現実」との距離を測ってみたりする。フィクションがなければ生きていなかっただろうと本気で思うし、フィクションによって今の自分があると本気で思う。
あなたもそうだろう。
でもフィクションが、いつからか自分から生まれてくるよつになった時、そしてそれが人の生き死にを扱うようなものであるとして、それをどう捉えるのかということを自分は先送りにしている、人は当たり前に死ぬ、当たり前に突然死ぬかもしれない自分がいる、当たり前に突然死ぬかもしれない自分にとって大切な人たちがいる、どうでもいい人たちもいる、誰にでも当たり前にそういうことが起き得るという可能性を、僕は都合よく取り出すことがある。
スパイダーマンが瓦礫になったワールドトレードセンターを見下ろすページを見て、衝撃を受けた、そんなことやっていいんだと思った、現実でもフィクションでもそこに生き死にがあって、それを自由に行き来することが出来てしまうということ、それ自体に自分がそれまで捉えていた現実が揺らぐことを感じた。アメリカンコミックの世界の捉え方が、僕の世界の捉え方を変えてしまった。スーパーパワーも異次元も全てカリカチュア、カリカチュアである以上その皮を剥いていった先には現実という実がある、その薄皮を剥ぎながら、そこにある皮という物語の意味を、現実という実のことを考えた。
たくさんのコミックが実写になった。それは喜ばしいことだった、ただただ無邪気に喜んでいた、僕がその皮を剥ぎながら読み解いた物語が、生身の人間の声や身振りで目の前に現れた。ミュータント同士の不毛な戦いよ。ヒロイズムを寸分履き違えたビジランテよ。結局戦いでしか戦いを止めることの出来ない愛国の戦士よ。
ヒーローと呼ばれる人たちを胸の奥に生かしている、自分だけではない、色々な人が、手から糸を出すことが出来ない役者が小児病棟を訪れる、手から糸を出すことがヒーローをヒーローたらしめているのではないとその行為が教えている、ヒーローというのは動詞だと、この間死んでしまったヒーローが言っていた。本当に言っていた。
やっぱりそういう、結局最後は自分を励ましてくれるような、あからさまな嘘を、自分は求めていたのかもしれなかった。
よく出来た物語の中で、その人はよく出来た、よく出来すぎた悲惨な目に遭って、遭い続けて、それを理由にして他人を悲惨な目に遭わせているうちに、後戻りが出来なくなった。
かく言う僕も、彼がもう戻れない、戻らないということをあらかじめ知っていながらそれを観ていて、わくわくはしていないまでも、どんな目に彼が遭うのか、どんな風に悲惨なパズルが嵌っていくのか、それを観に来ていて、そういう人々が三連休中日のレイトショーにはたくさんいた。
そこには何も超常現象は起きなくて、スーパーパワーを持つ人間も現れなくて、ただただ現実として、誰かの嘲りや暴力や嘘が彼を覆い尽くすだけだった。そして彼は真っ当な、とても真っ当なただの人間としてそれを受け止めることで、狂気と呼ばれているようなものをその身に宿した。
映画が始まって間もない段階で、彼が「狂っているのは俺か?現実の方か?」というようなことを言っていた。まだ映画の中では、それほど悲惨なことは起きていないように思える場面で、そういう台詞が挿入されていた。
コミックの中や、前作までの映画の中で、理由を与えられていなかった狂気に、きちんと理由をつけていくことにどれくらい意味があるのだろう、と思いながら、映画館に向かう自転車を漕いでいた。家々から狂った叫び声が聞こえてきていて、何事なのかと思っていたら、ラグビーの試合が行われていたのだということに、通りがかった飲み屋のライブビューイングを見かけて気づいた。一秒もラグビーを観ていないと言ったら、非国民と僕を指して言った人がいた。
狂気に理由なんてなかった。狂気に至る悲惨さだけがそこにあるだけだった。混沌を求める理由も何も描かれていなかった。火の中で彼が立ち上がるシーン、奥には群衆がいて、手前には僕らがいた。
フィクションが現実に追いついてしまっている、と僕は思った。いつも通り薄皮を一枚剥いたら、もうそこに現実があったという感じがした。
ああいうのに影響される人がいたらヤバいよね、と映画館を後にする人の群れの中で誰かが言った。あなたは、二時間、大きなスクリーンと大きな音の中であれを観て、一ミリも自分があれに影響されていないと言えるのか、映画館のシートに座る前と後で何一つ変わらなかったと言えるのかと聞きたかった。
彼は嘘つきのキャラクターだった。前作でも何度か自分自身が狂気に至ることになった理由を説明するシーンがあったが、いずれもその場限りの物語で、それぞれ合わせると結局矛盾した、出鱈目だった。
今回の映画も、すべては彼が話す出鱈目なのだ、と捉えられるような演出があった。
でもそれが出鱈目、嘘だろうと、だから何だというのだろう。僕たちはこれまでも、こんなに嘘を本気にしてきたじゃないか。
その嘘を、身に宿したままで、無邪気に現実を生きるのだなと思った。薄皮をゆっくりと剥きながら、その実の小ささ、空虚さに気づいた時にはもう遅いのに。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
