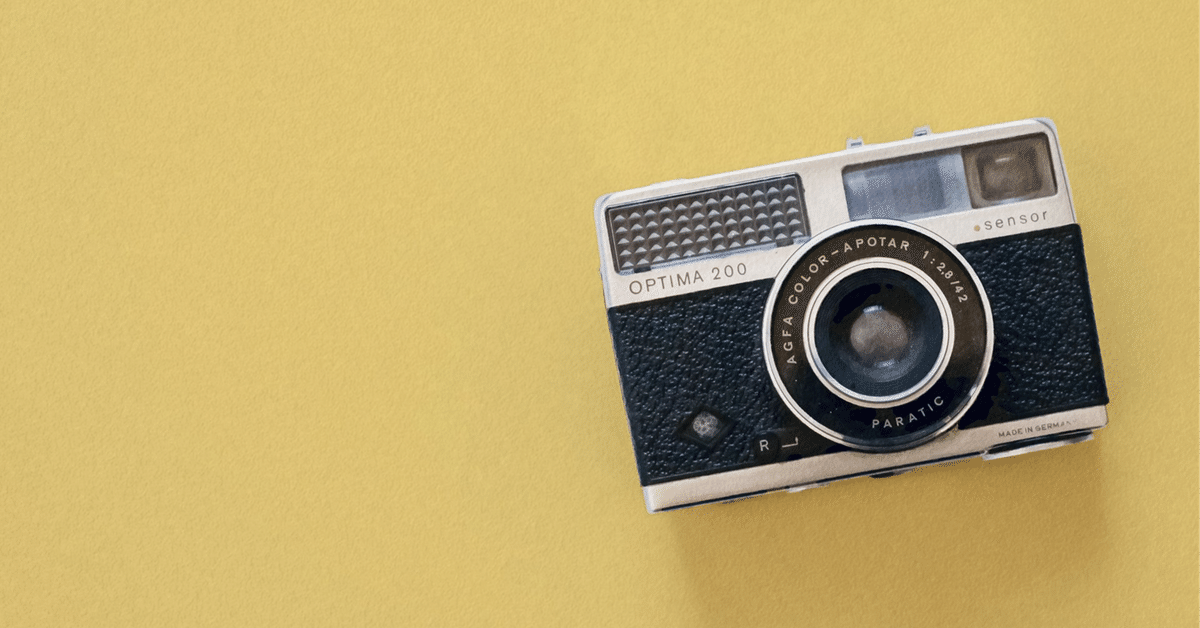
母がいた-36
先日、はじめて取材というものをうけた。僕がこうして書いている「母がいた」を読んで、朝日新聞の若松さんという記者の方がnoteの広報担当さんを経由して取材の申し込みをしてくれたのだ。ありがたい話だ。
若松さんの取材はとてもとても丁寧で、わざわざ東京から福岡まで来てくださった上に僕が話しやすいよう合間に雑談を交えてくれたりもした。最初はがちがちだった僕も、若松さんの温和な態度で次第に緊張が和らいでいって、たくさんの話を引き出してもらえた。
そうして完成した記事が公開されたので、よければ読んでみてほしい。とても素敵な文章になっていて、やはりプロの方というのはすごいんだな、とぼんやりした感想と共に尊敬の念が沸き上がってくる。
取材という言葉で思い出した話があるので、今日はそれを書こうと思う。
実は母はテレビに出演したことがある。僕が小学校低学年のころ、地元の自治体の活動として取り仕切っていた人権劇に関する取材をうけたのだ。台本や演出を誰が手掛けていたのかはよく覚えていないけれど、代表としてテレビ局の取材対応をしたのは母だった。
取材の内容はシンプルで、この劇を通して何を伝えたいですか、とか、息子さんも出演なさってますね、とかだった。そう、実は僕もその劇に出演して一言二言のセリフをもらっていた。子ども数人で「そうだ、あそぼうあそぼう」とかそんなセリフだったような気がする。
僕の話は置いておいて、母はリポーターさんからの質問にテキパキ答えていた。気合の入ったメイクと少し派手な服を着て、きりっとした表情で。なぜ鮮明にその描写が出来るのかというと、実はこのインタビューに答えている母の映像が手元にあるからだったりする。貴重な生前の肉声というやつだ。
僕や父は、母の話で盛り上がった時に必ずこの動画を再生する。声の記憶というのはかなり曖昧なようで、聞くたびに「ああそうそう、こんな声だったね」と思い出している。そういう点では、この動画を残しておいて本当に良かったと思う。動画がなければ僕の中の母の声はもっとぼんやりしたものになっていただろうなと感じる。
ただ、実は動画を再生するたびに少しだけ思うところがある。実際に生活の中で聞いていた母の声はもっと砕けていたような気がするのだ。おちゃらけた、おちゃめな話し方をする人だった。もちろん残っている動画は取材向けの話し方だから普段通りというわけにはいかない。だから、もっと日頃から動画や音声を残しておけばよかったな、と思っているのだ。
我が家にはビデオカメラがなかったので、ホームビデオというものが一切ない。残っている動画といえば、ガラケーが普及して動画が撮れるようになってからのごくわずかなものだけだ。そして当時はSDカードの容量なんてたかがしれていたので、わざわざ家で家族の動画を撮影して残しておこうとは思わなかった。
そういった事情から、僕ら家族の映像というものは貴重なものになっている。もっと撮っておけばよかった。こんなに恋しくなるなら、恥ずかしがらずにもっと残しておけばよかったといつも思う。
突然自分の話をするが、僕はずっと写真を撮られるのが苦手だった。自分の容姿があまり好きではなかったし、写真を撮って何に使うんだ、と思っていたのもある。けれど、カメラマンの友人が出来て、写真撮影のイベントに携わるようになって少し考え方が変わった。
人間いつ死んでしまうか分からない。それには当然僕自身も含まれていて、僕が今突然死んでしまったら、残された父や姉は何を見て僕を思い出すんだろうか。数少ない写真や動画を頼りに母を思い出す、今の僕のような経験をさせることになるんじゃないか。
そう思ってから、自分からすすんで写真を残すようになった。今は自分が写っている写真をクラウド上にまとめたものを、ある程度整理して父に伝えておこうとも思っている。
考えたくはないけれど、万が一父や姉よりも先に僕がこの世を去ってしまったときには、芸能人ばりに取れ高のあるクラウドファイルからできるだけ素敵に撮れた写真を遺影にしてほしい。死後まで可愛くありたいと思っているあたり母のしたたかさを受け継いでいる気がして笑えてくる。
もちろん自分の写真や動画だけでなく、父や姉の写真もよく撮るようになった。僕からというより、なんとなく家族全員、残しておいた方が良いと思っているようだった。
父とでかけたら写真を撮り、姉とは頻繁に近況報告も兼ねて動画などを送りあっている。こうしてどこかに残るのだ。何かがあっても、いつでも思い起こせるように。
取材の話から自分の死後の話に飛んでしまったような気がするけれど、どちらも「残しておきたい」という話に帰結しているのでまあいいか。
僕はこうして母がいたという痕跡を残していて、僕ら家族はそれぞれがいたという痕跡を残そうとしている。思い出せなくなっても、思い出すきっかけになるように。
そういえば取材を受けながら同じようなことを考えていた。これで誰もが忘れてしまってもどこかに僕がいた痕跡が残るのだと。母も取材をうけているとき、そんなことを考えていたのかもしれないと思うと、ちょっと母に近づけたようでうれしい。
これからもいろいろなものを残していこう。記事でも、写真でも、動画でも。そしていつか1冊の本にしたい。本になれば、国立国会図書館に納本されると聞いた。みんなが忘れても、どこかに残るなら、それは誇らしいことだと思った。
メディア映えを意識して
ちょっと着飾ったりしながら
僕らに思い出を残してくれた
そんな、母がいた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
