
123 ジャズ、アドリブ、即興性と遊び
1月22日はジャズの日
1月22日がジャズの日とは知らなかった。JAZZと綴るとき、JAは1月の英語表記Januaryの略としてのJAと同じ。そして22日は、ZZにも見える(人もいる)ということで、けっこう無理やりだけど。
なんとかの日というのは毎日のようになにかしらあって、だいたいは、そのときにXなどで即応する人が多いだろうし、私も「ふーん、そうか」と思う側である。嫌いじゃない。
だけど、たとえばこのJAZZの日でっせ、と言われたところで、それは私の中にあるJAZZ要素がダムの決壊のようにアウトプットし過ぎてしまうために、落ち着くまではどうにもならないですよ、となることもある。
私にとってのジャズは、ビバップ、モダン、フュージョンの3本柱がメインになっている。しかも、その周辺も含めると、ジャンルではとてもくくれない世界となっている。クラシックもポップスもロックもファンクも関わってくる。
そういえば、以前、誰かのXでジャズの特徴である即興(アドリブ、インプロビゼーション)について「パターンなので退屈」といった意見を見かけた気がする。確かに、ある種のパターンを延々と繰り返しているケースは多いし、音楽は曲名をつけた段階でひとつの完結した要素となることを求められるから、その範囲からの逸脱はやりすぎだと思われてしまう可能性もあるので、通常はちゃんとパターンを作って繰り返したりもする。
「おお、すげえ、そっちへ行くのか」と驚くようなことは、そうそうあるわけではない。むしろ「さっきは、○○の延長線上で、いまは△△のオマージュだ」といった「元ネタ」探しもできてしまう。
サンプリングが音楽の要素として認められて以来、こうした元ネタをいじる音楽は飛躍的に増えていて、それは「温故知新」であるとか「再発見」とかなんでもいいけれど、とにかく新鮮に聞えたり、楽しく聞えたら、それでいいわけだ。
突き詰めたら、どの音楽も、パターンなので退屈だと言えなくもない。それが「曲」として構成されたものだから当然である。
テクニックと情熱
私の解釈としては、こうだ。
ダンス音楽としてのジャズが大流行した結果、「踊れる曲」がもてはやされるようになるのだが、演奏している側は徐々に「また、この曲か」と退屈してくる。それに、同じ曲ばかりでは、自分の秘かに自慢できる演奏テクニックを披露できない可能性がある。
ビバップは典型だと思うけれど、定番の曲からコード進行だけ抜き取って、ぜんぜん別の曲にして、しかもそこに超絶技巧であるとかハイノートであるとか、楽器の限界まで追求するような演奏を加えていくことで、演奏家としての情熱をアピールしようとする。
そして「自由だ!」と感じている間は楽しいのだが、ビバップもしだいにパターンが見え見えになってくる。すると飽きてくる。
次に来るのは、これだ、あれだ、とミュージシャンはいろいろなことを考えて実験していく。むしろ譜面通りのアンサンブルでより面白くしよう、とか、楽器そのものを新しくしよう(シンセサイザーやサンプリングもそうだ)とか、これまでインストゥルメンタル中心だったけどボーカルを入れようとか、いわば「聞き所」を別の方向へシフトしていく。
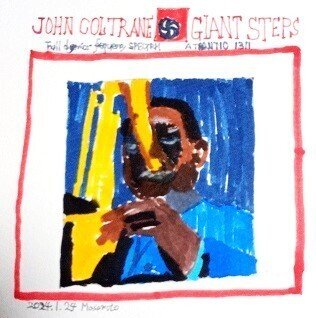
飽きたら別の遊び
だけど、それもやり続けていくと、きっと飽きてくる。そしてまた原点に戻る場合もあれば、これまで手をつけていなかった音楽のジャンルへの挑戦もあるだろう。手っ取り早いのは、ポップスでもよくある「コラボ」だ。意外な組み合わせによるケミストリーを試す。ジャズならバンドのメンバーを変える。ほかのバンドと一緒にやる。ジャンル違いの人たちと組む。あるいはソロでやる。
もうひとつの手っ取り早い方法は「カバー」だ。自分のオリジナルではなく、いわばスタンダードであるとか敬愛するミュージシャンの曲をカバーする。
だいたい、この2つをやって気分転換することが多いのではないか。
一方、ジャズは、ライブ演奏をメインとするケースが多いから、ある意味で「再現性」も求められる。「即興をするなら、演奏するたびに違う」というのは建て前で、実際、細かく見ていけばもちろん演奏するたびに違ってくるけれど、大枠ではレコーディングされた音に近いものを出す。これは演劇にも似ている。舞台で上演される芝居は、生身の人間たちのよる総合芸術としての側面もあって、昼公演と夜公演でも違うだろうし、初日と千秋楽でも違ってくる。客の反応を見て変えることもあるだろう。
そういう意味での即興なので、たとえば「今日は曲はやりません。おしゃべりだけします」といった「逸脱」は、とんでもなく即興的で前衛的であると同時に、「やりすぎ」感も強いので、やる人は少ない。
演奏者と観客の双方が満足できる接点をどうやって作るのかは、ジャズに限らずあらゆる大衆向けの芸術にとって大事な要素であるはずだ。少なくともかつてジャズが大衆向けの音楽だった時代には、そうだったろう。
子どものように「飽きたから別の遊びをしよう」とやるにしても、自ずとそこにある「範囲内」であることが約束されている。少なくとも有料の観客の前で演奏するなら、それが求められてしまう。
それはたぶん、クラシック音楽でも同じなのではないだろうか。
演奏家や作曲家が「やりたい音楽」と、観客が「聞きたい音楽」の接点を探る実験は、いまも世界中で繰り広げられているに違いない。
いいなと思ったら応援しよう!

