
ATPが生命のエネルギーの通貨とか意味が分からん!と思っているあなたへ
ATP(エイ・ティー・ピー)っていう分子がある。中学でも、高校でも、生物の授業でたぶん習う。
こいつは、細胞の中のミトコンドリアで作られる。
食べ物から取り出したエネルギーを使ってATPを作るのが、ミトコンドリアの仕事だ。
作られたATPは細胞のあらゆるところに配られて、いろんな仕組みが働くためのエネルギー源になる。
どうやって、エネルギー源になるんだろう?
生物学の教科書には、よくこんな図が描かれてる。

そして、こんな説明が書いてあると思う。
① X という分子と、Y という分子が結合して、XY という分子になるには、エネルギーが必要だとする。
② こういう場合、X と Y がただ一緒にいても、いつまで経っても XY にはならない。
③ ところで、ATP が分解されて ADP と リン酸になる時、エネルギーが放出される。
④ 細胞はこれを利用する。
つまり、
X + Y → XY
という反応と、
ATP → ADP + リン酸
という反応を一緒に進めて、
ATP から出てくるエネルギーを使って XY を作っちゃうんだ!
・・・っていう感じの説明だと思う。
なかなか難解だ・・・
代わりに、こんなのはどうだろう?
「ATP は、ADP よりエネルギーが高い。」
これを、
ADP:バネが伸びて、リラックスした状態
ATP:バネをギュ~っと縮めてカチッと留め金で留めた状態
と理解してみるっていうのは、どう?
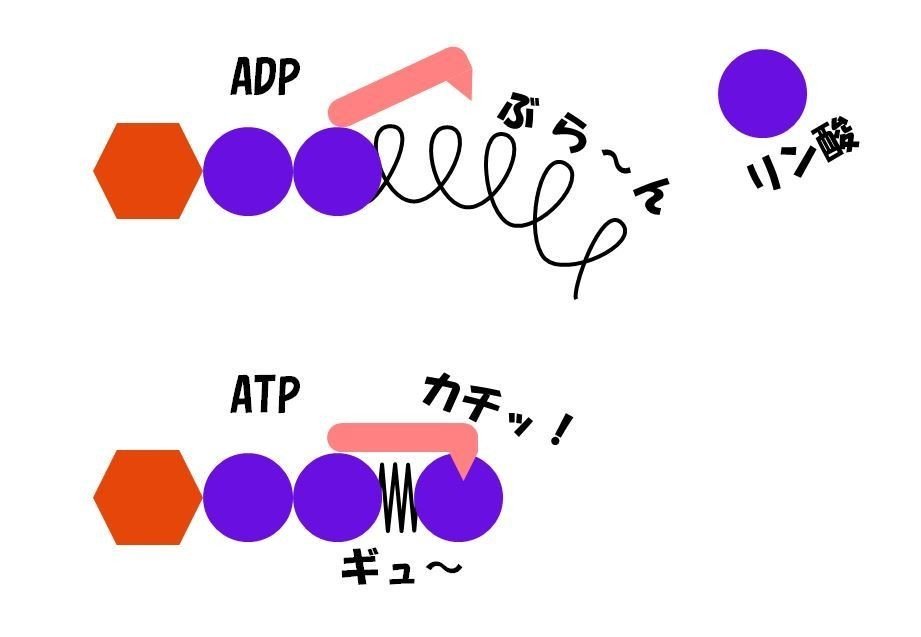
こんな感じのオモチャだと思ってみるんだ。
ミトコンドリアでは、バネがギュ〜っと縮められて、ATP が作られる。
この、今にもバネがピンッとはじけそうな危なっかしい ATP が、細胞の中のいろんな場所に配られる。
配られる先には、例えば X と Y から XY を作る装置(酵素)が待ち構えてたりする。
そこにATPがやって来て、
バネがピンッとはじけて、
バネの勢いで装置がピコッと動いて、
XY を作るという仕事をする。
こんな感じで、ATP は生命活動のエネルギー源になるんだ!
・・・っていうイメージはどうだろう?
もちろん、実際には ATP にバネがあるわけじゃない。
だけど、ATP のはたらきの本質が、
・エネルギーを一時的に閉じ込めておける
・小さくて運びやすいメディア
なんだって思えば、こういうバネが付いた空想上のオモチャで遊んでみるのも、ひとつの手だ。
遊んでみると、分かることがある。
エネルギーを、こういう小さなメディアに閉じ込めて配るっていうのは、とても頭のいいやり方だ。
食べ物からエネルギーを取り出すには、複雑で大規模な仕組みが要る。
細胞の中の、生命活動が行われているあらゆる場所に、そんな大規模な仕組みを配置するなんて無理だ。
そこで細胞は、ミトコンドリアっていう、エネルギー生産に特化した「場」を持つことにした。
ミトコンドリアでは、
・効率よくエネルギーが生産され
・それが効率よく ATP に閉じ込められて、
そして ATP は、それぞれの生命活動を担当する装置に配られていく。
おかげでそれぞれの装置は、エネルギー生産のことは気にせず、ただ ATP からエネルギーを受け取って、それぞれが担当する生命活動に専念できる。
つまり、ミトコンドリアは「発電所」なんだな。
電力を生み出すことに特化した発電所で、効率よく電力が作られて、その電力が工場や家庭に配られる。おかげで工場や家庭では発電のことを気にせずに、製品を作ったり家庭を営むことに専念できる。
この場合 ATP は、電力を伝える電線に相当するだろう。
細胞の中と、人間社会が、ある意味で同じ構図になっている。
とてもおもしろいと思う。
* * * * *
最後まで読んでくださって、本当にありがとうございます。
この投稿を気に入ってくださった方は
左下の ♡(スキ)を押して頂けると
とても励みになります。
(noteユーザーでない方でも「スキ」を押せます。)
