
認可保育園は公立と私立で何がどう違う? 公設民営って何? 保育の質や保育料の違いはあるの?
保育園の入園案内を見ると、認可保育園には「公立」「私立」の種別があることに気づきますね。さらに自治体によっては「公設民営」という第3の種別があることもあります。
それぞれ何がどう違うのでしょう?
公立、私立はどちらを選ぶべきなのか、それぞれの違いや特色について整理してみます。
公立・私立・公設民営の違い

保活の勘どころ オンライン講座「公立・私立の違いについて」より
公立保育園とは、市区町村が建てた建物に、市区町村が雇用した保育士が働いている保育園のこと。
私立保育園は、民間が建てた建物に、民間が雇用した保育士が働いている保育園のこと。
公設民営とは、市区町村が建てた建物で、業務委託を受けた民間の事業者が運営している保育園のこと。公立と私立の中間のような存在です。
厚生労働省『平成30年社会福祉施設等調査』によると、2018年の保育所等(保育園+認定こども園)の総数27,951園のうち、公営は8,495園。私営は19456園。
公立保育園は全体の30%程度で、認可保育園の多くは私立となっています。
では、それぞれの特色を解説しましょう。
公立の認可保育園の特色とは?

公立保育園の最大の特色は、働いている保育士が公務員だということ。
公立の認可保育園の保育士は、保育士の国家試験に合格するだけでなく、自治体が実施する公務員試験をパスすることが必須。狭き門をくぐって、保育の現場で活躍しているわけですね。
ちなみに公立保育園の園長になるには、一定の年数を経たのちに昇格試験があります。
この点、私立保育園は、園長になるためのステップは各運営母体によって異なるため、園全体をまとめる管理者(園長)の質や経験にバラつきがあることも多いようです。
公立保育園の特色1:ベテラン先生が多い
公務員である公立保育園の保育士。就労環境が安定しているため、長く働く保育士がたくさんいます。
そのため、さまざまな園を経験してきた「ベテラン先生」が、私立に比べると多め。経験豊富で安心できる反面、保育士との世代間ギャップに悩む保護者もしばしば、います。
中には、いまや当たり前の光景となった“送り迎えをするパパ”を「協力的で偉いわね」とほめちぎる保育士や、子どもの不調を”ママの愛情不足”と断罪する保育士も…。現代の育児観、ジェンダー観のズレに「ん!?」とモヤモヤを感じる場面もあるかもしれません。
公立保育園の特色2:職員が多い
予算の用途が市区町村できっちりと決められていることが多い公立保育園。看護師〇名、調理員〇名、保育補助員〇名、用務〇名など、保育士以外の職員が園内にキッチリと配置され、それぞれの役割も明確です。
保育士が保育のみに集中できる=質が安定している というメリットがあります。
公立保育園の特色3:保育の流れが一律
公立保育園の保育士の多くは、おおよそ3~6年程度で、自治体内の他の保育園へ異動します。市内・区内の公立保育園の中で、ぐるぐるとローテーションしているわけですね。
0歳の頃にお世話になった保育士と、卒園までおつきあいできることは稀かもしれません。管理者の園長でさえも、わりと高頻度で変わります。
というわけで、どの保育士が保育にあたっても保育の質が一定になるように、保育の内容が「属人的でない」のが特徴。どの園もだいたい一律・均一的な保育を展開し、保育の流れも似通っています。
公立の認可保育園の特色4:子どもファースト
保育園はそもそも子どもの福祉のためにあるもの。児童福祉法に位置づけられた「児童福祉施設」という原則があります。
公立の保育園はこの原則に忠実に、「子どもの育ち」を何より大切にします。言い換えれば、親の負担が多い園もある ということです。
例えば、昼寝布団のシーツは手作り推奨(というよりサイズ指定がトリッキーすぎて既製品が使えない!)、お迎え前にスーパーに寄ってはいけない(夕飯の準備より子ども優先!)、などなど、親が「ラク」することを良しとしない文化もまだまだ残っています。
公立の認可保育園の特色5:施設(建物)に年季が入っている
自治体によって違いはありますが、公立の保育園の多くは、1970年代から1990年代に建てられています。
というわけで、園舎はちょっぴり年季の入ったところが多いかも。
小さくても園庭を備えているところが多い反面、見た目や園内がちょっと暗かったり、登降園時のセキュリティシステムが前時代的だったりと、設備面では私立に見劣りがすることも少なくありません。
私立の認可保育園の特色は?

私立の認可保育園は、運営主体の法人が保育士や職員を直接雇用しています。
いま新設される認可保育園のほとんどは私立。ですが、保育士不足のおり、保育士の獲得に苦戦している運営主体も少なくありません。
中には、保育士として働いた年数が数年という状態で、園長を任されることもあるよう。元気のいいフレッシュな保育を展開している園も多い反面、管理上
私立の認可保育園の特色1:職員の異動が少ない
公立保育園のように職員が次々とローテーションしないので、卒園まで同じ先生と深く関わることもあります。
在園ウン十年というベテラン保育士がいて安定感がある反面、職員間の人間関係に問題が起こりがちというデメリットも。また、系列の保育園が新しくできたりすると、一斉に職員が入れ替わってしまうこともあるようです。
私立の認可保育園の特色2:個性がそれぞれに大きく違う
・毎日泥んこになって遊ぶことを推奨する園
・時間にとらわれず子どもの遊びのペースを優先する園
・身体を動かすことを推奨している園
・絵本を読むことや制作を重視している園
・集団での態度やお行儀をしっかり身に付ける園
・食育に力を入れている園
・小学校で困らないようお勉強もきちんとする園
などなど、とにかく多様で、個性がさまざまなのが私立保育園!
園によって保育の方向性がかなり違うので、見学の際はしっかりとヒアリングをすることが大事です。
私立の認可保育園の特色3:人員配置が園によって違う
園内看護師がいる園、いない園、調理係が多い園、少ない園…。職員の配置がある程度まで園に任されているため、園によって職員の構成がバラバラです。
系列園が多い園では1名の看護師が何園かを担当したり、運営母体の法人のさまざまな事業を、保育士や看護師が兼務していることも。
保育士が保育以外の業務、例えば用務(掃除や環境整備など)や調理を兼務する事例も…。結果的に、保育士の負担が増えることが予測されますね。
私立の認可保育園の特色4:保育サービスが充実している
公立保育園が「子どもファースト」なのに対し、私立保育園は保護者への保育サービスが充実していることが多いようです。
延長保育の時間が長い、日曜保育を行っている、使用済みおむつの持ち帰りなし、リトミックやサッカーなどの習い事が園内でできる、送迎バスがある、など、保護者にとってありがたいサービスを用意している園も増えてきました。
写真販売をオンラインで行っている、日々の連絡帳がスマホで見られる、など、保育の効率化も公立に比べて進んでいることが多いです。
公設民営の認可保育園の特色は?
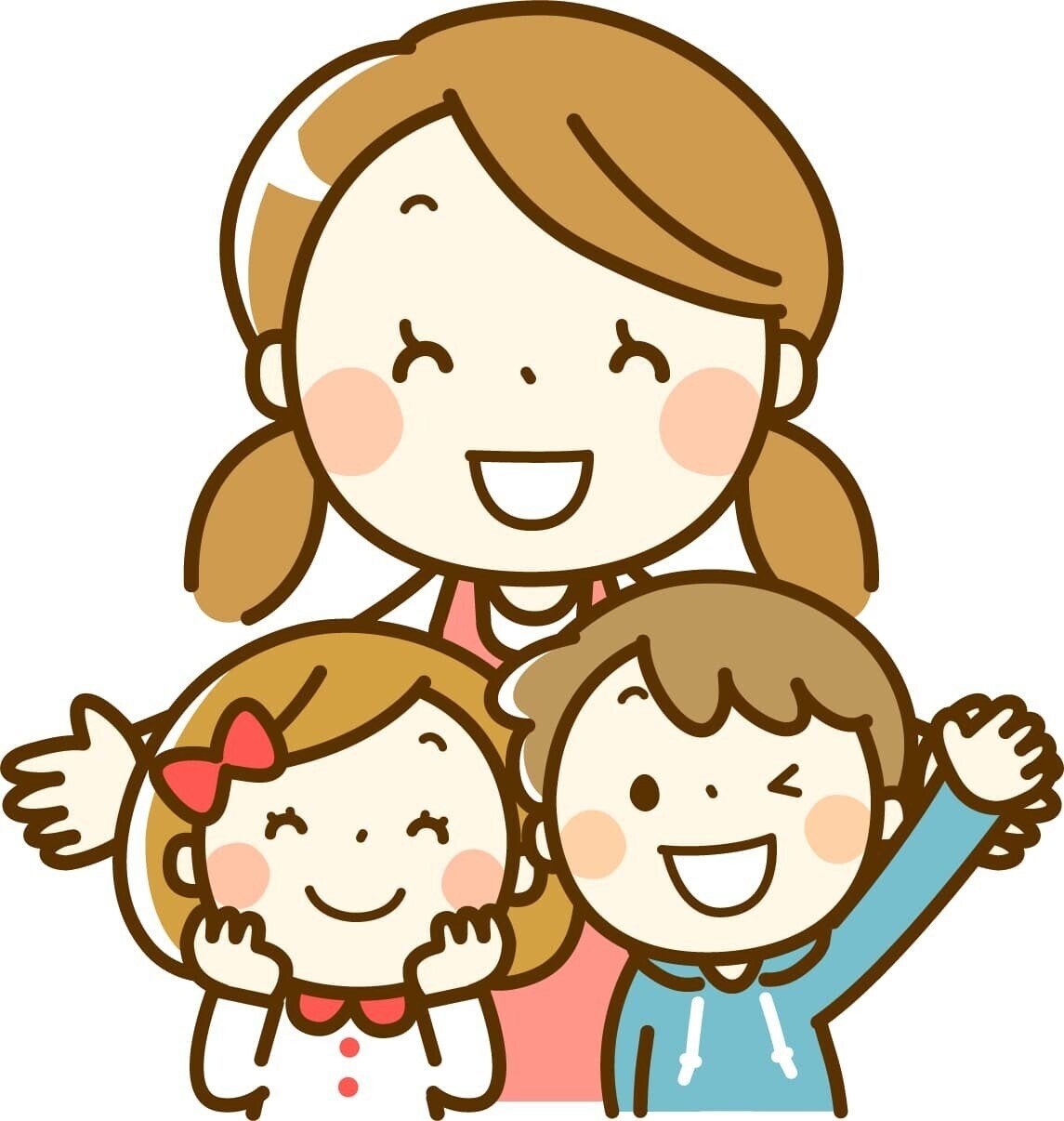
公設民営は、先に述べたように、官が設立した保育園を民が受託運営するという、公立と私立のハイブリッド型のようなところです。
市区町村によっては「管理委託」「指定管理者」などと呼ばれるところもありますが、全体数はかなり少なめ。
そして、市区町村によって人気もさまざまです。
例えば、東京都北区などは、公設民営(指定管理者)の園は「公立と私立のいいトコどり」という感じで人気があります。ですが、必ずしもそうとは言い切れない自治体も。
公設民営の目的の一つに「運営費の削減」があります。
もともと公立だった保育園が、予算削減を目的に公設民営化する事例も増えていて、要は、台所事情がなかなか厳しい園もあるわけですね。
結果、人件費などにそのしわよせが行き、保育士が居つかなかったり、非常勤職員ばかりだったり、殺伐とした雰囲気だったり…。残念ながら、運営費のムリが保育の質につながってしまっている例もあります。
運営の委託を受けた会社(指定管理者)が突然変わることもあり、保育士が丸ごと入れ替わる、つまり、保育園の中身がそっくり別のものになるという事例もあります。
保育園見学は、公立よりも私立をたくさん回ろう!
公立保育園は、いい意味でも悪い意味でも保育の流れが似通っているため、1~2園見ておけばだいたいの流れは一律同じということが多いです。
限られた期間で保育園の見学に行くならば、私立保育園を重点的に回ること!
私立保育園は、園によって個性さまざま、まったく違う保育を展開しています。また、同じ系列園であっても、園長の人柄や考え方によって保育の内容が変わってきます。
見学は私立を中心に行うことをおすすめします。
ライター:飯田陽子(保活ライター)
コピーライター/ライター歴20年+α。広告制作やライティング業務のかたわら、社会活動として2015年から東京23区内で保活講座を実施。子育て支援施設や保育園、マンションギャラリーなどで地域の保活情報を提供し、保活中のママ・パパに「保活のコツ」や「情報収集のポイント」をレクチャーする。有限会社ミラクルパンチ所属。
WEBサイト:http://www.meshiya.com/
