
できるか!兵士の命を犠牲にして民間人の被害抑制 問われる戦争倫理
イスラム組織ハマスが実効支配するパレスチナ自治区ガザへのイスラエルの攻撃が凄惨を極めている。その被害は、病院や学校、難民キャンプにまで及び、民間人の死傷は増える一方。一体、どうすれば、終わりの見えない紛争から民間人の命を守ることができるのか。その解を求めて、「戦争の倫理」について考えてみた。
地球を一回りする民衆の抗議デモ
「ジェノサイド(大量虐殺)をやめろ!」――。いま 世界中の都市とSNS空間で、ガザ攻撃を強めるイスラエルに対し、抗議の声が巻き起こっている。東京のイスラエル大使館近くでも「皆殺しやめろ」とか、「パレスチナに自由を」などと書かれたプラカードを掲げ、即時停戦を求める抗議集会が開かれた。
ハマスが10月7日に仕掛けた大規模テロによるイスラエル側の死者は1200人以上。さらに、240人以上が人質としてガザ側へ拉致された。一方、イスラエル軍の猛反撃によるガザ地区の死者は1万6000人を超えている。このうち、5000人以上が子どもで、国連のグテレス事務局長は「ガザは、子どもの墓場になりつとつある」と嘆く。
当初は、イスラエル支持の国際世論が支配的だったが、ガザ地区での住民の巻き添え被害(専門用語では付随的損害、collateral damage)が激増すると、状況は一転し、イスラエル批判が日増しに広がっている。
イスラエル軍は、ハマスと民間人を区別し、「無辜《むこ》の民」の巻き添え被害を回避する努力をしているのか? SNSやテレビで流れるガザの惨状を目にすると、国際人道法の「区別原則」を遵守しているのか疑いたくなる。
とはいえ、ハマスは、病院や学校などの民間施設に隠れてロケット弾を打ち込んでくる連中だ。「もちろん、我が軍は、事前に避難するよう呼びかけてし、細心の注意を払って攻撃している。そもそも論を言えば、住民の巻き添え被害の一次的責任はハマス側にある」といった反論にも一理ある。住民を避難させる義務を怠り、「人間の盾」にしていることにこそ問題の核心がある、というのだ。
国際人道法の限界――あいまいな均衡ルール
いずれにせよ、民間人の死傷にはゾッとさせらる。そのとき、たまたま、運悪く、間違った場所に居合わせただけで、前線の戦闘行為にも銃後の戦争支援(例えば、軍需工場に勤務など)にも参加していない「通りがかりの人たち」だからだ。自分たちに危害をまったく与えない無害な民間人(innocent civilian)ではないか。
兵士が子どもを含む無害な人びとを故意に殺害すれば、もちろん、戦争犯罪に当たる。しかし、国際人道法は、民間人の巻き添え被害を絶対的に禁止していない。戦争である限り、巻き添えは不可避であるとの前提に立っている。
ただ、攻撃の際、細心の注意を払って、巻き添えという「副作用」を最小限に抑えるよう義務づけている。司令官は、「均衡性」の原則を遵守しなければならない。我が方の予期される軍事利益(A)と、敵側の予期される巻き添え被害(B)が釣り合っていなければならないというルールだ。Aに比べ、Bが「過度」な攻撃は許されない。
でも、釣り合っているって何? 過度とは? イスラエル軍が、テロを企てるハマスの幹部1人をこの世から「排除」するのに、ガザの住民1、2人の巻き添え死ならば、AとBはバランスしているのか?ハマスの下っ端ではなく、最高指導者ヤヒヤ・シンワル氏が標的ならば、病院の医療関係者や患者ら100人、200人が巻き添えで死んでも過度とは言えないのか?
このように、均衡ルールの解釈は、極めてあいまいだ。軍事的必要性(A)と人道上の配慮(B)をはかる共通尺度を欠いているため、越えたら違法になる一線「レッドライン」が不分明だ。どうしても、紛争当事者の主観やバイアスが入り込み、双方に都合よく解釈されてしまう。「法律家頼みのアプローチ」に限界があるゆえんだ。
正反対の戦争倫理観――戦闘員保護と民間人保護の異なる優先順位
では、倫理・道義のレンズを通して民間人の巻き添え被害について検討してみよう。その際、闇雲に議論しても時間のムダなので、鍵となる二つの極端な主張を紹介する。
一つは、アメリカの政治哲学者で「正戦論」の代表的論客であるマイケル・ウォルツァーの見解だ。
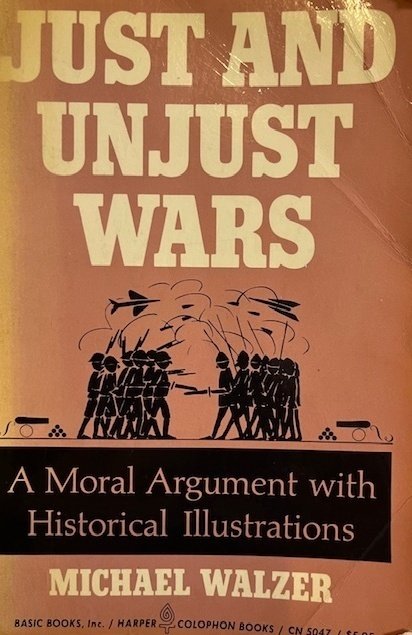
その特徴は、自国の戦闘員保護より敵国の民間人保護を優先することにある。民間人の巻き添え被害を最小限に抑えるには、自国の戦闘員の生命を危険にさらすリスクを甘受しなければならないと説く。たとえ住民を「盾」にとる違法な戦法を行使する卑怯な相手に対しも自軍のリスクを回避すべきではないという。
そもそも、敵の攻撃から身を守る手段を持ち、そのための訓練を受けている戦闘員と、その術《すべ》を持たない丸腰の民間人のリスクを同等に扱うことはできない、とウォルツァー指摘する。民間人の命に「重り」をつけて推し量らないと、「殺しのライセンス」を持つプロの兵士の命と釣り合わないという理屈である。
都市への空爆や砲撃は控える、命中精度の高い兵器の使用や破壊力の小さな爆弾の使用、訓練の強化、標的となるハマス幹部の行動パターンや所在などについてのきめ細かな情報収集……。ウォルツァーによれば、こうした戦術的配慮は当然だが、最終的には、兵士の命をかけて標的に出来るだけ接近して、敵兵かどうか正確に見極めない限り、攻撃は控えなければならない。
これに対し、イスラエルの哲学者で軍のアドバイザーであるアサ・カシャーは、逆の優先順位をつける。
ウォルツァー流の国際人道論は、自国の民間人を守るために戦う戦闘員の生命と尊厳をあまりに軽視していると反論する。カシャーにとって、自国の兵士は「制服を着た市民」だ。その命は、テロ集団が活動する「テロの聖地」の住民の命より重い。
もちろん、民間人保護は必要だが、いま問題にしている民間人のなかには、自発的にテロ集団の周りで生活したり、喜んで集団の「盾」になったり、必要に応じて銃を持ったりするなどテロに間接的に関与している住民もいると主張する。つまり、危害を加えられる恐れがまったくない無害な隣人とは言い難い、というのだ。
戦闘員を含む自国民の生命に最終責任を負う民主国の指導者が国民に対し、実効支配が及ばない国・地区の民間人――しかも、テロとの「共犯性」を完全に否定仕切れない住民の命の方が自国の戦闘員の命より重いと公言できるはずがない、とカシャーは断言する。ウォルツァーの説に従えば、戦闘員を不必要な危険にさらし、最終的に自国民の安全を損なう最悪の結果を招きかねないとも。
兵士の命をかける反乱鎮圧作戦
自軍の命を犠牲にして民間人被害を縮小せよと言っても、実世界でそんなことが可能なのか。
筆者の知る限り、オバマ米政権が2009年にアフガニスタンで実施した反乱鎮圧作戦(counterinsurgency)は、カシャーよりウォルツァーの戦争倫理観に近い。
この鎮圧作戦に派遣された地上軍兵士が準拠すべき軍事マニュアル(FM3-24MCWP3-33.5)は、現場の若手・中堅クラスに対し、住民の巻き添え被害を極力避けるために積極的なリスク受け入れを義務づけている(7章参照)。

大規模な地上軍を投入して武装勢力を封じ込め、住民の安全を確保するには、人心をつかむ必要がある。それには、住民の巻き添え被害をゼロに近づけなければならない。
それ故、「危ないと思ったら撃て」ではダメなのだ。至近距離から銃撃し、敵を殺害しなければ、自分も殺されてしまうギリギリの時点まで攻撃を控え、「確実に敵と分かるまで撃つな」が鉄則である。
これを遵守すれば、アメリカ軍の戦死者は確実に増える。じじつ、それまで年平均58人だった米兵の戦死者は、この鎮圧作戦(09―12年)で6倍に跳ね上がった。
兵士の命をかけないガザ侵攻作戦
米軍の武装勢力鎮圧作戦と対照的なのが、今回のイスラエル軍の作戦「鉄の剣」だ。戦闘員保護を重視するカシャーの戦争倫理を手本にして、ガザ側の住民の命を犠牲にしても兵士の犠牲を限りなくゼロに近づけようとしているように見受けられる。

AFP通信によれば、イスラエル軍は、ガザ側の死者を1万5000人以上と見積もっている。このうち、5000人がハマスで残りが民間人。大ざっぱに計算すれば、ハマス1人を殺害するのにガザ住民の2人以上が犠牲になる勘定だ。「他国軍の市街戦と比べれば、この比率は申し分ない」と軍の当局者はワシントン・ポスト紙に語っている。
もっとも、殺害したとされるハマス約5000人が本当に武装兵なのかは定かでない。戦闘への関与の疑いが希薄でも、ちょっとでも怪しければ、武装兵としてカウントしているのかもしれない。殺されたハマス対ガザ住民の巻き添え死の比率は、1対5以上と推定する専門家もいる。
イスラエル軍が高価値と見なす本命のハマス幹部に限れば、10月末の時点で少なくとも80人を殺害した、と軍の公式サイトに書かれている。おそらく、比率は1対100を超えると見られる。
一方、4万人規模のイスラエル軍が投入されたが、10月28日に始まったガザ地区への地上侵攻で戦死したイスラエル兵は12月5日時点で計81人に過ぎない。2011年には、ハマスに捕らえられていた兵士1人と、イスラエルの刑務所に収監されていたパレスチナの囚人1000人余との「不平等交換」に応じたこともある。
しかし、あまりに多いガザ側の死傷は、反イスラエル感情を一層強固にするだろう。命を奪われたパレスチナ人の家族や友人は、新たなハマスになりかねない。先の1対2の比率が正しいとすれば、ハマスの殺害は、組織の壊滅どころか、増殖を促していると言えるだろう。そうであれば、ハマスの思う壺だ。
パレスチナのコンサルタント企業が11月14日に公表した調査結果によれば、ガザとヨルダン川西岸のパレスチナ人住民の98%が「イスラエルが自分たちにしたことを決して許さない」と思っている。ハマスを肯定的に見ているとの回答も76%に上った。
いまガザで起きている紛争の性格についても、ハマスとイスラエルの戦争と見ているのは18%に過ぎず、約7割がパレスチナ人に狙いを定めた紛争と捉え、「パレスチナの勝利」を信じている。
苦渋の選択を迫られる政治指導者
さて、次のシナリオを考えてみよう。
ある軍事目的を達成するのに二つの戦術がある。
①敵側の民間人の死傷はゼロと予期されるが、自国の兵士100人の命を危険
にさらす。
②民間人1人と兵士1人の命を危険にさらす。
あなたが司令官や政治指導者ならば、どちらを選択すべきか?
ウォルツァーならば、迷わず①を選択するだろう。しかし、彼の議論を受け入れて、自軍を犠牲にしてまで敵国や介入先の民間人を保護せよと言っても、現実には、ナショナリズムの制約を超えて、それを指揮官、さらには政治指導者の責務として全うすることは難しいだろう。果たして社会が納得するだろうか。カシャーが言うように、兵士の犠牲が積もり積もれば、肝心の自国民の安全も守れなくなる。
単純な解決策などあろうはずがない。一種のジレンマだ。それを百も承知であえて言えば、2つの理由からウォルツァー流の戦争倫理を採用する方が無難かつ賢明ではないかと思う。
第1に、指導者が戦術的配慮の道義的箍《たが》を緩めても構わないと部下に指導すれば、兵士たちは、できるだけ緩く自分たちに都合よく解釈するだろう。
もとより、自分たちの命がかかっているのだ。自由解釈の余地が広がれば、テロリストか無害な民間人かどうかの判断が容易につかないときは、「不審者に接近するリスクをとらないで皆殺せ」などと極端な判断を許す恐れがある。「危ないと思ったら、すぐ撃て」では、民間人が巻き込まれて殺傷されるリスクは跳ね上がってしまう。
第2に、正規軍対非正規軍の非対称戦の場合、住民の巻き添え被害が極端に多いと、軍事的に制圧することができても、中長期の政治心理戦で負けてしまう。
武装勢力をあぶり出すためとはいえ、自軍の犠牲が伴わない空爆や砲撃で住居や生活インフラを破壊し尽くし、ライフラインを寸断すれば、地域の住民全体に「集団罰」(collective punishment)を課している、と住民たちに映りやすい。つまり、正規軍は、武装兵力というよりも、自分たちを敵にしている、と受け取られかねない。
大統領や首相とは辛い職である。たとえ自軍に犠牲を強いても、より大きな目的に立ち向かわなければならないこともある。その任に絶えるには、強靱な精神力と類いまれな指導力が求められる。しかも、政治家である以上、結果責任から逃れることはできない。
