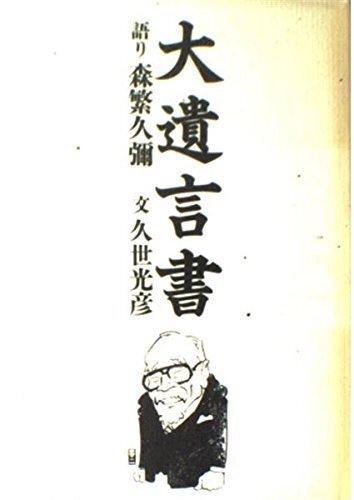「名言との対話」11月10日。森繁久彌「ピンとキリだけ知っておけばいい」
森繁 久彌(もりしげ ひさや、1913年5月4日 - 2009年11月10日)は、日本の俳優、歌手、コメディアン、NHKアナウンサー。昭和の芸能界を代表する国民的名優。享年96。
大阪出身。早稲田大学卒。アナウンサー,コメディアンをへて、1950年に「腰抜け二刀流」で映画デビュー。「三等重役」「夫婦善哉(めおとぜんざい)」などで人気を博す。テレビ、舞台にも出演。歌手としても「知床旅情」をヒットさせ,ミュージカル「屋根の上のヴァイオリン弾き」は900回以上の上演を記録した。死後に国民栄誉賞を授与された。
たゆまぬ研鑽で時代とともに成長を続け大きく花開いた国民俳優だ。この人はただの俳優ではなく、極めつけの文化人だった。44歳で処女作を発表以来、主要著書は54冊にのぼっている。そのうち、還暦を過ぎた63歳以降の著書が43冊と多いのも特徴だ。
「女房やセガレがどんなにボヤこうが、私はあくまで一世一代で、すべてが私と共にあり、私と共に無くなるのである。」
「目下開店中の八百屋のような万うけたまわりの芸術屋(アルチザン)を整理して、新しい冒険に船を漕ぎ出さねばなるまい。このまま立ち枯れるには、まだチット血の高鳴りが邪魔になる人生五十年である」
「そんなに大層なことは、この世の中に一つもない。大概笑ってごまかせることだ。」
2009年、世田谷文学館で、第11回世田谷フィルムフェスティバル「名優・森繁久彌」が開催されてみてきた。森繁久彌は、「世田谷区船橋に在住」とパンフにあるが、この特集を始めた頃はまだ存命だったということである。
「この度、ボクの古い映画を上映して下さるとのこと、少し照れくさいが、わたしの仲間だった久世光彦さんの展覧会も開催されると伺い大変うれしく、世田谷文学館には感謝申し上げたい。また先般は、マスコミで皆さんに多大なご心配をおかけしましたが、私自身はおだやかに秋をむかえております。」という挨拶文があり、最晩年の名優が正装して写っている。
国民作家という言葉があり、その栄誉を受けているのは、吉川英治と司馬遼太郎くらいであるが、国民俳優という言葉があるとすれば、それは森繁久彌しかいないだろう。
1950年代後半から60年代を通じて、映画での社長シリーズ、駅前シリーズ「森繁もの」の人気はすさまじく、55年の18本を頂点として、毎年10本以上の映画に主演している。また、64年の「七人の孫」以来、70年代に入ると、森繁久彌はテレビの人となった。そして、まさに全国民が敬愛する俳優になった。
森繁久彌の映画デビューは意外に遅く、37歳のときに「腰抜け二刀流」(並木鏡太郎監督)で初主演をする。早稲田大学を中退した痕、NHKアナウンサーとなって満州の新京(長春)に勤務し、33歳で帰国し役者を目指すが、なかなか芽が出なかった。
1936年以来、300本を越える映画に出演。舞台では、「屋根の上のバイオリン弾き」は、900回の公演。文化勲章受章時には「わが胸に あつくもおもく たちばなの きときわ 薫る 人ひとの愛」と詠んでいる。
森繁久彌は、パチンコのリズムに芸風のヒントを得ている。「リズミカルな動きと感情の推移」「次にどう出るかわからぬという未来を予測し得ない演技」。サラリしつこくなく点描して行くという二枚目半の芸風を開拓した。
喜劇俳優から、実力俳優へ、そして押しも押されもせぬ、大スターへのぼっていく。この道程も興味深い。96歳の大往生だったが、寝つきがよく15分もあれば熟睡できた。これが長寿の秘訣だった。
この人ほど、多くの賞をもらっている人もいないのではないだろうか。43歳。ブルーリボン賞。毎日映画コンクール主演男優賞。45歳。NHK和田賞。51歳。紺綬褒章。52歳。NHK放送文化賞。62歳。菊池寛賞。63歳。ゴールデンアロー賞。64歳。紀伊国屋演劇特別賞。毎日芸術賞。菊田一夫演劇大賞。65歳。芸術選奨文部大臣賞。68歳。創作集団文芸賞。70歳。東京都民栄誉文化賞。日本アカデミー特別賞。71歳。文化功労者。74歳。勲二等叙勲。78歳。文化勲章。79歳。日本アカデミー賞栄誉賞。83歳。日本映画批評家大賞。
この人はただの俳優ではなく、極めつけの文化人だった。44歳で処女作を発表以来、主要著書は54冊にのぼっている。そのうち、63歳以降の著書が43冊と多い。
「森繁久彌語り・久世光彦文」という「大遺言書」「さらば!大遺言書」を読んだ。森繁久彌のつぶやきが聞こえる名著である。
不思議な書である。森繁久彌が「語り」、久世光彦が「文」を書いたという形の本である。インタビューでもなければ、共著でもない。確かに久世光彦の文章なのだが、この二人の位置関係は、表紙や奥付で久世光彦の名前がほんの少しだけ下がっているところに現れているとも見える。この微妙な配慮がいい。「大遺言書」「今さらながら 大遺言書」「さらば 大遺言書」という連作をここ二日間で読み切った。
「週刊新潮」で2002年5月2日・9日号から始まった「大遺言書」の連載は、2006年3月まで続いた。卒寿を越えた森繁と、二まわりほど若い久世のどちらかが亡くなるまで続けるという約束だったが、2006年3月2日の久世光彦の逝去によりこの人気連載も終了している。そして、その森繁久彌も、今年2009年11月10日に96歳で大往生を遂げる。
森繁の自宅に久世が伺い、健啖家の森繁の相手を務めながら、森繁久彌という大いなる人物の回想を聞き出していう。そしてその時の様子や感じたこと、思い出したこと、そして森繁久彌という人物の陰影などが生涯の師匠と仰ぐ久世光彦の名文で記されていく。久世の慨嘆、感銘、感想、感慨などもいい。これは、晩年の生き様を描いた書でもあり、人生の書でもある。読者は、森繁久彌という国民的俳優の目を通して、歴史と人間を深く味わうことができる。
毎週原稿用紙7.5枚を4年近く書き続けたことになるが、互いの生涯を賭けた対話であったという印象を持った。書いた久世にとっても、書かれた森繁にとっても至福の時間だったと思う。
森繁久彌という俳優は、俳優としての実力は群を抜いているが、その土台は豊かな教養に裏打ちされていると思わずにはいられない。鋭い批評眼、本質をとらえる矢のような言葉などを読むと、優れた文化人であったという思いを強くする。
若い頃の森繁久彌は、やや軽い顔をしているが、だんだん顔が良くなって、晩年になるほど「いい顔」になっている。俳優という職業に命を懸けて少しづつ内容が磨かれていったということなのだろうか。向田邦子、松山英太郎、樹木希林など森繁久彌が愛した才能などの話も興味深い。
このごろの文芸作品にリズムと品格がないのは、作家に漢学あるいは漢詩の素養がないからだと森繁さんは言う。
長生きするということは、人と一人また一人と、別れてゆくことです。、、、この年になると、悲しいというのと違う。−−辛い
私にしてみれば、どの人も夭折です。
いつだって、人の世の主役は人間ではなく、歳月です。
人と人との間は、どんな親しい仲でも、薄氷を踏んでいるようなものです。
(今日もインタビューは歌で終わる。)
女優の華と人生とは、反比例の関係にあるんでしょうかねえ。因果なことです。
役者というものは、長火鉢一つで、人生をすべて表現しなければならないと言っても、言い過ぎではありません。
映画や芝居を見て学ぶということは、まあ、ありません。実際の人生の方が、はるかに可笑しいし、切ない。
味に贅沢なこの国に生まれて幸福でした。
勝(新太郎)は私との二時間ばかりの放談の場を、一つの「芸」の場にしようとしているんです。あのときの「殺気」を思い出すと、今でも鳥肌が立ちます。
芝居の仕事は、私の「真剣な遊び」です。
懸命に働きはしましたが、やっぱり運です。
正直言うと、私は自分の映画のほとんどを、恥ずかしいから見ていないのです。
(森繁さんは夜が更けて眠たくなるころになると、天眼鏡で「広辞苑」を眺めているのだというのだ。)
三割隠すところにこそ、「芝居」の真実はあるのです。
私は「小学唱歌」は、西欧の国で言えば「賛美歌」だと思います。
「小学唱歌」や「文部省唱歌」には、いまとやかく言われている「歴史観」や「国家観」や「国の心」とかいうものが、全て柔らかで優しい形で含まれています。
「芸人とは、芸の人でなく芸と人ということではないか、、、、」というの言葉の後には、「なべて『人』を失っているかの感なきにしもあらずだ。人が人たるを失って、世の中に何があろう」と続く。映画や芝居などより、実際の人生の方がおかしく、切ない。その人生から学びながら人をつくっていく。どのような職業も「人」が重要だが、人生を表現すことを生業とする役者は、見る人が役と人とがないまぜになってみているから、特に「人」が重要なのだ。遅咲きの国民的俳優・森繁久彌はその機微を知っていた。
森繁には名言が多い。「ピンとキリだけ知っておけばいい」を採ることにした。「プンからキリまで」とは、1から10まで、最上からから最低まで、はじめからおわりまで、という意味である。最高と最低を知っていると、どの間のものを評価できるということである。
このことは、蕎麦で実感したことがある。秩父のこいけで毎年食べた極上の蕎麦と立ち食いソバがそれだった。これは人物にもいえる。こいけでご一緒した冨田勲先生は、当時私は「人物の大吟醸」と表現していたが、ピンの人だ。この「名言との対話」で取り上げている人たちは「ピン」の人たちだ。人も「ピンキリ」である。可能な限り、ピンの方に近づきたいものだ。