
俳句とエッセーと諫早風景①~㉘『 海山村Ⅱ 』 津 田 緋 沙 子
俳句とエッセー 津田緋沙子『海山村Ⅱ』
写真とキャプション 山本博幸
風 の 道
平 成 二 十 九 年
① 巡 礼 の 旅
鉛 筆 も 子 の お さ が り や 春うらら
巡 礼 の 旅 の 終 は り の 薮 椿
聖 人 の 赦 し の 眼 致 命 祭
山 峡 の 秘 湯 卯 の 花 腐 し か な
青 嵐 白 鷺 は 樹 の 花 と な り
青 嵐 は ち ま き 長 く 応 援 部
口 紅 き り り ひ ま わ り の や う な 人
致 命 祭
「致命祭」これは長崎の風土に根ざした独特な季語、ふるさと季語のーつだという。毎年二月五日、長崎市西坂の丘の日本二十六聖人記念碑の前で行われる野外ミサである。
山 よ り の 供 花 は あ を も じ 致 命 祭 朝 倉 和 江
致 命 祭 市 電 ゆ つ く り 坂 くだ る 末 広 京
凍 雲 に 神 の 意 こ も る 致 命 祭 下 村 ひ ろ し
一五九七年一月、秀吉の禁令により捕らえられた宣教師と日本 人信徒二十四名は京都で左耳をそがれ、市中引き回しの上処刑地長崎までーケ月の長旅に出た。道中二名を加えた二十六名が、西坂の丘で傑刑に処せられたのが二月五日である。最年少聖ルドビコ茨木は十二才。霙めく寒さの中、 四千人が見守り、処刑後の十字架の穴には椿の木が植えられたという。
今年初めて致命祭に参列する機会を得た。大司教以下司祭、修道士、神学校生徒の列座のもと、オルガンの調べ にのって連祷、讃美歌、祈り、聖饗…、ときに鳥の声も聞こえた。巡礼の旅の一団もいて、 この日集まった老若男女は二千人に上ったという。
致命祭が果てると西坂の丘には騨雨が来た。




② 地 主 顔
日 雷 押 し 黙 り ゐ る 峡 の 里
つ か の 間 を 泉 に 眠 る 杣 の 犬
泉 へと つ づ く 野 道 と け も の 道
山 羊 五 頭 地 主 顔 し て 夏 野 ゆ く
消 し ゴ ム の つ く る 友 情 夏 季 講 習
青 嵐 心 に 鍵 の か か る 音
退 院 の 朝 の そ ら 豆 ス ー プ か な
雷
諫早は雷の多い所である。地理的条件によるのだろうが、年中
ごろごろ鳴っている気がする。おまけに長崎市に住んでいた時よ
り格段に音が大きく、稲光りも強く感じる。ものぐさな私でもプ
ラグを引き抜かずにはいられない時がたびたびである。
昨夏、隣町の森山図書館が落雷で火事になった。木をふんだん
に使い、広々とした自慢の図書館は消防や地元の人の奮闘で短時
間に消火できたものの五万冊もの本が煤や水を被った。現在、 一
部開館しつつボランティアも参加して本の清掃中である。秋の全
面開館をめざし、 工事中の建物には避雷ハネルなるものが取り付
けられるとか。自然の恵みと災害は裏表、人間の知恵に期待する
ばかりである。
「雷の多い時は豊作」 「稲妻は実りの証」とは昔から言い伝え
られていることらしく、今でも農家のおじいさんのロから聞いた
りする。それならいいな、我慢せねばとも思うが、 いざ迅雷とな
ると、雷は稲の妻…などとロ マンに浸ってはいられなくなる。
さて今年はどうだろうか。日雷はお断り、落雷なしで多めに、
と虫の良いことを考えたくなる。







③ み な 違 ふ
ひ ま わ り や 自 転 車 旅 の 子 の 未 来
鞄 よ り 猫 の 顔 出 す 夏 休 み
入 院 の 鞄 重 た し 今 朝 の 秋
初 潮 の 鼓 動 や 葦 の 目 覚 め た る
塾 の 灯 の い よ よ 明 る し 初 嵐
水 澄 む や 野 を 渡 り ゆ く は ぐ れ 雲
水 澄 む や 山 羊 の 鈴 音 の み な 違 ふ
風 の 道
今年の夏は豪雨や猛暑だけでなく風も強かった。台風かと思う
程の強風の日が何度もあり、私はびくびくしながら車庫の屋根を
見張る羽目になった。わが家の車庫の屋根のスレートは十年前の
台風で田んぼへ飛んだ前科がある。
家を建てる時の大工さんの言葉は「ここは風の道のあるけんね」。
それを私は素敵なことと聞いていた。渡り鳥たちがその道を飛ん
でゆく姿などを思い浮かべて。
ところがじきに、わが家にはそよ風など数少ないと解ってきた。
窓を開けるとカーテンは翻り新聞が飛ぶ。花の鉢がひっくり返る
のはよくある事で、油断するとバケツや箒、 コンテナが転がり回
る。最近は遠くに小さな竜巻が見えて緊張した。
十年前と違い周囲に家が増えた今は、車庫の屋根は飛ぶように
できていると澄ましてはいられない。台風期を前に遂に補強して
もらったが、今度は屋根屋さんの言葉が怖い。 「次飛ぶ時は柱ご
とですたい」。
強風も異常気象の一環なのだろうか。世の中も風向きがおかし
いし強風が吹き荒れている。 こちらに補強の手はあるのか。
踏ん張らねば。



④ 父 と 子 の 空
修 験 山 霧 の 育 て し 百 年 林
山 守 て ふ 美 し き 名 や 斧 の 露
語 り 部 の も は や 語 ら ぬ 萩 の 露
流 鏑 馬 は カ メ ラ 振 り 切 り 秋 高 し
炊 き 出 し の 里 の 賑 は ひ 小 鳥 来 る
今 朝 母 と な り た る 顔や木 の 実 降 る
屋 根 に 寝 て 父 と 子 の 空 流 れ 星
夏 惜 し む
今年も秋はちゃんとやってきた。黄を帯びてきた稲田の畔に彼
岸花が赤く、蕎麦畑の緑は風に波打って白露をころがしている。
遠く多良岳、普賢岳には霧が立つ日が増え、そろそろ渡りかと
見上げる空に白いちぎれ雲が流れる。自然と人の暮しが造り出す
この美しい風景。 「夏惜しむ」は新しい季語だというが、 この言
葉がまだ心に残る秋である。
今年の夏、長崎は二人の偉大な語り部を失った。谷口稜嘩さん
と土山秀夫さん。お二人は反核運動に携わる者たちの拠り所だっ
た 。
九月二十日、 ニ ューョーク国連本部での核兵器禁止条約署名式
に、長崎市長等はお二人の遺影を抱いて参加、 日本代表の姿の無
いその場を見守った。長崎平和公園では「一日も早い核廃絶を」
というメッセージカードをつけた風船が空へ放たれたという。
「先に逝く人は必ず何かを教えていく。別れの時に、遺された
者たちは贈り物を受け取る」と何かの本で読んだ。記憶に新しい
北九州豪雨災害や諌早大水害から六十年目の節目でもあった今年
の夏を、私は美しい秋の中で惜しんでいる。


春 泥
平 成 三 十 年
⑤ 空 飛 ぶ 話
面 会 の 保 護 司 林 檎 の 袋 持 ち
自 動 車 の 空 飛 ぶ 話 日 向 ぼ こ
花 屋 に は 花 の か を り の 初 氷
霜 柱 踏 む 三 才 の 子 の や う に
古 文 書 の 読 み 解 け ぬ 夜 冬 の 雷
臥 す 人 の 耳 す ま し ゐ る 冬 の 雷
寒 雷 や い よ よ 小 さ き 峡 の 里
葉 っ ぱ に 会 い に
十一月下旬、諌早市上山公園の自然観察会に参加した。山全体
がーつの公園となっているこの森は、長崎県では唯一 「森林浴百
選」に選ばれている。地元の上山小学校健全育成会が始めた親子
で楽しむ自然観察会は、三十三回めを迎えた。
今回は、講師の自然保護協会メンバーが前日に採集した公園の
樹木の葉っぱを各々がーつ選びとり、森にその葉っぱの木を探し
に行こうという企画である。福引のように葉っぱを選んだらまず
観察、 スケッチ。子ども達の目は鋭く発見の言葉が飛び交う。
前日の雨で森は苔が美しい。葉っぱを片手に目をこらして木々
を観察してゆくが、似て非、見つけるのは難しい。しかしその度
に子ども達は葉の色、光沢、鋸歯や葉脈の違いや木の特性を学ん
でいく。そして自分の葉っぱと出会った時の歓声! 以降はきっ
ちり自分の木を見つけ、当てていくのがすばらしい。全員が自分
の葉っぱの木と出会った日。 この日の思い出はきっとこれからも
上山の森を守っていくだろう。
子ども達への最後の課題はスケッチに俳句を添えること。心に
残る森林浴の一日だった。


⑥ 負 け ず 嫌 ひ
冬 凪 の 湾 に 女 の 声 の 増 へ
寒 月 や 影 も 私 も と ぼ と ぼ と
寒 月 や 土 黒 々 と 藍 の 甕
晩 照 や 立 ち 上 が り く る 冬 の 山
階 段 を 駆 け る 足 欲 し 冬 日 和
冬 凧 や 負 け ず 嫌 ひ の 次 男 坊
元 寇 の 海 見 は る か し 冬 の 凧
マ イ カ ー 顛 末 記
増え続ける高齢者の交通事故。さすがに私も二年位前からバス
や電車に乗る練習を始めた。待つということは難しく、 田舎の交
通事情は身に泌みた。
そんな中、秋の終わりについに私の車に寿命が来た。母の介護
を助けてくれたスバルのインプレッサ。十年も乗り続けたのは地
域事情と何より車が作ってくれた思い出のお陰である。
親しい整備工場で、もう車はやめると口にした私に社長は事も
無げに、あれ持っていけばと会社の代車の一台を指さした。そし
てあれよあれよという間に新しいマイカーはやってきた。何と私
のインプレッサのポールが形見のように取り付けられている!
少々のお手入れや交換、車検を済ませ、二十万円足らずの代金明
細の中に車両代八万円也と記されていたので、私はこの車に「ス
ズキパーマン」 と名づけた。
以来二ケ月、車利用は諌早、長崎に出かける場合と限定し、慎重に
運転している。料金所で普通車料金を出したり、 スーパーに乗って
行って駐車場に忘れて歩いて帰ってきたり、人に言えな話はある。
でも寒風、寒月の季節も笑いつつ、人の温もりを感じつつ凌いでゆ
くのだ。



⑦ 納 骨 の 旅
残 雪 や 二 百 年 輪 仄 明 し
ふ る さ と へ 納 骨 の 旅 春 の 星
ハ モ ニ カ を 吾 に 吹 く 子 や 春 の 星
川 鵜 来 て つ ん の め り た る 春 の 泥
地 図 に 辿 る 父 の 一 生 花 大 根
空 の 地 図 し か と 持 ち し か 鶴 帰 る
母 の 日 の 金 の 指 輪 や 折 紙 で
春 泥
春泥の頃は里が活気づく季節のひとつである。
普賢岳に僅かに残雪が見える中あちこちで耕転機が動き出すと、
俄に道路の様子が変わってくる。ふだんは舗装されたきれいな道
に、泥の塊が容赦なくぼとぼと、点々と転がり、へばりつき、そ
こに足跡がついたり轍ができたり…。少し白く乾いても、またす
ぐ新しいのが乗っかるのである。
田畑から耕転機や軽トラや長靴が運んできた春の泥、よく見れ
ば、猫車やリヤカーが頑張ったらしい泥跡や子どもや犬がさんざ
ん遊び散らしたに違いない痕跡もあって、 この道も一日を一生懸
命過ごした証のようにも思えてくる。泥には緑も目立つ。草の芽
やホトケノザ、イヌフグリなどがぺ っしゃんこにされたまま伸び
ていたり、花を咲かせていたりする。春を迎えた喜びはこんな所
にもある。
しかしである。小さな私の畑で今日も春の泥に長靴をかっぽん
かっぽんいわせていると、放射能に汚染されてしまったフクシマ
大地のことが、 三月十一日のことが、 しきりに思い出される。
痛みと怒りが沸き起こる。




⑧ シ ョ パ ン の リ ズ ム
雨 だ れ の シ ョ パ ン の リ ズ ム 梅 熟 る る
勢 ひ で 買 ひ た る 実 梅 一 抱 へ
昼 顔 や ろ ば の パ ン 屋 の 通 り ゆ く
昼 顔 や 海 を 争 ふ 日 々 百 年
百 日 紅 若 き 師 の 説 く 近 未 来
フ ラ ス コ の 花 瓶 に 岩 菲 理 科 教 師
地 下 鉄 の 大 東 京 や 金 亀 子
「 き ょ う だ い 」
ことしの伊東静雄賞は、鹿児島在住の山之内勉氏の作品「きょうだい」 であった。
きょうだいはいますか。/いません。 一人っ子です。/そう言
って何度姉を殺してきたことだろう。
と始まり、
なんだ姉さん。みんな、あなたを生きていた。/あなたは私た
ちを生きてくれていた。驚きと安堵、そして静かな涙。
と結ばれる。予防接種の後遺症のため、不幸な運命を背負ったお姉さんへの深い思いをうたった詩である。
受賞スピーチが心に沁みた。水を打ったような会場で誰も動かなかった。
「ただ二人の人に読んでもらいたくて書いた作品。 でも、その二人の人には読んでもらえない作品。文字の取得すらできない姉と、世間に姉をさらけ出したと怒り自分を勘当している父。しかし、伊東静雄賞を受賞したことで姉の人生が肯定されたような気がする。私は赦されたような気がする」と。
書くことは生きること。本物の言葉は心の底から生まれて育っていく…。そう思えてならなかった。
参考掲載 第二十八回 伊東静雄賞 受賞作品
『 き ょ う だ い 』
山 之 内 勉
きょうだいはいますか。
いません。一人っ子です。
そう言って何度姉を殺してきたことだろう。
セピア色に写った三人。若い父。若い母。切
り取られた小さな人。それを姉だと教えてく
れたのは遠い親類だった。予防接種の後遺症
で神様になったのだよ。寝たきりで口もきけ
なくて。お世話が大変でね。幼い神様には可
哀想だが一人で遠くへ移ってもらった。お腹
にいた君のためだとお母さんは泣いていたよ。
きょうだいはいますか。
います。寝たきりで口もきけない神様です。
そう言って何度父母を裏切ったことだろう。
でも私はオトウトになりたかった。父母に黙
って姉に会いに行ったのは結婚式の前日だっ
た。山深い初夏の緑の施設。どきどきしなが
ら初めて見た姉の顔は私にそっくりだった。
なんだ姉さん。鏡越しに毎日会っていたので
すね。あなたは私の中で生きていたのですね。
驚きと安堵、次に痛み、そして涙。
息子が五つになった時、姉に七五三の晴れ着
を見せに行った。初対面の甥と伯母は不思議
そうに見つめ合っていた。ひさしぶりに見た
姉の顔は息子にそっくりだった。なんだ姉さ
ん。あなたは私のそばに来てくれていたので
すね。驚きと安堵、そして涙。
きょうだいはいますか。
います。そう言っても寝たきりの母はもう怒
らなかった。弔いの後、山深い冬の施設に行
った。姉の顔は母そっくりになっていた。白
髪の模様も。しみの形も。前歯の抜け方も。
なんだ姉さん。みんな、あなたを生きていた。
あなたは、私たちを生きてくれていた。驚き
と安堵、そして静かな涙。



参考:伊東静雄の詩『そんなに凝視めるな』
そんなに凝視めるな わかい友
自然が与へる暗示は
いかにそれが光耀にみちてゐようとも
凝視めるふかい瞳にはついに悲しみだ
鳥の飛翔の跡を天空にさがすな
夕陽と朝陽のなかに立ちどまるな
手にふるる野花はそれを摘み
花とみづからをささへつつ歩みを運べ
問ひはそのままに答へであり
堪へる痛みもすでにひとつの睡眠だ
風がつたへる白い稜石の反射を わかい友
そんなに永く凝視めるな
われ等は自然の多様と変化のうちにこそ育ち
あゝ 歓びと意志も亦そこにあると知れ
⑨ 五 人 と 一 匹
鼓 打 つ ご と く 叩 き て 西 瓜 売 る
撫 子 や 稜 石 積 み て 鳥 の 墓
風 に 揺 る る 長 吉 長 兵 衛 へ ち ま 棚
草 の 花 子 に 従 は ず 鄙 暮 し
無 言 て ふ 万 の 声 あ り 草 の 花
分 校 は 五 人 と 一 匹 草 の 花
天 高 し 神 棚 に あ る 宝 く じ
西 瓜 愛
今年も西瓜の苗を五本植えた。師匠の教え通りに、何か埋める
のかという位大きな穴を掘り、鶏糞をたっぷり入れて土を被せる。
その上にしっかり苗を植え、祈りの手刀を切ってビ ニールの囲い
をつける。 この手順も三年目にしてスムーズになった。
西瓜の生命力は忽然と目に見え出す。 ビ ニールの囲いの内では
のんびり伸びるが、囲いの上に蔓がひらひらするようになるとそ
の時である。ビ ニールを外してやると、喜びに溢れるようにぐん
ぐん伸び始めるのだ。ある時西瓜は夜も伸びているに違いないと
気になって夜の畑に行ってみたら、伸びていますともと言わんば
かりに蔓をぴんと張り、西瓜は夜目にも緑だった。
西瓜の思い出は私には「家族」 である。若い父母や姉弟たちと
の昭和の暮し。 この年になっても鮮明なその思い出が毎年私に西
瓜を植えさせる。そして誰彼に食べさせて自分が喜びたいのであ
る 。
さてこれから私は鴉を見張らなければならない。暑さの中、厚
い西瓜愛を抱いて熱い草をむしっている私である。


⑩ 黒 葡 萄
鶏 頭 と 犬 と 眺 む る タ 焼 空
ソ リ ス ト の 喉 す べ り ゆ く 黒 葡 萄
葡 萄 売 る テ ン ト の 列 や 麓 ま で
竜 胆 や 媼 の 背 な の 寵 に 揺 れ
山 下 り る 子 ら 竜 胆 を 振 り な が ら
カ タ カ ナ の 電 報 遠 く 文 化 の 日
街 灯 の 早 も 灯 り し そ ぞ ろ 寒
拍 車
異常気象に拍車がかかってきている。目に見えて自然にも異変
が起こっている。
夏の初めうるさい程だった蝉の声がある時からぱたっと聞こえ
なくなった。早朝から元気な蝉の声といういつもの夏ではなかっ
た。聞けば度々の豪雨のせいだとか。地中で数年、やっと外へと
地表近くまで来た時の豪雨で溺れ死んだ可能性が高いという。無
惨としか言いようがない。
実りの秋の田んぼの様子も少々変だ。ジャンボタニシに幼苗を
やられ、あちこちにできた隙間を見れば、早朝から毎日網でタニ
シを掬っていたおじさん達を思い出し胸が痛む。
私も今年は草取りに追われた。萱やヒエが増えてすぐにのさば
るのだ。除草剤は使わないと決めているので遂に草払い機に挑戦
した。おっかなびっくりの虎刈り作業。 これも痛々しい。
胡椒屋さんは青唐辛子の味が変わったと首を傾げていた。昨日
初物で貰った青い露地みかんは少しスパスパだった。次には何が
くるか。急に秋めいてきた里の彼岸花を眺めながら少々怖い。


俺 の 名 刺
平 成 三 十 一 年 ・ 令 和 元 年
⑪ 白 菜 と 赤 子
星 月 夜 豚 売 ら れ ゆ く 高 速 道
磁 石 も て 針 さ が し を り 冬 日 向
白 菜 売 り 赤 子 と 重 さ 競 ひ を り
畔 話 白 菜 ひ と つ 手 渡 さ れ
悼 み 来 て 空 見 上 ぐ れ ば 枇 杷 の 花
ケ セ ラ セ ラ と ロ ず さ む 日 や 枇 杷 の 花
病 む 父 に 子 は 摘 み 来 し よ 寒 苺
コ ッ コ デ シ ョ
秋の長崎くんち、今年は椛島町のコ ツコデショも奉納された。
長崎港に近い椛島町は江戸時代宿屋が建ち並び江戸や大坂との交
易で賑わった。その中で大阪堺の船頭衆によって伝えられた堺の
「ふとん太鼓」がコ ツコデショの起源だという。
七年ごとの踊り町の順番。 コ ツコデショの前回の奉納は二〇一
一年東日本大震災の年であった。椛島町は今回特別な思いで太鼓
山を新調したという。七年過ぎた今も福島に変わらぬエールを送
りたいと福島県川内村の百年もののヒノキを譲り受けて。
四十人の男たちによって担がれた重さートンもの太鼓山はトバ
セ (走れ) マワレ (鳴門の渦だ) コ ツコデショ (宝の荷物はここ
だよ)と勇壮に天空舞を披露した。喝采の中、福島を思い浮かべ
た人も沢山いたに違いない。
くんちの後太鼓山は解体された。誰もさわれず大切に保存され
て七年後の出番を待つという。名残り惜しげに担ぎ棒を撫でてひ
とりがほろっと言った。 「木はだんだん乾いて少しずつ軽うなる
とよ。福島の大変さもそがんなれば良かなあ」

⑫ 海 は 青
パ ン ジ ー の あ ふ れ ゐ る 町 新 開 地
パ ン ジ ー を 植 ゑ る さ み し さ 消 す や う に
福 分 け と 媼 の く れ し 蕗 の 薹
遠 き 日 の 恩 師 の 声 や 蕗 の 薹
ス マ ー ト ホ ン に 白 旗 上 げ て 春 炬 燵
春 光 に 凱 旋 し て く る 校 旗 か な
大 根 の 花 の 十 字 や 海 は 青
女 主 人
秋の長崎くんちテレビ番組の取材が町にやってきた。
「笑ってこらえてダーツの旅」。
旅人は今をときめく俳優菅田将暉である。
放映を見て改めて、 テレビ取材に動じない人々の自然体と
潜在する故郷愛に感じ入った。
きわめつきは牡嘱小屋の女主人きよちゃんである。
彼女は夫の同級生。国道沿いの牡蠣小屋を娘さんと切り盛りし
ている。ブリキのバケツー杯の新鮮な牡嘱が三千円。薪の炉で焼
いて熱々を食べさせる。
突然現れた菅田将暉に「きゃっ」と叫んだ娘さんに対し、きよ
ちゃんは全く動じない。すばやく炉を整え、焼けた牡蠣の殻を自
ら開けてワンコそばのように次々と食べさせていく。
そして残念がる。 「もうちょっと先なら味が深まってもっと美
味しかとに」と。きよちゃんの心はひたすら美味の提供に向いて
いる。折々にわが家にも蕗味噌や花菜漬などを届けてくれる心で
ある。
別れが近づいたとき、きよちゃんのロから出た「家に泊まって
もらえたら…」 の言葉にはもっとご馳走したいのにとの気持ちが
ありあり。 いつか是非という菅田青年に「そん時は私の顔にもア
イロンかけときますけん」。見事な女主人ぶりであった。



⑬ 俺 の 名 刺
集 落 を あ げ て 野 焼 く や 峡 深 く
こ の 土 が 俺 の 名 刺 と 春 田 打 つ
終 電 の 出 て が が ん ぼ の 駅 と な る
ひ と り ぼ つ ち 水 族 館 に 海 月 見 る
蟇 鳴 く や 里 い ち め ん の 水 明 り
耕 転 機 ゆ る り と 止 ま り 蟇 わ た る
片 恋 の 五 月 の あ り し 汽 車 通 学
野 焼
諌早市大場町、諌早市内で一番標高の高いこの地には草原が点
在する。環境省の 「生物多様性保全上重要な里地里山」に指定さ
れている岩屋口草原(約百十ヘクタール)はとりわけ貴重な草原
で、 ここでは秋の七草がほぼ全種見られるという。
早春二月、野焼を見に出かけた。野焼は集落の住民のみで行う
というのが百年来の不文律。現在十二戸、最年少は五十二歳だそ
うだ。
まず晩秋に草を刈って作った上部の防火帯から火が入る。
パチパチ草の燃える音がたちまち大きくなり、下に向かつて火が走り
始めると今度は下の防火帯から火が入る。下る火と上る火、美し
い火焔は草原の中央で出逢うとやがて静まり、あとには綺麗な台
形の末黒野があらわれた。
草が牛の餌や茅葺き屋根に使われた昔と違い、野焼は今、集落
の日当り確保、山火事防止 (草原が防火帯の役目) のため、 そし
て何よりも集落の人々の 「文化の継承と誇り」である。草原は放
っておくと森になる。暮しの中で人の手が作りあげる草原という
美しい風景を無くしてはならないと私も強く思う。



⑭ あ れ や こ れ
若 竹 の 箸 の 香 れ り 山 の 飯
渓 谷 を 七 曲 り 来 る 鮎 の 川
古 里 の 川 に 父 と 子 鮎 を 釣 る
笹 芭 の 鮎 届 き た る 解 禁 日
金 魚 み な 名 前 で 呼 ば る 小 学 校
金 魚 屋 の 主 バ ッ ハ を 聴 く 青 年
空 蝉 や 子 の 残 し た る あ れ や こ れ
鮎 の 川
鮎釣り名人の顔が冴えない。鮎の棲む境川に川鵜が増えて、稚
魚を放流しても彼らに食べられてしまうというのである。川鵜が
見られるようになったのはここ数年らしい。川がどんどん変わっ
ていくよと言うロぶりからは川鵜のことだけではないと解る。
鮎釣り名人は、漁協から「あまり釣ってくれるな」と頼まれた
という逸話の持ち主である。少年時代は流れに石を積み、鮎を追
い込んで手で掴み取ったものだとか。古自転車の部品でのぞき眼
鏡を作ったり、取った鮎は笹竹に通すのが慣だったとか。そんな
話は何度聞いても楽しい。美しい川が目に浮かぶ。
境川は多良岳を源流とし、 町の中心を流れる川である。水量が
豊かで昔も今も水は澄み、初夏には蛍が乱舞する。しかし鮎は稚
魚の放流で生命をつないでいるのが現状だ。川が帰る海を失った
からである。鮎は、産卵された稚魚が海に下ってプランクトンを、
餌に育ち、春に遡上するから生息できなくなるのは当然と言える。
「上流をダムで切られ、下流は堤防で閉め切られ、 これで川と
言えるのかな」という言葉は実に重い。

⑮ 峡 の 空
立 秋 に 届 き し 手 紙 手 漉 き 和 紙
鮭 の 身 の 立 つ ほ か ほ か の に ぎ り 飯
三 さ い の お て が み ご つ こ ほ う せ ん か
燕 帰 る そ の 日 を 記 し 農 暦
秋 燕 や 青 深 深 と 峡 の 空
燕 帰 る 幼 ひ と り の そ を 知 れ り
鈴 虫 や 介 護 ホ ー ム の 夜 の 早 し
燕 帰 る
友人の山の家は戸ロの一番上のガラスが一枚きれいに外されて
いる。
土間の上に巣を作った燕のための入ロである。都会から帰
郷した彼がここで農業を始めてから十数年。今年もここをくぐつ
て燕はやって来て、先日、十羽にも増えて、 ここから南に帰って
いった。
初めはすぐ崩れていたという巣も板で補強され、今や古
巣の貫禄である。
帰燕の時はわかるそうである。何となく周囲がザワザワし始め、
やがてどこからともなく燕が集まってくる。今年など五十羽余り
が高い電線に並んだという。最後に飛び立った一羽は小さくて遅
れまいと必死の気迫だったと友人は目を細める。
雛の巣立ちの時も仲間の燕がやってくるそうだ。お祝いの虫を
持って? と尋ねると、それは無いよと笑っていたが、来年は目
を凝らして観察するに違いないという気がした。彼の話はいつも
詩集のようである。
お隣の納屋の燕もスーパーの入ロの燕も、ある日忽然と見えな
くなった。みんな今頃どのあたりを飛んでいるだろうか。あの小
さな体で東南アジア辺りまでの長い旅…無事を祈るばかりである。

⑯ 小 鳥 来 る
初 秋 刀 魚 父 の 忌 日 の 近 づ き ぬ
大 釜 を 磨 く 媼 ら 小 鳥 来 る
小 鳥 来 る 開 け 放 た れ し 農 具 小 屋
渡 り 鳥 龍 の ご と く に 明 け の 空
草 刈 る 手 止 め て 見 送 る 渡 り 鳥
黒 板 に 広 が る 世 界 夜 学 生
帆 船 の 来 る 海 原 の 蝶 の ご と
父 と 私 と 秋 刀 魚
秋刀魚は子どもの頃よく食べた魚である。父の好物だったせい
かも知れない。晩酌にご機嫌の父はよく秋刀魚のうんちくを語っ
た。刀のように見えるだろうとか、 目黒の秋刀魚とか。
家族七人のために母はいつも四匹を買い、 父に一匹、 後の六人
は半切れずつである。頭の方が当たった子どもが苦いと言うと、
父はどれどれと嬉しそうに腸を食べてくれたものだ。
ある日、七輪の火起こしを言いつけられた私は、焚き付け用の
反故紙の中に一枚の書き損じらしい手紙を見つけた。
「やよ子へ 君は……」と書き始められた言葉の新鮮さに思わず手に取って広げると、 それは前日何かでひどく母に叱られた私を父がかばって
くれているものだった。なぜ父がこんな手紙を書いたのか、 いや
果たしてちゃんと書き上げられて母の手に渡ったのか……。今でも不明である。 でも十分である。姉弟の中で一番叱られ者、自分は
貰われっ子かもとずっと思っていたが、 心にぽっと灯がついた。
見てはいけなかったような気がして、七輪に放り込んだこの紙切
れを、以来ずっと私は胸に抱き続けている。
秋刀魚の腸を食べると、 父の顔が浮かぶ。

掌 の か た ち
令 和 二 年
⑰ 行 幸 の ご と く
初 小 春 日 や ホ ー ム の 窓 の み な 開 き し
師 の 文 の 青 き イ ン ク 字 竜 の 玉
渓 流 の 鴛 鴦 追 う て ゆ く タ 日
行 幸 の ご と く 大 河 の 鴛 鴦 の 列
綿 虫 や 迷 ひ 込 み た る 坂 の 町
三 尺 の 寒 鯉 見 む と 着 ぶ く れ て
寒 鯉 を 見 む と 人 寄 る 太 鼓 橋
文 字 と は 日 本 語 と は
新聞のコラムに載った夜間中学の話が胸に泌みた。学校に通
えなかった高齢の人たちの教室。最初の日に黒板に「ちち は
は」と大きく書いたらそれだけで涙ぐむ人がいた。母の点々はお
っぱいだからねと言ったら、 「場所が違うんでは?」 「そんなの
表に出して良いものかね」と返ってきた、と。
先日、文芸コンクールの中高生の随筆原稿にふれる機会があっ
た。まず読むのに苦労した。文字が小さい、鉛筆が薄い、文字の
判読に苦しむ…。 ハズキルーぺをかけた上で虫めがねまで登場で
ある。 パソコン、 AI時代の子ども達にとって文字とは日本語と
はどんな存在かと頭の隅で考えさせられ続けた。子どもの頃読ん
だ、確かクレオの「最後の授業」で、先生は「国を奪われても母
国語を忘れない限り牢獄の鍵を握っているようなものだ」と諭し、
その言葉を私はずっと忘れられなかった。そうだと思う。
高校での 「文学の選択制」が問題になっている。便宜ばかりを
追う社会が、文字や言葉が醸してくれる豊かな時間を、豊かな社
会を、益々子ども達から奪っていくのではないかと私も危恨して
いる。

⑱ 掌 の か た ち
少 年 の ひ み つ 鳥 の 巣 見 つ け た る
鳥 の 巣 や 窪 め た る 掌 の か た ち し て
春 分 の 日 の ペ ン 先 の 影 淡 し
段 畑 の そ の 天 辺 の 揚 雲 雀
揚 雲 雀 ナ ナ ハ ン バ イ ク 疾 走 す
白 魚 を 食 べ て 散 り 散 り 赴 任 せ り
白 魚 和 え 祖 母 の や さ し き 手 の 記 憶
子 年 考
嘘か本当か解らない話。赤ん坊の時に私はねずみに醤られたと
祖母や母の昔話で語り継がれたこの話は、今でも家族や身内でね
ずみの話題になる度に出てきて皆笑い転げる。子年の二女が一番
大笑いする
今年もきっとと思っていたら暮れに夫が入院。静かな年末年始
に私はひとりで赤ん坊の自分を思った。ねずみの話で笑い転げて
いた普通の日々の有難さを思った。
そんな時、友人の書いた短編小説「餌食」が新春文芸賞を得て
新聞に掲載された。舞台は諌早多良の森。リスクを承知で生きる
ために餌に邁進する赤ネズミの行動に「生きるためには勇敢なだ
けでも臆病でも駄目。細心の注意と判断力、何より目立たないこ
とが大切」と悟り、クルド難民キャンプへと旅立つ青年の話であ
る。
朝タ眺める森の小さな赤ネズミを私は初めて意識した。美しい
森の中の厳しい食物連鎖、強者と弱者の現実は、人間の世界にも
あてはまる。よだかの星は今も輝いているか、窮鼠猫を噛む程の
気魄が私にあるか…。そんなことも考えた新年である。

⑲ 種 を 蒔 く
目 覚 ま し 時 計 胸 に 抱 き ゐ し 朝 寝 か な
種 蒔 や 育 苗 箱 の 長 き 列
遠 山 は む ら さ き 里 は 種 を 蒔 く
剪 定 の 鋏 の 音 や 二 人 ら し
風 船 の バ ス に 乗 り く る 日 曜 日
二 人 展 始 ま る 画 廊 夏 初 め
画 廊 よ り ひ ら り と 白 き ワ ン ピ ー ス
小 さ な 仏 壇 の 話
五十年以上も前の十二月。 ひとりの青年がとある仏壇店を訪れ、
小さな黒檀の仏壇を手に入れた。代金は冬のボーナスのほぼ全て。
その年、教員になったばかりで、初めての夏のボーナスでは手が
届かず、仏具店の主人に頼んで待ってもらっていた品だった。
彼は三歳で実母を亡くした。幼い男の子三人を残された父親はま
もなく再婚したが、新しい母が来たその日、彼は大暴れして庭の
柿の木に括られたとか。
覚えていないとめったに亡母の話はしなかった彼が唯一ロにし
ていた話である。食べるだけで精一杯だつた戦後の時代、亡母の
位牌は箪笥の上に飾られていたらしい。ボーナスをはたいたその
日、仏壇に母の位牌を納めた彼の胸中は如何ばかりだったか。
それから三十年余、実家に新しい大きな仏壇が来て、小さな仏壇
は御用終いとなった。でも仏壇は青年の家でアンティークめいた
インテリアになった。
今年三月十七日、久しぶりに仏壇の扉が開けられた。七十九歳
になった青年が人生を全うしたのである。彼が帰るべき場所はま
ずここだと家族には思えたのである。小さな仏壇のアナザーヒス
トリー。

⑳ 青 時 雨
お 出 か け の 一 家 と り ど り 夏 帽 子
子 は 父 の 麦 わ ら 帽 子 被 り た く
飼 育 科 の 生 徒 揃 ひ の 麦 藁 帽
新 し き 卒 塔 婆 を 濡 ら す 青 時 雨
白 靴 や フ ラ ン ク シ ナ ト ラ 風 の 人
白 靴 や 渓 の 吊 橋 渡 り 切 る
カ タ カ ナ 語 溢 る る テ レ ビ 積 乱 雲
兼 題 「 白 靴 」
玄関に並んだ五才の孫の靴。きれいなピンクにアニメの絵柄、
何だかあちこちキラキラしている。子の母によると「疾風」とい
う名までついているそうな。
本当に最近の靴コーナーは色とりどりだ。白い運動靴など探す
のに苦労する。駅伝やマラソンの選手の靴も蛍光色鮮やかにぴょ
んぴょん跳ねている。
白い運動靴で青春時代を過ごした私の一番の思い出は土曜日の
靴洗いだ。母の下命で、姉弟四人、運動靴と上靴をごしごしと洗
ったものだ。靴などそう頻繁に買ってもらえるものではなかった。
村には父が利用する靴の修理屋さんの小さな店もあった。
兼題の「白靴」に思い巡らすうちに、浮かんできた思い出があ
る。 NHKの確か「私の宝物」という番組。その回に登場した老
夫婦の宝物は、紫の袱紗に包まれた小石だった。 一人息子が特攻
隊で出撃する時、細々と靴修理の店を営む身では旅費を工面する
ことが出来ず、会いに行けなかった。戦後、やっと知覧の記念碑
を訪れた日、 ここを息子が歩いたかもとこっそり拾って持ち帰っ
たものだと。
なかなか俳句はできないが、兼題に難行苦行する時間が、私に
とっては豊かな時間のような気がする。 (了)

㉑ シ ン プ ル に
草 刈 つ て 捨 田 の ー つ 現 れ し
シ ン プ ル に 生 き む と 思 ふ 冷 奴
ご 苦 労 と お の れ 労 り 冷 奴
夏 空 や 合 宿 拠 点 の 大 食 堂
ス リ ッ パ は ロ コ コ 花 柄 夏 館
ひ つ そ り と 都 の 食 堂 水 中 花
ま だ 手 離 せ ぬ 亡 き 母 の 流 燈 よ
草 刈
長梅雨、豪雨、尋常ではない雨の降り様で、私の小さな畑の草
の伸び方も尋常でない。怖るべしという勢いのまさに「席巻」 で
ある。
たまの雨上がりに草取を決意したが、 むんむんたる湿気は耐え
難く、ぬかるみに足をとられ、根にしこたま泥を抱えてくる草の
重さに予想以上の体力を強いられた。体力、気力の限界、「今年
は畑を捨てる」とすぐに白旗、捨畑宣言である。
雑草のせいだけではない。避難勧告や指示が度々出る日々、ト
マトも茄子もオクラも七割方倒れ実の損傷がひどい。未練と痛み
はあるが自分大事を取るのだ。
かくて私の畑は草取りの段階を越え、かなりの草刈を必要とす
るところへきている。それでも放っている。あの草の中、南瓜や
西瓜が隠れているかもと眺めながら。
雨の合間に絶えず草刈機の音が聞こえてくる。その威力たるや
凄い。まさに、
草 刈 機 私 語 諸 と も に 薙 倒 す 谷 口 鐘
である。しかし数日すると刈り跡に早や緑がぐんぐんと…。 これ
も凄い。 この強さ、めげなさこそが今必要だなと納得である。 (了)


㉒ ア フ リ カ の 切 手
新 米 や 塩 む す び し て 一 日 め
新 米 の よ き 名 並 び し 出 荷 か な
み ど り ご の 初 お 目 見 え や 秋 祭
長 老 の 杖 の 指 揮 め く 秋 祭
百 年 を 変 は ら ぬ 里 や 松 手 入
ち ぎ れ 雲 秋 の ゆ き 交 ふ 交 差 点
ア フ リ カ の 切 手 見 て を り 文 化 の 日
新 米
九月末、数日で稲田の黄金色が一気に深みを増し、どつしりと
なった。 温かみのあるグラデーションが里一面に広がって、 つい
足を止めて眺めるほど美しい。もうすぐ稲刈りが始まる。今年も
ちゃんとここまできた。
これまでは螢が飛んだら田植え、町民運動会が終わったら稲刈
りと言われてきたが、近年の異常気象でずいぶん様変わりしてい
る。今年は六月の豪雨続きでなかなか田植えができなかった。連
日水路は水が溢れるように流れ、青蛙が手足を広げて流されてい
くのを見かけたりすると切なかった。その姿が、なすすべ のない
人の姿にも思えた。
やっと田植えをした後の猛暑、稲はぐんぐん伸びたが、水の見
回り、ジャンボタニシの駆除、消毒、畔草刈り…。農家の人の朝
は早かった。 そしてつい先日の 「これまでに例の無い猛台風」 で
ある。
毎年収穫したばかりの新米をご近所や知人からいただく。 「う
ちのお米食べてみて」と渡してくれる笑顔が新米と同じように輝
いている。わが家ではまず塩むすびを作る。おかずは自家製漬物
と味噌汁だけ。大切なことを忘れないためのささやかな祝祭であ
る。

実 り の 色
令 和 三 年
㉓ 星 の ベ ル ト
小 春 日 や 板 塀 に へ の へ の も へ じ
冬 構 牛 舎 を 回 る 槌 の 音
犬 小 屋 に 毛 布 重 ね る 冬 構
鯨 屋 て ふ 店 や 主 の 長 者 眉
星 の 子 は 星 の ベ ル ト を 聖 夜 劇
七 種 粥 野 の 明 る さ を 摘 み 入 れ て
寒 稽 古 ま こ と ち ひ さ き 剣 士 カ ゐ て
鯨 屋
旧商店街の端っこに小さな鯨屋が健在である。 「くじら」と白
抜きされた赤い職が立っている。 以前はゴム エプロン姿の小柄な
主がいて様々な肉やベーコ ンが置かれていたが、今は冷凍ケース
が二つ、あとは小豆や昆布、蒟蒻、煎餅も蝋燭も売っている。
この町に住みついて初めて鯨の肉に目覚めた私も折々に煮〆鯨
を買いに行く。その中で、あの主は体調を崩して店を切り回せな
くなり、娘さん夫婦が後を引き受けていること、 それは地元の人
の「店を止めんで」 の声に応えてのことらしい、 でも主特製のベ
ーコンはもう姿を消した…などを知った。
私は大いに納得した。 この店の鯨肉はほんとに美味しい。そし
てこの町の、とりわけ年長者には鯨は欠かせない味だ。筍が出れ
ば、新じゃがを掘れば、南瓜も勿論鯨で炊く。 「鯨は入っとん
ね」は美味しいの代名詞のようなものなのだ。少量を上手に使い、
媼たちの作る煮〆、豚汁、まぜ飯…その味には百年経っても敵わ
ないなと思ってしまう。
鯨屋は町の人の必要に応え、 必要な形になって残っている。赤
い幟は温かい気持ちもくれる。



㉔ 雲 ひ と つ
冬 木 の 芽 門 開 け ら る る 刻 を 待 ち
草 染 め の 草 摘 む 土 手 や ち ぎ れ 雲
摘 草 や 修 道 院 の 広 き 庭
摘 草 の 少 女 子 山 羊 の お 当 番
豆 腐 屋 の 小 上 が り 占 め る 春 炬 燵
雲 ひ と つ 眺 め て 入 る 大 試 験
大 試 験 待 つ 講 堂 や 大 時 計
大 試 験
タ方の ニ ュースに、大学共通テストのためフ エリーで長崎市へ
向かう離島の高校生の姿が映し出された。高校生たちは思ったよ
り明るい雰囲気を漂わせていたが、見送りの父母の表情には胸を
つかれるものがある。
何十年も前の私の受験の日の朝、 「これ」と言って、 母が差し
出したのは、父が肥後守できれいに削ってくれた三本の鉛筆だっ
た。 「家から通える国立」という条件で大学受験を許してもらつ
た私には一回きりのチャンスだった。Ⅰ期の受験の日には急性盲
腸炎で病院のベ ッドにいたからである。
しかし私は大失敗をやらかした。試験終了のベ ルで会場を出よ
うとした時、試験官に肩を叩かれたのである。 「名前を書き忘れ
ていましたね」と。解答用紙に名前を記入するより先に問題へ飛
びつかせた「正宗白鳥」は忘れられない。幸運を得たことの記憶
としても。
コ ロナ禍の中で受験生も翻弄された。 一点百人の世界。何がど
う転ぶかわからない一発勝負。確かに人生の分かれ道に立つ時だ。
どんな形で春が来ようともそこに希望の芽を見つけてくれること
を祈りたい。


㉕ 善 女 の 列
た ん ぽ ぽ の 顔 や ア ス フ ァ ル ト の 割 れ 目
潮 干 狩 お と な し き 子 の は つ ら つ と
潮 干 狩 足 裏 く す ぐ る 砂 の 息
入 学 の 子 の 嬉 し き は 定 期 券
野 花 摘 み 善 女 の 列 や 仏 生 会
耕 耘 機 下 り て 急 ぐ や 仏 生 会
虚 子 の 忌 の 踏 み ど こ ろ な き 落 椿
潮 干 狩
子どもの頃、福岡の志賀島に住んでいた。玄界灘に囲まれた海
の幸の宝庫、お陰で魚好きに育った。家のすぐ前が遠浅の海で春
になると潮干狩が日常の遊びである。たいてい服をびしょ濡れに
し、戦利品を手に揚々と帰ってくるのだが、 干潟の砂はさらさら
と銀色に光り、ちっとも汚れた気分はしなかった。
母は戦利品の貝や蟹、海藻などをこまめに料理し、夕餉の膳に
のせてくれた。浅蜊はバケツに海水を入れ、新聞紙をかぶせて一
晩砂を吐かせる。夜中、貝の口を開けて這い出してきている白い
にょろにょろした姿を見たくて新聞紙をめくり、顔に海水をかけ
られたこともある。味噌汁や清まし汁を堪能すると貝殻はおもち
ゃ。時に父母も一緒に浜に出た。大いに楽しみつつ、貧しかった
時代に、あの潮干狩は結構な家計の足しになっていただろう。
夫の定年後諌早に移り住んだ。干拓事業で目の前の海を閉め切
られた私たちの町からは潮干狩の光景も消えた。堤防の外海に辛
うじて残った浅瀬に、初夏赤い幟が立ち潮干狩場ができる。浅蜊
を放流して有料である。
潮干狩、ああこれも私から遠くなってゆく。

㉖ 歌 ふ ご と
目 薬 の 零 れ て ば か り 柿 の 花
水 明 か り 里 は 早 寝 の 夏 越 の 夜
草 の 香 の ほ の と 夏 越 の だ ん ご か な
鬼 灯 市 狐 も ま ぎ れ て を り さ う な
歌 ふ ご と 鬼 灯 市 の 下 駄 の 音
パ リ 祭 は 遠 し 田 畔 の 草 を 刈 る
ヴ ァ イ オ リ ン 聴 く カ フ ェ テ ラ ス パ リ ー 祭
小 崎 登 明 さ ん
四月、長崎はまたひとり大 切な語り部を失った。
小崎登明さん、享年九十三歳。 カトリック修道士であり、 コ
ルべ神父の研究者であり、 聖母の騎士学園の校長も務めた人。そ
して文芸を楽しむわが町の住人だった。
小崎さんは異色の語り部だ った。被爆直後、小さな子から助け
を求められても振り切り、自 分をいじめた先輩が大怪我に苦しむ
姿にはいい気味だと思ったと自分の弱さを隠さずに語った。
一月に勝臓がんが発覚し長崎の聖フランシスコ病院のホスピス
に暮らし始めた小崎さんは三月末に長崎平和推進協会主催でのオ
ンライン講話をした。語り部最後の日を自覚しての涙ながらの心
情吐露だったという。
「焼け野原を歩きながら優越感というかエリート意識が湧いて
いた。なぜそんな気持ちを持ったのか。 目の前でたくさんの人が
死んでいるのに」と。 そして被爆者の心を研究する被爆心理学の
必要性を指摘した。
七月、 八月の長い慰霊の月がもうすぐ始まる。小崎さんの思い
を粛然と受けとめ繋いでゆか ねばと思う。


㉗ 実 り の 色
七 タ や 自 転 車 漕 ぎ て 会 ひ に ゆ く
父 と 子 の 七 タ 教 室 屋 根 の 上
七 タ や 星 に な り た る 人 の 数
消 え な む と 千 の 雫 や 大 文 字
大 文 字 闇 に し み じ み ひ と り な る
山 峡 の 実 り の 色 や 敬 老 日
吾 亦 紅 晩 年 良 し と わ が 手 相
伊 東 静 雄 の 手 紙
「先日は久しぶりにお顔見ることが出来、うれしくなつかしか
ったです。二年の仰臥生活の後見る旧友のなつかしさといふもの
は…」
「さっき、看護婦さんが、ああシンドといって大きい木箱を持
ちこみました。あっ舞鶴からと…」
こんな書き出しの二通の手紙が七月から諌早図書館で公開され
ている。詩人伊東静雄が昭和二十六年に入院先から旧友木下昇氏
に宛てたもので長く未発表だった手紙である。木下氏は佐賀高等
学校、京都帝大で伊東が親しくつきあった同級生、文学を通して
の仲間ではない。
「私はもうあきらめて出来るだけ心やすらかに死ぬことの工夫
をして参りましたのに…」などと詩人仲間に書き送っていた伊東
にこの旧友との再会が如何ばかりのものだったか。手足を一寸動
かすにも心を用いよとの医師の厳命の中、仰向けで書いた二通の
手紙には喜びが溢れている。
それにしてもと思う。伊東静雄ほど、 その書簡類がたくさん残
されている文人はそうそういないのではないか。読み捨てるには
惜しい魅力をその文章が持つからではないか。諌早人の身びいき
だろうか。



そんなに凝視めるな
伊東 静雄
そんなに凝視めるな わかい友
自然が与える暗示は
いかにそれが光耀にみちてゐようとも
凝視めるふかい瞳にはつひに悲しみだ
鳥の飛翔の跡を天空にさがすな
夕陽と朝陽のなかに立ちどまるな
手にふるる野花はそれを摘み
花とみづからをささへつつ歩みを運べ
問ひはそのままに答えであり
耐える痛みもすでにひとつの睡眠だ
風がつたへる白い稜石の反射を わかい友
そんなに永く凝視めるな
われ等は自然の多様と変化のうちにこそ育ち
あゝ 歓びと意志も亦そこにあると知れ
昭和12年「知性」12月号に掲載
㉘ 奮 戦 の 跡
台 風 と 奮 戦 の 跡 鬼 瓦
す ん な り と 持 て ぬ 海 鼠 の 網 袋
売 り 上 手 笑 ひ づ か れ の 酉 の 市
た こ や き で ほ か ほ か 祝 ふ 七 五 三
七 五 三 記 念 登 山 の 大 家 族
タ 時 雨 山 河 消 し ゆ く 芭 蕉 の 忌
芭 蕉 忌 や 枯 野 の 空 の 太 白 星
翁 塚
さ ざ 波 や 風 の か ふ り の 相 拍 子 翁
わが町にも松尾芭蕉の句碑があると知ったのは去年の今頃であ
る。 「翁塚」 の名を気にもとめず訪れた旧深海村塩屋崎観音堂。
その境内の一角に、小さな塚を持つ句碑が雲仙岳の見える海に向
かって建っていた。 ここは多良岳の熔岩が流れ出して有明海へ突
き出した断崖絶壁。かつては鷲の飛び立つような老松が一面を覆
っていたという。
郷土史に「深海村は江戸時代から風雅の人多く、鍬を手にしつ
つ俳句を詠じた」 の一節がある。長崎深堀藩の飛地で下級武士た
ちの郷は諌早一撲の舞台ともなったが、観音堂は句座の場でもあ
ったらしい。
この風雅は連綿と続き明治中期以降の諌早俳壇を背負った荒川
一々を生んだ。彼の師桐子園竹外は芭蕉の孫弟子であったとか。
荒木一々は三十二歳の時「奥の細道」に感動し自らも奥州を巡遊、
芭蕉の歩いた道を辿りながら多数作句している。
翁塚の前に立ち故里の先人たちを思うと「風のかふりの相拍子」
が涼やかに聞こえてくる気がする。
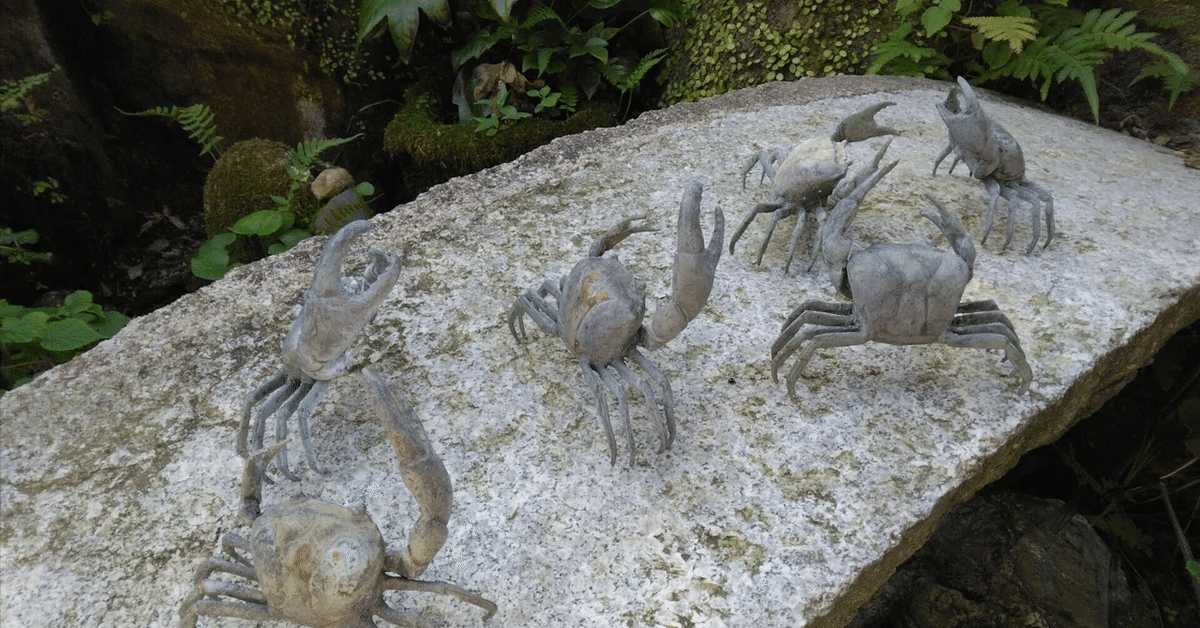
銀 の 鈴
令 和 四 年
㉙ な み な み と
城 下 町 ち ひ さ き 羽 子 板 市 の 立 ち
冬 ざ れ や 写 真 に 残 る 画 鋲 あ と
仔 牛 生 る 牛 舎 も メ リ ー ク リ ス マ ス
往 診 の 医 師 の 自 転 車 ク リ ス マ ス
元 日 の ま こ と 真 白 き タ オ ル か な
若 水 を 掬 ぶ 希 望 を つ つ む ご と
若 水 や 犬 の 椀 に も な み な み と
ク リ ス マ ス 生 ま れ
わが家の犬はクリスマス生まれである。夫が膵臓癌の手術をし
た年に生後二ケ月でわが家の一員になった。夫は犬嫌いだったが、
娘たちが強行突破した。 「クリスマス生まれよ、すごいでしょ。
みんなで散歩に行こうよ」と掌に乗る程の仔犬を夫の胸におしつ
け有無を言わせなかった。
名前はお父さんが、と命名権を貰った夫は満更でもなさそうな
顔で「むさし」と名づけた。そのときは娘も私も夫でさえも「ク
リスマス生まれ」 に希望を見ていたのだ。
犬のいる暮しが始まって想定外だったのはクリスマスが様変わ
りしたことである。もはやクリスマスは「むさし」 の誕生会、 星
の輝く幻想的な雰囲気は一切無くなった。しかし夫と「むさし」
はつかず離れずの良好な関係を作り、夫は術後十五年を生きた。
十六才になった「むさし」は最近どうやら耳が聞こえないらし
い。背後から近づくと飛び上がって驚くし、 目も少々白味がかっ
てきた。だがそれを苦にしたり落ち込んだりは全く無い。クリス
マス生まれはやはり格が違うのかと私はわが身を恥じている。 (了)


(つづく)
付録:『諫早文化』第16号に掲載された津田緋沙子さんの短歌とエッセー
「高来町三部壱日記」
わが家の目の前は有明海に向かって田んぼが堤防の所まで
広がっている。その先は諌早干拓の調整池。遠く普賢岳の姿
も見える。道草好きの犬を連れて毎朝田んぼ道を散歩する。
季節の移ろいと人の暮らしをしみじみ感じさせてくれる道で
ある。
白鷺の親子伴ひ耕転機
三月の田を打ち起こしゆく
早春の田んぽの畔はにぎやかだ。ホトケノザ、イヌフグリ、
カラスノエンドウにスズメノエンドウ、ときどき土筆も顔を
出している。朝日をあびて草の露は煌めく。
田んぽの土は黒味を帯びている。「冬に何回も打ち返して
息ばさせとるけんで、よか性格になっとる。」農業委員長の
長老の言葉だ。
田植え準備の田起こしが始まると田んぼの虫目当てに白鷺
が増えてくる。今年生まれの子鷺も一人前に土をつつく。耕
転機について回り、後ろに飛び乗ろうかとする豪の者もいる。
しかし、耕転機の主はさして気にする風もない。この地に住
み始めた頃はこの光景に家族をあげて大騒ぎし感激したもの
だ。
八十八夜の頃、水門が開けられ多良岳の水が一斉に田んぼ
に流れ込む。満々と水を湛えた田んぽは急に広くなったよう
に感じられる。青空を映し山を映し白い雲は水面を流れて行
く。ぷくぷくと小さな泡は生き物たちの目覚めか。夜になる
と水明かりが静かに里を包む。
水路奔る梅雨の豪雨や青蛙
手足広げて流されていく
「蛍が飛んだら田植え」と言われているが、去年は早い梅
雨入りと度々の豪雨で、植え付けが遅れたり植え直しをした
りと、農家の苦労は手に取るようだった。離農、農業従事者
の高齢化、耕作放棄地の急増など現代の農業の抱える問題は
この里にも顕著である。
ある時夜道を帰っていく耕転機にライトが点いていて吃驚
したことがある。牛が鋤を引いているのを覚えている私は田
んぽの仕事は日中と思い込んでいた。近所の山守の長老は「い
つの時代の話な」と笑い飛ばした。「この前見た耕転機は八
百万円やった。運転席は冷暖房つきでさあ…。」後はしんみ
りした口調になる。「機械を使えば楽さ。あがん上等は広か
農地向きにできとる。でも良かとば見れば良かとの欲しゅう
なる。若か頃は兼業して勤めの給料で機械代ば払いよったけ
ど、年取ってやめればねえ。きつかよ。」返す言葉もない。
田植機のふしぎを飽かず眺めゐる
幼は朝の光の中に
農家の人の朝は早い。夜明けと共に水の見回りをしたり大
きな網を持ってジャンボタニシの駆除をしたりしている。消
毒、畔の草刈り等々暑い日中の仕事も尽きない。台風の来る
夜に田んぼの傍らに停んでいる人を見かけて胸をつかれる。
それでも田んぼの道を歩いていると希望の種を発見する。
農作業についてきて畔で遊んだり田んぼの生き物にふれ
あったりしている幼い子たち。家族総出の田植えや稲刈りで
一人前の働きをしている中学生、高校生たち。彼らが農業に
生きる祖父母や父母たちの心を理解し、忘れずにいてくれな
いか。
田んぼの中にコスモスの道を作ったり、野菊や姫百合は残
して畔の草刈りをしたり、用水路に蜆を放流したり、稲刈り
後お役ご免の案山子を川の番人にしたり…、里の人たちのこ
の遊び心は、苦境を何とか乗り越えていく力をも生み出すの
ではないか。
新米の出荷告げゐる有線の
声晴れ晴れと山に谺す
九月の末になると田んぼは二、三日で色づき始める。温か
みのある黄色のグラデーション。実りの色は足を止めて見
入ってしまう程美しい。今年もちゃんとここまで来たなと思
う。
稲刈りも結いの作業だ。田んぼの端っこの、機械が回りに
くい所の稲が鎌で刈られ畔に並ぶと明日が稲刈りだなとわか
る。早朝から軽トラックの列ができ、大きな話し声や笑い声。
機械が来るとあっという間に稲刈りは進んでいく。刈るばか
りか田んぼの中で稲扱きをして籾にまで仕上げてしまうのだ。
ぼんやり眺めながらふと気がついた。今年はれんげ畑も案
山子も稲架も見かけなかった。これもコロナのせいなのか。
月代の道帰りゆく藁車
里はしづかに秋収めゆく
刈田の藁の匂いは何故か懐かしい。どこかで藁くずを燃や
している煙の匂いも懐かしい。
荷台に堆く藁を積んだ車が何台もタ暮れの田んぼ道を帰っ
ていく。サイロの飼料のように丸い形にまとめられて乗せら
れているものもある。藁車が通ると今年の米作りは終わりと
いうこと、秋収めである。刈田には切り株から芽を出した穭
が青々としている。たかだか十数センチなのに短い穂を出し
ているものもある。秋納めの田んぼは少し寂しい。でも美し
い。惜しみない労働が生み出した一枚の絵だ。 (了)
追 悼
何と言ったらいいのだろう。
津田さんの悲報に接して、言葉が出てこない。
津田さんの『海山村Ⅱ』をノートに掲載し出したのも、
少しでも、あなたの療養の励ましになればとの思いからだった。
願いむなしく、私たちの思いは届かなかった。
もうあなたと話せないと思うと、なんとも言いようのない
寂寥の思いが込み上げてくる。
とっても、チャーミングな人だった。
笑顔がとびっきり素敵な人だった。
痩せて小さな体、おかっぱの髪型にくりっとした大きな瞳。
決して弱音を吐かず、後ろ向きな言葉を聞いたことがない。
朗読がとても上手だった。
伊東静雄の詩を読むあなたを、幾度となく羨望の眼差しで眺めた。
いつでも、周りの人たちを気遣い、励まし、協力を惜しまず、
そして、何に対しても前向きな姿勢を崩すことはなかった。
肉体は滅んでも、あなたの魂は諫早の空の上をふわふわと
飛んでいるような気がしてならないのです。
諫早の空の下で、またお逢いしましょう。
( あなたを忘れないために、あなたを偲ぶよすがに、飾らない普段のあなたの言葉を残しておきたくて )
2022年11月30日
エール、ありがとうございました。元気出ました。嬉しくてあなたの方に向かって手を振りました。がんばりますよ~。
海山村を読んでくださってありがとうございます。いつかあなたが「書いた者にとって読んでもらえるのが一番うれしいですね」と言われたこと思い出しています。過分なお褒めにあずかって、でもあなたの言葉だからちょっとは、真に受けて、いい気になりそうで、えへへです。病院を出たり入ったりの日々で新しい化学療法を受けています。外見はいたって元気です。楽しいことも。いろいろあるし~。フォーラム頑張ってくださいね。盛会を祈っています。
2023年1月7日 ※長崎新聞「短歌ありて」欄に短歌批評の掲載を連絡
明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。思いがけずのびっくりニュース!嬉しいより恐縮にしばられました。でも、あなたに取り上げてもらえるのは嬉しい!ありがとうごさいます。勉強します。御用納めの日も御用始めの日も真面目に化学療法をしてきました。なんか楽しく終わって楽しく始まった去年今年でした。ノータリン賞受賞者らしく?新しい年も元気に過ごしたいです。
2023年1月23日
新聞読みました。ありがとうございました。自分でも好きな一首だったのでよけい嬉しくて。あなたの確かな筆力で私の詠みたかった里の美しい風景、人の暮らしがありありと浮かぶようでした。
ほんとに身に余る光栄です。これからもまたあなたに読んでもらえるような歌をがんばろうと思いました。ほんとに、本当にありがとう。水曜日から7分の4回目の治療が始まります。勇気凛々でいきますよ~。昨日までの私と明らかに違います。どうぞこれからもお体に気をつけてご活躍を。楽しみにしています。まずはお礼まで。
2023年4月16日 ※海山村Ⅱのネット掲載の承諾依頼への回答
お久し振りです。菜の花忌かれこれ、お疲れ様でした。そろそろまた、あなたの新しい作品ができた頃では?
ああ~、私長い休暇だな。今日はまた嬉しいメールをありがとうございます。あなたのメールはいつも私をワクワクさせてくれます。載せいただけるなんて光栄につきます。友だちがいて、忘れないでいてくれて…、繋がりがいっぱい力をくれます。本当にありがとう。選考してもらえるように文書かかなくっちゃ!と、またまた勇気凛々です。最近少し体調好転の感じが自分でもしています。頑張ります!
ほんとに!早く元気にならなくっちゃ。暗~いお話、期待大です。あなたの弱者への温かい眼差し、生きていくことへの希望がどんなふうに織り込まれているか…。私は今何となく病院物語みたいなのを書き散らしています。病気になったから見えること、わかること、出会うことができた忘れ難い人、宝物のようなことは書いておきたいと思って。
これ、内緒ですよ。はは~。
2023年4月17日
いえ、いえ、とんでもない。自在にお使いください。あなたのnoteです。
エッセーなので、そのときの等身大の私がいることがいいのかなと思っています。
そこからあなたが忌憚のない感想を展げてくださると嬉しい。
読んでもらえる楽しみです。
ありがとうございます。
津田さんへ
4月に通信をいただいた直後、私も思いもよらない病を得て入院してしまい、退院してあなたに拙作『死者の都』を掲載した西九州文学第50号をお届けしたのが7月11日だった。
しかし、あなたの葬儀はすでに7月3日に行われていたのだと伝え聴きました。
あなたに読んでもらえなかったことが、何よりの心残りです。
あなたは、きしくも自身のエッセー(夏惜しむ)の中で「先に逝く人は必ず何かを教えていく。別れの時に、遺された者たちは贈り物を受け取る」と書かれていた。
私たちは本当に、あなたから溢れる贈り物を受け取ったのだと思います。
これからも、あなたが心血を注いだ『海山村Ⅱ』の残りの俳句とエッセーを掲載していきたいと思います。
あなたがこの世界に生きた証しの一つとして。
津 田 緋 沙 子 さ ん の 紹 介

津田緋紗子(つだ・ひさこ)
昭和18年9月13日 韓国ソウル生まれ
昭和19年 母、姉と山口県仙崎へ引き揚げ
以降、父の郷里 福岡で学生時代をすごす
昭和41年 長崎市で就職
平成2年 諌早市の住人となる
平成14年 稲田眸子に師事
俳誌「少年」入会
伊東静雄研究会会員
平成29年5月 少年叢書として俳句とエッセイ集『海山村』刊行
令和3年4月『諫早文化』第16号に「高来町三部壱日記」を執筆
令和4年9月 少年叢書として俳句とエッセイ集『海山村II』刊行
*俳句とエッセイ集 海山村II 少年叢書 初版第一版=令和4年9月1日
令和5年7月3日 葬儀が行われる。
下記に長崎新聞に掲載された津田さんの短歌と評論が載っています。どうぞ併せてご覧ください。
