
仕事がつらければ、早期退職より「働き控え」が生きやすい
佐藤大朗(ひろお)です。早稲田の大学院生(三国志の研究)です。20年弱続けた会社員生活を辞めて、アラフォーの無職、大学院生です。
自分にとって重要な「お金」の部分について、2024年を振り返ります。
今年の経験を通じて、迷える社会人・大人たちに向けて、「お金を貯めた早期退職(FIRE)」よりも、いま話題の「働き控え」を真似したような生き方をオススメします、という記事です。
こんなことを言っている甘いやつが、凍え死なずに、暖房の効いた部屋でnoteの記事なんか書いている、という事実が、だれかの気休めになれば幸いです。※現代社会で、必死に現状に耐えているだれかを不愉快にするかも知れませんが、理想的な「企業戦士」はこんなnoteなど見ないでしょうから、きっと見つからないので大丈夫だと思います。
ぼくは2024年、「働き控え」により、心身の健康を取り戻しました。それが2024年の社会との関わりの重要な発見だったなと思います。深夜のノリで、少しまとめをしてみようかと思います。
FIREしたと言えるのか?
2024年を振り返ったとき、20年弱続けてきた会社員生活を辞めたことが、ぼくにとって最大の変化でした。
・大手系列の正社員を辞めて
・あまり熱心に転職活動もせず
・大学院生(博士課程)に進学し、
・趣味(三国志)に振り切った研究をして
・年齢的に大学教員になる期待値ゼロ
客観的にみると、なんと自滅的な生き方なんだ、という気がします。この状況を他人に説明するとき、近年の新語を借りて、「FIREです」ととりあえず言ってきたのですが、
・1億円は持ってない
・絶対に働かないと決めたわけではない
という中途半端な状態ですから、原義・狭義の「FIRE」である「金融的な自立と、早期の退職」と言えるのかよく分からない。
コロナ禍後、世間では「FIRE」という概念をぶち上げたがよいものの、厳密なFIREに当てはまるひと(1億円以上あって、二度と働かない)が少ないので、「サイドFIRE」や「リーンFIRE」など、まやかしの下位概念、場合分けが生まれておりますが、これは宜しくない。
他人に説明するときに不便です。相手に分かってもらえなければ、言う意味がない。「働いてますやん」というツッコミにも怯えます。また、複雑な概念は、自分の生き方の指針になりません。内面から不安になります。
退職から半年間の変化
いまの状況が経済的に自滅的で、市民権を得られず、自信を失うリスクがあるならば、また働けばいいじゃないか、という気がします。
しかし、会社を辞める直前、「自分の身体」を1個の生命体というか、1つの物体として認識できなかった。
立場に照らして、思ってもいないこと、本当にいいと思っていないことを、取り繕って肯定する場面が多かったからでしょう。パワハラを受けていたということは全くありません。
「ここの社員で、この立場と役割にある」ことの納得感がゼロに近い、なんならマイナスに突入していた。1日働くたびに、「経済的な安定と社会的な威信をキープするために、なんとか現状を正当化せねば」と、3日ずつかけて悩むレベルでした。※回復が間に合わない
電車のまどに映る自分のすがたを見て、これを1個の自分の体と認識できなかった。「何だこれは」って思うんです。SFのようです。1個の統合された物体として存在することが「理解」できなかった。通勤時、階段の上り下りが、認知-運動の連携がくずれて、うまくできなかった。立ちくらみ。
ホワイトカラー50代の平均年収は900万円だそうです。コスパ良好。だが、このまま現状をやり過ごして、自我を壊し、口を半開きで椅子に座り続け、年齢を年収に換金したところで、それは意味があるのか。
最終出社日から半年ぐらい経ち、さいきん、お風呂に入っていて、「ああこれは自分の手だ。自分の足だ。お湯のこちら側(内側)は、統合された自分の体であるな」と、しみじみと感じられたのでした。
べつに会社に虐待されていたわけではないが(むしろ優遇?され、気を遣われていたが)、その会社にしがみつくことが、自分に対する虐待だったのでしょう。だから、辞めた会社のことは悪くは思いません。
「働き控え」という知恵
2024年、耳にする頻度が上がった言葉は、「働き控え」です。Google検索に付随したAIに、世間での使い方を教えてもらいました。
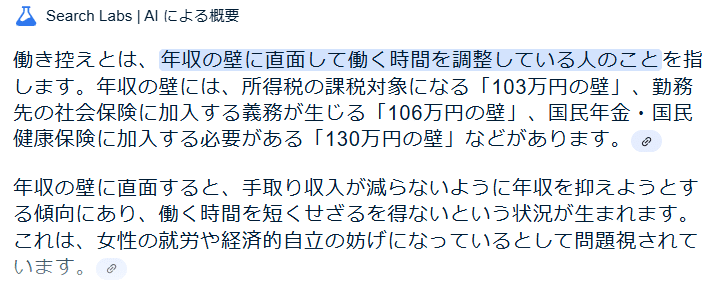
ぼくは税制とか政策の論争をしたいのではなく、ひとりの人間としての生き方に、この「働き控え」という概念を適用してみたい。
「働き控え」をしている「主婦」や学生が何をしているか。
現行の社会の制度に対して違和感があるけれども、それらと戦う気力も余裕も興味がないから、なるべく制度と衝突しないかたちで、無言で身を守っているのだと思います。
アメリカの大統領交代、景気動向、東欧方面の戦争、近隣アジア諸国との緊張、与野党の政局動向、インフレ比率、金利上昇、最低賃金、労働市場の需給、人口ピラミッド、財務省……それら難しい議論をするのは自分の役目ではない。それよりも、自分の生活を最優先にして、「やばそうなところには近づかない」を静かにやっている。
サイレント・ストライキです。
為政者の目線ならば、「国力を高める制度設計が」「財政規律と自国通貨の信認を」「制度の周知徹底が」みたいな言い方になりますけれど(それはそれで合っていると思いますが)、
それら大きな話を回避して、みずから死なない範囲でやり過ごしているのが、「働き控え」だと思います。
働きたいのは、やまやまなんですけど、なんだかヤバそうなので、私はこれ以上は辞めておきます。世間にはご迷惑をかけて申し訳ないですが。
疲れたら「働き控え」を
税金や社会保険料の「年収の壁」(がけ)は、自分のひとりの力ではどうにもならない、所与の環境です。
そこで、昨今話題の「年収の壁」に限定せずとも、より一般化して、「既存の社会(雇用慣行、組織風土、常識)が生きづらいから、ちょっと遠ざかろう」「休憩しよう(死なない範囲でやりくりをして)」という生き方も、「働き控え」に含めたらどうでしょうか。
サイレント・ストライキです。
会社はどうあるべき、職場はどうあるべき、上司部下の関係は、職場のアセスメントで、待遇の良し悪しが、人事評価の納得性が、制度の欠陥が、とか小難しいけれども負け筋の戦いを挑むのではなく、すっと身を退くのも、知恵のひとつでは。既存の環境は、そう簡単には変わりませんよ。
「働き控え」の態度を真似るのです。
一時期もてはやされたFIRE(1億円を貯めて、二度と働かない)という生き方は、難易度が高くて現実的ではないから、いろいろな亜種が出てきて、空中分解した印象です。
それよりも、現役世代(65歳未満、あるいは70歳未満)でも、いまいち仕事がうまくいかなければ、「働き控え」であると自認して、体勢を立て直せばいいんじゃないですかね。
働きたいのは、やまやまなんですけど、なんだかヤバそうなので、私はこれ以上は辞めておきます。世間にはご迷惑をかけて申し訳ないですが!!
ぼくの現状も「働き控え」ということにしましょう。これ、ちょうどいいです。言葉がやわらかいし、分かりやすい。気負いもない。
「働き控え」は恵まれた感じがする
「働き控え」って、なんだか甘っちょろい(恵まれた)感じの言葉ですよね。これが当てはまるのは、親とか配偶者の扶養に入っているひとが多いですが、この甘っちょろさがいいのです。
「独立生計の社会人は、仕事を辞めて、過去の自分の扶養に入る」でいいじゃないですか。とりあえず、とりあえずです。
いまの働き方にうまく適応できてないな、合ってないな、と思ったら、「働き控え」がいいですよ。
しがみついて働くほうが、自分に対する虐待です。ぼくに限っていえば、ムリヤリ働いていた期間、あまり記憶が残っていません。実質的に寿命が縮んだも同然ですからね。緩慢な死刑ですからね。ろくでもない。
「働き控え」をして、過去の自分の扶養に入ろう!!
もし資産収入があるならば、それはセルフ生活保護です。自家製ベーシック・インカムです。がんばってきた、過去の自分の恩恵にすがりましょう。世代間対立を、せめて自分のなかで解消しましょう。
失業すれば(長い待機期間やブランクがありますが)失業保険がもらえますし、再来年以降、税金や社会保険料が安くなります。日本は、給与明細(あるいは確定申告)の数値上の弱者にとって優しい国です。
ひどい働き方をして、自分のことすら、わけが分からなくなるぐらいならば、「働き控え」を。社会に対して納得感が持てるようになったら、また働けばよいのではないでしょうか。
「働き控え」は馴染みます。訳の分からない横文字の「リーンFIRE」や「コーストFIRE」より分かりよい。孤独で不安であればこそ、概念を鍛えることはだいじです。単なる言葉遊びじゃないかと譏られても、メリットのほうが大きいと思います。
