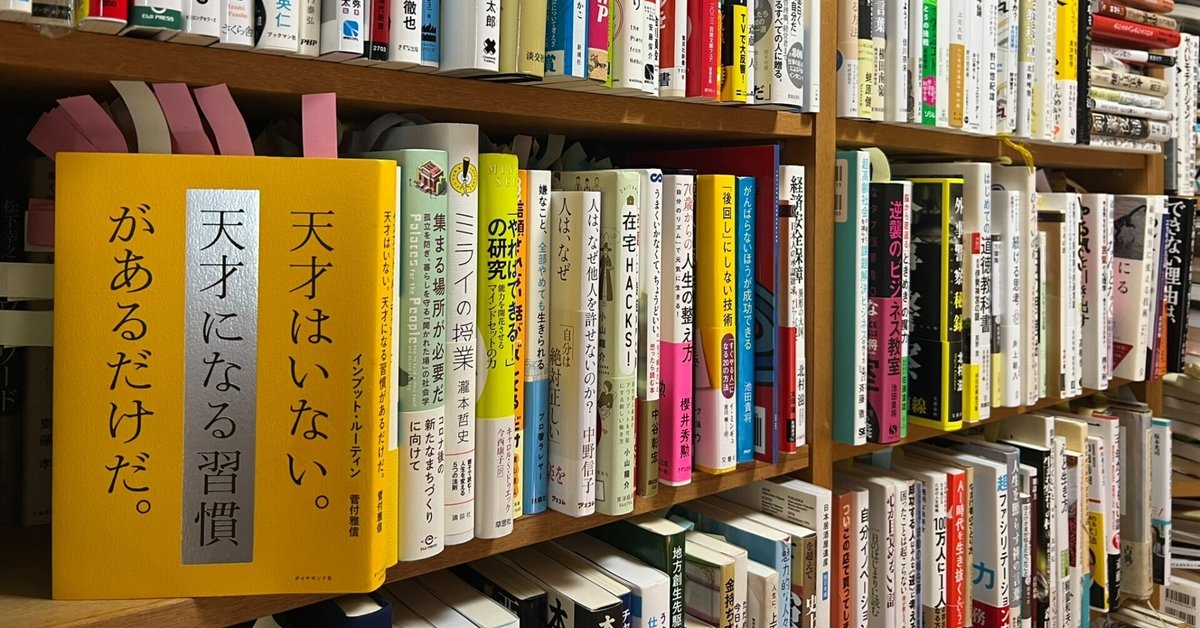
一日平均七冊の読書
今日のおすすめの一冊は、菅付雅信(すがつけまさのぶ)氏の『天才はいない。天才になる習慣があるだけだ。』(ダイヤモンド社)です。その中から「桁はずれの読書家」という題でブログを書きました。
本書の中に「一日平均七冊の読書」という心に響く文章がありました。
インプットの質と量を考えるうえでベンチマークになる一冊に、「打ちのめされるようなすごい本』(文春文庫)がある。亡き通訳者でありエッセイスト米原万里(よねはらまり)の書評を網羅した名著だ。
米原の読書狂はかなり知られるところで、本人もこう記している。「食べるのと歩くのと読むのは、かなり速い。(中略)ここ二〇年ほど一日平均七冊を維持してきた」。一日平均7冊とは驚異の読書量だが、本書の核は「すごい本」の紹介とその表現の巧みさにある。
たとえば、トマス・H・クックの「夜の記憶』について、米原はこう紹介している。「軽い気持ちで頁を捲(めく)るや、恐怖で身体が強ばり、読み終えずに寝たら悪夢にうなされそうな気がして書庫の床に座ったまま最終頁まで突き進んだ」。
オリバー・サックスの「手話の世界へ』については、「発見の驚きと喜びに満ちた本だ。読了後、付箋をつけた頁の方がつけない頁を上回ったことに気付いた。その付箋が、私の目から剥がれた鱗にも見えてくる」。
プーラン・デヴィの『女盗賊プーラン』をめぐっては、「昨年インドの総選挙で貧困層の圧倒的支持を得て国会議員に当選した元女盗賊の半生記である。
(中略)なお老婆心ながらご注意申し上げる。並みの意志力しかお持ちでない方は、この本を開く前に、火急な用事は片づけておくこと。読み始めたら最後のピリオドまで、たとえ火事でも中断するのは不可能であるからだけではない。読了後は最低丸一日茫然自失状態に陥って何も手に付かなくなるからだ」。
これらのような強烈な読書体験を促す名著・珍著をこの本はたたみかけるように紹介しており、読書というインプットの質と量を考えるうえで最高の指南書になっている。
◆菅付氏曰く、クリエイティヴのプロに求められるのは、圧倒的な量のインプット。それも、読書、映画、音楽、すべてにわたってだ。そして、それがあってはじめて、上質なアウトプットができる。
優れたアウトプットは、インプットの新しい組み合わせによって生まれる。同時にそこには、「意外性のある組み合わせ」が必要だ。
◆圧倒的で桁外れの読書量がなければ、優れたクリエイティヴは発揮できない。
それにしても、一日に七冊の読書というのは、かなり桁外れすぎるが…
インプットを増やし、クリエイティビティを高めることができる人でありたい。
今日のブログはこちらから→人の心に灯をともす
