
『カタカムナ』は本当に縄文時代の古代文明なのか?
世の中の研究者ですら解けなかった謎 を、私が解明してしまったかも??

世の中の『カタカムナ』の解説って、そのほとんどが『縄文時代の古代文明』として紹介されてますよね?
でも、『カタカムナ』のことを、深く分析してみると……
カタカムナの『縄文時代の古代文明』説を調べると、実はいくつもの矛盾が見つかるのです。
まずは『カタカムナ』の第1句を見てください。
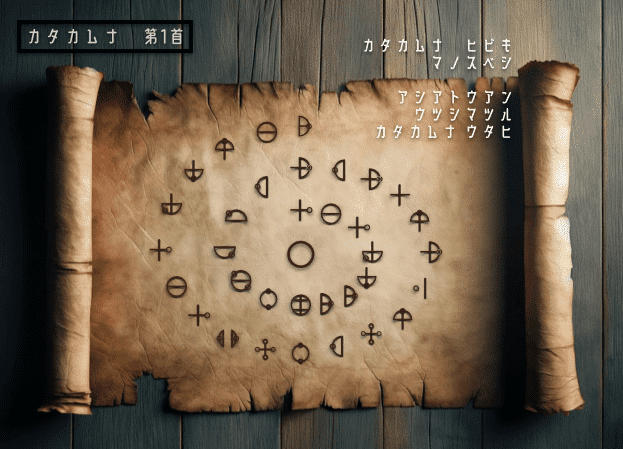
この画像は、螺旋状の文字盤が『カタカムナ』の文字です。
画像の右上には、カタカナでその読み方が書かれています。
こう書いてあります。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
『カタカムナ』 第1首
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
カタカムナ ヒビキ マノスベシ
アシアトウアン ウツシマツル
カタカムナ ウタヒ
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
【漢字に直すと?】
カタカムナ 響き 間の術示し
蘆屋道満 写しまつる
カタカムナ 詩
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
・
・
あれ? 漢字に直せるの?
まず、そこがおかしいですよね?
縄文時代と言えば、もっと ウッホッホ族 のはず。
なのにこの言葉使いの、『蘆屋道満 写しまつる』って、歌舞伎っぽい言い回し。
これ、本当に縄文時代の言葉? 本当は、いつの時代のモノなの?
・
・

実際に私が分析した結果、『カタカムナ』の執筆年は、970~1050年の範囲まで、年代を絞り込めました。
『平安時代』

これは、過去の研究者の方々の意見とは、大きく違います。
これだけ年代にズレが出るということは、どちらかが正しくて、どちらかが間違っているわけです。
では一体、どちらが正しいのか?
他の研究者とは違うことを言ってるけど、本当なの?
テキトーなことを、勘で言ってるだけでは?
・
・
それではなぜ、『カタカムナ』の本当の執筆年代は、平安時代なのか?
ひとつずつ、その謎を解き明かしていきましょう。
まずは、誰にでも分かる『簡単な証拠』からスタートしてみます。

・
・
『カタカムナ』の本当の執筆は、いつなのか?
もし、言われているとおり『カタカムナ』が縄文時代の言葉なのだとしたら、当然、現代とは言葉が変わります。
戦国時代の言葉(時代劇)ですら、「拙者」とか「ありがたき幸せ」とか、「かたじけのう、ござった!」みたいな、わけのわからない 古語の呪文 が飛び交ってるわけですから、縄文時代の言葉なんて、ウッホッホ語 だったのでは?
少なくても、現代人にスッと意味が通じる発音 ではなかったはず。
ところが、『カタカムナ』を全80首、一通り読んでみると、明らかに意味がスッと通る句が、ところどころあるのです。
たとえば『カタカムナ』 第4首。

━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
『カタカムナ』 第4首
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
イハトハニ カミナリテ
カタカムナ ヨソヤコト ホグシウタ
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
どうでしょう? これ、本当に縄文時代の言葉に感じます?
ちなみに、これを漢字に直すとこうなりますよ!
『意は永遠に 神なりて カタカムナ 四十八言 ほぐし歌』
四十八言(よそやこと)って、『ホツマツタヱ』の『あわ歌』の音数のこと。
それによく見ると、この『カタカムナ第4首』の響きって、奈良・平安時代の言葉に似てますよね?
参考までに、時代が近い【万葉集】の言葉の響きと比較してみましょう。
【万葉集】 3253番歌
(遣唐使の出発を見送る側の歌)
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
葦原の 瑞穂の国は
かむながら 言挙げせぬ 国
しかれども 言挙げぞ 我がする
事幸くま 幸くませと
【意味】
葦原の瑞穂の国(日本のこと)は、「神の作法」にならって
たとえ心の中では、嵐のように心配してたとしても
心に秘めて、言葉には出さない。そのようなつつましい国だ。
けれど、私は言葉に出して、あえて言わせていただく。
「どうぞご無事で神に守られますように!」
ちなみになぜ、この句を選んだか? というと、『カタカムナ』も第17首以降は『カムナガラ』という言葉が多発するからなのです。
つまり『カタカムナ』も、時代的にこの【万葉集】と、そこまで離れていない。
……『カタカムナ』平安時代説が有力になってきたでしょう?
平安時代の証拠は、まだまだ続きます!
続いて、平安時代の証拠 その3 は?

次に、『カタカムナ』 第7首 を見てください。
エネルギーが特に強い! と言われる、有名な5・6・7首の最後の句です。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
『カタカムナ』 第7首
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
マカタマノ アマノミナカヌシ
タカミムスヒ カムミムスヒ
ミスマルノタマ
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
この句は、発音を追いかけると、意味が分かるようで分からない……という、そこそこ微妙な暗号に見えます。
しかし、漢字に直すと実はこうなるのです。
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
『勾玉の 天之御中主神(アメノミナカヌシ)
高御産霊神(タカミムスビ)
神産霊神(カミムスビ)
水丸の球』
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
天之御中主・高御産霊神・神産霊神とは、『古事記』に出てくる「造化三神」のことで、あの天照大御神よりも格上となる、宇宙創造の神々とされています。
古事記の編纂って、奈良時代(712年)です。縄文時代ではありません。
平安時代の証拠は、相当かなり固まってきましたが、ダメ押しとして、その4 の証拠も見てみましょう。
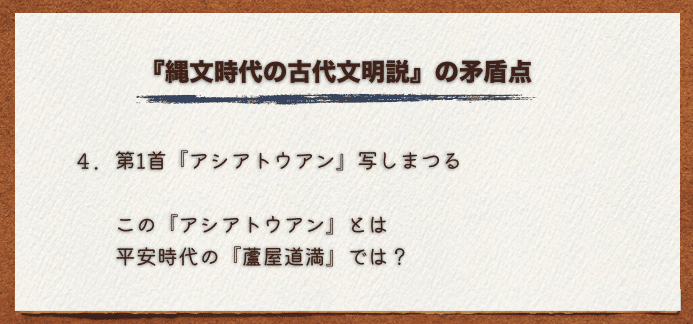
『カタカムナ』 第1首 を見てください!
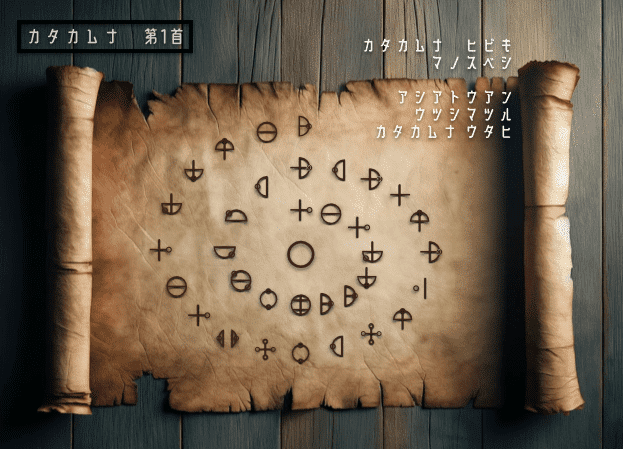
『カタカムナ』の全80首はこの句からスタートするのですが……
なんて読めますか?
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
『カタカムナ』 第1首
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
カタカムナ ヒビキ マノスベシ
アシアトウアン ウツシマツル
カタカムナ ウタヒ
━─━─━─━─━─━─━─━─━─━─
まず最初に注目するのは、歌舞伎風の表現である『アシアトウアン うつしまつる』が何を意味するか?
そもそも『アシア トウアン』という名前そのものが、縄文時代のウッホッホ族の発音ではないでしょう。「名字+名前」の組み合わせですから。
オリジナルには、古代文明時代の『初代シャーマン』の名前が記されてたのでは?
その後、何代も写本が繰り返されて、現存する最後の写本が『アジア・トウアン』作だっただけでは?
そう考える方もいるかもしれませんが、そうなると、『奈良・平安期』の流行であった「5・7調」で書かれた句が目立つことの説明がつかない……。
・
・
そもそも、ここで署名している『蘆屋道満』って、平安時代の歴史に名を残す法師・陰陽師だったのです。(藤原道長や安倍晴明と同時代の人)
歴史に名を残すくらいの、とんでもないシャーマン!
ネットで検索しても出てきますよ!
神のご神託を受けながら『カタカムナ』を書き写したのが、その時代のシャーマンである『蘆屋道満』だったなら、『カタカムナ』の執筆年は、970~1050年あたりという解釈が、がぜん信憑性が高くなってきたでしょう?
平安時代の証拠がどんどん固まってきましたが、今度は『文字』の面からもアプローチ。
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
『縄文時代の古代文明』の矛盾点
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
5.『カタカムナ』の文字の「サ」と「キ」と「リ」は「カタカナ」そのもの。これを『縄文時代の文字』と主張するのは、さすがに無理がある。
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-
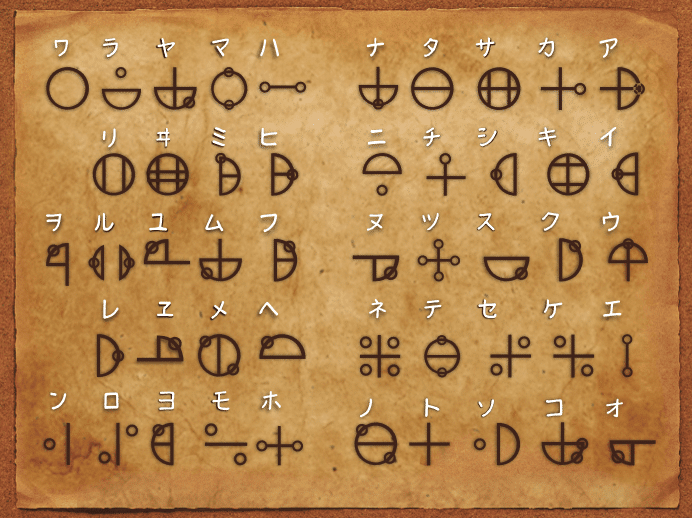
『カタカムナ』の文字は、『記号』のような独特の絵文字です。
しかも、グルグル螺旋を描きながら書くという、「読ませる気」がサラサラない文字の書き方。
実は、別な機会に神様に聞いたところ、この文字は秘匿文字で、秘術のやり方を、権力者に悪用されぬよう、『カタカナ』を参考にした、暗号文字で書かれたそうな。
だから、近畿地方の神社で『ご神体の巻物』として残っていたもの以外、『カタカムナ』の文字が見つからないのは、そのような理由。
最初から秘匿文字だったので、一部の人しか知らなかった。
《カタカムナの秘匿文字》

全部で48文字ある中で、いくつかはカタカナに似てる字もありますが、完全に一致するのは、その中の3文字。

この3文字は見ての通り、カタカナをマルで囲った状態。
『カタカナ』(片仮名)の起源も、『ひらがな』と同じように、『平安初期』だそうですよ。
『ひらがな』は、平安期の女性の間で流行した、「漢字を崩した文字」なのは有名ですが、『カタカナ』もそれにやや遅れて作られた、『ひらがな』に対抗した、男性バージョンの文字だったとか……
参考リンク・・・・・・なぜ日本語には「ひらがな」と「カタカナ」があるのか?
・
・
実際に、『カタカムナ』が降ろされたのは『平安時代』
神様から降ろされたのは、『蘆屋道満』
この事実を知った後なら、世の中でいわれている『縄文時代の古代文明説』は間違いだと気づきますし、時代考証が違っているということは、その訳も……?
もしかしたら、私のHPで本当の『カタカムナ』の訳を見られるかもしれません。

+++++++++++++++++
前回の記事……私と『カタカムナ』の出会い。『カタカムナ』は本物なのか?
次回の記事……『カタカムナ』は神様からの謎かけ?
+++++++++++++++++
💻Homepage……https://hironomichi.jp/

