
中学1年生への職業講話:家づくりと進路選択で大切なこと
先日、職業講話として中学1年生の子たちに話をする機会をいただきました。毎年お呼びいただいています。いつも、中学1年生にどんなふうに話すと伝わるだろう?とか、10ぐらいある職業の中から、建築の話を選んでくれた子たちですが、建築に進む子たちばかりではないので、建築以外の、人生の話も織り交ぜたいなぁと思いながら試行錯誤しています。
話を聞いてくれる子たちは、みんないい子ばかりで、本当にいつも感心しています。ちゃんと最後には質問もしてくれて、静かに集中して話を聞いてくれます。
今回は、ちょっと長くなりますが、話をした内容をまとめてみました。
はじめに
皆さん、こんにちは。今日は職業講話ということで、お話をさせていただきます。私の名前は加賀江広宣といいます。「シンケン」という住宅会社に勤めています。皆さんの中で「シンケン」の名前を聞いたことがある人はいますか?
おとといから、雪がすごかったですね。みなさん雪遊びはしましたか?私は自然豊かな場所に住んでいて、家のまわりにはたくさんの雪が積もりました。昨日は雪で休校になったのでわが家の子どもたちも雪遊びをしていました。わが家の子どもたちもみなさんと同じぐらいの年で、中3、中1、小5です。なので、わたしは、皆さんのお父さんと同じぐらいの年だと思います。会社はこの中学校の近くですが、自然がたくさんあります。会社の周りも一面の雪景色でとてもきれいでした。

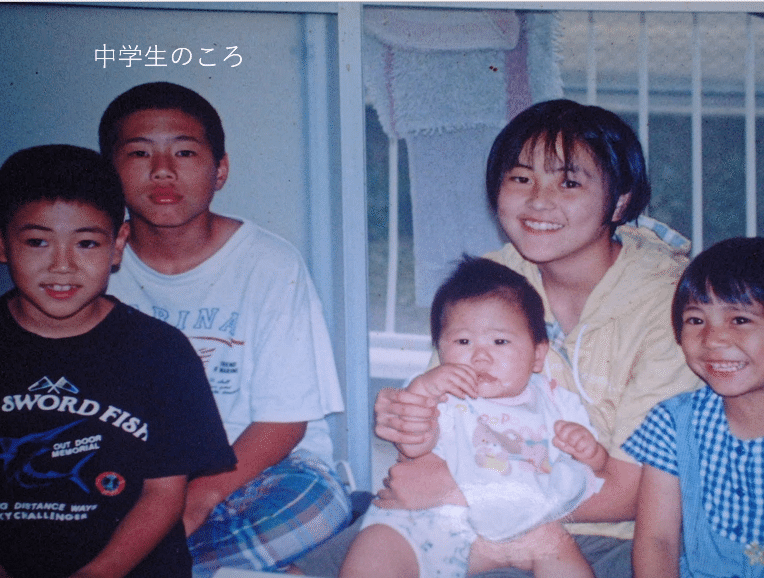
これはわたしが、ちょうどみなさんと同じ中学1、2年生ぐらいのときの写真です。5人兄弟の長男で野球部でした。わたしは運動神経が悪いので、野球部では一度もレギュラーにはなれませんでした。野球部にいじめっ子がいて、いじめられていたので、あまりいい思い出はありません。
だけど、そんな私でも中学3年生のときに同級生の女の子に告白されたことがあります。いま、わたしは44歳ですが、女の子から告白されたのはこの時の1回だけです。いま、結婚しているわたしの奥さんはその時の女の子ではありません。告白されなくても結婚することはできますよ。
中学校を卒業してからの進路は、高校は工業高校のインテリア科、大学・大学院で建築を学び、いま、シンケンで家づくり、建築の仕事をしています。
今日は家づくりや建築のお話をしながら、皆さんにとって少しでも将来の参考になるようなお話ができればと思っています。
建築の仕事とは?

この学校を誰がつくったかわかりますか?
生徒の答え:建築士!
実は、建築士だけでこの建物はできません。建築の仕事にはたくさんの役割があります。みなさんが今いるこの教室も、多くの人が関わってつくられました。設計する建築士だけでなく、実際に建物を建てる職人さん、大工さん、鉄筋を組む人、窓をつける人、電気を通す人、水道を通す人など、さまざまな専門家が協力しながらつくり上げています。
ちなみに、建築士というのは資格の名前です。わたしは建築士ではありませんが、建築に関わる仕事をしています。例えば、家を建てた後にお客様の家を訪ねて、暮らしの様子を聞いたり、問題がないかを確認したりしています。また、会社のシステム管理などの仕事も担当しています。いろいろな人の仕事が合わさって、人の建物ができます。それは学校のような大きな建物だけではなく、小さな住宅でも同じです。
どんな家が良い家?
私がこれからお話しすることは、一つの考え方です。答えではありません。いい家をつくるためにはいろんな道があります。そのつもりで聞いてください。
家は人生の中で多くの時間を過ごす場所です。ある統計によると、人生を80年だとすると、約54年は家で過ごし、そのうち29年が起きている時間なのだそうです。家というのは、それほど長くいる場所だからこそ、住みやすく、心地よい空間であることを大切にしたいと考えています。

いい家はどんな家かを、一言で言うなら、「心地よい家」です。そのために考えることはたくさんあります。
空間は気分をつくる
ゲームセンターに行くとどんな気分になりますか?

生徒の答え:ワクワクした気分、楽しい気分。
図書館に行くとどうでしょう?

生徒の答え:落ち着いた気分。眠くなる。
緑豊かな公園に行くと?

生徒の答え:リラックスした気分。
そうですね。
その場にいることを想像しただけでも、そういう気分が心の中に湧いてくると思います。人は、空間にいるとその空間によって気分が変わります。どんな空間にいるか?は人の心に影響を与えるものです。
住宅も同じように、空間のつくり方によって、そこに住む人の気分が変わります。明るく開放的な空間と、暗く狭い空間ではそこにいる時の気分はちがうものです。先ほど人生80年のうち、54年は「家」で過ごす。という話をしましたが、54年過ごす家という空間がどんな気分をもたらしてくれるか?ということはその人の人生にとってすごく大切なことだと思いませんか?だからこそ、家づくりでは「どのような気分で過ごしてほしいか」を考えながら設計することが大切です。
家づくりにおける「情愛」と「自然」
人生で長く過ごす、心地よい家をつくるうえで、いちばん大切にしているのは、「情愛」と「自然」です。
情愛
情愛というのは、人を思いやる気持ちや、身近な人に向けられる優しさや愛情のことです。
家はただの箱ではなく、その中で暮らす人がいます。そこで暮らす人たちがつながる場所です。特に、家族の関係においては、「思いやり」が大切になります。例えば、家事をしやすい家の設計をすれば、日々のストレスが減り、家の中が穏やかになります。家族全員が心地よく過ごせるような工夫をすることが、良い家づくりにつながるのです。
私は、「家族に思いやりが芽生え、みんなが仲良くなれる住まい」を目指しています。家の中の動線や間取りによって、自然と会話が増え、家族がつながる設計を考えています。
自然
もう一つ大切にしているのは、「自然を感じられる家」です。さきほど、自然豊かな公園にいると、リラックスした気分になると答えてくれましたが、家ではリラックスして過ごしたいですよね。
私の家は、庭に大きな木があり、四季折々の変化を感じることができます。木陰ができることで夏は涼しくなり、春には新緑が美しく、季節の移り変わりを身近に感じられます。
また、窓の外に見える景色も重要です。家の中から緑が見えると、それだけで心が落ち着きます。明るい日差しや風の通り道を考えた設計をすることで、家の中でも自然を感じながら暮らすことができます。
家を建てるときは、人だけでなく、自然との調和を意識することが大切です。私たちの家づくりでは、「人も自然も満足し、互いに生かし合う家」を目指しています。
例えば、窓から見える景色を美しくする工夫をしたり、光がうまく差し込んで明るくしたり、風が通るようにしたりすることで、気持ちが穏やかになります。また、家の間取り次第で家族の関係性も変わります。

例えば、キッチンから家族の顔が見える設計にすると、暗くて閉鎖的なきっちよりも家事が楽しくなり、会話も弾むようになります。洗濯物を干すことや、掃除をすること、片づけをすることなど、やらなければならないことがストレスなくできるようにすることで、お母さんやお父さんがイライラすることが減るようになります。いろいろな工夫を重ねて、家族が自然と仲良くなれるような家づくりを考えています。
進路選択と生き方について
ここにいるみなさんは、建築に興味があるみなさんですが、最終的には建築の道に進まない人の方が多いかもしれません。建築の道に限らず、これから生きるうえで大切だと私が思っていることを最後にお伝えしたいと思います。
自分の意志ではどうしようもないこと
人生の中では、自分の意志ではどうしようもないことに直面することがあります。そんなときにどう向き合うか、選択肢はいくつかあります。
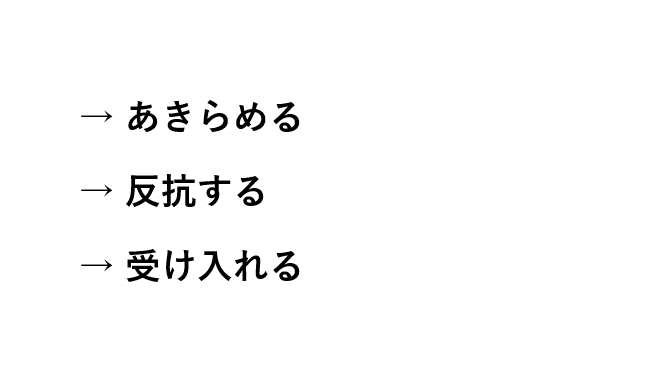
あきらめる - 行動:何もしない。流される。
反抗する - 行動:文句を言うだけ。文句を言いながら行動する。
受け入れる - 行動:何もしない。その状況を受け止めつつ、自分にできることを考えて行動する。
どれを選択するか、どんな行動をするかは自由です。あきらめるのも、反抗するのも、文句を言うのも、何もしないのも自由です。だけど、最終的には全部自分に返ってきます。
わたしが子どものころ
最初に私が中学生のころの写真がありましたが、わたしは兄弟が多かったです。一人だとお小遣いをあげることができますが、5人もいると私のお父さんお母さんはお小遣いをあげることが難しくなります。
そこで私は小学校5年生のときに自転車を買うために新聞配達をはじめました。いまでは、中学生がはたらくということはできないのですが、みなさんと同じ中学生のころも朝6時前に起きて新聞配達をしてから学校に行っていました。

高校を出たら働こうと思って工業高校に行きましたが、もっと勉強したいと考えたときに、新聞配達で自分でお金を稼げば大学にも行ける!と知ってそれで大学院まで行くことになりました。
もし家庭の経済的なことで「あきらめる」を選んでいたら、大学にも大学院にも行けませんでした。しかし、「どうすれば学び続けられるか」を自分なりに考え、行動を起こしたことで、今の自分があります。どんな状況でも、「自分にできることは何か」を考えて行動することで、未来は開けていきます。
将来のことを考えたとき、どんな仕事をしたいか、どんな人生を歩みたいか、悩むこともあるでしょう。私も中学生の頃、最初は建築ではなく、発明家やコックさんになりたいと思っていました。
しかし、興味があることを追求していくうちに、高校ではインテリア科に進みました。そして、もっと学びたいと思い、大学・大学院で建築を学ぶことにしました。
最初からはっきりと決められなくても大丈夫です。ただ、「興味があること」を大切にしてください。いろいろな経験をして、思いを深めながら進路を決めていけばよいと思います。
「自分が進む道は自分で決める」誰かに決めてもらうものではありません。決められるものでもありません。もし、道がなければ「自分で道をつくる」ものです。親や先生の意見も大事ですが、最終的に決めるのは自分自身です。自分で決めたことは、困難があっても乗り越えられるものです。
生徒からの質問
Q1: 建築の道に進んだのはどうしてですか?
建築の道を進んだのは、やっぱり物を作るのが好きだったからです。最初は単純に「ものを作るのが楽しい」と思っていたからです。
実際にやってみると「人の暮らしより良くすることに貢献できる」やりがいのある仕事です。
家は、人が長い時間を過ごす大切な場所です。その家のつくりによって、人の気持ちや生活の質が変わります。わたしは、自分の人生を「できるだけ人の役に、社会の役に立つように」生きたいと思っています。建築の仕事は、社会や人々の暮らしに大きな影響を与えられる仕事なので、とてもやりがいを感じていますし、楽しいです。
Q2: 建築に決まりごとはありますか?
そうですね、建築には多くの決まりごとがあります。建築基準法という法律があり、安全や住みやすさを守るためのルールが細かく定められています。
例えば、この教室の窓の大きさも、法律で「教室の広さに対してこのくらいの窓が必要」と決められています。同じように、住宅でも「部屋には必ずこれくらいの窓を設置しなければならない」などの規定があります。
また、ちょっと変わったものだと、人が過ごす部屋は「天井の高さは最低2.1メートル以上にする」という決まりもあります。
Q3: 建築の仕事を続けているのはどうしてですか?
わたしは大学で建築を学ぶなかで、「建築は社会を変える力がある」と強く感じました。
極端な例ですが、もし国が「窓のない家」を推奨したら、町全体が暗く閉鎖的な雰囲気になり、人々の気持ちも沈んでしまうでしょう。そんな社会はどんな社会になるでしょう?逆に、光や風が入って心優しくなれるようなデザ家が増えたら、そんな社会はどうなるでしょう?建築のあり方が社会に与える影響はとても大きいとわたしは思っています。
そのことを実感してから、「人々が心地よく暮らせる空間をつくることで、社会に貢献したい」と思うようになりました。それが、私が今でも建築の仕事を続けている理由です。
また、もちろん、単純に建築が好きだからというのもあります。好きなことを仕事にできると、たくさんの困難があっても乗り越えられるものです。やはり「好きなことを続ける」ことが、大切だと思います。
まとめ
今日は、建築の仕事について、そして進路選択や生き方についてお話しました。
建築の仕事には多くの役割があり、さまざまな形で関わることができる。
空間は気分をつくる
良い家とは、心地よく、家族が幸せに暮らせる空間。
家づくりにおいて「情愛」と「自然」を大切にする。
興味のあることを大切にしながら、自分の進む道を考える。
自分が進む道は自分で決める。
道がなければ、自分でつくることもできる。
皆さんも、自分が「興味があること」を大切にし、それを仕事にできる道を探してみてください。人生の選択肢は一つではありません。
これからの皆さんの未来が、素晴らしいものになることを願っています。
本日はありがとうございました。
