
#11 書店員/出版者【北田博充】②
【H…Hiromi / K…北田さん】
▪️H.では、北田さんが好きな本は何ですか?
▪️K. 好きな本、絶対インタビューで聞かれるんですよね。でも、そもそも本が好きかどうかもわからないんですよね。
▪️H.当たり前になりすぎているんですか。
▪️K. そうですね。常に身近にある空気のような存在なので好きとか嫌いの対象じゃないんですよね、本って。
職業として本屋をやっているので、本を好きとか嫌いって感じたことがなくて、 あえて言うなら仕事なんですよ。本を読むのも仕事だし、本を選ぶのも仕事。そこに好きとかって感情が入らないんですよね。しいて言うなら、本が好きなのではなく、本を売ることが好きなんです。
▪️H. これまで見てる本の数が違いますよね。自分が興味のない範囲の本も読まれていますもんね。
▪️K. 自分が楽しむために読むというよりは、売るために読むわけですから。読んだ時にどういう売り方をするかを考えながら読むわけなので、純粋に楽しむ読書というのとは違う「職業読書」です。
▪️H. 見え方変わりますね。こういう風に置くとお客様が喜んでくれるだろうなとか、売れるだろうなっていうのを考えながら読むんですか?
▪️K. そうですね。どこの棚で何と並べるかは考えるし、どういう人が買うのかなっていうのも考えながらですよね。
▪️H.なるほど、自分が楽しむじゃなくて、
その先のどんな人が本を選ぶかっていう。
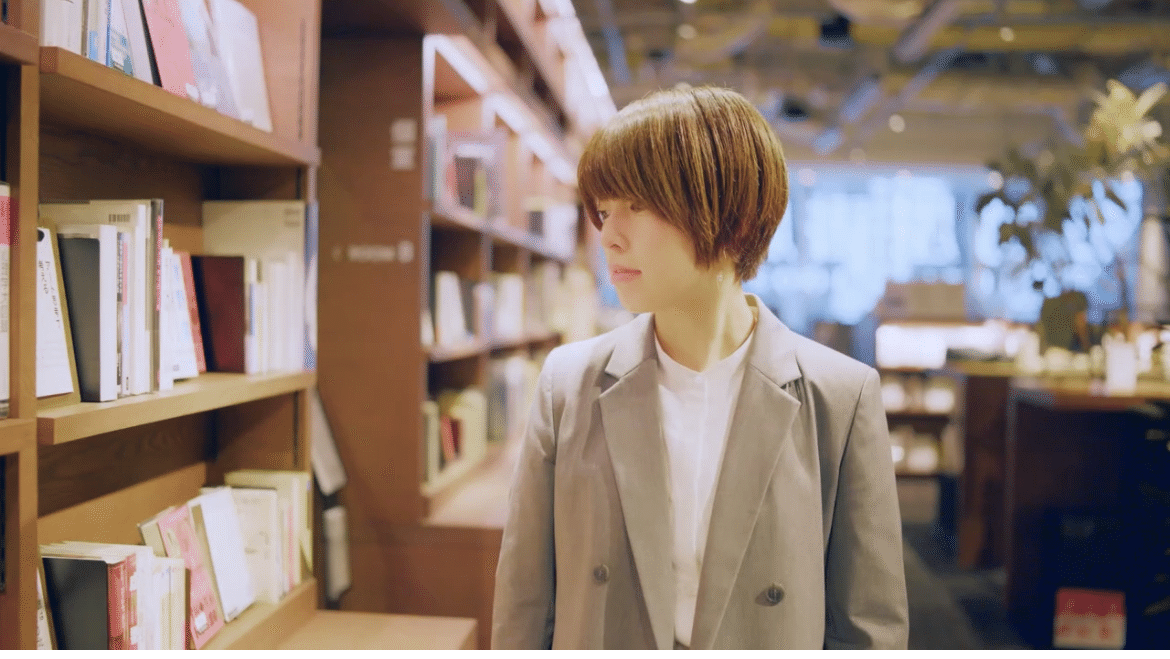
▪️K. もちろんです。
なので、基本的には世の中的に売れているものは
読まないです。
▪️H. そうなんですね。
▪️K.だって、例えば村上春樹の新刊を自分が読んだところで、売れ行きに関係ないじゃないですか。私が読まなくても勝手に売れていくんで、そういうものは読むだけ時間の無駄なんですね。仕事としてやっている人間からすると。楽しむ読書は引退してからでいいと思っています。
▪️H. 逆に、まだまだ売れてはないけど、
これは!みたいな本を前に読むってことですか?
▪️K. そうですね。
▪️H.どういうアンテナを立てられてるんですか?
世の中的にはまだ出てないじゃないですか。
▪️K. でも、そういう嗅覚は自然と身についてくるもんですよ。長年働いていると。1冊の本にはいろんな情報があるじゃないですか。書名、著者名、出版社名、価格、 あとは帯の推薦文とか、裏表紙、あらすじとか。1冊の本ってものすごい情報が詰まっているでしょ。それを瞬時に情報を分析して、これはこういう本だっていうのを見極めるのが書店員の嗅覚というか。
読む前からなんとなくわかる部分もありますよ。
これは面白いだろうなとか、これは売れるだろうなっていうのはだんだん見極めがつくようになってきます。
▪️H. それすごいですね。簡潔にこれはこういう本ですって薦めてていけるのっていいなと思います。
北田さんはいろんな方お会いされていると思うんですが、本でインタビューをした方、出版の業界の方など影響を受けた人っていますか?
▪️K. 影響を受けた人。難しいですよね。いろんな人に影響を受けてると思うんですけど、自分の出版社で本を出してる作家さんかもしれないですね。
▪️H. 確かに、その人の思いを伝えたいし、知ってほしいから本を広めようってことですよね。
▪️K. そういう意味では、そうかもしれないですね。
▪️H. どういう人たちなんですか。

▪️K. その作家さんによって違うんですけど、身内みたいな感じですかね。 なんとも表現が難しいです。ビジネスパートナーでもなければ、家族でもない、なんか微妙な関係ですかね。
大切な人には違いないです。
▪️H. 別に血縁関係でもなければ、元々昔から知ってる人でもなく、本を通して、大切な人ができているって素敵だなって思いました。
その人の捉え方とか考え方とかが
共感できるんですか?
▪️K.言葉にすると安っぽくなってしまうので、言葉にするのが難しいですね。自分が伝えたいことと違う感じになりそうで。
▪️H.言葉も捉え方によって、みんな違いますもんね。たまたま取った本で、著者さんのことを
知らないんですけど、「本当にこの人、私の気持ちわかってくれているな」と感じたことがあって。そんな人に出会えるきっかけが本はあるなと思っています。物としても好きですけど、
著者さんの考え方とか生き方とかを知れるのも
本の魅力かと思います。
北田さんが思う本の魅力ってありますか。
▪️K. 情報収集するんだったらネットでいいし、娯楽だったら本以外にも面白い娯楽があるし、本の1番の魅力っていうのは、情報とか娯楽じゃない部分じゃないですかね。
じゃあそれが何かって言われると、
それもやっぱり言葉にするのが難しいんです。
例えば、Hiromiさんが友達を持つことの魅力ってなんですか?って言われたらどう答えますか?
▪️H. 支えてくれてる人とか?

▪️K. 私の中では本と人はほぼ同じなんです。
本との出会いっていうのは、
人との出会いと一緒なんですよ。
本を読まなくても別に生きていけるじゃないですか。友達がいなくも死なないし、
普通に生きていけるのと同じで。
でも、友達がいると人生楽しいじゃないですか。
▪️H. わかりやすいです。
▪️K. 人の出会いって、いい出会いもあれば、
良くない出会いもありますよね?
でも、それって結局自分が引き寄せてるみたいなところもあったりします。
自分の嫌な面をちゃんと指摘してくれる友達とか、気づきを与えてくれる友達の方がありがたかったりもするし。
本を読むことによって、自分の新たな側面に気付いたりとか、そういう点も友人関係の中で気づきを得るのと近いと思います。
▪️H. 確かに、人との出会い、本との出会いは
近いなと思いますね。
私自身、親も共働きで1人で家にいることが多くて、 その時に本が友達のような感じだったんですよ。一緒にいてくれる、新しい世界を教えてくれる友達だなと思ったのを今、思い出しました。
寄り添ってくれていたのが、本だったかもしれません。
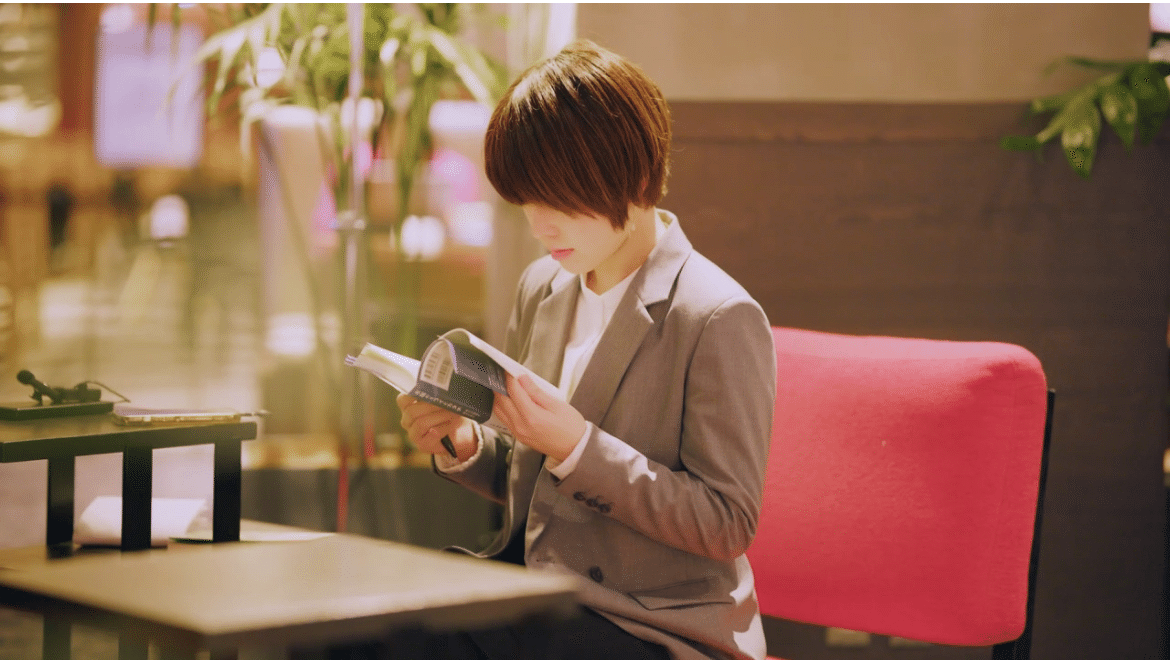
▪️K. 本って、人が書いているものだから、
人に近いっていうのは当たり前っちゃ当たり前なんですけど。でも、紙の本って1冊1冊、重さも違えば、手触りも違えば、使っている紙が違うから匂いも違うし、大きさも違うし、思想も違ったりする。本そのものがやっぱり人に近いんですよね。
本って紙でできているから、
ちょっと間違うと手を切ったりするでしょ。
そういう危険な部分もあるわけですよね、本には。人もやっぱり近づくと危険な部分があったりするし、逆にプラスになる部分もあったりしますよね。
世の中に同じ本ってないんです。
内容は似ていたとしても捉え方、
表現の仕方とかは違っていて、
全く同じ本はないんですよね。
人間でもそうじゃないですか。
双子でそっくりに見えても、
やっぱり違う人間でしょう。
それと一緒ですよ。
大きい書店に行くと、何万冊と本があるわけで、
そこにいろんな入口があるわけですから。
▪️H. 確かに人と本って似てますね。
1冊の本で人生が変わる人もいるじゃないですか。この本のこの言葉に救われてもう1回頑張ろうと思えたとか。それって人との出会いも
一緒じゃないかなって思いました。(③に続く)
【第11回目ゲスト】
北田博充さん
梅田 蔦屋書店 店長・文学コンシェルジュ。
大学卒業後、出版取次会社に入社し、2013年に本・雑貨・カフェの複合店「マルノウチリーディングスタイル」を立ち上げ、その後リーディングスタイル各店で店長を務める。2016年にひとり出版社「書肆汽水域」(https://kisuiiki.com/)を立ち上げ、長く読み継がれるべき文学作品を刊行している。2016年、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に入社。現在、梅田 蔦屋書店で店長を務める傍ら、出版社としての活動を続けている。2020年には本・音楽・食が一体となった本屋フェス「二子玉川 本屋博」を企画・開催し、2日間で3万3,000人が来場。著書に『これからの本屋』(書肆汽水域)、共編著書に『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』(朝日出版社)、共著書に『本屋の仕事をつくる』(世界思想社)がある。
