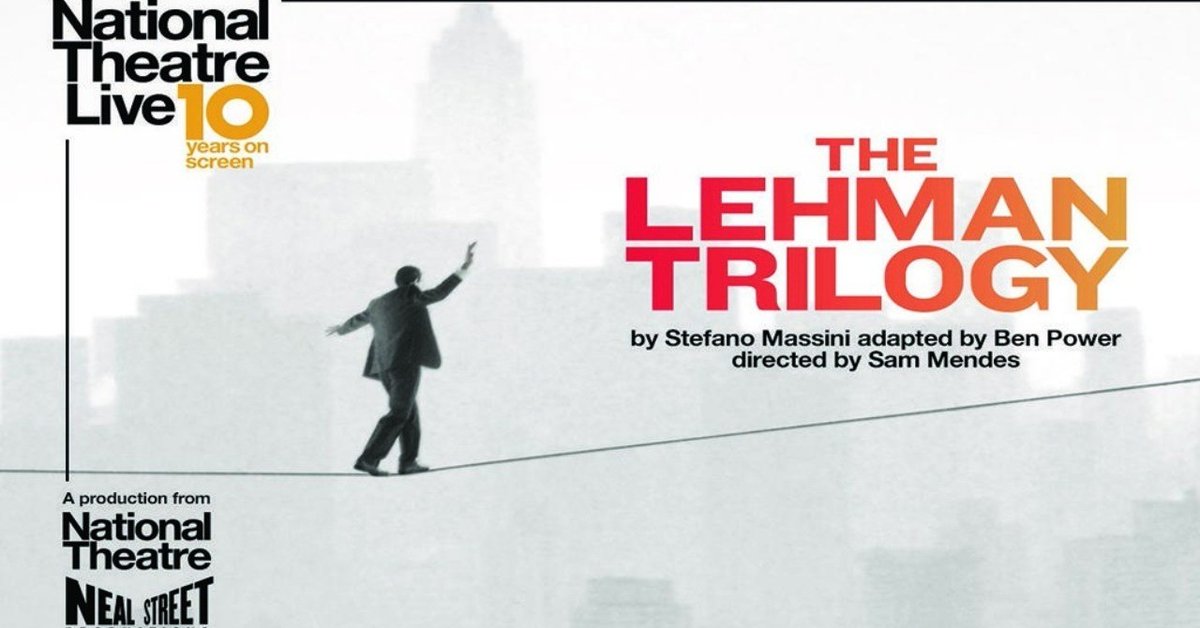
『リーマン・トリロジー』をみた
天下のナショナルシアターライブ、今までもいくつか観ていて、ほぼハズレがないのだが、今回は格別にイイ!という評判しか聞こえてこなかった本作。気になりつつも諸々忙しくもう無理かなと思っていたのだが、俳優をやっている友人がお勧めしてくれたので、それならばと終映直前に駆け込んだ。結果、行ってほんっっとーに良かったです。ありがとう友よ。
あのリーマンショックのリーマン家の話。わたしは一族の盛衰記みたいなものがそもそも好きで、我が人生における最高傑作の座はガルシア=マルケス『百年の孤独』でいまだにゆるぎない。が、この度、本作に最高傑作演劇部門を授けようと思う。何様か。
もう上映が終了しようという頃なので、ここからそれなりにネタバレします。まだ観ていない、自分の目で観るまでは何も知りたくない、3月のブロードウェイ公演で観る、日本で再上映を待つ、という方々はここでお別れです。アデュー。
まず目を奪われたのは舞台装置。
ガラス張りのオフィスを模した回転するキューブ。場面ごとに映し出される映像がガラスの向こうの背景となる。無機質な箱のような部屋が、その折々であらゆる場所に変化する。それはもちろん、俳優たちの演技とシーンを作る力がそう見せているのだが、違和感を生じさせないデザインとその使い方によるところも大きい。舞台の変化だけでも美しくて楽しめる。
美しいのは舞台に限らない、語られる言葉はまさしく叙事詩であった。たった3人の俳優がすべての人物を演じ分ける。その演技の確かさはもちろん、語られる言葉の豊饒さ。けっして美辞麗句ではない、なにしろユダヤ系移民としてアメリカに渡ったリーマン兄弟の成り上がり物語である。兄弟間やビジネス上の激しいやりとりも、恋にまつわるコミカルな駆け引きも、大きな戦争という災厄も、各々が逃れられなかった悪夢も、ブラックサーズデイによる悲惨な自殺者たちの描写も、なのにすべてうっとりと聞きほれてしまうのだ。
そして音楽。生演奏のピアノが奏でるシンプルなメロディは「第4の語り手」と演出家サム・メンデスが言うとおり。演劇で生演奏はそう珍しいことではないが、悪目立ちせず効果的に使われることは意外に少ない。
わたしが印象深かったのは、綱渡りのエピソード。ニューヨーク証券取引所の前でパフォーマンスしていた曲芸師パプリンスキ。彼が綱を渡っては戻ることを繰り返すようにリーマンのビジネスが大きくなっていく。パプリンスキがついに綱から落ちた日、リーマンショックで兄弟もシンクロするように落ちたのだった。ニューヨークの空中をひとり綱渡りしている、パンフレットの表紙にも使われているイメージは、150年に渡る一族の盛衰を象徴しているかのようだ。
時代や歴史という時間の流れを、イマココに現前させるのは舞台しか出来ないことだ、というサム・メンデスの言葉に深く頷いた。
