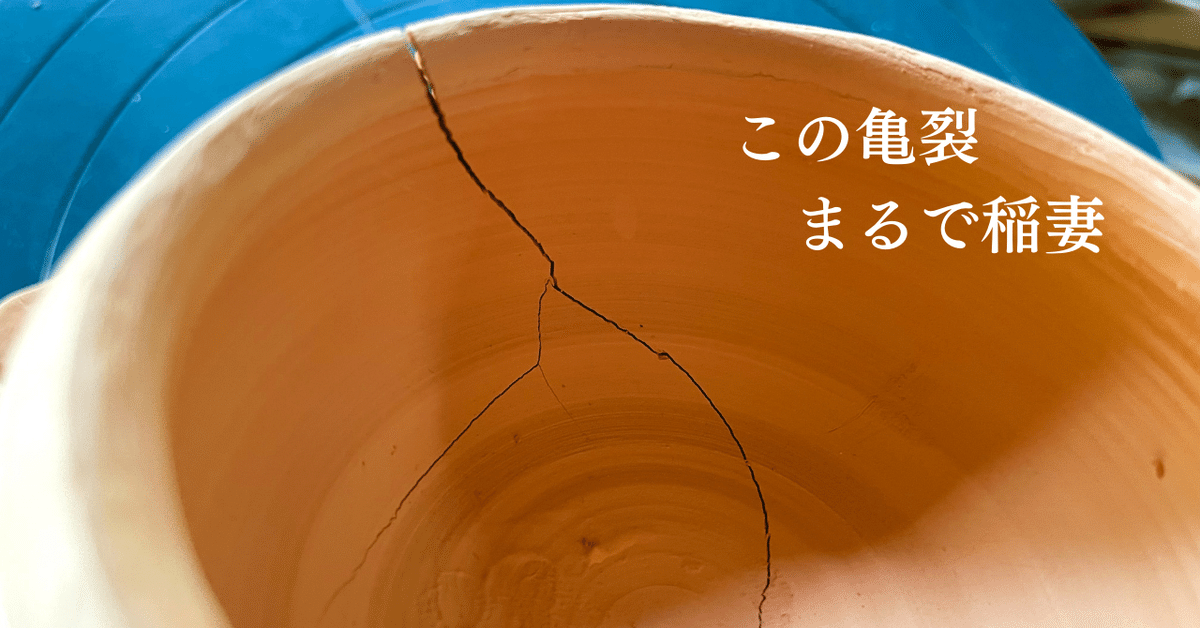
“上手くいかない行程と、そのモノ”が教えてくれることがある
お待ちいただいている作品がありまして。
陶器の、陰陽セットになる作品なのです。
それが、どうにも。
難航しております。
① 陶土で成形
② 乾燥
③ 800度で素焼き
④ 絵付け
⑤ 釉薬かけ
⑥ 1230度で本焼き
⑦ 窯内でゆっくり冷却
⑧ 金銀で絵付け
⑨ 750度で焼成
⑩ 時には、更に別の絵具で絵付け
⑪ その場合は、その絵具の適温で焼成
⑫ ようやく完成
という、そもそもが複雑で長い道のりの作品なのです。
が!
今回の分については、②と③でボツるのです。
陶土は、成形したら、水分が均一になるように養生しながら、ゆっくり時間をかけて乾燥させます。
完全に乾燥したら、窯詰めして、素焼きです。
このどこかの段階で、修復が難しいような状態の亀裂が入るんです。
今までも作っているモノなので、よもやこんな難航するとは思ってませんでした。
先日、素焼きしたものも、陰陽の片方が割れてたし...。
で。
思ったわけです。
何かしらの無理を「モノ」に対して強いている。
それは、もしかしたら、わたしの姿勢かもしれない。
そんなことがあったので。
最初に作り始めた時と一部変更した成形工程を、もとに戻してみようと思っています。
手間は増えるのですがね。
割れないこと優先の方が、資源と時間の削減に繋がる。
乾燥中に割れたものについては、陶土に再生することもできるからまだマシなのですが。
素焼きで割れたら、リサイクルも難しいので泣けますからねえ。
もっとも、陶片から作る作品、というのも、わたしのラインナップには存在しますから。
極力ムダにはしない方向では、あります。
それこそ、すごい手間がかかるので、たくさん作れないモノにはなるけど。
できるだけ、捨てずに生まれ変わらせたいですから。
だって。
別の素材でも、生まれ変わらせる作品って、企画しているくらいなので。
そっちの方は、まだ実験段階を出ていなくて、お披露目にいたっていないけれど。
それと。
今回の素焼きで亀裂が生じたモノも、
この後、回復させる手段を考えてあります。
普段使いにするような器ではなく、
「とある儀式に使うための祭器」
ですから、想定している手段で、蘇らせることは可能ではないかなと。
一度やってみて、それでもダメな時は、潔く諦めましょう。
それまでは、実験あるのみです。
なにしろ。
まるで稲妻のように生じた亀裂。
美しいじゃありませんか。
この無作為に生じた亀裂を、
そこに留めた品として完成させる。
それこそ、祭器として造られたこの器が、自ら望んだ形かもしれないのだから。
いいなと思ったら応援しよう!

