
広川町のむかし(平安時代)
平安時代 (約千二百年〜八百年前)
本編に入る前に…。
「有田地方と広川町のむかし」(昭和57年発行)は外江素雄先生が広川町の郷土史を小学生向けに綴った書籍です。当時2000部ほどしか発行されず、地域の図書館にも貸し出し本はありません。しかし、この本の内容は地元住民でも知らない地域の伝統文化や地名の歴史が記載されており、非常に貴重な資料となっております。我々郷土史プロジェクトのメンバーがこつこつとデジタル化を行いました。承諾いただいた外江先生、協力してくださった皆様に感謝申し上げます。
広がる荘園(しょうえん)
奈良時代の終わりころから、土地を新しくきりひらいて、税を朝廷に出すことのいらない田畑をもつことがみとめられるようになりました。このような田畑は「荘園」と呼ばれ重い税に苦しんでいた百姓たちは、わりあてられた土地をすてて荘園領主のもとへにげこむことが多くなったのでますます荘園は広がっていきました。
西広「針ノ木(はんのき)」を推理する
飛鳥時代の項で調べた「身明(しんめい)」のすぐ北側の地は「針の木(はんのき)」と呼ばれている土地です。おそらくこの地名はもともと、「はりのき」と呼ばれていたと思われます。
「はりのき」とは、「治田の柵(はりたのき)」がここにおかれていたことから名付けられた地名であるとみてもまずまちがいないでしょう。
「治田(はりた)」とは奈良・平安時代にのみ使われた言葉で、歴史を証言する貴重な呼び名なのです。
「治田(はりた)」とはすでに開墾(かいこん)の終わった田のことですが、その持ち主はだいたい土地の豪族でした。彼らは「田堵(たと)」と呼ばれ、その下で働く百姓を「田部(たべ)」といいました。
津木の猪谷(いだに)地区に「ダベ」と名付けられた所がありますが、「田部(たべ)」からきているのかも知れません。
平安時代の前半、この田堵(たと)と荘園領主とは治田(はりた)をめぐって全国各地ではげしい対立があったといわれています。
西広地区にも田堵(たと)がいて、周囲の荘園領主と争いがあったとみられます。
「治田(はりた)の柵(き)」とは、まさにそういう時期に、田堵(たと)が治田のまわりに柵(さく)をめぐらして自分の土地を守ろうとした光景を雄弁に物語っているのです。
「地名は歴史の証言者」―西広の「針ノ木(はんのき)」ほどこの言葉にあてはまる地名はありません。

比呂(ひろ)庄の領主は藤原氏に
全国各地で荘園がふえ続け、土地について強い力をもつ小豪族や百姓があらわれました。彼らは自分の土地を国司や他の豪族から守るために、都の貴族や寺や神社にゆずり、その貴族や寺や神社を本家(ほんけ)、領家(りょうけ)とあおぎ、自分は荘園の管理者となりました。
このような荘園をもっとも多く集めて、実力第一をほこったのが藤原氏一族でした。
比呂の荘園もそのほとんどが藤原氏を領主としていました。
しかし、少なくとも平安中期ごろには、藤原氏一族の中の者が比呂庄を別々に分けて持っていたようです。
そして、藤原氏の手から、平安後期近く、その一部は熊野の那智山(なちさん)へ、さらに鎌倉時代にさしかかろうとするころには京都の蓮華王院(れんげおういん)(三十三間堂)へ寄進されました。
比呂庄を寄進した女官(じょかん)の願い
那智山に自分の持っている宮前庄(みやざきのしょう)(今の有田市宮崎町)と比呂庄の土地を寄進したのは、当時、京の都の宮廷に仕えていた藤原氏の女性でした。彼女の位は内侍尚侍(ないじのかみ)で、これは女官たちをとりしきる重い職でした。
彼女の生きた時代には、天皇や貴族による熊野詣(くまのもうで)がさかんになっていました。信仰心の厚い彼女は熊野詣がかなえられなかったかわりに、土地を那智山に寄進したのです。
彼女が寄進するにあたって申し送った手紙が、現在、那智神社に残されています。次のページに、今ふうに書きなおして紹介してみましょう。

なぜ? 「安諦(あで)」から「在田(ありた)」へ
平安京を開いた桓武(かんむ)天皇のあとをついだのが平城(へいぜい)天皇でした。この平城天皇はそれまで皇太子でいる時は「安殿親王(あでしんのう)」と呼ばれていました。朝廷の大臣たちは紀伊国に天皇がいままで呼ばれていた名前と同じ呼び名の郡があることはほっておけないと考えました。それで、命令によって「安諦」を「在田(ありた)」に変えさせたのです。
「在田(ありた)」はそのころの中心地「荒田(あらた)」村(現在の宮原東部)からとったものでしょう。
<挿話>
鹿ヶ瀬峠(ししがせとうげ)の「がい骨伝説」

今から八三〇年も昔のことです。
壱叡(いえい)という若いお坊さんが、熊野へお参りに行くとちゅう、鹿ケ瀬(ししがせ)峠の山中にある古ぼけた小屋に泊りました。
ま夜中のことです。壱叡(いえい)はなんとはなく目がさめてしまい、しばらくうつらうつらしていました。ふと・・・・・・・・さきほどからだれか人の声がしているような気がしました。何をいっているんだろう、とよく耳をすまして聞いていると、それはお経をよむ声だったのです。
その声は、少しのササのゆれる音にも消されるくらいずい分低いかすかな声でした。
壱叡(いえい)は、だれか私と同じような旅のお坊さんが先にこの小屋にきているんだな、と思って、静かにそのかすかに流れるお経を聞いていました。そのお経は、いつも壱叡(いえい)がよんでいるのと同じお経でした。
一巻、二巻、三巻と、お経の声はいつ終わるともなく続きました。
「こんな真夜中にもお経をいっしょうけんめいあげるとは、なんて熱心なお坊さんなんだろう。」
壱叡は半分あきれ、半分感心して聞いていました。
その声は、遠くの山の尾根が少し白み始めた夜明け前、やみました。
明るい朝日が小屋にさしこんできました。
しかし、小屋の中にいたのはやはり壱叡(いえい)ひとりでした。ふしぎに思った壱叡は、夜中に声のした方をさがしてみましたが、別に何も見つかりません。壱叡(いえい)は確かに声のしたと思われる方角のヤブの中をのぞいてみました。
するとどうでしょう。深いササヤブに守られて横たわっているかのように、一体のがい骨が見つかったのです。その骨は五体が全部つながったままで、よほど古くからここにあったのでしょう。まきついたツタの下には緑のコケがびっしりはりついていて、まるで衣服をつけているように見えました。そして、おどろいたことに、がい骨の口の中にはまっ赤な舌があるではありませんか。 その舌は、まるで何かをうったえているかのように口の中でじっとしていました。
壱叡(いえい)は、これは何か事情があるにちがいない、お経をよむわけを知りたいものだ、と思って、もう一晩この峠の小屋に泊まることにしました。
その夜も、やはりあの低いかすかなお経をよむ声が聞えてきました。がい骨の口の中の赤い舌は一筋の月光に照らされて静かにうねっていました。

夜明け前、壱はそのがい骨に手をつき、ひれふして言いました。
「夜ごと、このように死んだのちもお経をよんでおられるのはきっと何かの深いわけがあるのにちがいないと思っておうかがい申し上げます。どうか、そのわけをお聞かせ下さい。心残りなことがこの世にございましたら、かならず私がうまくとりはからいいたします」
すると、がい骨は、あのかすかな声でこう答えていいました。
「わたくしは円善(えんぜん)という、比叡山の僧であったが、百年前熊野まいりのとちゅう峠まできて病気になって死んでしまった。わたくしは、生きている時、六万部といわれるお経を全部最後までよんでしまおうとちかいをたてていた。しかし、半分もいかないうちにここで死んでしまったのだ。かたくかたく心にちかっていたのに、と思うと残念でたまらず、それで、わたくしは死んでからもここにとどまって残りのお経をこうしてよんでいるのだ。だが、それももう終わりに近い。ここにいるのもそう長くはない。ここを去って、わたくしは菩薩のいる浄土へ旅立つ日も遠くないだろう。」
それを聞くと、壱叡はがい骨に深く頭を下げ、静かにそこを去りました。
次の年、壱叡(いえい)はふたたび熊野詣のとちゅう鹿ヶ瀬峠を通りましたが、もうがい骨はどこにもありませんでした。
その一〇〇年前、比叡山の円善(えんぜん)というお坊さんかこの峠で病気になって死んだということです。

熊野詣(くまのもうで)を考える
奈良時代からの仏教が、しだいに真剣な信仰心を失って政治や目の前の利益に利用されるようになると、これにあきたらない皇族(天皇家)や貴族たちは、遠くきびしい旅をしなければならない熊野三山(速玉(はやたま)神社、本宮大社(ほんぐうたいしゃ)、那智大社(なちたいしゃ))にこの世の救いを求めました。
都から大勢のともをひきつれて熊野まで往復したので、巾三(じゃく)尺三寸(ずん)の街道はよくととのえられていきました。
特に天皇や上皇(一度天皇の位をしりぞいた人)は熱心で後白河(ごしらかわ)天皇などは生涯三十三回もお参りしています。それで、この道は「熊野御幸道(みゆきみち)」とも呼ばれました。
長く流行した理由
一、本地垂迹説(ほんちすいじゃくせつ)(仏が人間を救うため、仮に神の姿になって現れたという考え)がひろまり、熊野三山の神がそうであるというふうに伝わったこと。
二、新宮大社を中心とする熊野の兵力は大きく、常に朝廷側にひきつけておこうという政治的なねらいがあり、熊野の方でも、朝廷からそのつどさずけられる官位(朝廷の位) や賜わり物など利益が少なくなかった。
三、全国各地にちらばって熊野詣(もうで)をすすめ、道案内や王子社での儀式までおこなった「先達(せんだち)」とよばれる山伏(やまぶし)と、熊野三山の祈禱師で宿の世話をした「御師(おし)」とよばれる人々が活躍したこと。
四、京都や鎌倉などからはへき地にあるため、女性や貧富の差別なくお参りすることをすすめたこと。 当時、このような寺社は少なかった。
歓迎されない天皇の一行
身分の高い人が熊野詣(もうで)をする半年から一年も前から、都から役人がきて、「街道を安全に美しくしておくこと、往復の宿のこと、食料のこと、荷物運びの人夫(にんぷ)や馬のことなど」、地元の領主にかたく申しつけて帰っていきます。
約四百年間、百回をこえたといわれる熊野への御幸(ごこう)(天皇や上皇が旅すること)の多くが秋から冬にかけておこなわれたというのも、二か所の川の旅があるつごうから雨期をさけたということもありますが、往復の食料や人夫(にんぷ)を地方から出させるのにもっとも良い時期であることが最大の理由であると思われます。
平安後期、白河上皇(しらかわじょうこう)の一行八百十四名が通ったときは、米十六石(こく)、馬百八十五頭も差し出さねばならなかったといいます。
そのほか、おかし、酒、酢、塩、みそ、だいず、土器、炭などさまざまなものを大量に用意させられました。まったく御幸(ごこう)なんてきてほしくないものでした。
長い街道のところどころには、休けいや旅の安全を祈るための「王子社(おうじしゃ)」がもうけられてありました。
この広川町内にはいつの頃できたのかわかりませんが、「井関(いせき)王子」「津兼(つがね)王子」「河瀬(ごのせ)王子(古くは白原(しらはら)王子であった)」「馬留(うまどめ)王子」などがあったことが知られていますが今は「河瀬(ごのせ)王子」だけがよくその跡をとどめています。
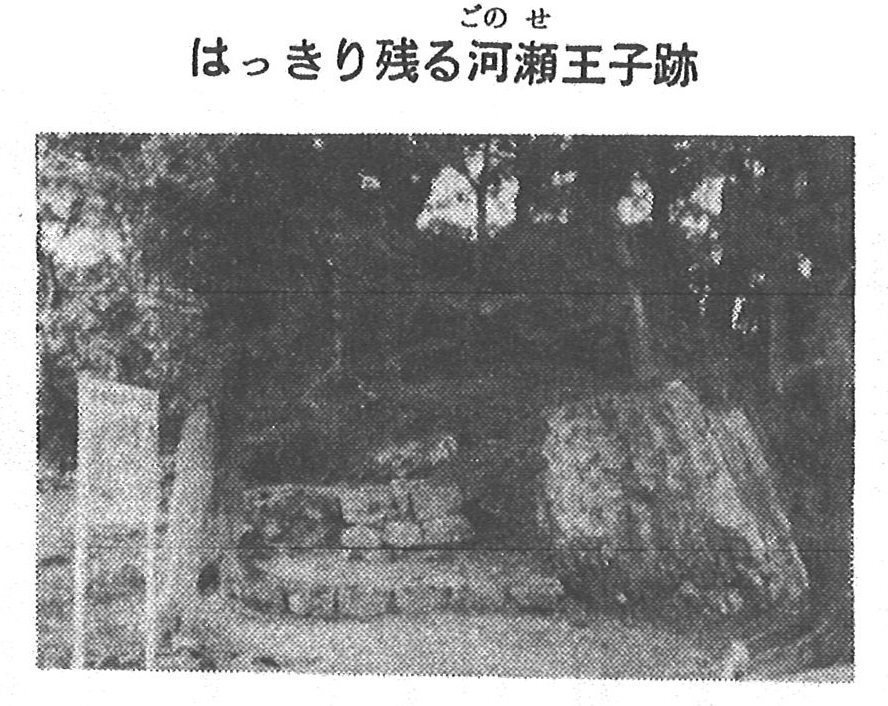
家出人を見つける「法華塚(ほっけづか)」
長い旅には苦しいことも多く、鹿ヶ瀬峠(ししがせとうげ)には熊野へいくとちゅうで病気で死んだという伝説の円善上人(えんぜんしょうにん)をおまつりした小さな社があり、「法華塚(ほっけづか)」と呼ばれています。
この「法華塚(ほっけづか)」は、いつのころからか、ここにお参りにくれば家出人や行方不明者が見つかるといういいつたえができ現在でも、遠く大阪あたりからでも時々お参りにくる人があるということです。
藤原氏からはなれて
比呂(ひろ)庄も平安時代の初期には藤原氏のだれかが領主であったようですが、前にもみたとおり、藤原氏一族の中の人が別々に領主となって、さらに寄進によって藤原氏以外の人の手にわたっていきました。
それを図で示すと・・・

西広、鳥羽(とりば)氏と金剛谷(こんごうだに)
西広、大葉山のふもとに現在も鳥羽(とりば)さんという家がありますが、広川町誌(田中重雄先生筆)によると、この方の祖先は、平安時代後期に比呂庄の一部と由良庄が京都の蓮華王院(れんげおういん)領であったころ、土地のとりしまりのため荘官としてやってきた樋口(ひぐち)氏ではなかったかということです。
西広の大場(おおば)の地に今も石壇がのこっていて、そこは宇佐(うさ)八幡の旧社地であり、近くに金剛谷(こんごうだに)と呼ばれている所があります。
「金剛(こんごう)」というのは仏教で力をあらわす言葉だそうですが、ずっと昔、そこに鳥羽(とりば)氏一族の氏神や氏寺があったといわれています。このすぐ近くに「舞殿(まいどの)」という地名も残っていますが、鳥羽氏らが、その昔、ここで舞を楽しんだあとかも知れません。
河瀬(ごのせ)地区、鹿ヶ瀬(ししがせ)峠のすぐ下に今も鹿ヶ瀬さんというお家があります。
この家も平安時代、熊野那智山から荘官としてやってきた「熊野八荘司(くまのはっしょうじ)」に数えられる家柄をついだ旧家といわれています。
<挿話>
岩渕(いわぶち)に伝わる三輪明神の伝説

ずっとずっと昔のことでした。
岩渕の里に、小原主膳(おはらしゅぜん)という若者がおりました。
主膳は何かねがいごとがあったらしく、はるか大和の国の三輪(みわ)明神社と長谷寺(はせでら)の観音さまにお参りにいくことにしました。
主膳のねがいは何であったかわかりませんが、とにかく、三年の間、毎月、岩渕から大和までの遠い山道を往復しなければなりませんでした。
彼は大和の三輪の里でいつも一夜の宿をとることにしていました。この宿は、信心ぶかい井窪仙斉(いくぼせんさい)という老人とそのひとり娘がひっそりと生活しているまずしい家でした。
仙斉と娘にとって、毎月きまってお参りにやってくる主膳との出会いは何にもましての楽しみでした。仙斉はいつしかこの若者を娘のむこにむかえたいとねがうようになりました。娘にしても主膳のことを思わない日はなかったのです。
ところがいつまでたっても二人は、この気持ちを主膳に伝えることができませんでした。
どうしてでしょうか。
それは、もし主膳が二人のねがいをききいれて娘と夫婦(めおと)になっても、主膳は遠い紀伊の国へ娘を連れていくことになるでしょう。
仙斉にとって娘とはなれてしまうことは、それはもう生きているかいのないほどつらいことでした。いや、娘にしても、年老いた父をこの里にひとりおいていくことなどとうていできないことです。
二人の悲しみをよそに月日はどんどんすぎて、主膳の願をかけた三年がもうすぐこようとしています。
そしてついにその時がやってきました。
主膳はこれまで三年間の心あたたまるもてなしに対して感謝し いつもより多くのお礼を差し出しました。
「主膳どの」
仙斉はその夜、決心を主膳にすべてうちあけ、深々と頭を下げて、娘をもらってほしいことを何度もたのみました。仙斉の悲しい決心に娘はただ泣くばかりです。
「仙斉どの、わたくしの方こそ、あなたの娘と夫婦(めおと)にしてもらえまいかといつも思っていたのでございます。
しかしながら、わたくしの方とて、仙斉どのをひとり残して、娘を連れていくことなど申し上げることもできず、そんなことを、もしわたくしがしようものなら、たちまち三輪明神さまのおいかりにふれて、これまで三年の間の願かけ参りもすべて水のアワになることでございましょう。」
長く重苦しい時間が流れました。
「仙斉どの、わたくしどもとごいっしょについてきてもらえまいか。」
主膳がそういったとき、窓の外にはうっすらと夜明けが近づいておりました。

三輪(みわ)の里を後に
夫婦(めおと)のさかずきをくみかわし、家をたたんで主膳と娘が三輪の里を後に、旅立ったのはそれからまもないころでした。

二人のあとには、仙斉が小さな荷物をしょってはればれと歩いておりました。
岩渕の里におちついた仙斉と娘は里の人たちにあたたかく迎えられ、主膳とともに幸せな日々を送っていました。
信心深い仙斉は、一度はいってみたいと願っていた熊野権現(ごんげん)さまへお参りの旅に出ることにしました。
約一ヶ月の後、仙斉は長い旅から帰ってきましたが、何か考え込む日が多くなりました。
仙斉は、この岩渕の里の人たちがお参りする明神さまがないことに心を痛めていたのでした。
主膳や里の人にこの悩みをうちあけた仙斉は、大和へもどって三輪明神をこの里にむかえいれることにしました。
仙斉が運んできた三輪明神のご神像に神さまがやどっているとされる物は、石であったか、板のようなものであったかわかりませんが、里の人たちはたいへんよろこんでこの新しい神さまをむかえました。
さっそく、小さな社(やしろ)(神さまをまつる建物)が建てられ、仙斉は三輪明神の世話をするため、そのすぐそばに小屋をたてて住みました。 この小屋を「紫の庵(むらさきのあん)」と名付けました。 社を建てたところは今も「明神谷」とよばれている所です。
ある夜のこと、仙斉は夢の中で三輪明神の声を聞いたような気がしました。その声は重々しくどこか苦しそうでした。
聞きとれませんが、たしか、次のように言っているようでした。
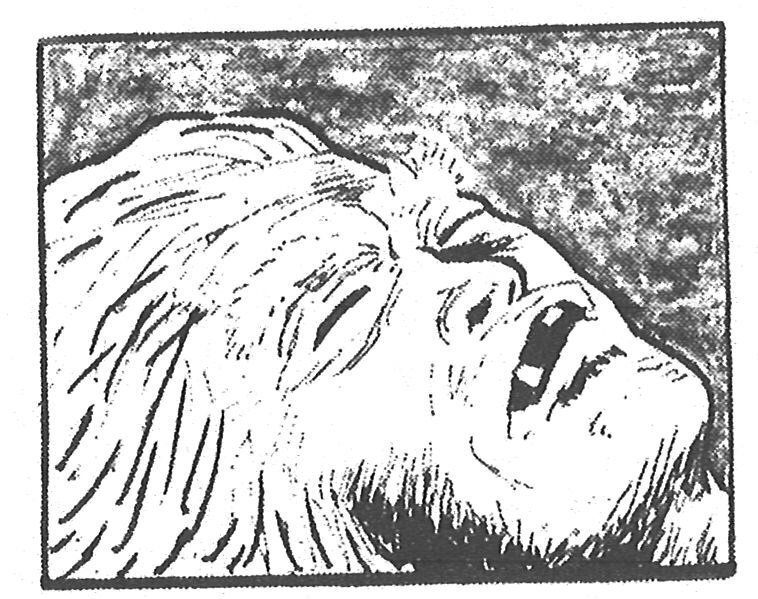
「広々とした大和から、こんなにせまく小さな谷にまつられて苦しくて仕方がない。どこかもっと広い土地へうつしてくれ。」
声はしだいに小さくなりました。仙斉は、次の日、重い足どりで三輪明神のご神像をせおい、上津木の老賀八幡(ろうがはちまん)神社の横へまつりました。
それは、天治(てんじ)二年(一一二五年)、九月のことでした。井窪仙斉や小原主膳の子孫は今もなお岩淵に何軒か同じ姓で続いています。

ヤマトと岩渕の里 大昔からの強いつながり
今から千七百年も前(四世紀前半)に、ほぼ全国を統一したといわれる大和朝廷は、今の天皇家の祖先を中心としていくつかの豪族が集まったものでした。朝廷をいる者は「大王(おおきみ)」と呼ばれ、オオキミは現在の桜井市三輪山のふもと磐余(いわれ)に大きな宮をつくって住んでいました。
私たちは「ヤマト」といえば、奈良市や斑鳩(いかるが)、明日香(あすか)(飛鳥(あすか))などを思い浮かべますが、もとは、この三輪山のふもとの磐余(いわれ)のあたりが「ヤマト」であったのです。

磐余(いわれ)では全国から送られてくる品々の市がひらかれ、また、ここは神をまつる儀式のおこなわれる神聖な土地でもありました。
この三輪山のふもとには、いろいろな専門の仕事をする笠縫部(かさぬいべ)といわれる人々が多く住んでいました。
岩渕の三輪明神は三輪の里から勧請(かんじょう)(神仏の霊をむかえること)されたという伝説について、本社の大神神社(おおみわじんじゃ)で宮司をされている佐藤氏(郷土史研究家)は、
「笠縫部(かさぬいべ)が大和と紀伊を結んで存在していたと考えしめるものがある。三輪明神社があることのほか、金屋(かなや)とか湯笠(ゆかさ)(湯浅の昔の名前らしい)という地名なども三輪の笠縫部が(かさぬいべ)が移り住んだ土地だと想像される。」
と言っておられます。
また「自分の住む土地に『神を勧請(かんじょう)する』ということは、ひとりの月参りなどがきっかけになるようなそんな軽いものではなく、以前からよほど両方の土地に強いつながりがあるか、里の人々の多くが移転してきてもといた土地の神を勧請する、という場合などの方が自然である」とも話しておられます。
井窪(いくぼ)氏はヤマトの笠縫部(かさぬいべ)か
三輪明神を岩渕に勧請(かんじょう)した三輪の里人、井窪仙斉(いくぼせんさい)とはどういう人だったのでしょうか。
佐藤氏は「おそらく笠縫部(かさぬいべ)であったのではないか。」と推定されました。では、どのような仕事を専門にした笠縫部だったのでしょう。
三輪は古くから製鉄の中心地でもありました。郡内には金屋、湯浅、吉備など製鉄に関係のある地名も残されており、これらに関する笠縫部もおそらくヤマトからこの地にやってきていたことでしょう。仙斉が娘を連れてきたという話は、製鉄の作業をする中に女性の役割が大きかったということとも関係はないでしょうか。つまり、女性の技術者もいなければ、製鉄文化を伝えにくいという事実かも知れません。
尚、奈良県大和盆地には電話帳によると三十軒の「イクボ」の姓があり、現在、岩渕にある井窪家は伝説どおり大和の三輪の里からやってきたことは確かであると思われます。
岩渕の三輪明神の伝説は、広川町の最も奥地である岩渕がすでに、千二、三百年も前からかなりな人里として開けていたことを私たちに教えてくれました。
もし、いつの時期か、物語として作られていなければ、岩渕がはるか昔にヤマトと深いつながりがあったことなどまったくわからなくなっていたことでしょう。
名島(なしま)も古代、製鉄の地
江戸時代後期に出版された「紀伊続風土記」には、南金屋地区のことについて次のように書いています。
「金屋はずっと昔の文書には釜屋(かまや)と書いてあり、古くは、名島で鋳物(金属をとかし、型にいれて作った物)職人をしていた者がこの地にうつってきたので、金屋とよばれるようになった。」
この記録が確かとすれば、名島も古くから製鉄を業とした一団がいたようです。奈良時代、広、湯浅地方は「奈郷(なごう)」と呼ばれていましたが、この「奈」は、名島の「名」を指しているとすれば、ここは高い文化を持った製鉄の地、当地方の大きな集落があった土地ではないかとも想像されます。
名島と金屋に接している殿(との)地区には一般に「オケチ大明神」と呼ばれ、「気鎮社(けちんしゃ)」といわれる小さな社があります。これは、三輪明神社(みわみょうじんしゃ)にふくまれる「華鎮社(けちんしゃ)」=花鎮(はなしずめ)の社(やしろ)と同じではないかと思われます。
名島もやはりヤマトと何かつながりがあったのでしょうか。
武士団「湯浅党」の成長

荘園はほんらいは国に税を納めなければなりませんでしたが、領主となった貴族や寺社は、その高い地位を利用して、税を納めなくてもよい田にすることが多くなり、国の役人が立ち入ることさえできないようになりました。
こうして地方の政治が乱れてくると、荘園に荘官としてやってきた人々などは、自分たちの手で荘園を守るために力の強い男たちをやとい、武器をもたせました。彼らはやがてたたかうことを専門にする集団となりました。これが武士団といわれるものです。
在田(ありた)地方では、湯浅庄の荘官であったと思われる湯浅氏が武士となり、平安末期、宗重(むねしげ)の代になって「湯浅党」という強力な一団をつくり上げました。
在田郡はこのころ、「宮前(みやざき)」「保田(やすだ)」「宮原」「糸我(いとが)」「湯浅」「比呂(ひろ)」「藤並」「田殿」「石垣」「阿弖川(あてかわ)」の十の庄にわけられていました。
湯浅党はこのうち、宮前庄(みやざきのしょう)、比呂庄、阿弖川(あてがわ)庄をのぞくそのほとんどを支配するほどにのし上がってきたのです。
そして、在田の中心地は湯浅にうつりました。
この時代、宗重が湯浅町青木の小さな山上に築いた湯浅城はとちゅう焼かれたりこわれたりはしましたが、約三百年間もこの地を守る砦として重要な役目をはたしました。
平清盛(たいらのきよもり)を助け平家の家人(けにん)に
平清盛の一行が熊野詣のため切目(きりめ)まできた時でした。都で、源義朝(みなもとのよしとも)らが兵をあげたという知らせがはいりました。
すぐにとってかえそうとした時、いちはやくかけつけ、清盛の一行を京都まで無事に送ったのが湯浅宗重(むねしげ)ひきいる湯浅党武士団でした。この時のいくさは「平治(へいじ)の乱」とよばれていますが、この戦いに勝った清盛は、宗重(むねしげ)を平家の直接の家来である「家人(けにん)」としての地位を与えることにしました。
また、熊野によせる信仰もこのことがあってからますます高まっていきました。
平家(へいけ)という当時最大の力をバックに湯浅党はさらに勢いを増していきました。比叡山(ひえいざん)でおこった大きなあらそいをしずめるために清盛は軍団をさしむけたとき、その侍大将には宗重が命じられたということからも、湯浅党がどれほど実力をつけていたかがわかろうというものです。

宗重(むねしげ)の決心、有利な源氏へ
天下をひとりじめしたような平氏一族も、ついにライバル源氏に完全にほろぼされる時がきました。
平家の家人(けにん)として力をふるった湯浅党の一族の命ももはやこれまで……と思われました。
しかし、時代の流れをよむ宗重は、文覚上人(もんがくしょうにん)の力を得て、源氏にくらがえすることにみごと成功したのです。
さらに宗重にとっては幸運なことがおこりました。それは、源頼朝(よりとも)、義経(よしつね)の間に仲たがいが起ったのです。鎌倉にいる頼朝は弟の義経を捕えるために「追捕使(ついぶし)」(のちの守護)を各地におきました。
けっきょく頼朝(よりとも)は義経(よしつね)を討ってしまうのですが、この仲たがいで、紀伊の武士のほとんどが義経の方に心を寄せていたのに対し、宗重(むねしげ)だけは頼朝方(よりともがた)につきました。
こうして、湯浅党は、今度は一転して源氏の直接の家来(御家人(ごけにん))として、次の鎌倉時代にも在田地方のナンバーワンとして勢力をふるうのです。 このかげには、鎌倉においてけんめいに頼朝にうったえて、湯浅一族の命を救った文覚上人(もんがくしょうにん)のことをわすれるわけにはいきません。
<挿話>
湯浅党を救った文覚上人(もん がくしょうにん)

父のおこした「平治(へいじ)の乱」によって伊豆に流されていた源頼朝。文覚上人もそのころ、後白河法皇(ごしらかわほうこう)のいかりにふれて伊豆にとばされていました。
いつしか、文覚を師とあおぐようになった頼朝に対し、上人(しょうにん)はしきりと平家を倒すことをすすめ、ひそかに京に帰り、平家を討てという命令(院宣(いんぜん))を持ち帰りました。
やがて、源平の合戦が始まり、しだいに平氏はおされていきました。
屋島の戦いでも平氏は敗れ、その一族の平忠房(たいらのただふさ)は家来である湯浅宗重のもとに逃げのびてきました。宗重はこの忠房を湯浅城(宮原の岩室城(いわむろじょう)という説もある。)に三百人の兵がかくまいたてこもりました。そのころ、比呂の鹿ヶ瀬の峠に砦を築いていた熊野別当湛増(くまのべつとうたんぞう)らは、湯浅城をはげしく攻めましたが、三ヶ月たっても城はなかなか落ちません。
さて、この知らせを聞いた文覚はたいへん心を痛めました。
というのは、文覚が日ごろ特に目をつけて教えみちびいていた弟子の父はこの宗重だったからです。
このままでは平氏とともに湯浅党の人々も消される運命が待ちかまえています。なんとかして、湯浅党を救いたい。
そこで文覚は頼朝に対し、「忠房をあなたのいる鎌倉に差し出せば湯浅党の一族を許して下さるように」と願い出たのです。
頼朝の方も、前から文覚によって湯浅党の実力を知らされ、宗重は平氏をみかぎり源氏方にくらがえしようとしている本心であることを聞かされていたものですから、この願いはききとどけられることとなりました。
その年の十二月、忠房は鎌倉へ送られていきました。
在田(ありた)をねらう熊野別当湛増(くまのべっとうたんぞう)
鹿ヶ瀬峠(しかがせとうげ)に城を築く
熊野街道が鹿ヶ瀬を通っているすぐそば、現在、関西電力の鉄塔がたっている所は峠でも最も見はらしのきく場所です。
雑木林にうもれていますが、よく見ると平らになった壇がいくつもあり、それは大きな石組みによってつくられた曲輪(くるわ)(城や砦の構築物のあった所)であることがよくわかります。
ここには平安末期に熊野の勢力がやってきて構えた城があったのです。 城といっても砦のようなものであったのですが。
比呂庄の東部が熊野の領地になったことは先にのべました。
このころ、熊野の水軍(海賊といわれていた)はたいへん強く、源氏方も平氏方もこれをなんとか味方にひきいれようと、結婚により親類関係を結ぶなどずいぶん苦心していました。
熊野も最初は平氏方についていましたが、別当(とりしまりの中心になる職)に湛増(たんぞう)という僧がなってからは、源氏方に組みするようになり、壇ノ浦の戦いでは、その強力な水軍がものをいって平氏は敗れさりました。
牟婁地方をおさえていた熊野の軍はさらに飯高(ひだか)地方にも進み、在田をねらっていました。
鹿ヶ瀬の城はこのようなときに築かれたのです。
しかし、在田地方には手ごわい湯浅党がそのほとんどをおさえています。なんとか、湯浅党を討つ機会はないものかとチャンスをうかがっていたとき、屋島の戦いから平忠房(たいらのただふさ)が湯浅宗重のもとへにげこんできたというわけです。

みごとな主眼寺(しゅがんじ)の観音像
西広にある「独開(どっかい)」という地名はどういうことでつけられたのかはっきりしません。しかし、平安の昔にこの地に建てられていたという手眼寺(しゅがんじ)の山号が独開山(どっかいざん)であったといいますから、仏教に関係ある言葉ではないかと思われます。
現在の手眼寺は小さな堂を残すだけですが、その中には、みごとな「千手観音像(せんじゅかんのんぞう)」がまつられています。
これだけの観音像をおくことができた当時の手眼寺の大きさ、よほど重要な寺であったことなどがしのばれます。

大飢饉(ききん)の発生
一一八〇年夏の日照りは、その後三年にわたる有史以来の大飢饉を西日本にもたらしました。
源氏と平氏のはげしい戦いが源氏の勝利に終わった原因のひとつにこの大飢饉を上げる学者もいます。というのも、源氏のなわばりである東日本はこの時逆に豊作であったのです。
熊野別当湛増(べっとうたんぞう)が北上して鹿ヶ瀬(ししがせ)氏をおさえ、在田の地にまでやってきたのは、この大飢饉のため少しでも食糧を多く手に入れる必要にかられたからでもあったともみられます。
有名な「方丈記(ほうじょうき)」にはこの時のようすをこう書いています
「塀や道のほとりに飢えて死んでいる人は数もわからないほど多い。死体をほおむることもないので、死体のくさるにおいが町や村にたちこもり、しだいにくさって姿を変えていくありさまは目もあてられない。みな力つきて道や川にはいきかう車や船影も見当らない。
京の仁和寺(にんなじ)の隆暁法印(りゅうぎょうほういん)という人、お経もあげてもらえず死んでいく人を気の毒に思って死体をみつけては額に「阿字(あじ)」と書いて仏の縁(えん)を結ばしたが四月五月でその数は四万二千三百あまりにものぼった。」
