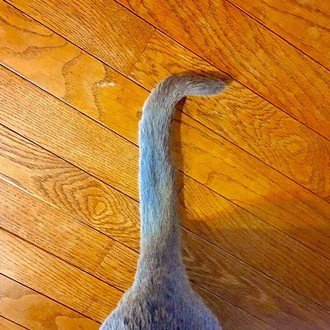【宅建勉強】4つの分野と、取り組む順番について
宅建試験で出題される問題には、大きく分けて4つの分野がある。「権利関係」「宅建業法」「法令上の制限」「税・その他」というのが大枠だ。
出題数は分野ごとに異なり、その難易度も大きく変わる。
出版社によって多少の差はあると思うが、ボリュームが多いものから並べると概ねどこも権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他の順で冊子の厚みが異なると思う。
では、実際の試験問題はこのボリュームに比例した出題数になっているのかというと、実はそうではない。範囲が広いからと言って、その分そこからたくさん問題が出るというわけでもないのだ。
つまり、分野ごとの難易度も加味しつつ、学習範囲と出題数のバランスを考えどの分野により力を入れるかを決めていくのも、合格への大きなポイントとなる。
問題構成と分野ごとの出題数
宅建試験は、基本的に何問目〜何問目にこの分野の問題が来るというのが決まっていて、各分野の出題数も例年の流れでいくとほぼ固定されている。
出題される順番と配点はこんな感じ。
権利関係: 14問 問1から問14まで
法令上の制限: 8問 問15から問22まで
宅建業法: 20問 問26から問45まで
税・その他: 8問 問23から問25までと問46から問50まで(免除科目)
そして、よく議論されるのがこれらをどのような順番で取り組めばいいかという問題だ。
各予備校のコラム記事やネットの情報、受験した先人たちがおすすめしている順番は、おそらく以下の2種類が多いかなと思う。
①権利関係→宅建業法→法令上の制限→税その他
これは、4つの分野の中で一番勉強する範囲が広く内容が難しい上に、50問中14問出題される権利関係から始めるという方法。
各出版社の分野別テキストでも一番最初にこの権利関係の冊子が来ているものが多い。(試験で問1に来るからというのもあると思うけど)
難しいからこそ後回しにせず、早めに着手してしっかり理解するという作戦だ。
②宅建業法→権利関係→法令上の制限→税その他
もう一つは全50問中20問と一番出題数が多い宅建業法から取り掛かり、次に配点の高い権利関係を固めていくという方法。
宅建業法は権利関係よりも難易度的にはとっつきやすく暗記項目も多いため、まずは宅建業法を極め次に権利関係、法令上の制限と進んでいくという作戦である。
そして、私が実際に取り組んだ順番はどうだったかというと、こちら。
宅建業法→法令上の制限→権利関係→税その他
①とも②ともちょっと違う、権利関係を3番目に取り掛かるという作戦。
なぜ私がこの順番で取り組んだかは後述するが、まずその前に、そもそもこれらの分野がどんな内容なのかというざっくりとした概要と、全く予備知識がなかった私が取り組んでみて感じた印象、体感みたいなものをまとめてみようと思う。
どんなことを勉強するのか?
単品購入は100円、300円のマガジン購入で「宅建まとめマガジン」に入っている記事が全て読み放題になります。
メンバーシップ内でも読めますので、宅建記事以外にも色々読みたい方はそちらもおすすめです。
ここから先は
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が参加している募集
サポート、嬉しいです。小躍りして喜びます^^ いただいたサポートで銭湯と周辺にある居酒屋さんに行って、素敵なお店を紹介する記事を書きます。♨🍺♨