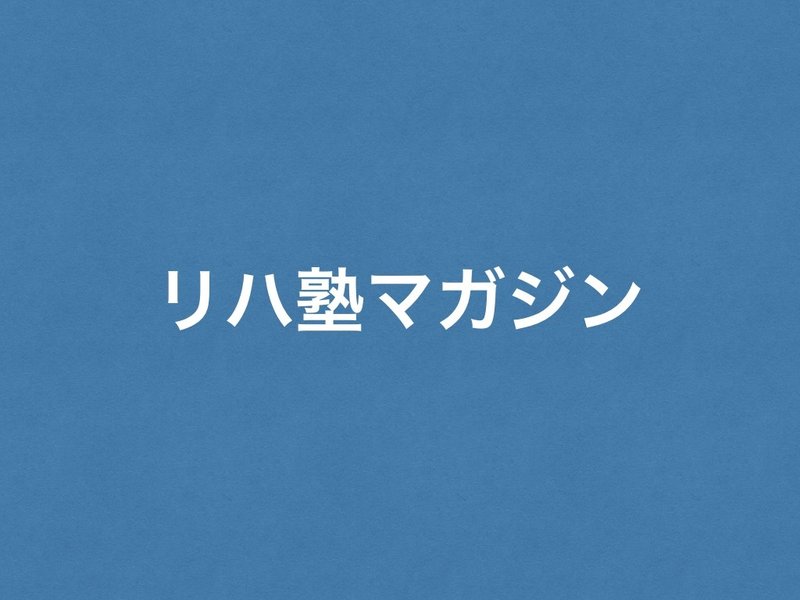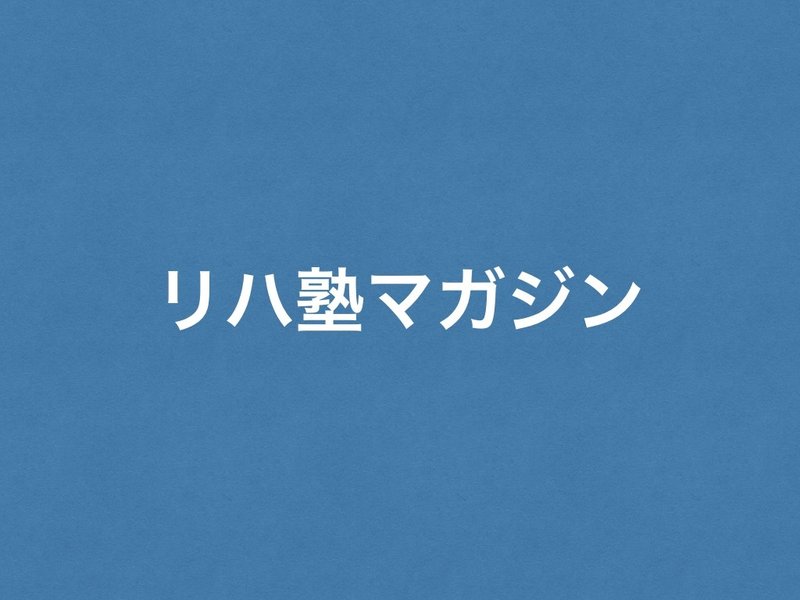腸脛靭帯の硬さ、ほぐすのは正しい?間違い?
リハ塾の松井です!
臨床であるあるな問題の1つに「大腿外側の硬さ」があります。
もう少し具体的に言うと、腸脛靭帯の硬さが挙がることが多いかと思います。
腸脛靭帯は脛骨外側に付着し、硬さがあると膝関節屈伸の動きに影響を与えます。
また、腸脛靭帯は大腿外側全体にかけて走行する長い組織という特性上、腸脛靭帯に頼った姿勢・運動制御によって遠心性にパツパツに伸張されていることも多々あります。
なので、硬いからといってマッサージやモビライゼーションを安易に選択することは逆効果になる