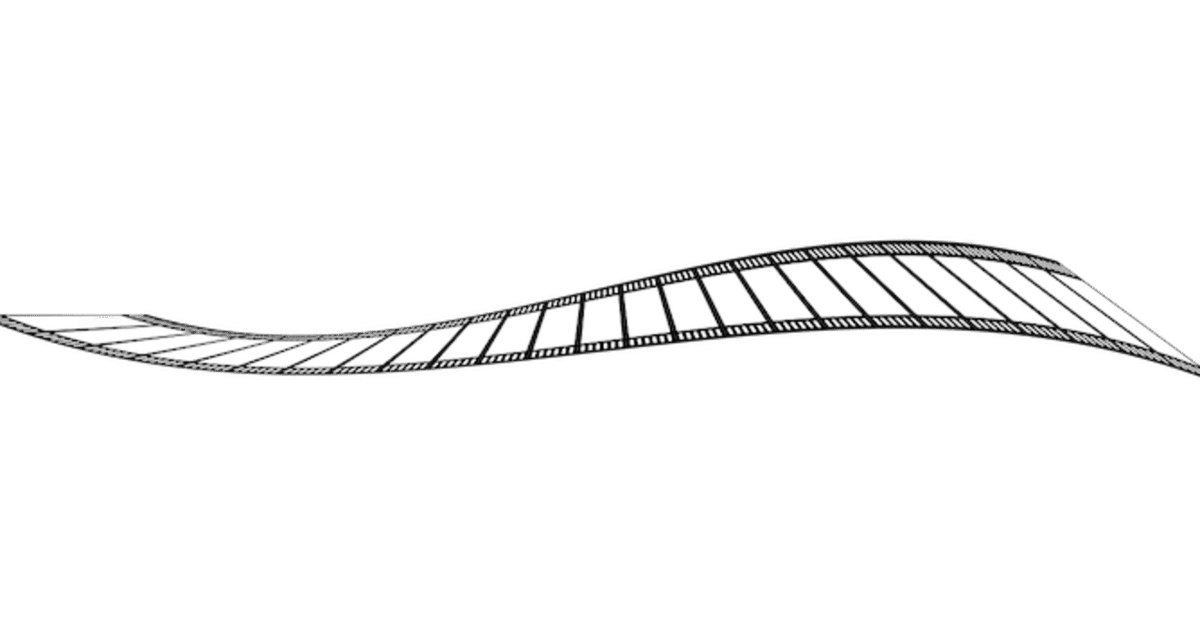
今日見た映画(2020/06/26)
・極道の妻たち 監督:五社英雄(1986年)

いわずと知れた極妻シリーズの第一作がNetflixで配信されていた。ヤクザ、暴力、セックス。こうした刺激的なイメージばかりが先行して食指が動かなかったことは認める。公開から34年もたって初見とは恥ずかしい限りだが、結論から言うと傑作だった。岩下志麻の徹底した役作りについては言及するまでもない。自分より上の立場の人間には絶対忠誠。下の立場のものには大きく構えて支援を惜しまない。まさに「姐御」という言葉を体現している。しかしこの作品で岩下志麻に勝るとも劣らず魅力的なのは彼女の妹・池真琴を演じるかたせ梨乃。自分では人生を選べない真琴が徹底的にめちゃくちゃにされる。姉には勝手に御曹司との縁談を押し付けられ、グアムで再会した世良公則演じるヤクザにはレイプされ、半ば強引に結婚させられる。それでも組事務所の女将として構成員たちに料理を振る舞う健気な真琴。特殊ではあるが”幸せな家庭”を得たように見えたのもつかの間。直後にカチコミに遭遇し、さっきまで自分の手料理を食べていた男たちが目の前で射殺される。姉との取っ組み合いの末(日本映画史に語り継がれる例のシーン)、これからは姉妹の関係ではなく互いに極道の妻として生きていくことを決意する。やっとの思いで世良公則のもとに戻るも再び襲撃。夫を刺されたことへの報復に手元にあった拳銃でヒットマンを射殺する。かたせ梨乃のラストシーンは一度見たら絶対に忘れない。片手に拳銃。両胸を露わに呆然とした表情。体中に返り血を浴びている。腹を刺されて虫の息の世良公則は瀕這うように彼女の乳首を吸っている。何かの宗教画、もしくはフランシス・ベーコンの絵画に見紛うような映像。「極妻」をジャンル映画として侮るなかれ。こんなものを演出できる五社英雄。すでに故人ではあるが恐るべき才能だと思った。
・砂の器 監督:野村 芳太郎(1974年)

漫才コンビ米粒写経(特に右側の天才)の影響で遂に見てしまった。原作者の松本清張が試写で「原作を超えた」と言ったとか言わないとか。居島さんが言っているのだから信頼できる話なのだろう。殺害された被害者の身元すら明かされない前半部分。「カメダ」の謎を解くために日本中を奔走する丹波哲郎演じる今西刑事。被害者の身元が判明するものの殺害される動機が全く見当たらない。そしてピアニスト和賀英良が演奏する「宿命」にのせて、丹波哲郎が事件の全容を解き明かしていく。本浦秀夫が和賀英良を名乗るようになるまでの辛い過去。存在を隠さざるを得なかった父親。数十年ぶりに我が息子の写真を見て「こんな人は知らない!」と叫びながら慟哭する父親。音楽にのせて物語がクライマックスへと向かっていく。捜査会議で報告する体で丹波哲郎のモノローグが続くのだが、これがなんと説明的なナレーションには聞こえない。居島さんが時に笑いを交えて、時にシリアスな口調で繰り返しこの映画を語る理由が少しだけわかった。
・泥の河 監督:小栗康平(1981年)

昭和の終わりが近づいた1981年に公開されたモノクロ映画。「戦争が終わって10年」というセリフで時代が読み取れる。川べりの小さなうどん屋の息子と対岸につながれた船で暮らす少年とその姉との交流を描く。うどん屋を切り盛りする父親はどうやら満州に出征していたようだ。戦死した仲間がいる一方で、今もなお生き続けていることに虚しさを感じている。優しい母親は実は略奪婚。夫には本来結ばれるべき人がいたのに、今こうして自分と暮らしていることに申し訳無さを感じている。対岸の船で暮らすのは母子3人家族。「夜に船に来ちゃいけないよ」という言いつけを破り見てしまった真実。船で暮らす家族は母親が身体を売ることで生計を立てていたのだ。2つの家庭の出会いのシーンからその事実は匂わされていたが、うどん屋の息子が決定的な瞬間を目撃することをきっかけに物語が幕引きを迎える。橋のあちらとこちらを行き来する子どもたちの交流から浮き彫りにされる戦後日本。貧困から這い上がろうとする人。慎ましく生活する人。社会の不条理に翻弄される子どもたち。たったひと夏の出来事を語ることで高度成長直前の日本へとタイムスリップさせてくれる素晴らしい作品だった。そして2回しか顔を見せない加賀まりこから目が離せない。
