
ドリアンとかミクソリディアンとか(前編)
一応 全部 書き出しましょうか?
アイオニアン Ionian イオニア
ドリアン Dorian ドリア、ドーリア Doric mode
フリジアン Phrygian フリギア
リディアン Lydian リディア
ミクソリディアン Mixolydian ミクソリディア
エオリアン Aeolian エオリア
ロクリアン Locrian ロクリア
これら「各 教会旋法(church mode, Gregorian mode)の名です」と紹介してしまいたい所なのですが、そういう訳にいかなくなってしまっている、というのが今回のトピックです。
この状況が、数多の人々を困惑に陥れていると推測します。
コードスケールを齧るのをやめて下さいお願いします(本音)
さっきの7つの名称(とその表記揺れとか)が使われる文脈は、音楽分野に絞る場合、それでも可能性として2通り考えられます。
一つは「旋法(mode)」にまつわる話題。
もう一つは「コードスケール(chord-scale)」の話題の場合です。
この二つは、とある理由から「すごく明確に区別」しておきたい。
誰のためか?
別に「特に困惑していない」なら、区別視しないで地続きだと考えていても良い…とも言い得るのかもしれませんが、その感性は少数派な気がします。
※以下、「コードスケール」を「CS」と略します。
🔹
前述の両話題で「これらの名称が共通して出て来る」理由は明快です。
CSの側が、教会旋法の呼称を流用したからです。
というわけで「偶然の一致」とかではないし関係あるのは確かなのですが、しつこいですが「両者が同じ」だと考えてしまうことを推奨しません。
どう違うのか。
“旋法” の話をする場合は、中心音(tonal center)の話題が欠かせません。
(※この記事にて後述)
一方でCSシステムという(即興演奏の)理論は「スケールを用いるだけ」であって、先の “旋法” における「中心音という概念の重要性」の話は、ほぼ無関係の文脈と言って差し支えありません。
だから、要するにCSシステムは、本当に「ちょうど都合が良かったので、名称群を流用しただけ」だと考えておき、
CSの話をする時は、「ドリアン」とか出て来ても「“旋法” の話ではない」のだと思って臨む必要があるかもしれない…人によっては。
――というのが、今回の話です。
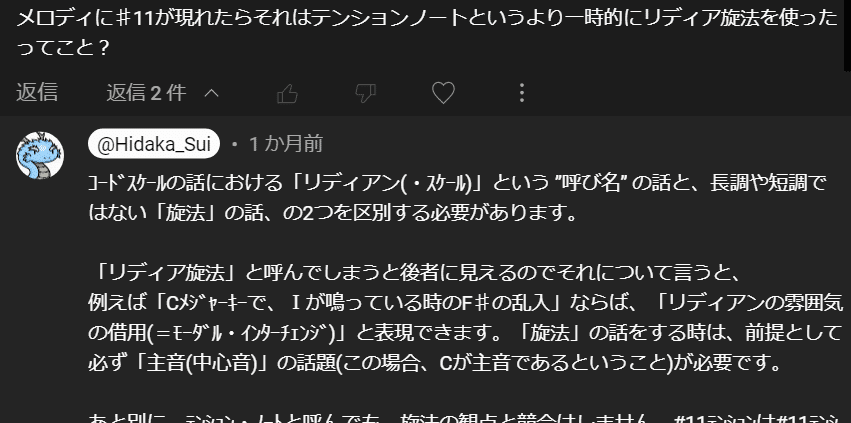
中心音(tonal center)
先に「中心音」の説明をします。
恐らく語の用例の数が不充分なため、一概に決めつけできない所はあるかもしれませんが、これは ”総称” です。
調性的な音組織における「主音(tonic)」、
教会旋法【い】における「終止音(final)」or「フィナリス(羅 : finalis)」
あるいは調式(Diàoshì)における「落音(Luò yīn)」or「結音(Jié yīn)」
…などと「文化圏とその体系によって呼称が異なる」というような事情は度外視してしまいたい時に、「中心音」とひっくるめて呼んで済まします。
なので、読み進めるに当たっては「主音 的なもの」だと思って下さい。
今回は簡単に流してしまいますが、世界各地の音楽の実例に「中心の音」とでも呼ぶべきような概念は、不思議と共通して存在しているみたいです。
そうでなければ “総称” なんて成り立たないので。触れてだけおきます。
教会旋法(適当)
事前知識としてもう一つ必要なんです。前編はこれの説明で終わります。
🔹
西欧の「教会旋法」と呼ばれるモノ、勉強熱心な方ならお気づきのはずですが、どう見ても 2つ(?)あります。
【あ】冒頭のように 7種(または省略して 6種、5種)紹介されるケース
【い】4種、または「ヒポ~」等という名称と共に 8種 紹介されるケース
「第三旋法」とか数字で呼んでいる場合もあります。それは【い】です。
の2つです。
【い】は、「音楽史」としての、より古い概念としての教会旋法です。
“こちらの” これらについて調べるのは、「歴史を勉強したい」方のみで良いと思います。「作曲の勉強」としては、意義に乏しいです。
聞いたことがあるので、万が一その場合は勉強して下さい。)
今回は、“中世の” 教会旋法【い】のことは、忘れて下さい。
1...2の...ポカン。
🔹
厳密にはさらに「古代ギリシアの奴」含めて3つあるかもですが、流石に割愛します。
(“正確さ” を以て)教えることが出来る人間が存在するのか怪しいです。「何が正確か?」すら、今日わからないな、という状況です。
ルネサンス期の人も、ギリシア語の解釈ミスしたらしいです。
我々は、そうして生まれた「間違ってた方の呼称」を有難く受け継いで、今日 使っています。
――Although both diatonic and Gregorian modes borrow terminology from ancient Greece, the Greek tonoi do not otherwise resemble their mediaeval/modern counterparts.
ダイアトニック・モード(注:【あ】を指す。)とグレゴリアン・モード(注:【い】を指す。)は、共に古代ギリシアの用語を借用しているが、
件の古代ギリシアの「トノイ」(注:前述 “古代ギリシアの奴”)とは、(名称以外の)その他の点では似ていない。
https://en.wikipedia.org/wiki/Mode_(music) 2023/12/08 閲覧
古代ギリシアのは「関係が薄い」と思って下さい。1...2の...ポカン。これが元祖のはずなんですけど。
念押し確認しときます。
今日でいう “教会旋法" は、中世の教会旋法から呼称を引き継ぎ、
中世の教会旋法は、古代ギリシアの音楽理論(※これは教会旋法とは呼ばない)から一部 呼称を借りている。
でも正直この辺、調べてもよく分かりません。要出典(無理みたい)。
教会旋法(“Modern” Western modes)
※この記事は以下、全て「旋法」の話です。後編までCSの話は無し。
【あ】とは、今日における「長旋法と短旋法 以外の音組織」の実例です。
厳密には区別し得る部分ですが、「長旋法」は「長調」、「短旋法」は「短調」と読み替えても、概ね困らないと思います。
「長調とも短調とも違うやつら」の話です。
(↓ここスルーできない人用)
と言っても「アイオニアン」と「長調」を区別するケースは皆無なので、ここは同じです。
同様に「エオリアン」と「短調」も、自然短音階(natural minor scale)を選択するなら同じです。
「短調」は、構成音がフレキシブルな所も含めて、“短旋法” という(最広義の)旋法と見なせる。
🔹
「旋法」や「モード」と言えば、現実的に思い浮かべる意味があるのは、
【あ】の意味での「ドリアン」「フリジアン」「リディアン」
「ミクソリディアン」「ロクリアン」の(7-2=)5つになります。
この内、中世(あるいは中世ファンタジー)のニュアンス、またケルトの系譜などで、圧倒的に「ドリアン」、
次に、ブルース~ロックの系譜などにて、「ミクソリディアン」が頻出となります。
続いてヘビーめなロック、フラメンコ、日本風などにて「フリジアン」、
最後の「ロクリアン」は、かなり使い方に思案を要する、異端児です。
「リディアン」は使い易いんだか使い難いんだかよく分からん感じです。
🔹
なお、以上の参考曲は「厳密にその旋法からはみ出さないこと」を意図した作品では全くないため、あくまでもニュアンスの参考程度にして下さい。
現実的にも、この感じで「旋法感を意識してみた」程度に使うことの方が普通かと思います。そうしないと退屈なんでね。
拙作『7つの前奏曲』は、実質「7つの教会旋法による(部分もある)前奏曲集」です。
以下は比較的 長区間に渡って「厳密め」な例です。
ドリアン:Toby Fox『ruins』0:00~1:01
ミクソリディアン:植松伸夫『チョコボのテーマ』、Enya『Orinoco Flow』※1
フリジアン:Infraction & Alexi Action『Dune』※2、鷺巣詩郎『DECISIVE BATTLE』※3
ロクリアン:(考えようによっては)バーバパパ『ウ"ィ"エ"』主部ベースライン
リディアン:P-MODEL『美術館で会った人だろ』サビ以外 割とずっと ※4
※2 動画内 “Trap Part” のみ(ちゃんと)旋法としての Phrygian Dominant みたいになっている。
※3 主にメロディのみ注目する場合。和音が Em になったり E△ になったりするため。
※4 前奏だけ左のギターが (階名)シ♭ を鳴らすため、
(ちゃんと)旋法としての Lydian Dominantみたいな稀有な感じになっている。
せめて、旋法らしく
さて、今日の7つの教会旋法(【あ】= Modern Western modes です。)は、「ピアノの白鍵」を用いて説明されることがよくあります。
ここから先は
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
