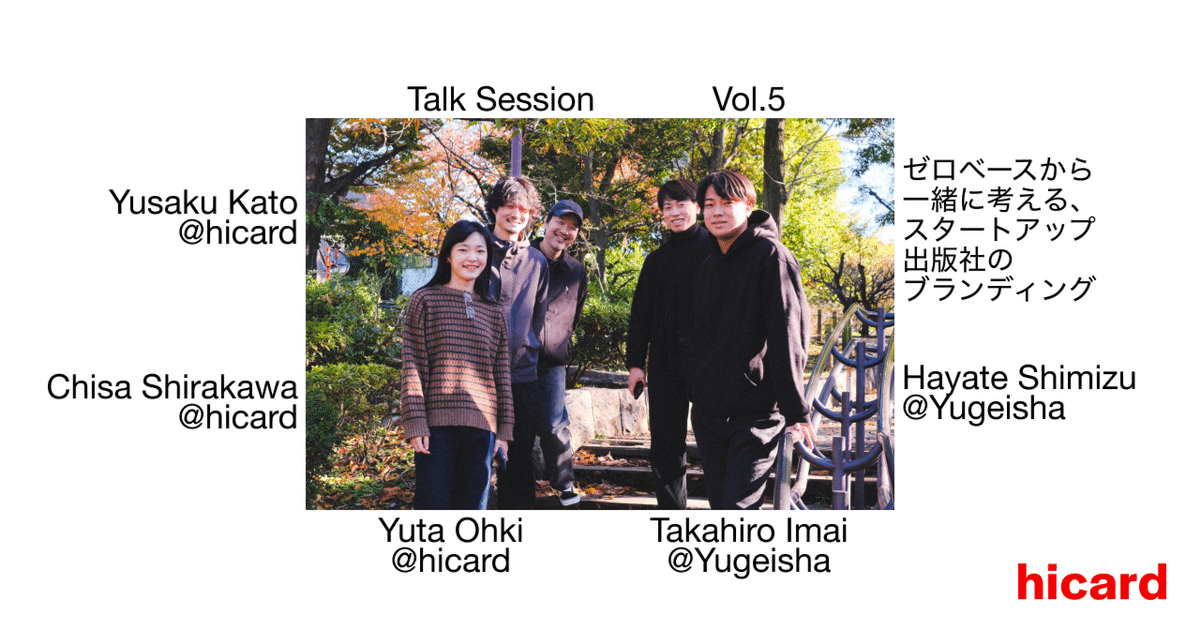
ゼロベースから一緒に考える、スタートアップ出版社のブランディング
こんにちは!hicard PRのannaです。
hicardは、株式会社游藝舎のWebサイトリニューアルからブランド構築までを手がけました。游藝舎の代表取締役である今井昂洋さん、取締役の清水颯さんと、hicardのメンバーでプロジェクトを振り返ります。
▼ 株式会社游藝舎のコーポレートサイト


インタビュイー
株式会社游藝舎
代表取締役 今井昂洋さん
取締役 清水颯さん
株式会社hicard
アートディレクター 加藤優作
デザイナー 白川智早
ディレクター 大木雄太
游藝舎のらしさを伝えるWebサイトに
―― まずは游藝舎さんについてお話しいただけますか。
清水: デジタルコンテンツが膨大な時代において、一過性に終わらない、100年後も読まれるような書籍を作り残していきたいと思い、2023年の7月に出版社として游藝舎を設立しました。今は実用書やビジネス書をメインで扱っていますが、これから絵本やアートブックなども手がけたいと考えています。

―― Webサイトのリニューアルを考えた理由を教えてください。
清水: 今までのサイトは会社設立に合わせて取り急ぎ作ったもので、設立から1年ほど経った今、実際に出版物も出てきて会社としてのフェーズが変わってきたので、改めて游藝舎の取り組みや「らしさ」を伝えるWebサイトにしたいと考えました。

とにかく良いものを作りたい
―― 依頼先としてhicardを選んでいただいた理由は何だったのでしょうか。
清水: hicardの代表takeさんは前職の時の同僚で、お互い退職後も仲良くしていました。hicardさんがオフィスで開催するパーティーにもよく遊びに行っています。takeさん以外のメンバーの方々とも接する中で、とてもフレンドリーな会社だと感じています。
今井: 私は今までhicardさんとは接点がなかったのですが、とにかくクオリティの高いサイトを作りたかったのがまずあって。
游藝舎を立ち上げるきっかけの一つでもあるのですが、あまり知名度が高くなくても本当に面白い作家さんであれば私たちの力で広めていきたいという考えがあります。そういった方々が游藝舎に出版を依頼しようと思った時にまずWebサイトを見ると思うのですが、その時にサイトのクオリティが高くないと依頼しようと思わないですよね。
清水の繋がりでhicardさんのことを知り、今までの実績も良かったのでhicardさんにお願いすることに賛成しました。

「そうそう、これこれ!」の提案を出すためのコミュニケーション
―― プロジェクト進行中に感じたことはありますか。
今井: 制作会社に依頼をすると、思っていたものと違う仕上がりになるという経験は珍しくありません。でもhicardさんは、まず私たちが要望を伝えた時に「こうした方が良いのでは?」と積極的な提案が多くて、その豊富な引き出しやアイデアに驚かされました。初回のロゴ提案の段階から、「そうそう、これこれ!」と思えるアウトプットが毎回返ってくるのです。
清水: 今までの経験だと、枠に収まった提案が多くて、こちらが厳しめにフィードバックをしてようやくこれなら良いかなと思えるものが出てくる…ということが多かったのですが、hicardさんは常に柔軟な提案をしてくれたのでとても助かりました。私たちが積極的に具体的な提案やリファレンスを提示したわけではなくゼロベースから一緒に考えてもらったのですが、游藝舎について「うちはこういう会社なんです」「こういうことをしていきたいんです」と方向性を伝えた上でhicardさんにさらにヒアリングをしてもらい、それをもとに制作を進めていただきました。要件としては「インパクトのあるサイトを作りたい」という非常にざっくりとしたものでしたが、その中でしっかりと形にしていただけたことが印象的でした。

―― hicard側で提案時やプロジェクトを進める中で考えていたことや感じたことを教えてください。
加藤: 最初のキックオフの段階で、游藝舎さんからいくつか挙がってきたキーワードと、社名やビジョンから、ビジュアルの方向性が見えてきました。游藝舎さんの中に伝えたいメッセージや理念がしっかりとあったので、ブランドパーソナリティもイメージしやすく、絞られた方向性の中でアイデアを広げていくことができました。
白川: 「游藝舎」の漢字からイメージを膨らませることもしましたね。三字それぞれ思いを込めて選ばれているので、それを活かせないかなと。
また当初の予定にはありませんでしたが、制作の途中で、游藝舎を短い文章で表現したブランドステートメントを提案しました。それが指針となり、私たちとしてもデザインを進めやすくなったと思います。

大木: 僕は実装担当の方とコミュニケーションを取るのがメインだったのでデザインの過程にはあまり入っていなかったのですが、側から見ていて2人(加藤・白川)が非常に純度の高いアウトプットを作っているなと感じました。
―― プロジェクトを進める中でのコミュニケーションはどんな感じで進められたのでしょうか。
清水: 良い意味でコミュニケーションコストがすごくかからないプロジェクトだったと思います。こちらがフィードバックして修正してもらって…のやりとりを何度かするものだと想定していたのですが、良い提案が複数あるので選ぶのに迷ったくらいで。最終的には、游藝舎のイメージはこっちだよね、と意思決定をしていき、とてもスムーズに進められたと思います。
コミュニケーションツールは基本的にSlackとFigmaを使っていましたが、Figmaで制作過程を見せてもらえるのが新鮮でしたね。「あ、今まさに作業してるな」と、リアルタイムで見えたり。一般的に制作過程は隠したいものだと思いますが、それを見せてくれていたので信頼できましたね。
加藤: 游藝舎さんからいただくフィードバックが簡潔でわかりやすかったのも良かったです。こちらが提案したものに対してご指摘はほとんどなく任せていただいていたので、進めやすかったです。
清水: クライアントとしては、余計なオーダーはせずにhicardさんのアウトプットを信じることが重要だと思います。スタートとゴールをしっかり伝えて、あとは漠然としたお願いでもhicardさんはしっかり形にしてくれるので、安心して任せられると思います。
今井: hicardさんはレスポンスがとにかく速かったですね。アウトプットが早すぎて、逆にこちらが待たせてしまうくらいでした。
白川: プロジェクト全体としては、2023年の12月からVIやロゴを作り始めて、Webサイトが完成したのは2024年の6月頃だったので、約半年でしたね。スケジュールが最初から適正に引かれていたのが良かったなと思います。
「良い会社だね」と言われるようになった
―― リニューアル後、周りの方々から何か反応はありましたか。
清水: 社内ではサイトが見やすくなった、使いやすくなったという声があり、社外の反応としては、まずサイトのアクセスが上がったのと、評判もとても良くて「良い会社だね」と言われることが増えました。私たちがやりたいことやブランドの軸がより明確になった成果だと思います。
大木: サイトがすごくシンプルなので、ステートメントやブランドが伝わりやすいのだと思います。お二人が游藝舎でやりたいことやサイトで伝えたいことの意思が明確だったのも、良いものが作れたことに繋がっていると思います。Webサイトの制作ではクライアントが入れたい情報がたくさんあったりSEO対策などもあったりで冗長なページになりがちですが、今回余計な情報を入れたくなかったのはありますね。シンプルな構成で伝えたいところだけにフォーカスしています。

書籍に捉われない、価値あるものの残し方
―― 游藝舎さんが今後挑戦したいことなどありましたら教えてください。
清水: 「いま、 残したいものがある。」を游藝舎のステートメントとして掲げていますが、書籍というのはその中の一つの手段であって、他の手段もあっても良いなと考えています。そこで2025年から媒体に捉われない新しい取り組みを始めようと計画しています。良いものを残すために、例えば伝統工芸に焦点を当てたり、さまざまなアーティストさんと組んで展覧会をしてみたりなど、価値あるものを長く残すことをテーマにした活動などを視野に入れています。

今後ともよろしくお願いいたします。
インタビュー・執筆:石原杏奈 @anna_ishr
