
Introductionーバンド/手足 #崖っぷちロックバンドHAUSNAILS
ロックバンドをやっている。
バンドメンバーは霊媒師の家系の末裔であるギタリスト、魔法少女の力を受け継ぐ由緒正しい一族出身のドラマー、夜の間だけ時々女体化する宇宙人のベースボーカル、そしておれ。以上だ。
因みに、全員野郎である。
随分と荒唐無稽な書き出しになってしまったが、まずみんなに知っておいてほしい事実なので致し方ない。
就職祝いのディーゼルの腕時計の黒い文字盤が、午前三時を示している。時計の送り主は猫の肉球程のリビングダイニングに置かれたソファベッドですっかり熟睡している母親だ。看護助手をしているオカンはおれの就職が決まってから時短勤務になって、今日は遅番だったらしい。年々少しずつ小さくなっている気がする毛布越しの背中を横目に、おれは最小限の足音と引き戸の開閉音を残して自室へ引っ込んだ。明日は土曜だ。午前中の貴重な陽射しを犠牲に気ままな夜更けを怠惰に過ごそうと、荷物を放り出し風呂に入ってから部屋に戻り、パソコンで録画していた音楽番組を適当に流す。
結局専門学校在学中に就職をキメられなかった道楽息子は100円ショップでの1年余りのバイトを経て、去年の10月から小さな音楽メディアの編集職に派遣社員として就いた。頑張れば正社員になれるかもという派遣会社の可愛いおねーさんの謳い文句を愚直に信じ、気がつけばもう4か月になる。バンドでの経験と、昔から好きだった文章を書くことを両方とも活かせる今の仕事は天職かもしれん、なんて思う事もあるが、編集者の宿命たるこの毎日終電ギリギリ残業デフォルト状態だけはちょっと不安になる。趣味と実益を兼ねた今のおれの驚異的なガッツは若い男の身体だからこその成せる業に過ぎないわけで……なんて、将来を嘱望される若き音楽家の卵がショボショボ気にしている時点でキモが小さすぎるが。
そもそも都内のくせに通勤に一時間半もかかる時点でモチベーションダダ下がりである、早いところ六本木の駅前好立地芸能人御用達の超高層マンションにひと部屋買えるようなメジャーミュージシャンにおれがなれば良い、とは頭では理解してはいるの、だが、いかんせん健やかに音楽を続けるためにも生活を守らねばならぬ。我には年老いた母親もおる。いつまでも脛をかじり続けるわけにもいかぬゆえ、この手元にある力を最大限に活かして東京砂漠をクロールせねばならぬのだ。
せめて瞬間移動でも出来たらええんやけど、とおれは狭いベッドの清潔なシーツに身を預けじつと手を見る。そう言えば喉が渇いたな、リュックの中に飲みかけのカフェオレのペットボトルを入れっぱなしにしていた気がする。ベッドから対角線上、扉付近に放り投げたリュックとの微妙な距離感がもどかしく、じつと見つめた右の掌をそちらへ向けて軽くひと振り、固く閉ざされたジッパーに視線を集中する。
Anelloのロゴの入ったツマミが軽い金属音を立てて動いた。噛み合ったジッパーが、さも当然であるかのようにゆっくりと開く。ものの十五秒で黒いナイロンリュックは全開になり、中から脱走したフェレットのような所作で褐色のペットボトルが飛び出してきた。クラフトボスのブラウンじゃない方。ベッドに胡坐をかいたおれの手元に飛び込んでくる。眉間が痛ぇ。キャップを開けてひと口含む。これは完全に明け方まで眠れないやつ。
言い忘れていたが……と言うか、そもそもわざと避けて通ろうとしていたが。
おれはいわゆる超能力者だ。バンドではギターボーカル。何を隠そうおれ自身も荒唐無稽な仲間たちの一員であった。
超能力、とひとことで言っても透視能力や瞬間移動など思い浮かぶものは沢山あるだろう。おれの場合は一般人が思いつく限りの超能力の中でも一番しょぼいやつ。いわゆるちょっとしたサイコキネシス。これも正直最近やっとコントロール出来るようになったところだし、数か月前までは手からモノを溶かす硫酸のような謎の液体を出す、ぐらいしか出来なかった。アマゾンの野生生物か何かかよ、おれ。
勿論今の仕事にも役に立ちゃしねえし、バンド活動にも使えねえ。瞬間移動でも出来りゃあ通勤時間の短縮と定期代の節約にでもなるもんだが、手足のように使いこなせるような便利なもんでもない。以前一度念力で楽器を鳴らしてみるなどしてみたが、普通に弾く方が普通に楽だった。
まえに、ウチの愉快なメンバー達に自分が持って生まれた少年漫画的文脈で言うところの異能力について、日頃不便な事はないのかと聞いてみた事がある。
陽気で顔の良いギタリストは何故そのような愚問を投げるのだと言わんばかりのキョトン顔で、「俺はお前と違って生まれつきの力じゃないし、大して不便なこたねえかな。時々『最近肩が重い気がする』とか友達から相談受けたり、視えちゃいけないモンが視えちゃったりする以外は」と答えた。
常に元気の有り余っているドラマーはおれの質問の意図を解さぬ様子で、「オレは楽しみだよ? 母ちゃんや姉ちゃんみたいに誰かのために戦うの。めっちゃロマンチックな二足の草鞋じゃない?」と、瞳に銀河系を浮かべて回答した。
スカしたベースボーカルとは、普段あまり喋らない。ヤツも口が悪い割に無口なので、学校でもスタジオでも目が合ったがすぐに逸らした。どうせ昼はオンナ漁り夜はオトコ漁りしてるんだから、己のイヤラシイ肉体を最大限にエンジョイしている事だろう。めでてぇこった。
役に立たない力は持っていても宝の持ち腐れだ。使わない道具などとっととメルカリで売り捌いて小遣いにでもしたいもんだ。二束三文でも、ギター弦ぐらいは買えるかもしれない。
PC画面では、黒い揃いのスリムスーツに身を包んだヴィジュアル系バンドが演奏をしていた。スーツ姿とは今時珍しい。サウンドもなんだかちょっと古臭いが、バキバキのエレキギターとペンタトニックのコード、ドスの効いたハスキーなボーカルのがなる声はなかなかカッコイイ。パーマが軽くかかったロン毛の髪を振り乱し、白い手袋に包まれた手でスタンドマイクにしがみつくように身をくねらせるイケメン。赤黒いアイシャドウに囲まれた見事な二重瞼の奥の黒目はぎらぎらと赤い照明を弾いている。おれもいつか、お前みたいになれるかよ。無理か。だっておれ、役立たずのエスパーだとかピンボーカルやないとか以前に、華もなんもないただのお洒落メガネデブやしな。
そんな事を考えながら汚れた黒縁眼鏡のレンズをティッシュで磨き、かけ直して画面をのぞき込んだ瞬間、思わず声が出た。
あ、このバンドのボーカル、ウチのレーベルの社長や。
ロックバンドを、やっていた。
レコードレーベルの事務所には、もう三か月以上は顔を出していない。就職の報告をしに行って、それっきりか。毎日の忙しさにかまけて気づけばライブはもう半年はやってないし、高二の時に神保町で中古で買ったアコギはもう一か月以上は押し入れの中だ。現役のバンドマンとしてテレビにも出るようなプレイングマネージャーの社長の顔すら忘れるおれは、果たして今でもバンドマンを名乗って良いのだろうか。
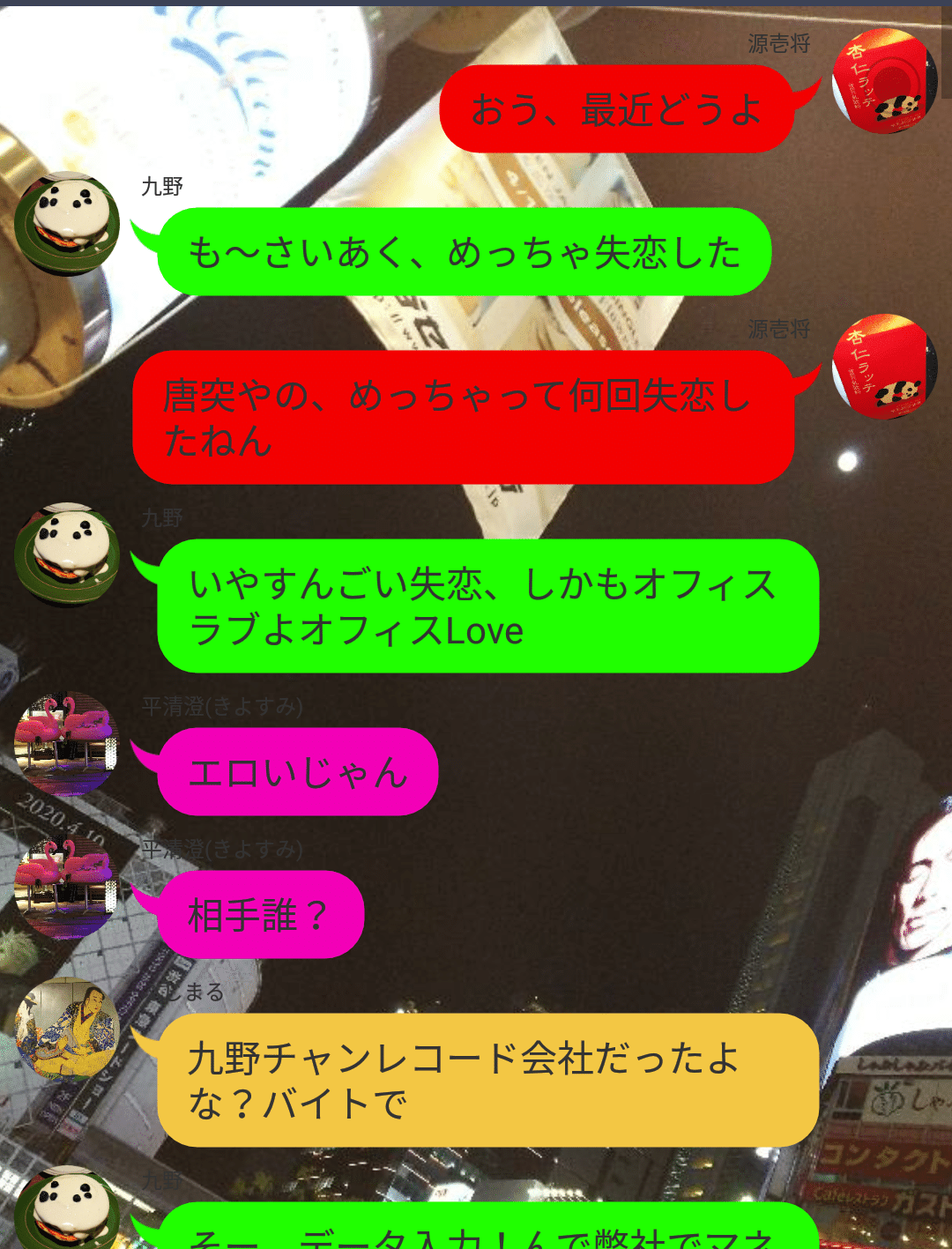






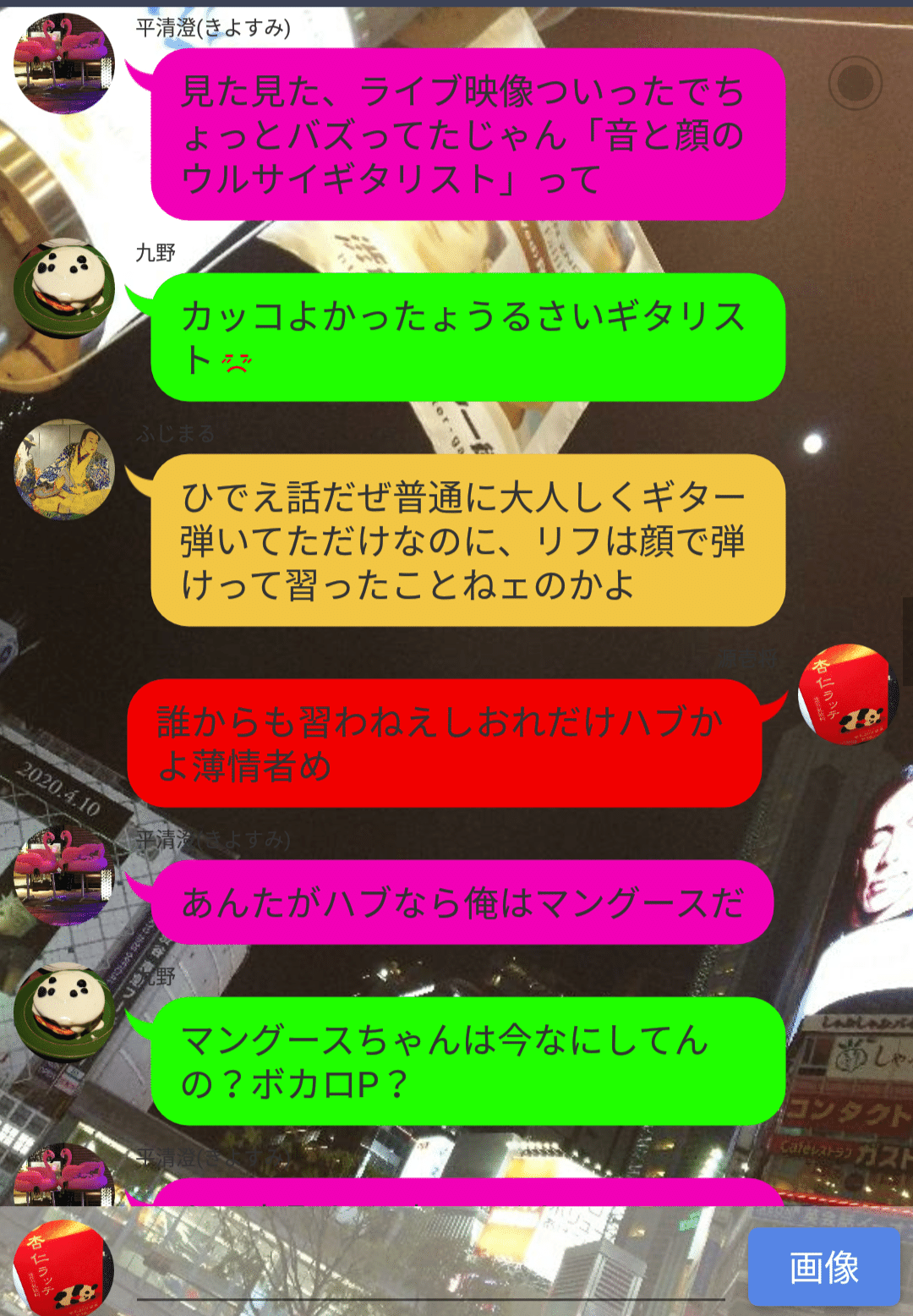






三か月前にやり取りした近況報告を意味もなく眺めた。アイツらも色々大変なんやな。それなりに楽しくやれとるんやろか。
事務所のある下北沢にも、もう先月から行っていない。何故なら金がないからだ。三か月分ずつ購入するのが決まりの通勤定期を買ってしまったために今月は引きこもり生活。次の給料日まであと五日、齢二十二にもなって情けないが明日は母親と連れ立って食料品の買い出しの荷物持ちだ。この際カノジョが欲しいなんて欲は出さないから、こんな夜には瞬間移動で、あの慣れ親しんだ駅前に連れていってほしいと思った。
スマホの時計は六時を示した。もう早朝だ。近くで小さなパン屋を営んでいる隣の夫婦が部屋の扉を閉める鍵の音がする。
意識を手放して体感三十分。実際にスマホを確認すると、たったの五分間。深い深い暗転から目覚めひりつく瞼を引き上げると、そこには見覚えのある早朝の空があった。
レコーディングが長引いた日、先輩バンドのイベントの打ち上げに無理やり付き合わされて朝帰りになった日、初恋が破れた、あの日。あの日もあの日もあの日もそこにあったくすんだ青に、オオゼキの赤い看板が慎ましく鎮座する。
底冷えする風に横っ面を叩かれて大げさに身震いする。流石にスウェットにパーカ(グレムリンのプリントが入っている)のみの装備では冷える。そして思わず口をついたのは、「もうちょいマシなタイミング、なかったんか……」。
瞬間移動、出来るようになった。(再開発ほやほやの下北沢南西口前)(脚を肩幅に開き棒立ち)(眼鏡どっかやった)(髪の毛生乾き)
参ったな、夢かと思い一度二度と目をこすり頬をつねってみたりとベタな行動をとってみるも、視界は変わらないどころか下膨れの頬っぺたはひたすら痛いのみ。冷えた空気で唇が乾いていく。手元にはスマホと、キースヘリングのスマホケースに挟んだ残高一五九〇円のパスモのみ。帰ろうと思えばパスモで帰れるし、もしかしたら瞬間移動で帰れるかも。
……いや、このまま帰るなんて、つまらん。
血の滲んだ下唇を噛んで足元を見る。おれはなるべく怪しまれないよう、且つコンクリートで足の裏を傷つけないよう心がけながら旧南口前のセブンイレブンでスリッパを買い、さもご近所にお住まいのひとり暮らしのバンドマン然とした顔で上階のガストに入店した。
ガラガラの店内が夢の中にいるような気分を更に加速させるが、メイクが若干浮いてきた店員のお姉さんに促されるがままにボックス席に就いて流れるように注文をキメる。フライドポテトとハンバーグモーニングセット、それとビール。しめて一四〇〇円弱。パスモの残高ギリギリである。そして、頼み過ぎだ。
おれはすっかり覚醒した脳味噌で指先を動かし、たんまりとテーブルの上を占領した料理達を横目にLINEを起動し、仄かな背徳感をひと口含む。
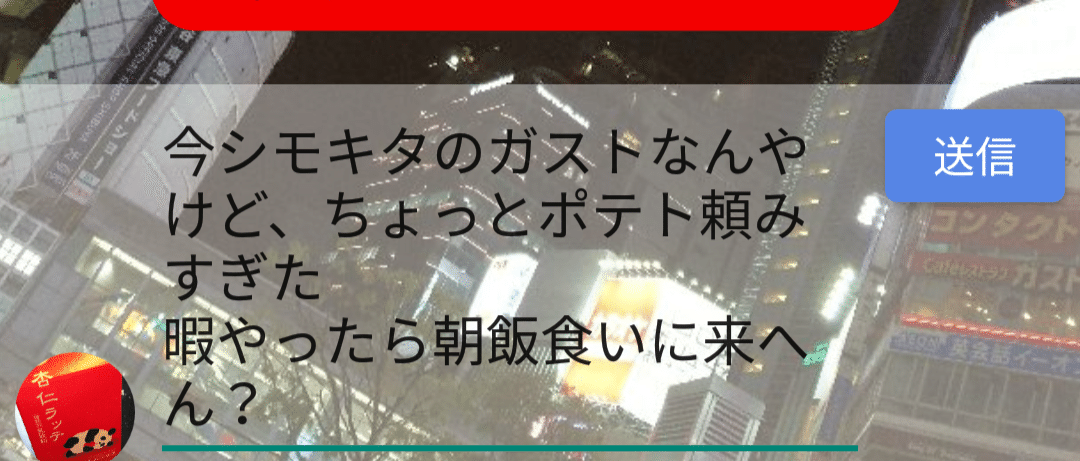
ここまで入力して、手を止めた。一瞬だけ気が遠くなる。削除キーに親指の爪が降れる。伸びかけの爪からふと視線を前方へ移すと、ヒトの気配。
見覚えのある細い首とオーバーサイズのストライプTシャツ。金髪のショートボブ。ベースボーカルが音もなく目の前の席に座っていた。
二度見した。そりゃそうだ、呼んでもいないうえにここにいるはずもない相手が一瞬で目の前に現れたのだから。当然、次におれの口をついて出た言葉は「なんで自分がここにおるんや」。
「知らない、気づいたらシモキタの駅前にいた」眠たそうな金髪は前髪をかき上げながら、あろうことか、あんたが望んだからじゃない? と責任を転嫁してくる。まさか、と鼻で笑い飛ばそうとも、今さっき瞬間移動をキメた野郎はテレパシーが使える宇宙人に返せる言葉を持ってはいなかった。
宇宙人は「で? なんの用」と完全におれに呼ばれたテイで話を進める。なんもかんもないわ、と言いかけておれは手元のスマホに視線をやった。用、あったな、そう言えば。
手元に綴った口実を述べる前から、相手は皿の上にアホみたいに盛られた黄金色の芋をつまんでいる。憎たらしい口の中に吸い込まれていくフライドポテトを眺めていたら、なんだかすべてが馬鹿馬鹿しくなって、おれは一息にジョッキを煽り、乾坤一擲こう切り出した。
「キヨスミ、あのさ、」
今から少し話をしよう 言葉はいつも頼りないけど
それでも少し話をしよう 歌にして逃げてしまう前に
(バンド/クリープハイプ)
《終》
いいなと思ったら応援しよう!

