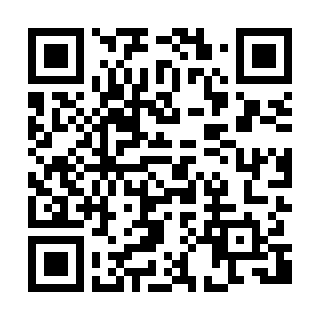【決算書知識②】別表7を理解できていますか?
法人に保険を提案する際の別表7「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」について
保険募集人の皆様にとって、別表7「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」は非常に重要な資料です。この明細書は、法人税の申告に際して、欠損金や災害による損失を損金として計上する際に必要となります。今回は、この明細書の基本的な内容とその重要性についてご紹介します。

そもそも「欠損金」とは?
法人税法第2条第19項では、欠損金を「各事業年度の所得金額の計算において、その年度の損金がその年度の益金を超える場合に、その超過部分」と定義しています。要するに、欠損金とは税法上の赤字であり、「益金-損金」の計算結果がマイナスとなった場合の金額を指します。
欠損金と会計上の赤字の違い
会計上は利益や費用として計上できても、税法上では益金や損金として計上できない場合があります。そのため、欠損金と会計上の赤字の金額は必ずしも一致しません。
例えば、損金不算入項目(後で説明します)が100万円ある場合、会計上の赤字よりも欠損金の赤字は100万円少なくなります。
そのため、確定申告の際には、会計上の赤字をそのまま計上せずに、税法に基づいて再度損益を計算する必要があります。
損金不算入とは?
損金不算入とは、法人税の計算において、会社の経費として認められない費用のことを指します。会計上は経費として計上できる項目であっても、税法上では損金(税務上の経費)として認められないため、課税所得の計算においては除外されます。
損金不算入の具体例
以下に、代表的な損金不算入の項目をいくつか挙げます。
役員報酬の過大部分: 役員報酬が過度に高額であると判断された場合、その過大部分は損金として認められません。これは、適正な報酬を超える部分が法人税の計算において損金不算入となるためです。
交際費の一部: 法人が支出する交際費のうち、一定の限度を超える部分は損金不算入となります。交際費には飲食費や贈答品費用などが含まれますが、全額を損金として認めるのではなく、一部を税務上の経費から除外します。
罰金や過料: 罰金や過料、違約金などは損金として認められません。これらの支出は企業の不法行為や規約違反に起因するものであり、税務上の経費として認められないためです。
寄附金の一部: 法人が支出する寄附金についても、一定の限度額を超える部分は損金不算入となります。寄附金には企業の社会貢献活動などが含まれますが、税法上ではその一部が経費として認められない場合があります。
損金不算入項目が存在する場合、会計上の利益と税務上の利益に差異が生じます。具体的には、損金不算入項目の金額が加算されることで、税務上の課税所得が増加し、その結果として法人税の負担も増えることになります。
例えば、会計上の利益が100万円であっても、損金不算入項目が20万円ある場合、税務上の課税所得は120万円となります。このように、損金不算入は税務分野において重要な要素となります。
別表7の基本内容
前置きが長くなりましたが、別表7について説明します。別表7「欠損金又は災害損失金の損金算入等に関する明細書」は、法人が過去の欠損金や災害による損失を当期の損金に算入する際に、その詳細を記載する書類です。

控除前所得金額・損金算入限度額
図の赤枠の部分です。別表4から「控除前所得金額」を転記します。その後、「損金算入限度額」を記載しますが、中小法人等事業年度である場合は、損金の100%算入が可能です。しかし、中小法人等事業年度ではない場合の損金算入限度は50%となります。
当期の控除額
図の黄色枠の部分「当期控除額」です。当期に控除する金額について記載します。
前期以前の欠損
図の青枠の部分「控除未済欠損金額」の部分です。前期以前に発生した欠損金額で控除されずに繰り越されている金額を記載します。発生年度ごとに記載してください。
翌期繰越額
図の緑枠の部分「翌期繰越額」です。前期以降の欠損額から当期の欠損金控除額を引いた金額を記入します。
欠損金は10年繰越ができる
企業経営において、赤字が発生することは避けられない現実です。しかし、法人税法では、この赤字(欠損金)を将来の利益と相殺することが認められており、結果として税負担の軽減を図ることができます。この欠損金の繰越控除期間が10年間であることは、中小企業にとって非常に有利な制度です。今回は、欠損金の繰越控除について詳しく解説します。
欠損金の繰越控除とは?
欠損金の繰越控除とは、法人が事業年度において生じた欠損金(赤字)を、翌事業年度以降の利益と相殺することができる制度です。具体的には、ある年度に赤字が発生した場合、その赤字を将来の利益から差し引くことで、課税所得を減少させることができます。
10年繰越の意義
法人税法の改正により、欠損金の繰越控除期間が従来の9年間から10年間に延長されました。この変更により、企業は以下のようなメリットを享受することができます。
長期的な経営計画の支援: 欠損金の繰越期間が10年間に延長されたことで、企業は長期的な視点で経営計画を立てることが可能となります。特に新規事業の立ち上げ時など、初期投資が大きく赤字が見込まれる場合には、この制度が大きな助けとなります。
景気変動への対応: 経済状況や市場の変動により、一時的に赤字が発生することはよくあります。10年間という長い期間にわたって欠損金を繰り越すことができるため、企業は景気の波を乗り越えやすくなります。
財務安定性の向上: 欠損金を将来の利益と相殺することで、税負担を軽減し、キャッシュフローの改善を図ることができます。これにより、企業の財務安定性が向上し、投資や雇用の維持に役立ちます。
欠損金の繰越控除の適用条件
欠損金の繰越控除を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
青色申告の承認: 欠損金の繰越控除を受けるためには、青色申告の承認を受けていることが前提となります。青色申告を行うことで、企業は税務上の様々な優遇措置を受けることができます。
適正な帳簿の保存: 青色申告に基づき、適正な帳簿を作成・保存していることが求められます。これにより、税務調査においても欠損金の正当性を証明することができます。
期限内の申告: 欠損金の繰越控除を適用するには、期限内に確定申告を行うことが必要です。申告が遅れると、繰越控除の適用が認められない場合があります。
繰越欠損の具体例
例えば、ある企業が2024年度に500万円の赤字を計上した場合、その欠損金は2034年度まで繰り越すことができます。2025年度に600万円の利益が発生した場合、2024年度の欠損金500万円を繰り越して相殺することで、2025年度の課税所得は100万円となります。このように、欠損金の繰越控除により、企業は税負担を大幅に軽減することが可能です。
保険募集人にとって「別表7」を把握しておくべき理由
バレンタインショックにより、損金性の商品にメスが入りましたが、損金が全くなくなったわけではなく、一部損金の保険商品・全額損金の掛け捨ての保険などは存在します。これらの商品を損金を「ウリ」にしてお預かりする事はこの記事の読者の方であれば、さすがにないと思いますが(信じています)、少なくとも損金の話をする場面はあり得るので、その際に別表7を見ておかないと、「今期利益が出そうなので、この保険商品に加入いただければ一部損金が作れますよ」のような恥ずかしいご提案をしてしまう可能性があるという事です。
法人保険を学ぶなら、HELLObaseへ。
▼公式ラインから無料セミナーに参加できます▼
https://s.lmes.jp/landing-qr/1657179873-xOZNRzwK?uLand=TYhweT