
ランダム/まぐれ/運の世界
運の要素についての書籍3冊。タイトルは「ビジネス書」「自己啓発」の要素が前に出されているが、内容はそこまでではない。
まぐれ
(この本は、そこまで運の要素にフォーカスしているわけではなかった)
▶️ 合理的なモデルが普及するとは限らない
タイプライターの文字の並び方は最適ではない。容易にタイプできるように、ではなく、タイプの早さを抑えられるようにああいう並び方になっている。電子化が進んでいない時代、リボンが絡まるのを避けるためにそんなことをしたのだった。
▶️ ビュリダンのロバの話。占いなど、ランダムな結果を使って選択肢から選んでしまうという方法
読者の皆さんも、これまでにビュリダンのロバを演じたことがきっとあるだろう。日々のちょっとした手詰まりを「コイントス」で打開した、つまり意思決定の過程で偶然に任せて物事を決めたことがあるはずだ。
▶️ 場当たり的に作られた法律
ソヴィエト連邦の崩壊後、ロシアにかかわった西側の実業家たちは、同国の法体系に悩むことになった。法律同士が対立し、矛盾していたのだ(中略)
法律はあまりに混乱していて、何かの法律に従うためには他の法律に違反しないといけない、そんな状態だった。
▶️ 日々の値動きにつけられた解説は、ほとんどこじつけ。
▶️ 重要なシグナルは変化率の大きさである。2%の変化は、1%の4〜10倍くらい重要だし、7%の変化なら十億倍くらい。価格変化の重要度は線形ではない。
コツは、価格の変化率が大きいときだけ注意することだ。何かの価格が普通の日よりも大きく変化しないかぎり、それはノイズだと考える。
誰かが何かを言うとき、その人が十分にふさわしい条件を備えていないかぎり、伝えようと思ったことよりもむしろ、その人自身のことのほうがずっと明らさまになる。
成功する人は偶然を味方にする
著者が「偶然」の要素に注目したのは、彼が養子であり、30代半ばになって実母と再会したことが関係しているようだ。

偶然の要素については、スポーツ選手に多い誕生日(早生まれ、遅生まれ)のこととか、多くの人が「成功は実力、失敗は運のせい」という楽天的な判断をするという話など。
本の後半は、累進消費税の提案に多くのページが割かれている。
成功はランダムにやってくる
▶️ 10000時間の練習によりプロになれるのは、ルールが一定のジャンル
チェス、テニス、プログラミングなど
▶️ イノベーション的な変革では、ルールそのものが変わる。
▶️ 手書きアニメーターの話。個人的に身につまされた箇所、、
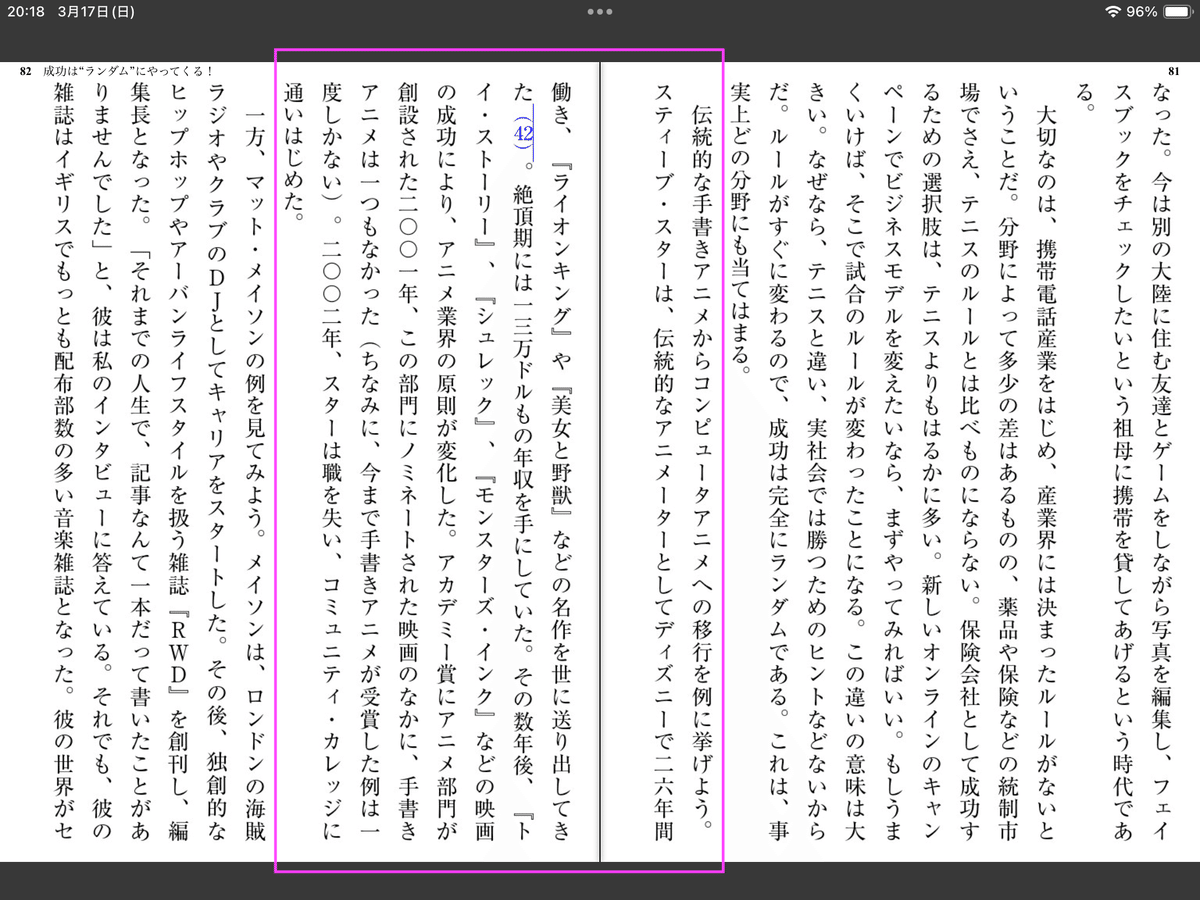
▶️ 勝ち馬が勝ち続ける。スティーブン・キングは有名になったあと別のペンネームでもミステリを書いたが、そちらはあまり売れなかった(そのことを公表してからはよく売れた)
▶️ 軌道に乗るか分からないものは、100%を1種類に賭けるのではなく、10%ずつ10種類の賭けをすること。
