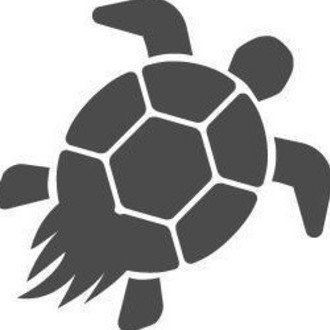「最善のリサーチ」を読んでみて
はじめに
現在、ストラスブール大学の修士課程に進んでおり、私が特に勉強したかった UX に関しては授業が2つ用意されています。
UX & Usability
User Research
それぞれの違いは、またどこかで書こうかと思います。
以前は「UX & Usability」の授業でオススメされた以下の本を読みました。
今回は「User Research」の授業で、いくつかの本をオススメされたので、その中から1つピックアップして読むことにしました。
それが「Just Enough Research」(日本語訳:最善のリサーチ)です。
本の概要
2013年に初版が出ており、そこから何度か改訂版が出ています。
UXリサーチのやり方や手法を、著者の経験を交えて教えてくれています。
例えば
インタビューの仕方
ユーザビリティーテストの計画や方法
ペルソナの作り方
など、具体的な手引書として使えます。ページ数も252ページ(内容は230ページ程)と比較的かなり読みやすいボリュームです。
日本語バージョンは半年前(2024年5月末)に出たばかりで、10年越しにでた待望の本になっています。まさに今読むべき本という感じです!(だから選んだというのもある笑)
「A Book Apart」シリーズに関して
「A Book Apart」シリーズというWeb技術に関連した本のシリーズがあり、この本はその1つです。(日本でいう「技術の泉シリーズ」に近い)
このシリーズが今後は日本向けに翻訳されるそうで、第一弾がこの本でした。
個人的には今後翻訳される予定の
「Design for Cognitive Bias」(認知バイアスを考慮したデザイン)
が登場するのが楽しみだなと思っています。

個人的な用事や大学院の課題もあり、結構ながらで読んでしまったので、内容が少し曖昧になってしまった部分もありますが…
読んでみて良かった点
- ビギナーに優しい本
非リサーチャーや UX リサーチャーのビギナーな人にとっては、相対的に UX リサーチの方法を教えてくれるとても良い本だなと感じました。
また、ある程度リサーチャーとして経験がある方でも、自分のやり方と比較して、足りていなかった部分を補ったりできるんじゃないかなと思います。(私は非リサーチャーなので、こう言うのもアレですが…)
- 手順を教えてくれる
1つ前に付随しますが、本書は UX リサーチにおいて多くの手法を紹介してくれます。そして、全てではないですが、ある程度の過程や手順を教えてくれます。
昨今インターネットで多くの情報が手に入りますが、幾度となく改定されまとめられた本なので、手元に1冊あるだけでも、リサーチ中に困った時に読み返せる本だと思います。
なので、個人的には
本書をざっくりと一度は読む
気になった章をもう一度読み直す
or
実際のリサーチで必要に迫られた時にその章だけを読み直す
と言う感じが良さそうな本だと思っています。
- マーケティング的な知識も学べる
短い章ではありますが、6章の「競合リサーチ」はマーケティング的な側面が強く、本書に出てくる SWOT 分析がその例だと思います。

引用:https://ferret-one.com/blog/swot
この本だと多くは掘り下げないので、過去に私も受講した Google のデジタルマーケティング基礎がオススメです。
読んでみて改善してほしい点
- 実践した手法を検証するのが難しい
本書では多くの手法を教えてくれるのですが、それを自分で実践した時に、そのやり方が本当に正しいのかを検証するのが難しいと感じました。
例えば、8章の「分析とモデル」ではアフィニティ・ダイアグラムについて具体的にやり方を教えてくれます。
アフィニティ・ダイアグラム:情報をグループ化するためのフレームワーク

引用:https://www.canva.com/ja_jp/graphs/affinity-diagrams/
自分達でこれをいざやるとなると、それっぽいことはできると思いますが、その後の評価や分析は経験がない人にとっては、それらしい答えしか導き出せない気がしています。
これに限らず、その後に作成するペルソナ・メンタルモデル・ワークフローなど他のことにもこれは言えると思います。
- UX 関連の内容は薄い
本書が、そもそもそういう本なので仕方ない側面もありますが…
例えば、7章の「評価的リサーチ」では、ヒューリスティック分析について触れますが、その具体的な方法まではやらず、続く内容のユーザビリティテストに進んでしまいます。

引用:https://pantograph.co.jp/blog/uiux/heuristicanalysis.html
ユーザビリティテストの方法に関しては、ある程度の記載があるのですが、その前段階である分析に関しては自分たちで行う必要があるため、個人的にはもう少し解説してほしいなと感じたポイントです。
終わりに
私の大学院では、実際にグループワークでサイト分析からユーザビリティテストを行います。そのため、事前にフレームワークを体系的に学習して、頭の片隅に入れて置けるのはとても助かりました。
もちろん、実際にやってみるとなんか違うなと思う点はありますが、それは本書でも実際のプロジェクト・予算・時間に合わせて柔軟に対応すると記載されていました。
なので、リサーチの手法はあくまでも1つのフレームワークとして、自分達のやり方に落とし込んでいくのが良いのかなと感じました。
いいなと思ったら応援しよう!