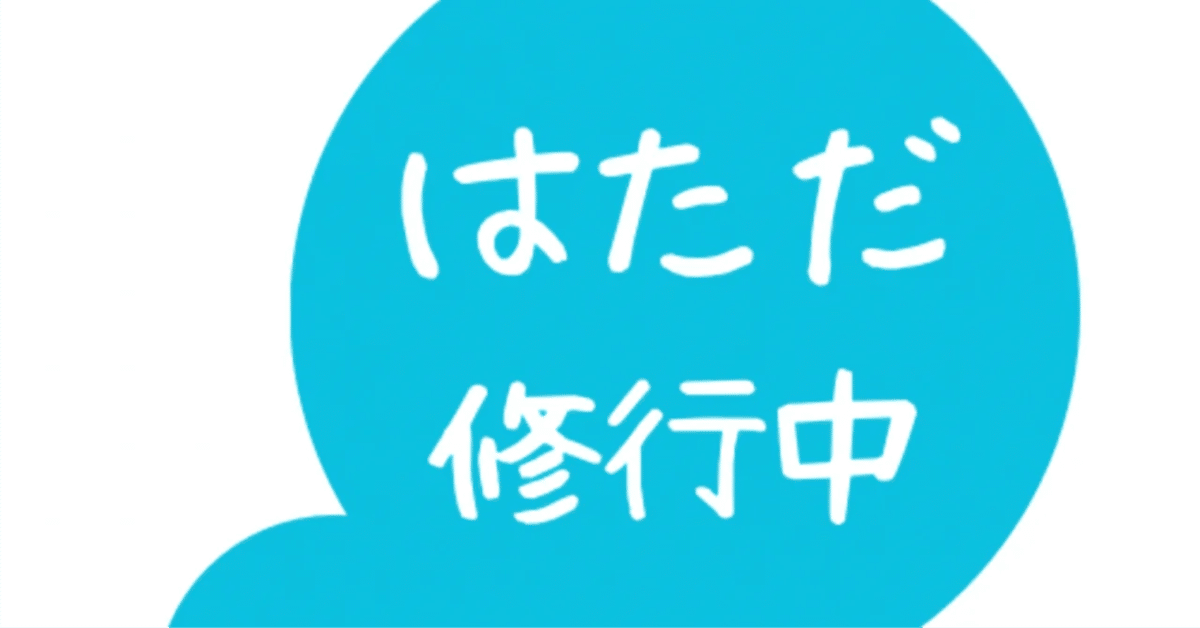
経営関係の勉強で出てくる“S”
通勤中、歩いている間に繰っている暗記カードに、「3S」「5S」と連続で出てきます。
3Sは、
Simplification(単純化)
Standardization(標準化)
Specialization(専門化)
のこと。
そして5Sは、
整理
整頓
清潔
清掃
躾
と、まさかの日本語ローマ字の頭文字。
ちなみに、3Sについて、カードには他の情報を書いていませんでが、“生産の合理化”を考える際の基本原則のようなものだそうです。
5Sは、“製造現場での職場環境改善のための活動”だとか。
最初の「整理」、「整頓」、「清潔」の頭文字をとって3Sというのもあるそうです。ややこしい。
先の3Sは「合理化の3S」「改善の3S」として、他と区別するそうです。
合理化の3S、改善の3Sって、以前書いた「ECRS」にも通じますね。
ECRSは改善の4原則、確かに通じるものです。
そもそも最後のSは、Simplifyだし。
ただ、Specialization(専門化)は、少し毛色が違うようだけど…
取り扱う製品・品種を絞り込み、特定の事業内容に専門特化することで、必要となる作業の種類や工数が減る。
専門化することで業務に対するスキルやノウハウを得やすくなる。
https://www.das-corp.co.jp/blog/%E5%90%88%E7%90%86%E5%8C%96%E3%81%AE3s/
この記事を書くのにググっていたところ、7Sも発見しました。
「企業戦略における、幾つかの要素の相互関係をあらわしたもの」として、マッキンゼー&カンパニーが提唱したものだそうです。
【ソフトの4S】
Shared value (共通の価値観・理念)
Style(経営スタイル・社風)
Staff(人材)
Skill(スキル・能力)
【ハードの3S】
Strategy(戦略)
Structure(組織構造)
System(システム・制度)
7Sって言いながら、ここでも3Sが出てきているΣ(・ω・ノ)ノ!
この7Sについては「優れた企業では、各要素がお互いを補い、強め合いながら戦略の実行に向かっているとされる。」と解説されています。
なるほど、このことを転じるなら…
「Sがいっぱい」とか、「このSは○○○○のS!」って覚えるだけでなく、各々の要素を理解するとともに、その関係性と、関係によって何が機能するのか…ということをちゃんと考えられることが大切なんだ!
…とあらためて思いました。
