
『ハンディーマン』第三話
今回、ハンディーマンという「なんでも屋」の話を書こうと思ったのは世の中のニッチな世界観を拡散しようと思ったわけでもなく、ただ知らないけど少しだけ知ってみたいと思った事をAIと探りながら書きました。
たった一つでも誰かの興味を擽ることが出来たら幸いです。
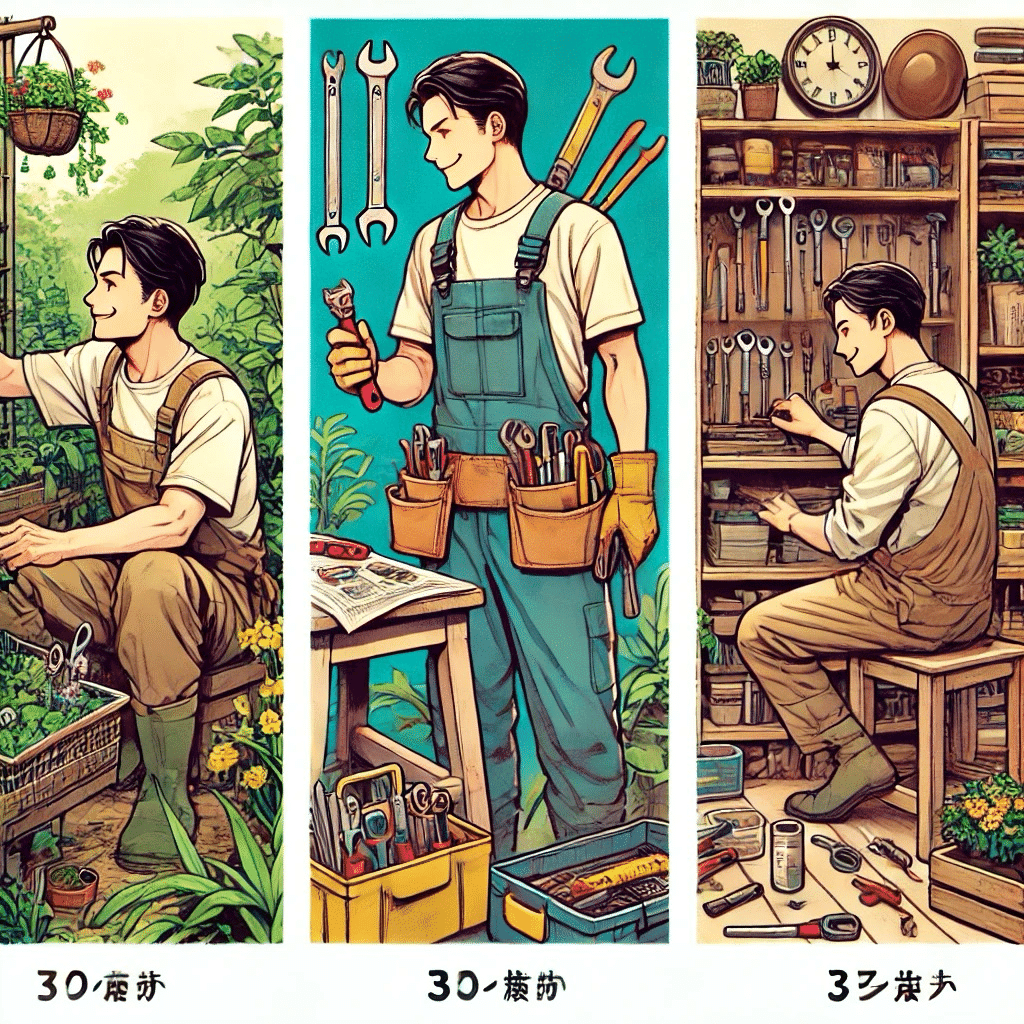
それでは、あなたの意外と知らない世界へ。
「失踪したペットを探せ」
ある雨の降る夜、武蔵商会の小さな店舗に、一人の中年男性がずぶ濡れで駆け込んできた。
彼の名前は山本健太郎。
仕事を終えた後、いつも出迎えてくれる愛犬が家から忽然と姿を消し、必死で探し回ったものの見つからず、武蔵商会の評判を聞きつけ、最後の頼みの綱として駆け込んだのだ。
「どうか、助けてください。あの子がいないと…もうどうしたらいいか分からなくて…」
武蔵は少し驚きながらも、彼の話を聞き、山本の愛犬が失踪した経緯を整理した。
健太郎の愛犬、ポチは、12歳の老犬で、家族同然の存在だった。
歳をとってからは外で遊ぶことも少なくなり、普段は家の中で大人しくしていたという。
だが、昨日の夜、ふと目を離した隙に、玄関の隙間から外に出てしまったらしい。
「まずは落ち着きましょう。失踪した場所と、その周辺で見かけた情報がないか聞き込みをしてみましょう」と武蔵は穏やかに語りかけ、山本を少しでも安心させようとした。
翌朝、武蔵と山本はポチの失踪現場近くの公園に向かい、聞き込みを開始した。
周囲の人々に声をかけ、ポチの特徴を説明し、目撃情報がないかを尋ねるが、誰も彼の姿を見ていないようだった。
老犬であるポチは、人に慣れていて、人見知りすることもないため、どこかの家に迷い込んでいる可能性もある。
そう考えた武蔵は、近隣の住宅にまで足を運んで捜索を続けることにした。
「もしかすると、ポチは以前の散歩道に戻ったかもしれませんね。」
武蔵が言うと、山本はふと表情を変えた。
「そういえば…年を取ってからはもうほとんど歩かせてなかった道がありました。でも、あそこまで歩いて行けるんでしょうか…」
武蔵と山本はかつての散歩道へ向かうことにした。
そこは河川敷の小道で、ポチが若い頃によく散歩に訪れていた場所だった。
雨上がりのぬかるんだ道を進むと、どこか懐かしい匂いが立ち込めており、武蔵は、ポチが昔の記憶を頼りにここに来たのではないかと考えた。
河川敷を歩くこと数十分、ふと遠くの草むらで動く影が見えた。
武蔵と山本は駆け寄ると、そこには泥まみれになり、疲れ果てたポチが座り込んでいた。
山本は思わず大声で叫び、ポチに駆け寄る。
「ポチ! よかった…本当に、よかった…」
ポチは山本の顔を見上げ、弱々しくも安心したように尻尾を振った。
その姿を見て、武蔵は深く胸を打たれた。
山本にとって、ポチは単なるペット以上の存在であり、長年の友として家族の一員だったのだ。
帰り道、武蔵は静かにポチを抱えて歩きながら、ふと山本に尋ねた。
「どうしてそこまで必死になってポチを探していたんですか?」
山本は一瞬目を伏せ、ゆっくりと答えた。
「実は、妻が亡くなってからずっと、私を支えてくれていたのがポチなんです。
妻が残した最後の家族で、彼がいるからこそ、私は一人じゃないと思えたんです。」
その言葉に、武蔵は山本の強い絆と心の痛みを感じた。
彼は何気なく引き受けた「ペット探し」の依頼が、これほど深い愛情に根差していたとは思わなかった。
そして、ただの「何でも屋」ではなく、依頼者の心の支えとなれるような存在でありたいと、改めて決意したのだった。
家に帰ると、ポチは心地よさそうに眠りにつき、山本も安堵の表情を浮かべていた。
武蔵は静かに部屋を後にし、見上げた空は、まるでその日一日の苦労をねぎらうかのように晴れ渡っていた。
こうして、「何でも屋 武蔵商会」の日常は続いていく。
どんな依頼であっても、そこには依頼者の思いが込められており、武蔵はそれを丁寧に受け止めながら、また新たな一歩を踏み出すのであった。
