
冬至に向けてとカラダとココロ
12月にはいり、二十四節気では
12/7は、大雪
12/21は、冬至になります。
冬至は、西洋占星術では、太陽が山羊座にはいるタイミングとなります。

冬至とは
冬至は、最も夜が長くなる。つまり、
一年で最も昼の時間が短くなる日のことである。
……
生命の象徴である太陽の力が最も弱くなる日であることから、「死に最も近い日」と考えられ、恐れられてきた。一方で、この日を境に日照時間が延びていくことから、陰の気が極まって陽の気に向かう折り返し地点としても位置付けられていた。この考えが「一陽来復」というもので、衰運をあらため幸運へと向かうみそぎの意味合いで柚子湯に浸かる風習がある。
冬至とは、夜の時間が最も長くなる日でありながら、季節をもたらす太陽への深い信仰を感じさせる重要な日として位置づけられていたようだ。
自然と共に暮らしていた昔の人々は、冬至や夏至は特別なものだったのかもしれないですね。

冬至のおススメ食材とは
「ん」がつくものを食べる
冬至の日は、「ん」がつくものを食べるのは、今も、冬至にはよく言われますね。
南瓜(なんきん)=かぼちゃ・ニンジン・キンカン・寒天
これらは、
「ん」が2つつく食べ物となり、縁起担ぎにうってつけだとされた。
……
なぜ「ん」のつく食材が運気を向上させるのかについては諸説がある。「うん」を呼び込むといった説や、いろは歌の最後が「ん」なので一陽来復のように開運を願うなどといった説がある。

冬至の食材は冬の理にかなった食べ物
かぼちゃやキンカンは、ビタミンや食物繊維などなどが含まれています。
風邪予防や便秘解消などに効果があります。
寒天は、食物繊維が豊富です。
同じく、便秘解消や腸内環境を整えるのに効果があります。
また、冬至に食べる良いとされているものは、小豆粥。
この四つの食材の共通点は、
動脈硬化や高血圧の予防に効果があるということ。
冬は、寒さによる血管の収縮や運動不足などで血圧が上がりやすくなります。
そのため、かぼちゃやキンカンや寒天・小豆粥は、高血圧や動脈硬化の予防に対しても良い食材なので、冬の食材としても理にかなっていると感じます。
そう思うと、冬至だけでなく、冬は積極的にとりたい食材ですね。
また、小豆粥については、
小豆粥は、小豆や小豆の赤い色は、厄を払い運気を呼び込む縁起物とされてきた。
そうです。
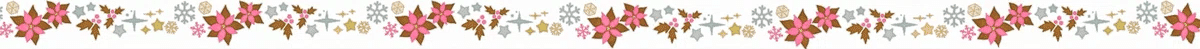
冬至に向けてするとよいこと
冬至に向かう今は、陰が極まる時期になりますので、内面をみていくのに良い時とされています。
内面でいらないものを手放したり。
内面だけでなく、家の中の掃除やデジタル系の断捨離もよいですね。
冬至に向かう今、カラダもご無理せず、柚子やかぼちゃなどなどで、今から風邪予防対策をおこなってもいいですね。
カラダやココロが、たとえいい感じでも、そうでなくても。
冬至の日には、太陽の光をたっぷり浴びて、2025年に向けての計画を立ててみるもよし。運気のきりかえをおこなっていきましょう。

今日も、おたちよりいただき、最後までお読みいただきありがとうございました。
