
父の名言「心は貴族」は、時を経て迷言に変わった
わたしはごくごく中流家庭で育った、3人姉弟の長女である。茨城県南の借家の一軒家に住み、まわりにはほどよく田園風景と住宅街が混ざり合い、東京の短大に行くまで、そこでのんびりと暮らしていた。
2階のわたしの部屋の窓からは、常に牛久大仏の後頭部だけがやたらと眩しく輝いていたのを、今でもよく覚えている。
そして、もうひとつ、今でも覚えているものがある。
それは、父の名言…いや、迷言だ。
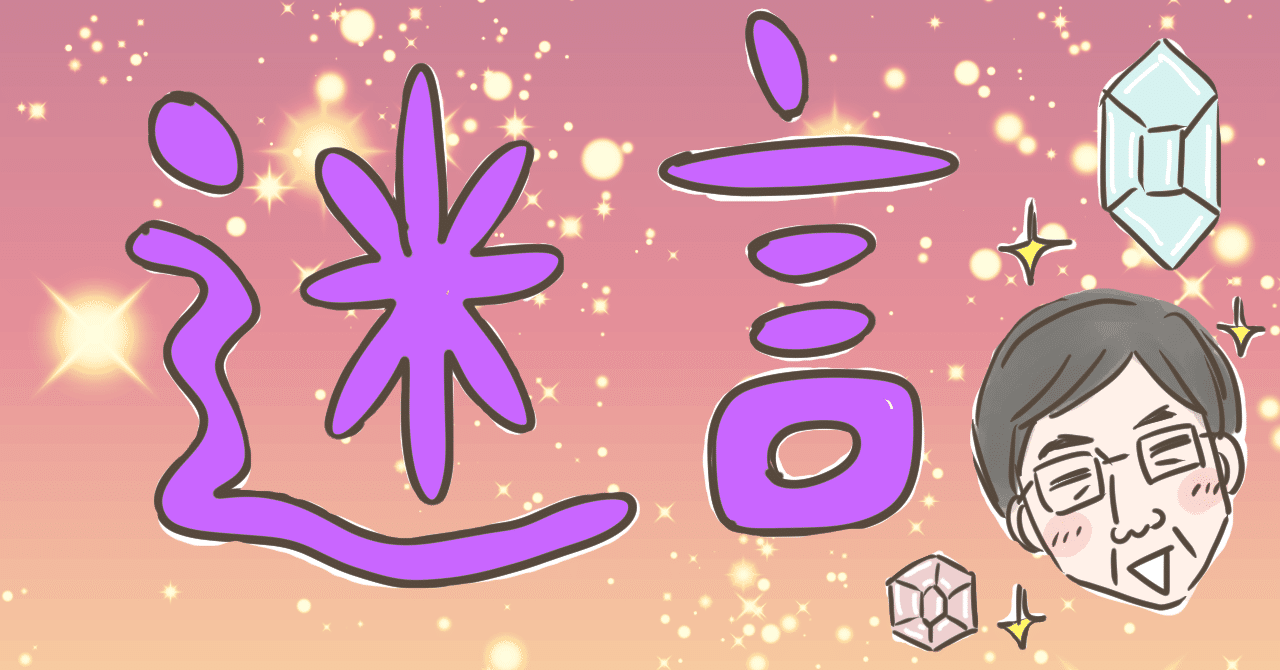
その言葉を聞いたのは、確かわたしが高1だったか、高2だったか…
父は齢にして45くらいだったと思う。
父は、家族で食事をとっている時に、つけていたテレビを
「ぷっっっっちん!」
と口に出しながら消し、突然クラシック音楽を大音量で、かけ始めたのだった。
確かメンデルスゾーンだったかなんだったか、そんな名曲だったと思う。
父は音楽好きで、わたしが小さい頃は、ビージーズやカーペンターズなどの洋楽もたしなみ、お酒が入るとテレサテン、なんだかしみじみする演歌を大音量でエンドレスリピートする習慣があった。
そしてその頃は、当時父が気に入っていた「シャ乱Q」の再生率がやたら高かった。
そんな中、突如現れたクラシック…
…なぜ、クラシック…?
そして、次の瞬間、父は耳を疑うような話を始めたのだった。
「いいか?心は貴族だ。
質素な生活、質素な食事…でも、我が家は心は貴族だから。
心は貴族!!」
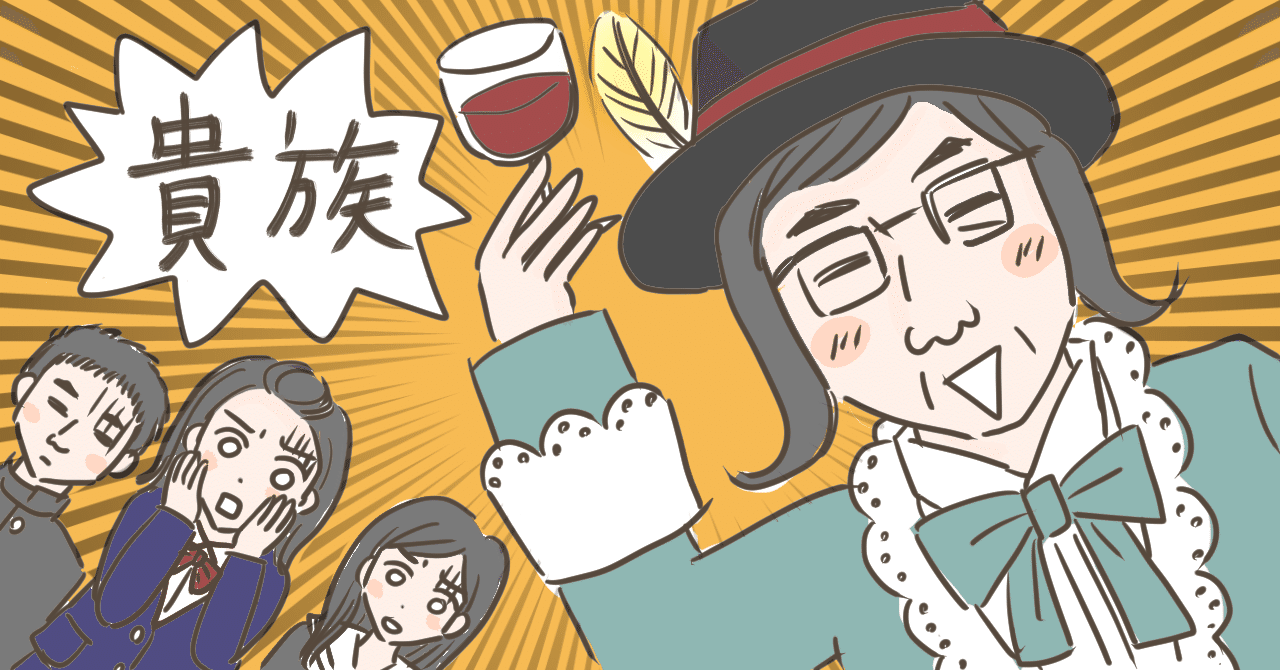
言っていることがよくわからなかった。
父はドヤ顔だった。
その時食卓には、焼き魚や煮物などなどが並んでいたように思う。
今思うと、それほど質素とは思えないメニューだったが、当時は常識も知らないただのイキっている女子高生だったので、質素な食事、と言われ納得していた。
なぜ突然「心は貴族」発言をしたかはわからないが、その言葉はわたしにとって「突然現れた、なんだかわからないけど、わからないだけに、やたらわたしの心に妙に残る、不思議な言葉」として、心の片隅に定住することになった。
そしてそれは、わたしの人生にたびたび顔を出す。
例えば、20代前半の頃。
わたしはロックやパンクに憧れて、高円寺にある家賃6万9千円のワンルームで一人暮らしをしていた。
当時、アパレル販売員をしていて、かなりの薄給で、夜ごはんに使えるお金は100円の日もたびたびあった。
仕事が終わって、自宅近くのコンビニに寄り、100円で「カップラーメン」を買うのか、それとも突然食べたくなった「ポテトチップス」を買うのか…
本気で迷った。

わたしはよく「ポテトチップス」を選んだ。なんてロックなチョイス!!食べたいから今買うのだ。貧乏なんかじゃない、だってわたしは「心は貴族」だから!!
「心は貴族」はとても便利な言葉になっていた。自尊心を保てるのだ。たとえ、貴族とはかけ離れた生活をしていたとしても、心の中のことはリアルな懐事情とは別なのだ。
心の片隅から引っ張り出したその言葉は、都合よく自分を肯定できる魔法の力を持ち始めたのだった。
またある時は、20代後半の頃。
わたしは演劇などにも興味を持ち始め、下北沢にある家賃7万4千円の1Kのアパートに住んでいた。
今思うと、なんでそんなに家賃の高いところに住んでいたのかと疑問が残る。若いって恐ろしい。
わたしはその頃、一度、社会からドロップアウトし、定職を失った時もあった。
派遣のバイト(主にスーパーでソーセージなどの試食を提供する)やパスタ屋のバイト(昼と夜はそこでまかないを食べられる)を掛け持ちしながら、なんとか生活をつなぎとめていたが、
一度体調を崩し、バイトを何日か休んだことで、電気、ガス、水道、携帯が止まる。もちろん家賃は滞納。
携帯は、来た電話は受けられるが、かけることやメールを送ることはできない。
なけなしの10円玉を握りしめて、公衆電話で電話を折り返す惨めさったらなかった。

お金がないと心が荒んでいく。
身をもってそのことを知る。
風俗で働くか否か。
街で配られたポケットティッシュに書いてある電話番号にかけるか本気で悩む。
お金がなくなると、余裕がなくなるから、人に優しくできない。
思考もどんどんネガティブになるし、疑心暗鬼になる。妬む、恨む。
そんな時、ふっ…とあの言葉を思い出した。
「生活は質素、でも心は貴族」
心は貴族…
生活は質素…というかどん底だけど、心は…心だけは貴族でいたいよなぁ…
貴品は保ちたいなぁ…お金はスッカスカだけどさ…
荒んでいく自分自身に耐えられない…
しみじみと感じた。
心の、底の底の底の底のほうから、魂が叫んでいた。
その時、なんかわかった気がしたのだ。
もしかしたら、父は「心は貴族」と自ら言い聞かせることで、自分自身を励まし、モチベーションをなんとか保っていたのではないか、ということを…
もしかしたら、父はあの時辛かったのではないか…?
そしてそれから、わたしも家庭を持ち、実家に帰った時にふと「心は貴族」を思い出したので、父に聞いてみたのだった。
「むかし、言ってたよね、心は貴族…って」
きっと、父も懐かしんでくれるに違いない…わたしはそう信じて疑わなかった。
しかし、返ってきた言葉は驚くべきものだった。
父は、細い目をまるくして言うのだった。
「えっ?そんなこと、言ったっけ?」
なんということか…
わたしは驚きのあまり、声を失った。

本人は全く覚えていなかったのだ。しかも、まるで初耳といった感じで、まるでわたしがおかしなことを言っているような雰囲気でもあった。
わたしは、なんとも言えない奇妙な気持ちになって、
「なんでもない」と半笑いで返した。父に似ているわたしの細い目は、宙をさまよった。
サポートも受け付けております。いただいたサポートは、活動費として、有り難く使わせていただきます。
