
ひっくり返される前に
控えめで慎ましい、なのに美しい、そんな京の文化を学びたくて、京の都へやって来ました。
…しかしやっぱり京都にも、“それっぽい”ものが溢れていて、しかも高価。
そんなニッポンの都で思い出す、エルサレムの都。
こうして彼らはエルサレムに着いた。
イエスは宮に入り、その中で売り買いしている者たちを追い出し始め、
両替人の台や、鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。
そして、人々に教えて言われた。
「『わたしの家は、あらゆる民の祈りの家と呼ばれる』と書いてあるではないか。
それなのに、おまえたちはそれを『強盗の巣』にしてしまった。」
マルコの福音書11:15-17
ユダヤ人にとって、傷のない最上の家畜と穀物を神にささげるという信仰は、
ユダヤ人にとってはあたりまえの文化だった。
ところが、いつしかその文化が商業化されていった、エルサレムの都。
「ささげもの、売ってますよ!」
というビジネスが誕生したのだ。
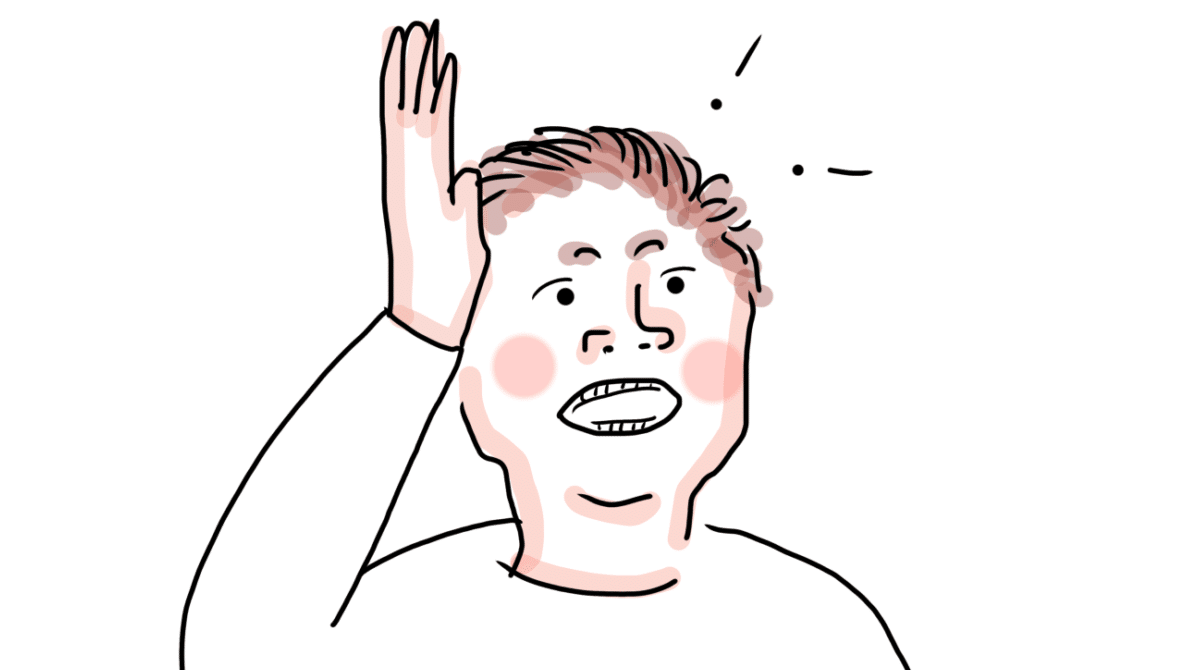
需要もあったかもしれない。
でも、イエスはそれを赦さなかった。
商売人を「強盗」と呼び、商売道具をひっくり返したのだ。
商売人は「良かれ」と思って始めた商売だったかもしれない。
都にのぼる道中の負担を減らしてあげたいとか、そんな他人の益を計って始めたかもしれない。
だが、いけにえは、商業化されるべきものではなかった。
そんな商売が始まってしまえば、“本来”のいけにえの意味が、信仰が、文化が、損なわれる。
「あっちで買えばいっか〜」
そんな商売のおかげで、ユダヤ人たちの信仰はどんどん形式だけのものになっていく。
「助けになりたい」と他人の益のために始めたビジネスや活動であっても、2歩3歩先まで考えないと、
助けるどころか、自立を阻害したり、文化や環境を壊してしまったり、不信仰に陥らせてしまう。
イエスは破壊をもたらす商売人たちを厳しく叱責し、彼らの商売場を「強盗の巣」と呼び、
売る者も、買う者も咎めました。

京都の文化もまた、奪われかけているような気がする。
「おばんざい」もそのひとつ。
控えめな、おもてなし料理の文化。それがおばんざい …ではなく、
無駄をなくし、無駄を省き、あるもので作られた食卓。それが本来の「お番(いつもの、粗末な)菜」だ。
なのに、今や京都のおばんざい屋さんは、「あるもの」ではなく、こだわりの食材をわざわざ仕入れたり、
「無駄なものはない」という“コンセプト”で、お金を取るべきではない食材を、高値で提供するお店だってある。
(もちろんすべてのお店がそうではない)
慎ましくも美しい「文化」は、商業化されたことで、
その美しさと慎ましさを損ないかけている…としたら、
その商いはいつか、ひっくり返されやしないだろうか。
教会も、クリスチャンも、いろんなビジネスをスタートさせはじめている。
私たちには、形式だけの人間にならないことも、形式だけの人を生み出さないことも、両方が神に問われていると思う。
