
【苦手を克服なんて時代遅れ?!】これからの時代は『代替』で乗り越える時代に
先日ニュースで
スパコンよりすごい量子コンピュータが出現したと観ました。下記ニュースの真偽は置いておいて…。私達の生活が変わるかもしれないと思うとワクワクしますね!
電卓を使う、使わないの教育論争
スパコンより身近な話になりますが、子ども達が勉強をする際に『電卓』を使うか、使わないかが議論にあがることがあります。
結論からいうと、
TPOに合わせて使えばよい
と私は考えています。
日本の大抵の親御さんは
電卓を使ったら『頭を使わなくなる』といって電卓を使用しての計算はさせない方が多いです。
私も多数派の親でありました。
他の親御さんと違うかもしれないのは、
電卓をオモチャとして使わせていたこと
そのせいか、学校のドリルの計算は苦手だけど、生活に関する計算は得意だということ。
これについては長くなるので、また別記事にしようと思っていますが、ドリル計算のときは一切電卓を使わせなかったし息子から
『使いたい』
と言ってくることもなかったのです。
バランスよくやればいい
計算をウンウンいいながら、やっていた結果。
算数は息子の最苦手科目になってしまいました💦
それをみて感じるのは、
解らない問題は電卓を使ってもいいのではないか、ということ
頑張れば解る問題においては頭をひねっても良し。そのさじ加減こそ難しいのですけどね。
勉強する目的を考えてみよう
算数を勉強する目的ってなんでしょう?
四角い頭をまるくするため???
考えは人それぞれですが、私は
生きていく上で何通りもの『考え方』のパターンを身につけるもの
だと考えています。
ですので、思考するには計算がいいような気もするのですが計算の答えに至るまでの
『どうやったらいいかな?』
のほうを思考してほしくて、計算自体は一部電卓を利用してもよいのではないでしょうか。
日常生活ですでに苦手分野は外注していませんか?
子ども時代はなるべく不便にする教育をしておいて、親である大人達は苦手分野はプロに依頼していますよね?
何かが壊れたら修理を依頼するし
外食しては『自分では作れないわ〜』と言います
子どもを塾に通わせるのも代理ですよね。親が教えたっていいわけですもんね。
ASDの子たちにおいては、苦手分野が
・多岐にわたる
・苦手さがより深い
だったりするので、苦手を克服させるのは骨が折れる作業となります。
得意なこと・好きなことを伸ばしたほうが親子ともに幸せに成長できるのです。
とはいえ、苦手を乗り越える体験をしなくていいのか?
好きなことだけ伸ばしていていいの?
という疑問が出てくると思います。確かに社会に出たら苦手なこともやらなくてはいけない場面があります。それなら、
『少しずつ』数年単位で実行することをオススメしたいと思います。
漢字や計算などは、1日少しずつ。目的は
『自分もやればできる!』
と自信をつけてもらうことに他ならないのです。
それと、ASDの子といっても学校の勉強がずば抜けてできる子もいますので一概にはいえませんが、
もし学校の勉強ができなくても、生活力を身につけることを重点的にさせたほうが生きていく上で子ども自身がラクになります。
そういう意味でも、最先端なものに扱えるようにしておくこと。苦手の代理をお願いできる人間に育てたほうがいいわけです。
他人に頼れるようにする教育を
親世代の頃よりも時代の移り変わりは激しくなっています。
苦手を克服するのも人間を高めるにはいいことかもしれません。
ですが、得意を追求し社会の役に立つのもいいことではないでしょうか。有名な偉人たちはそうだったと記憶しています。
今の学校教育では、
他人に頼れるようになるための教育をしていません。
自分でできることは自分でやりましょう
ということは常々教育されていますが、頼ってもいいんだよという教育もしてもらいたいものです。
だからこそ家庭でなるべく早い時期から他人に頼ってもよい、という教育をバランスよく行う必要があると考えます。
小学校高学年から中学生になったら、お金を使った『代理』『時短』の方法を学ばせてもよいと個人的には思っています。
・苦手分野の代理
・時短につながる方法
最近話題の『退職代行』については、責任として自分でケリをつけなさい!と思う一方で気持ちも解るし、悩んで自殺してしまうくらいなら利用して気持ち切り替えて『次に行く』のもアリなんじゃないかと。多用しちゃ駄目ですけどね。
まとめ
いつも書いてるのですが、子育てするときに
『絶対こう!』
『〇〇をしたほうがイイ!』
と偏りができるより、
どちらもいいとこ取りで、バランスよく取り入れると固定観念が強い人間にならずにすむのでは、と思っています。
今回の例でいうと、例えば
・電卓を使う問題と使わない問題にわける
・学校では皆に合わせて使わないが、家では使う
・小学校では使わないで中学生から使う
などなど。ご家庭の考え方に応じてやってみてくださいね〜。
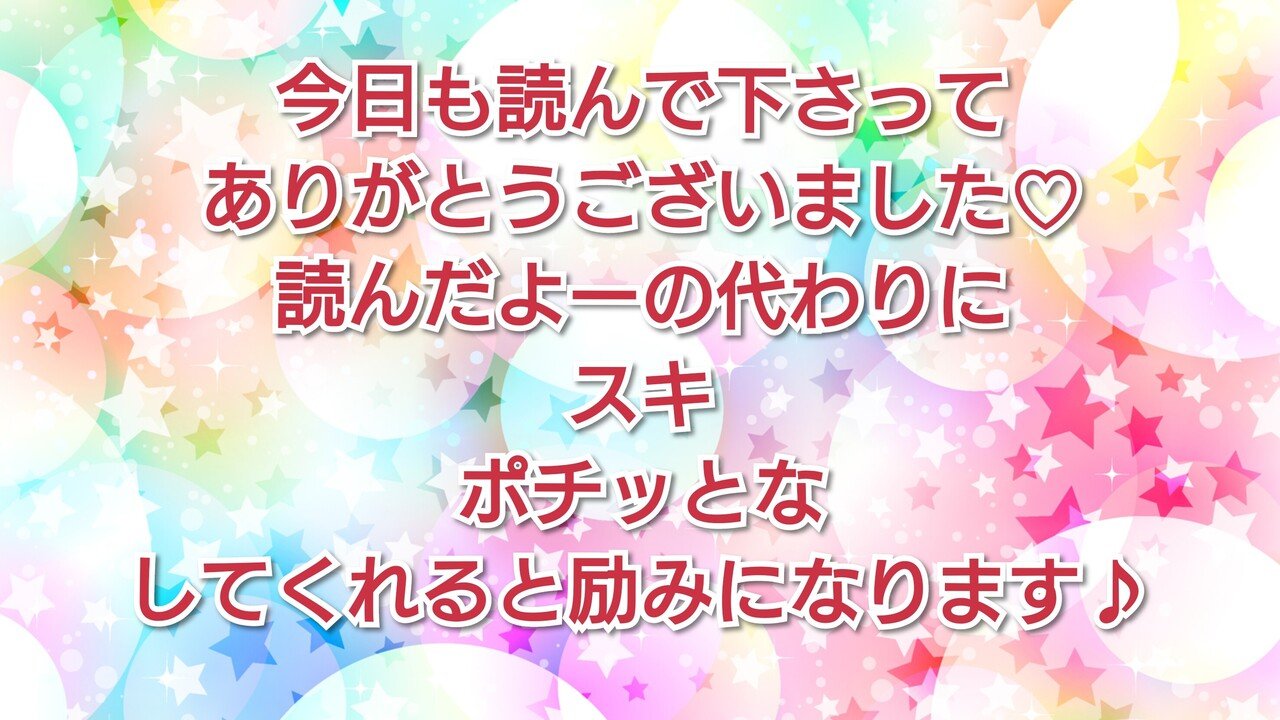
【コチラの記事もオススメ】
