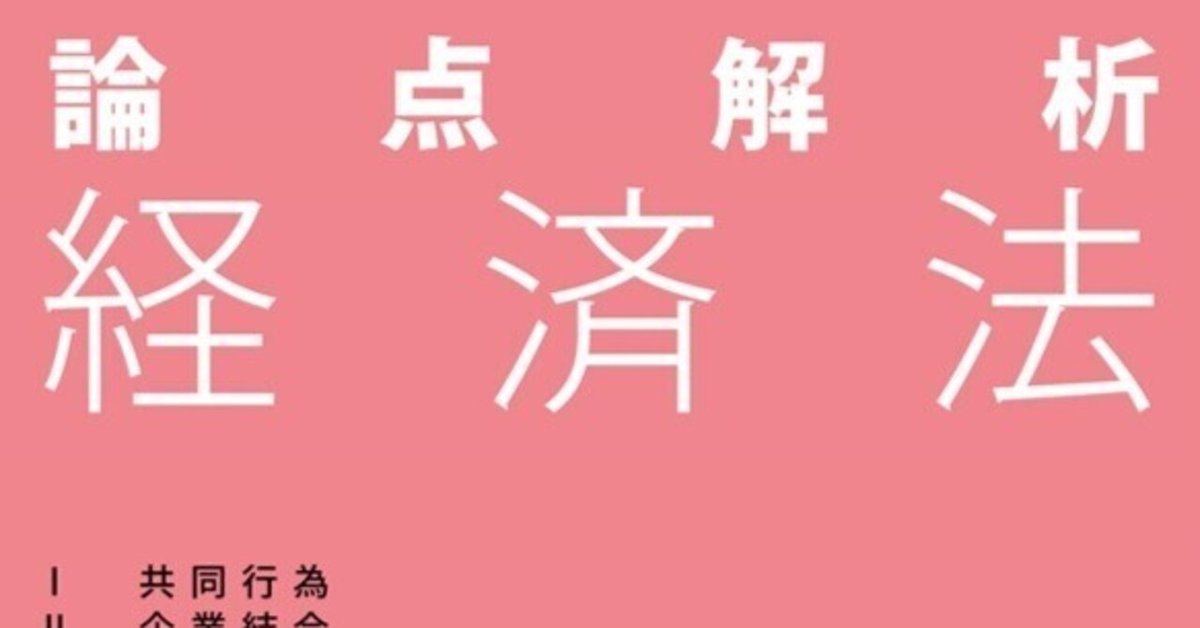
論点解析経済法(第2版)Q21 解答例
こんばんは。司法修習の手続もある程度完了し、あとは郵送するだけとなりました。期限に間に合いそうで良かったです。
本日は、『論点解析経済法(第2版)』Q21の解答例です。この問題は、事業者性が問題となるものであり、不当廉売がメインテーマとなっていますので、不当廉売を理解するためには有用な問題だと思います。ぜひ取り組んでみてください。一応、合格者が書いた答案ですし、教授の添削も受けているので、ある程度は信頼できると思います(笑)。あと、今までの解答例をすべて無料公開に設定しました。ぜひご覧ください。
それでは、以下、解答例です。
1 Y村による福祉バスの運行は、不当廉売(独占禁止法(以下、法名省略)2条9項3号)にあたるとして、同法19条に反し、違法とならないか検討する。
2 不当廉売のような不公正な取引方法の主体は、事業者(2条1項)であるところ、Y村のような地方自治体も「事業者」にあたるかが問題となる。
(1)「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい(2条1項)、なんらかの経済的利益の供給に対応して反対給付を反復継続して受ける経済活動を行う者であれば、その主体の法的性格は問わない。
(2)本件において、Y村は、福祉バスの運行という経済的利益の供給に対応して、運賃という反対給付を反復継続して受けている。
(3)したがって、Y村は、「事業者」にあたる。
3 「供給に要する費用」とは、総販売原価を意味する。総販売原価とは、廉売対象商品の供給に要するすべての費用を合計したもののことをいう。そして、総販売原価には、可変的性質を持つ費用とそれ以外の費用(以下、「固定費」という)がある。
本件において、Y村による福祉バスの運行について要する費用は、①リース料として年間あたり120万円、②運航委託費として、福祉バスの運行のない日は1日6000円、福祉バスの運行のある日は、1日1万円、③燃料費として、福祉バスの運行のない日は1日800円、福祉バスの運行のある日は1日1600円である。①リース料は、福祉バスとスクールバスの運行に共通してかかる費用であり、運行回数の増減に応じて変化する費用ではないため、固定費にあたる。これに対して、②運航委託費及び③燃料費は、福祉バスの運行の有無によって変化する費用であるため、可変的性質を持つ費用にあたる。
4(1)2条9項3号は原則違法類型であり、不当廉売を規制している目的は、廉売行為者自らと同等又はそれ以上に効率的な事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるような経済合理性を有しない廉売を規制することにある。総販売価格を下回る価格設定については、事業者にとって長期的にみれば経済合理性を有する場合もあるため、総販売原価を下回る価格設定のみから直ちに経済合理性を有しないものと判断することはできない。
もっとも、総販売原価を下回る価格設定のうち、商品の供給が増大するにつれ、損失が拡大するような価格設定は、経済合理性が認められないことから、「著しく下回る対価」については、廉売対象商品を供給しなければ発生しない費用、すなわち、可変的性質を持つ費用を下回る対価のことをいう。
(2)本件において、可変的性質を持つ費用は、上記3の通り、②運航委託費及び③燃料費である。②運航委託費は、福祉バスの運行のある日は1日1万円、福祉バスの運行のない日は1日6000円であるから、その差額は、4000円である。また、③燃料費は、福祉バスの運行のある日は1日1600円、福祉バスの運行のない日は1日800円であるから、その差額は、800円である。そのため、福祉バスの運行の有無によって、1日4800円の差額が生じる。福祉バスは、1日2往復であるから、1日片道あたり、1200円の差額が生じていることとなる。福祉バスの乗客数は、1回平均5人程度であるから、乗客1人につき1運行あたり240円の可変的性質を持つ費用が発生している。Y村における福祉バスの運賃は、一律200円であるから、これは前記可変的性質を持つ費用である240円を下回る価格である。
(3)したがって、「供給に要する費用を著しく下回る価格」であると認められる。
5 「継続して」とは、必ずしも廉売が間断(かんだん)なく行われている必要があることを意味するものではなく、廉売行為が一時的なものにとどまらず、相当期間にわたって繰り返し、行われているか、その蓋然性があることをいう。
本件において、Y村における福祉バスの運行は、毎週月、水、金と定期的に行われているため、相当期間にわたって繰り返し行われているといえる。
したがって、Y村における福祉バスの運行は、「継続して」行われていると認められる。
6 「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」とは、他の事業者の事業活動を困難にさせる結果が招来される蓋然性が認められる場合をいい、現に事業活動が困難になる必要はない。そして、そのような蓋然性の有無は、廉売行為者の事業の規模及び態様、廉売対象商品の数量、廉売期間、広告宣伝の状況、廉売対象商品の特性、廉売行為者の意図・目的等を総合的に考慮して、個別具体的に判断される。
本件において、A地区の住民らに対して小型タクシーによる運送役務を供給してきたタクシー事業者T1~T5は、本件福祉バスの運行によりA地区でタクシーを利用する住民が半減し、タクシー事業者T1は、従来A地区に営業所を設置していたが、利用者数の減少を理由に当該営業を廃止している。もっとも、Y村が福祉バスの運用を始めた目的は、A地区に住む高齢者らがX市内の病院や商業施設に行くことができるようにするためである。また、Y村は、福祉バスの運行にあたり、数度にわたって、タクシー事業者らに対して、本件福祉バスの意義について説明し、タクシー事業者らと協議を行っている。そして、乗客1名についてタクシー代金から500円分の割引を受けることができる「福祉タクシー助成券」を、1年に50枚、A地区に居住する高齢者全員に交付した上で、「福祉タクシー助成券」利用額の総額を、Y村が、タクシー事業者に対して支払うこととしている。そのため、T1~T5の営業区域内における小型タクシーの料金は、初乗り1.5kmで610円、以後300mごとに80円であることも考慮すると、福祉バスが与える影響は限定的なものであるといえる。
したがって、他の事業者の事業活動を困難にさせる結果が招来される蓋然性は認められず、「他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがある」とはいえない。
7 以上より、Y村による福祉バスの運行は、不当廉売(2条9項3号)にあたらないため、19条に反せず、違法とならない。
以上
以上になります。最初に一応合格者の答案と言っておきながら、申し訳ないのですが、答案を読めばわかるように、公正競争阻害性について言及していません。『論点解析経済法』の解説に従えば、この答案で十分かもしれませんが、教授からは、公正競争阻害性に言及してくださいとのコメントをいただいています。みなさんが答案を書く際には、公正競争阻害性にも言及して書いてみてください。
それでは、今日はここまでです。最後まで読んでいただきありがとうございました。
