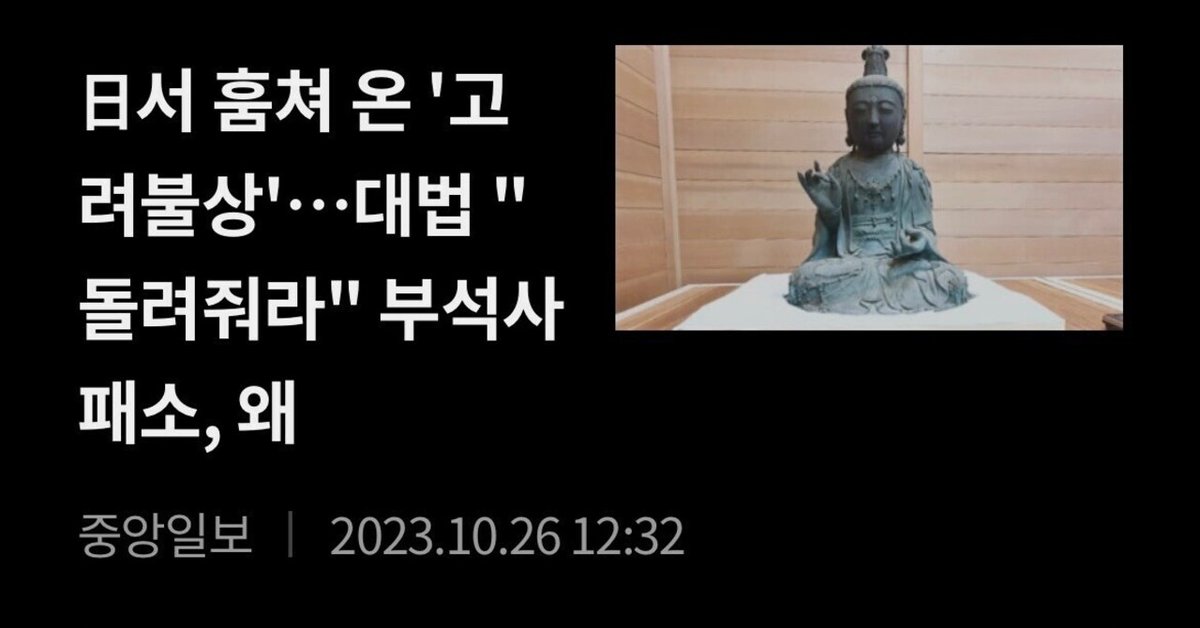
対馬の仏像(観音寺の観世音菩薩坐像)
先日は「韓国人の窃盗団によって対馬から持ち出された仏像」についてのニュースでもちきりでしたね。韓国の最高裁にあたる大法院が、仏像の所有権を、対馬の観音寺にある……とした判決を下したのです。冒頭の画像は、それを報じる、中央日報のWeb誌面です。
「日서 훔쳐 온 '고려불상'…대법 "돌려줘라" 부석사 패소, 왜」
訳すと「韓国で盗まれた『高麗仏像』…最高裁『返還せよ』、浮石寺敗訴、なぜ」という感じです。
2011年に韓国へ持ち去られて以来、これでやっと仏像が対馬に帰って来られるかも……ということになりました。まぁでも住職さんがおっしゃっていましたが、本当に手元に帰ってくるまでは、ホッとすることができませんね。韓国を代表するメディアの一つ、中央日報の前述の誌面タイトルを見ると、暗澹たる気持ちになります。
さて今回は、そうした窃盗事件の経緯をnoteに記していこうとは、思っていません。書き始めると怒りで筆が走り過ぎそうな気がするためと、経緯については他にいくらでも記事が読めるからです。
ここでは、盗難からの経緯よりも、(4人合計)前科56犯とも言われる韓国人の窃盗団に持ち去られ、釜山港の文化財鑑定官に「模造品」と判定された仏像(←グル?)……その仏像そのものについて、ネットで調べて分かったことを記していきたいと思います。
■対馬・観音寺の由来(歴史)
対馬は、室町時代から朝鮮王朝との通交で中心的な役割を果たし、江戸時代の徳川政権下においてはその窓口を独占した大名家、宗家が長らく統治していました。
そして天正8年(1580年)には禅僧の景轍玄蘇が、宗家に迎えられ、朝鮮との外交にあたります。玄蘇は、例えば(豊臣秀吉による朝鮮出兵)文禄・慶長の役でも、明との交渉役を務めた人です。その後の慶長2年(1597年)……もしくは16年(1611年)に、玄蘇は、対朝鮮半島の外交機関ともいえる禅寺「瞎驢山以酊庵(以酊禅庵)」を建立しました。
そんな玄蘇がいなくなってからは、宗家に依頼される形で、江戸幕府は京都五山の禅僧を、対馬の以酊庵へ、輪番(ローテンション)で派遣。それまで同様に対朝鮮半島との外交の、中心機関として機能させました。
そんななか、享保17年(1732年)に以酊庵の本堂が焼失。その時に、現在の対馬市厳原町国分にあった西山寺を、他の場所へ移し、跡地に以酊庵を再建しました。そして江戸も幕末になると、以酊庵の対朝鮮半島の外交機関としての役割が終わります。
明治に入ると以酊庵は廃寺となり、そのあとに復帰したのが、対馬藩主の宗とのつながりが深く、臨済宗の対馬における中本山である、鶴翼山西山寺です。もともとあった地に戻されたのです。
韓国の窃盗団に盗まれた「観世音菩薩坐像」は、そんな鶴翼山西山寺の末寺として建てられた、瑞正山観音寺の本尊でした。
瑞正山観音寺は、対馬市内にある鶴翼山西山寺から、おおよそ北へ40kmの距離にあります。ちょうど島の中央部に位置する場所にあり、対馬市内からは車で55分、徒歩では99分ほどかかります(Googleマップによる)。
■対馬・観音寺の観世音菩薩坐像
瑞正山観音寺の銅造りの観世音菩薩坐像は、高さが50.5cmで重さは38.6kg。ふっくらとした頬に、少し伏し目がちの穏やかな目鼻立ち。体に対してお顔を含む頭部が大きいような気がしますが、そんなゆったりとした風貌は、お願いごとをすれば、どんなことでも怒らずに話を聞いてくれそうにも思えます。
その頭部には、少し高めの髻が結ってあります。制作当初の頭頂には、きらびやかな宝冠を載せていたと思われますが、その宝冠は、朝鮮半島から渡ってきた時なのか、その後なのかは不明ですが、なくなってしまいました。でも宝冠の他にも、耳たぶをふさぐ大きな耳飾り……耳璫をつけ、胸には大きな胸飾が掛けられ、膝まわりまで装身具……瓔珞がまわっています。
右手は胸の前まであげて、左手は膝の上に出して、いずれも親指と中指をまるめて合わせています。ちょうど阿弥陀如来の印相……来迎印の一つ「下本中生(げぼんちゅうしょう)」のようにです。
観音寺の創建がいつなのか分かりませんが、1526年に記された同寺の財産目録には、「観音寺の本尊に観音菩薩像を奉安する」と記されています。つまり1526年には、既に瑞正山観音寺が存在し、観音菩薩坐像が同寺にあった可能性が高いということになります。
ちなみに本山の西山寺の元の名称は「大日寺」でした。現在の名称「西山寺」と変わったのは、室町時代の1512年のことです(いつ「鶴翼山」となったかは、ネットでは不明)。同寺のサイトに記された由来には、宗家十代の貞国公の室(正室?)を、大日寺に祀るにあたり、現在の鶴翼山西山寺と名前を変えたとしています(15世紀後半)。いずれにしても鶴翼山麓西山寺は、その前から存在していたということです。
■像内の結縁文《けちえんぶん》に記されていたこと
長崎県の公式サイトによれば、瑞正山観音寺の観音菩薩坐像は「優作であることに加えて当像が極めて貴重な存在となっている」とし、その理由として「像内から発見された結縁文」を挙げています。
その結縁文には「高麗国瑞州浮石寺」「天暦三年」などの記述がみられ、朝鮮半島忠清道瑞山郡にあった浮石寺に、同像が天暦3年(1330年)に安置されたと記されています。
結縁文の全文は下の通り。(ネットを検索すると結縁文の画像が見つけられます。いずれも韓国のニュースサイトが(勝手に)掲載しているものです。ちなみに原本は盗難を免れて、日本国内にあるそうです)。
南贍部洲高麗國瑞州地浮石寺堂主觀音鋳成結度文
盖聞諸佛佛菩薩大誓願而慶諸衆生也雖無彼我平等以●
佛言無因衆生難化依此金口所說第子等同發大願鑄成觀音一尊安
浮石寺●兖供養者也所以現世消災致福後世同生安養而顧也
天曆三年二月
文中の「●」部分は、筆者が読み取れなかった箇所です。
結縁文を、現代語訳すると、高麗国の瑞州にある「浮石寺」に安置されたとあります。記されたのが天暦三年二月……西暦にすると1330年となっています。このことから、瑞正山観音寺の観世音菩薩坐像は、朝鮮半島が高麗時代に作られた、高麗仏ということが判明しました(結縁文が、どれだけ信頼性があるかは不明です)。
南贍部洲の高麗国、瑞州の地にある浮石寺の堂において、觀音を鋳造して結度文を掛けました。この文には、諸佛や菩薩が大きな誓願を立ててすべての衆生を喜ばせるという意味があります。彼我、つまり他者と自分の区別はなく、平等であるという考えから、何らかの原因で衆生が難しく感じられることがあるかもしれませんが、この金口(真言や聖なる言葉)に従って、私たちは皆、同じ誓願を持って、觀音を一尊鋳造し、浮石寺に安置し、供養します。その結果、現世では災厄が消え、福がもたらされ、次の世では平安に生きることができると信じられています。
天曆三年二月(1330年)
1330年当時の朝鮮半島(現在の韓国と北朝鮮)は、高麗王朝が治めていました。同王朝は、10世紀初頭に新羅や百済を下して半島をほぼ統一。それから、14世紀末に李氏朝鮮が建国されるまで続きました。
ただし、10世紀後半から13世紀後半までは、契丹、女真、遼、金、宋、そして元などの大陸諸勢力からの圧迫をうけ続けました。特に13世紀前半からは、元に朝貢しはじめ、ほぼ属国化。元寇……つまり元が日本に侵攻した1274年と1281年には、朝鮮半島の高麗軍は元軍とともに対馬などを蹂躙しています。その後、1287年に元に併合され、その支配は1356年まで続きました。
そして結縁文にある「天曆」は、元の元号ですので、仏像が作られて、この文が書かれた時点では、元の統治下にあったということです。
1392年、朝鮮半島は李氏朝鮮時代に入ります。この時に何が起きたかと言えば、いわゆる排仏運動、破仏政策です。日本でも江戸幕末から明治にかけて、廃仏毀釈運動がありましたが、李氏朝鮮時代のそれは、より苛烈でした。
Wikipediaによれば「僧は都の漢陽に入ることを禁止された上、賎民階級に身分を落とされた。また、全国に1万以上もあった寺院は242寺に限定され」ました。さらに、それだけでは済まず、1407年には88寺院、1424年には36寺院を残して廃寺とされます。同サイトには、それぞれの年代で存続が認められた宗派と寺院が一覧できますが、対馬の瑞正山観音寺の観世音菩薩坐像の所有権を主張する現在の浮石寺は、そのリストの中には、入っていません。
とはいえ、韓国に盗まれて戻ってきていない《観世音菩薩坐像》ですが……その所有権を主張していた、韓国側の浮石寺の現在の住所は「瑞山市」です。次項で記すとおり、もともと仏像は「瑞州」の浮石寺に安置されたもの(というのが有力)。そして対馬の観音寺の山号が「瑞正山」。「瑞」という文字が、仏教でどういう意味を持つのか、どれだけ使われることの多い文字なのか分かりませんが、なにか因縁を感じてしまいます。
■結縁文の発見当時は友好関係にあった?
『つしまプレス』というブログの、2006年5月に記された記事に、結縁文が発見された当時の様子が記されています。
「40年も前になりますが、当時この寺の住職だった、安藤良俊さんが仏像の掃除をしようと像を持ち上げたところ、像の底がはずれて中から書状や、薬のようなもの、ガラス玉、布などが出てきました。」
「40年前」というのが、いつのことを指しているのか分かりませんが、少なくとも1966年よりも以前に、当時の住職だった安藤良俊さんにより、結縁文が発見されたということ。
ただし、このブログがどこまで正確かは分かりません。調べてみると、安藤良俊さんという方は、対馬市内にある「醴泉院」という寺院の住職さんということしか分かりません。同院の住職になる前に、対馬から車で1時間の距離にあり瑞正山観音寺の住職をされていたのか、もしくは両寺の住職を兼任されていたのか……ネットで調べた限りは不明です。
そのブログ記事によれば、住職の安藤さんは、韓国との友好的なつながりを熱望されていたそうです(重複しますが、同ブログが書かれたのは、仏像盗難よりも前のことです)。そして「昨年、浮石寺のある忠清南道・水産郡より、20名あまりの人が、仏像を見学に来られました」としています。「昨年」とは、記事を起点にすると、おそらく2005年のこと。
「返してください」と言われたらどうしよう? という心配もありましたが、だいじょうぶ!「700年もの間、仏像を大事に信仰してくださって有り難うございます。私達の町にもぜひ いらしてください。」と友好の印に、水産郡で発見された、国宝の香炉のミニチュアを頂きました。(寺に飾ってあります) また、先日は、釜山より同門の寺の檀家さんたちが、20名来島、寺にお参りの後漁協の岸壁で、放生会の儀式をして、活きた魚を海に返しました。」
記事にはそう記され、住職の安藤さんが願っていたとおり、瑞正山観音寺の仏像が、日本と韓国の架け橋になったと思われていたようです。
■仏像は再び日韓の架け橋となれるだろうか
ちなみに、前述した醴泉院の住職だった安藤良俊さんは、民俗学者の宮本常一さんと、親しい間柄だったそうです。民俗学者の宮本常一さんは、対馬を5回、壱岐を4回訪ねたそうです。その時のことは著書の『忘れられた日本人』に記されています。
また先に引用した『つしまプレス』の記事には、主語が不明ですが、こうも書かれています。
「民俗学者の宮本常一さんとの出会いもこの、観音寺でした、総代の村瀬さん達と、お酒をのみながら頭部観音をなでて『なんていい顔の仏像だろう』と話したのは有名です」
こちらの頭部観音とは、同じく瑞正山の観音寺にある観音様のようです。総代の村瀬さんとは、同寺の永久総代を65年間務めた村瀬敬三さんと思われます。
村瀬さんは昨年(2022年)3月に90歳で亡くなられたと、読売新聞オンラインの記事に記されています。また同記事には、仏像の所有権が観音寺にあるという韓国の裁判所の判決を受けての、村瀬さんの子息のコメントが記されています。
「おやじは寺を守ってきたことを誇りにしていた。まさかご本尊様が盗まれるとは思っていなかった」と村瀬さん。「『戻ってくるまでは死にきれん』と言っていた。おやじにも、いい報告ができる」としのんだ。
観世音菩薩坐像の所有権は、韓国の大法院(日本の最高裁)での判決でも、対馬の観音寺にあると認められました。それでも本当に対馬に戻ってくるのか? という不安は、本当に戻ってくるまでは拭えません。1日も早く戻ってくるよう、願わずにはいられません。
<参照サイト>
長崎県の公式サイト
つしまプレス
読売新聞オンライン
■追記……韓国Wikipedia
以下は対馬の観音寺について記している、韓国のWikipediaの一文です。
간논지(일본어: 観音寺)는 나가사키현 쓰시마시 도요타마정 고즈나에 위치하고 있는 임제종의 사찰이다. 그러나 이 사찰은 쓰시마 불상 도난 사건과 관련하여 피해를 입은 장소로 손을 꼽히고 있다. 그러나 도난 당했다는 쓰시마 불상 자체가 왜구의 약탈물이고 간논지 사찰이 이를 알면서도 원주인인 충남 부석사에 돌려주지 않고 소유한 것이므로 본질적으로 간논지 사찰이 피해자라고 할 수는 없다. 도둑이 훔친 물건을 다른 도둑이 제자리에 돌려놓은 사건이다.
わたしは韓国語が分からないので、ChatGPTに翻訳してもらいました。すると下記のような文言が……。(元の訳では「浮石寺」が「部石寺」となっていたので修正。そのほかは原文ママです)
観音寺は、長崎県対馬市豊玉町小綱に位置する臨済宗の寺院である。しかし、この寺院は対馬仏像の盗難事件に関連し、被害を受けた場所として挙げられている。しかし、盗まれたとされる対馬仏像自体が外国人の略奪品であり、観音寺がそれを知りながらも本来の所有者である忠南(忠清南道)浮石寺に返さずに所有していたので、本質的に観音寺が被害者であるとは言えない。盗賊によって盗まれた物を別の盗賊が元の場所に戻した事件である。
本当に返してくれるのでしょうか……。
いいなと思ったら応援しよう!

