
【生活保護法】基本事項の覚え方
こんにちは。erimaです。
試験に出やすい生活保護法の基本事項について超簡単にまとめてみました。
福祉系の国家試験で、生活保護法に関する問題は頻出項目です。
これから勉強される方や、試験前の最終確認に少しでも参考になれば幸いです。
生活保護法の目的
生活保護法の目的は以下の通りです。
国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
生活保護法は、日本国憲法第25条の「生存権」の理念に基づいています。(←ニコニコして生きる生存権!)
病気やケガで働けない、もしくは働いていたとしても収入が十分ではなく、このままでは人として最低限の生活ができなくなる恐れがあると認められた場合に、国の責任の下で生活を保障してもらえますよ、というものです。
防貧的機能と救貧的機能
社会保障制度は「防貧機能」(貧困を防ぐ)があります。みんなでお金を出し合って貧困にならないように備えていこうとするもの。
一方、生活保護制度は「救貧機能」(貧困から救う)があります。これは、社会保障制度ではカバーできず、貧困状態に陥ってしまった人を救い出そうとするものです。
また、生活保護はもらいっぱなしではなく、生活保護受給者の自立を助長するという部分が重要なポイントになります。
生活保護の開始・廃止理由
生活保護の受給開始の主な理由は、
第1位「貯金等の減少・喪失」
第2位「傷病による」
第3位「働きによる収入の減少・喪失」
となっています。
次に、生活保護の廃止の主な理由は、
第1位「死亡」
第2位「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」
第3位「失そう」
※「その他」を除く
となっています。この順位は平成26年~平成30年まで変わっていません。
出典:厚生労働省生活保護の被保護者調査(平成30年度確定値)より〈https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/hihogosya/m2019/dl/h30gaiyo.pdf〉
20歳~30歳の若年層では、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」での保護廃止が多くなっていますが、高齢者世帯では保護廃止理由として「死亡」が圧倒的に多くなっています。
生活保護の受給に至っても、再び働いて十分な収入が得られるようになり、生活保護の廃止となるのが理想です。
しかし、高齢化の進行もあり、なかなか難しい状況であることがうかがえます。
生活保護法の4原理
✿国家責任の原理

✿無差別平等の原理

✿最低生活保障の原理

✿保護の補足性の原理

生活保護法の4原則
❀申請保護の原則
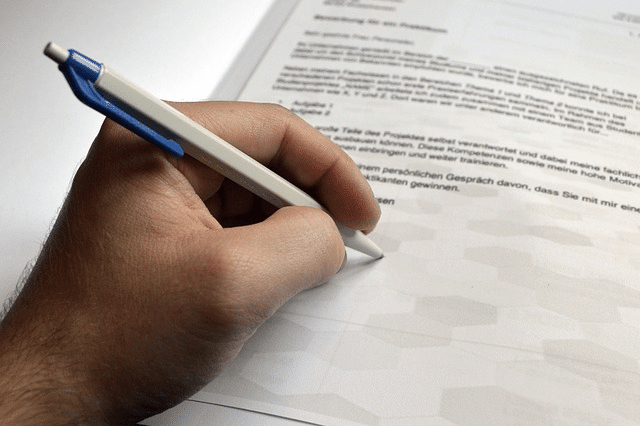
❀基準及び程度の原則

❀必要即応の原則

❀世帯単位の原則

この4原理と4原則ですが、私は紙に絵(図?)を書きながら覚えました。
よければ実践してみてくださいね。
生活保護の8種類の扶助
生活保護には以下の8種類の扶助があります。
①生活扶助
②教育扶助
③住宅扶助
④医療扶助
⑤介護扶助
⑥出産扶助
⑦生業扶助
⑧葬祭扶助
基本的には金銭給付ですが、医療扶助と介護扶助に関しては現物給付となっています。
ちなみに、生活保護受給者でも介護保険料の支払い義務があり、「生活扶助」から支払われます。
※しかし、介護保険サービスを実際に利用したときに発生する自己負担額は「介護扶助」から支払われます!ちょっとややこしいです。
以上です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
いいなと思ったら応援しよう!

