
【2025年最新】FP1級学科試験に独学で合格した話
1.はじめに
2025年1月26日のFP1級学科試験で合格点を超えました。
【合格点】
- 基礎編:66点
- 応用編:68点
※合計120点が合格ライン
あまり高い点数ではないので、自慢できるわけではありませんが、独学でコツコツ進めた結果、無事に合格点を超えることができました。
FP2級を取った後、「FP1級って難しそう」「どんな勉強をすればいいかわからない」って思ったことありませんか?
実は、私も最初は同じように不安だらけでした。でも、自分が信じた勉強をコツコツ進めた結果、無事に合格することができました!
この記事では、私が実際に取り組んだ勉強内容やスケジュール、使った教材をすべて共有します。FP1級学科試験の合格を目指している皆さんの参考になれば嬉しいです!
<簡易な自己紹介>
私は、2024年春に国内大手SIerを退職した元SEの40代男です。今は、ただの無職で専業主夫的な暮らしています。今年(2025年)は、色々な資格を取得し、それを活かして2026年には独立開業したいと考えています。FPについては、2級を2024年9月に取得したばかりでした。
2.FP1級学科試験概要
まずはFP1級の学科試験について簡単に記載します。
- ライフプランニング
- リスク管理
- 金融資産運用
- タックスプランニング
- 不動産
- 相続・事業承継
上記の6分野に分かれていて、かなり専門性の高い内容が問われます。
試験は細かい知識が問われるマークシート方式の「基礎編」と、記述式で主に計算や試算の能力が問われる「応用編」の2部構成です。FP2級よりも深掘りした内容が多いので、かなり勉強量が必要になります。
試験概要の詳細はこちらを参照
また、合格率は8%〜15%前後と低め。FP2級と比べても難易度がかなり高い試験です。ただ、だからこそ、合格したときの達成感やスキルの価値は非常に大きいです!
3.FP1級合格に向けた勉強内容とスケジュール
3.1 全体スケジュール概要
大まかなスケジュールは以下です。

3.2 フェーズ1 (59時間)
一番最初に取り組んだのは、応用編の主に計算問題です。
色々調べた結果、応用編より基礎編の方が難しいため6割以上取るのは難しいらしいとのことで、応用編で点数を稼ぐのが王道の戦略ということがわかりました。
この王道の戦略に則って、応用編の計算問題から勉強を始めました。
具体的に実施したことや実施するときのポイントは以下です。
分野を絞って、直近の過去問(2024年9月)から6〜9回分を実施する。
例えば、応用編のライフプラン分野だけに絞って、過去問を数回分取り組む。
最初はテキストを見ながら解いても良い。
分からないものは、解答解説を見て、計算の仕方を理解した上で、覚える。(何も見ないで解けるようにする)
回答解説を見てもわからない場合は、応用編の解答解説動画を出している梶谷さんのYoutubeを見たりもした
このようにして応用編の一つの分野を絞って過去問6〜9回分について実施する。
計算問題はパターンが少ないので、これをこなすと、その応用編の当該分野の問題はだいたい解けるようになる。
1つの分野が熟練できたら、次の分野を集中して取り組む。これを繰り返して、5分野すべて熟練するまで行う
上記をこなすのに、1分野にかかる時間は、7.5〜14.5時間でした。
各分野にかかった時間は以下表に整理したので参考にしてください。

ちなみに、過去問はFP1級ドットコム(過去問道)を年間契約して利用しました。
例えば以下のように応用編の道場で該当回を選択する。

3.3 フェーズ2 (23時間)
フェーズ1を経ると、応用編の問題については解ける自信がついてくるが、初見の問題に対して対応できる力がついているのかが分からない。
したがって応用編の力を計るために、模試を解きました。
(もちろん応用編の全分野を実施する)
最新の模試だけでなく、過去の模試もメルカリなどで買い集めてやり込みました。このフェーズで使った模試は以下です。

TAC模試は、模試が3回分あるため使い勝手が良く、コストパフォーマンスも良いです。ただし、類似問題も多いです。
このフェーズで模試をこなす中で、応用編については自信がつきました。
このフェーズの後半では、初見の模試を解いても70〜80点程度は取れるようになっていました。
この時に実施した模試の点数を参考に載せておきます。

3.4 フェーズ3 (84時間)
応用編はほぼ完成したので、ここから基礎編に取り組みましたが、このフェーズが一番大変でした。勉強時間も一番かかっていますし、何よりわからない問題ばかりなので、最初の方は辛いです。
応用編の時と同様に、過去問道場を利用して、分野を絞って解いていきながら、学習を進めます。このときのポイントを以下にまとめます。
過去問道場を利用して、分野を絞って出題しその分野で5〜6割程度の正答率になるまで、その分野をやり続ける
1日に多いときで40問程度、少ない時は10問程度解いていた
1分野で合計100問程度を目安にやっていた
4択問題の各選択肢について、正誤の根拠が言えるようになることを目指す(漫然と問題をこなすのでは意味がない。問題とその答えを覚えることも意味がない。本質的な理解を目指す)
ただし、苦手な分野は、難易度が「難しい」や「やや難」は捨てても良いかもしれない。実際に自分は、「リスク管理」は、そもそも「難しい」「やや難」は出題させなかった
同じ分野を100問程度やり続けると流石にそこそこ知識がついてきて、5〜6割くらいの正答率になった
各分野との関連した問題も出るため、タックス分野が一番重要であり、分野の重要性の順番で基礎編は勉強を進めました。(こちらのサイト参考)
タックス>>相続・事業承継>不動産>金融>ライフ>>リスク
基礎編の勉強と並行して、応用編の計算問題のやり方を忘れないように工夫しました。 具体的には、3日に1回程度、応用編の全分野の問題を解くようにしました。
このフェーズで実施した各分野ごとの基礎編の問題数は以下です。

3.5 フェーズ4 (29時間)
基礎編の過去問を分野ごとにこなすことで、5〜6割程度解ける力がついた後に、模試に取り組みました。
なお、基礎編の模試は過去問や過去模試から一部再利用されているため、完全に初見だけの問題というのはないため、点数は上振れしていると考えた方が良いです。
時系列になっていませんが、この時に実施した基礎編の模試の結果は以下です。
(また、フェーズ5で実施した模試の結果も含まれています)

3.6 フェーズ5 (55時間)
仕上げのフェーズです。
毎日、本番形式で基礎編と応用編(過去問or模試)を実施しました。
このフェーズでは、とにかく本番形式で基礎編と応用編の問題を実施して、間違ったところや不安な箇所を適時復習して仕上げていきました。
フェーズ1の時からやっていたことですが、覚えきれていなかった重要な制度や計算式などについては、キーワードだけメモ帳などに残しておき、翌日や3日後、1週間後などにその詳細内容をアウトプットできるかを確認していました。
(例えば、「国民年金の支給額の計算方法」や「所得税の計算の流れ」、「建築基準法の高さ制限」などなど、たくさんあります)
試験の前日にも、このメモも利用して良い復習ができたと思います。
4. 試験当日
試験当日は、余裕を持って起床して、試験開始の30分以上前に会場入りできるように準備しました。また、朝食と昼食を含めてコンビニで購入して行き、お昼休みの1時間も勉強できるようにしました。
また、試験中のドリンク持ち込みが可能だったので、エナジードリンクを飲みながら解いたことで、集中力が持続して良い結果になりました。
(エナジードリンクの効果を実感できる人にはお勧めです)
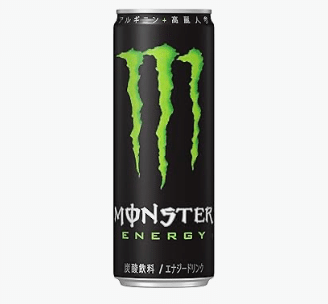
試験中、午前午後とも試験時間終了する前に退出する人がかなりいましたが、自分は全ての問題が解き終わっていても、見直しや計算のやり直しをして、最後まで粘って1点でももぎ取ろうとしました。
5.合格に役立った教材と活用法
以下の3種類を使用しましたので、それぞれ説明していきます。
・テキスト:1級FP技能士(学科)合格テキスト
・FP1級ドットコム(過去問道場)
・模擬試験:TACやLEC、ビジネス教育出版社から発売されているもの
5.1 テキスト
テキストは以下の1冊だけ使いました。

上記テキストを使用するときの注意点ですが、初期段階からテキストを頭から読む勉強はしないことです。頭からテキストを読んでいたら、いくら時間があっても足りないと思います。
自分の利用方法としては、過去問や模試を解いている中で、不明点があったり整理して覚えたい事項があった場合に参照していました。いわゆる辞書的な使い方です。
ある程度知識がついた後に、パラパラ読む程度であれば良いと思います。
辞書的な使い方以外では、試験の1〜2週間くらい前からたまにパラパラ見る程度でした。試験が終わった今でも見たことがないページが大半だと思います。
5.2 FP1級ドットコム(過去問道場)
直近10年分程度の過去問について、いろいろな形式で学習できます。
FP1級ドットコム(過去問道場)
スマホで気軽に勉強できるので、移動の隙間時間などに利用できますし、分野や難易度で抽出した出題もできるので、使い勝手が良いです。
また解説も詳しいのでとても勉強が捗ります。
5.3 模擬試験
過去問をやり込むことも大切ですが、本番は初見の問題を解く必要があるため、その練習として市販の模擬試験を活用するのが良いと思います。
出版社ごとに少し特徴があって、TACは基礎編応用編ともに3回分ついているのでコストパフォーマンスは良いが、一部再利用の問題があったり、難易度も中程度です。
ビジネス教育出版社は、基礎編1回分、応用編2回分なので、TACと比較すると費用が高く、また問題の難易度は高いです。

6.かかった費用
前章で紹介した教材を記載しています。
受験料以外だとテキスト、模試、FP1級ドットコム(過去問道場)となります。詳細は以下参照してください。

7. 最後に
FP1級は確かに難しい試験ですが、計画的に勉強を進めれば必ず合格できる試験だと思います。
この記事はあくまで私個人の経験をもとにしたものですので、万人に活かせる内容とは限りませんが、FP1級を目指す方に少しでもお役に立てば幸いです!
疑問や質問などあればコメントいただければ可能な限り回答します。
本記事を参考にYoutube動画も作成しましたので、併せて参考にしてください。
8.参考
最後に、勉強時間や実施した模試や過去問について、どの程度の量をこなしたのかを改めてまとめますので、参考にしてもらえればと思います。
総勉強時間:250時間程度 ※ながら勉強の時間はカウントしていません
勉強期間:2024/11/17 〜 2025/1/26 の約2ヶ月半
過去問:直近8回分の過去問を基礎編応用編ともに3回程度
模試:15回分
FP1級ドットコム(過去問道場):1251問(以下画像参照)

