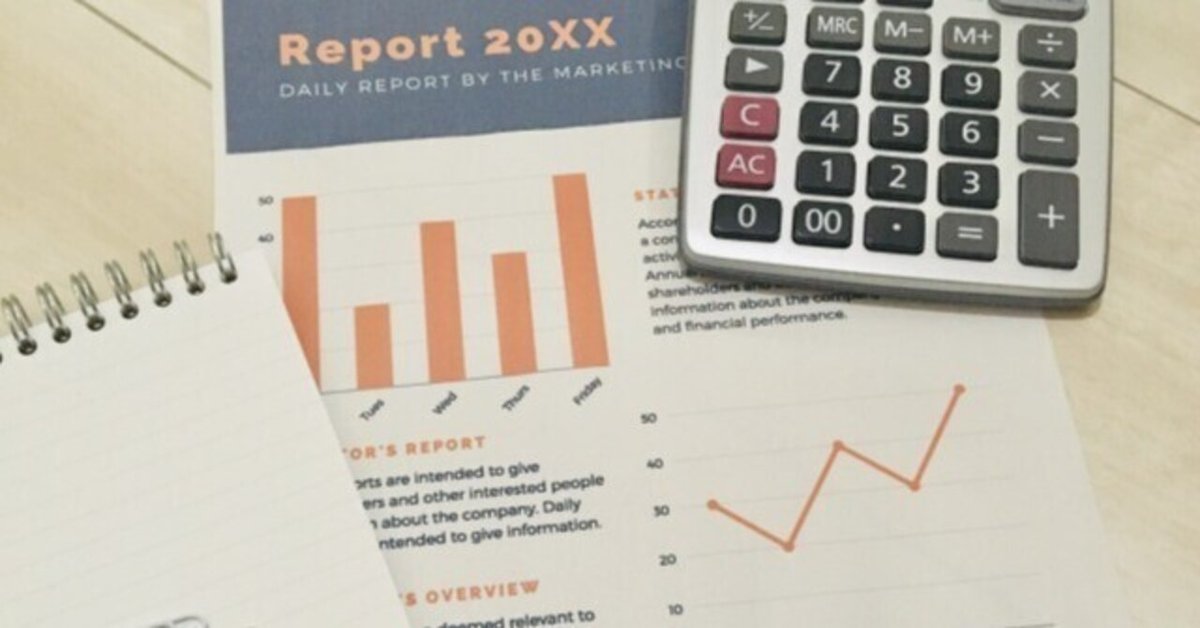
新規事業はほとんど失敗する
「私がやれば成功確率は格段に上がる。そんな低い確率になるわけがない」
昔々、僕が「新規事業は10にひとつ、成功すれば良い」と言ったとき、カウンターパートナーのコンサルタントから反論されました。成功するのが目的ですから、上手くいくならそれが一番良い。しかし、その人の実績がそんなに高いなら、世界的に引く手あまたになるはずです。
もちろん成功してもらうのに超したことはない。しかし、失敗する可能性も視野に入れて次の手を考えておかなくてはいけないと考えています。「絶対に失敗できない挑戦」など、企業の歴史の中で30年に1度あれば多すぎるくらいだと思います。
下記に示したとおり、アビームコンサルティングの調査では、新規事業の成功率は、良くいっても7%~9%程度です。これは他のアカデミックな研究でも似たような数値が示されています。
ほとんどが失敗するといわれる新規事業。アビームコンサルティングが発表した調査結果によると、大手企業の新規事業が立ち上げに至る確率は45%、単年で黒字化する確率は17%、累損解消に至る確率は7%、中核事業にまで育つ確率は4%しかないそうです。

ただここで問題なのは、「成功」をどう定義するかです。僕は、初期投資を回収できるのが成功の最低条件だと考えていますが、事業を立ち上げさえすれば良いとなれば、成功隔離は50%前後まで上昇します。議論する上で、言葉の定義は大事だと認識するきっかけにもなりました。
■許容可能な損失
さて、この新規事業は結局、立ち上がることなく撤退となりました。そのこと自体は仕方がないと思っています。「新規事業は10にひとつ、成功すれば良い」と僕は考えているわけですから。
実は、現場の若手から「もう無理です。このまま突っ込むと大きな損失になります」とアピールがあったことがきっかけで、僕が撤退を言い出しました。「許容可能な損失」の範囲を超えてしまうと判断したからです。
そもそも現場が撤退を言い出すのは難しいのです。この場合もそうで、プロジェクトリーダーは、なんとか形にしたいと四苦八苦しているのがわかりました。
撤退戦を指示・統率できるのはトップだけだと僕は考えています。ただ、TOPがさまざまな理由でその判断ができないのであれば、疎まれても強硬に主張するのが参謀の役割のはずです。ですから3ヶ月間、徹底して撤退を要求しました。
■レモネードの原則
めでたく撤退が決まりましたが、その後も問題は残りました。この新規事業に取り組んだことがなかったかのように扱われ始めたのです。社員に向かって新規事業へスタートをぶち上げていたのに、撤退については特段の告知もありませんでした。「新規事業? なにそれ」とやり過ごそうとする雰囲気が充満していました。それはダメだろう、と当然、思いました。
新規事業の多くは失敗します。失敗したくなければ何もしなければ良い。しかしそれでは、緩やかに右肩下がりの状況に陥ります。だから、新規事業は取り組まなくてはいけない。
大切なことは、たとえ失敗したとしても、失敗の経験を学習機会と捉え、新たな取り組みに活用しようと考えることです。失敗であれなんであれ、取り組んだことの総括が必要なのです。ところが「なかったこと」にされては、失敗の経験から何も学べなくなってしまいます。
人間は失敗を隠したがるものです。僕だって昔は、失敗を隠すためにさまざまなことを画策しました。しかし、それは1ミリも得にならない。人間は経験から学ぶ生き物です。特に失敗の経験から学ぶのです。失敗をなかったことにしてしまえば、何も学べないまま、同じ失敗を繰り返します。
■人間は失敗から学ぶ生き物である
新規事業開発支援に関わる機会はいまのところ多くはないですが、関わる場合はたいていこの経験を話します。そして、もう一つの重要な命題「スモールチャレンジの機会を増やす」重要性を強調しています。
10に1しか成功しないなら、チャレンジを10回に増やせば良い。それぞれ、許容可能な損失の範囲を決めて、失敗から学びつつ、チャレンジの機会を増やす。3000万円で1つのチャレンジをするより、300万円でできるチャレンジを10個作ることこそ、凡人が新規事業成功する秘訣だと思うのです。
元経理責任者としても付け加えるなら、スモールチャレンジの機会をたくさん作れるように資金調達してくるのがCFOの重要な役目だと思っていました。
*小見出しのタイトル「許容可能な損失」「レモネードの原則」はエフェクチュエーション理論の5大原則から言葉を借りています。下記を参考まで。
*エフェクチュエーション理論については、こちらの記事を参考に。
