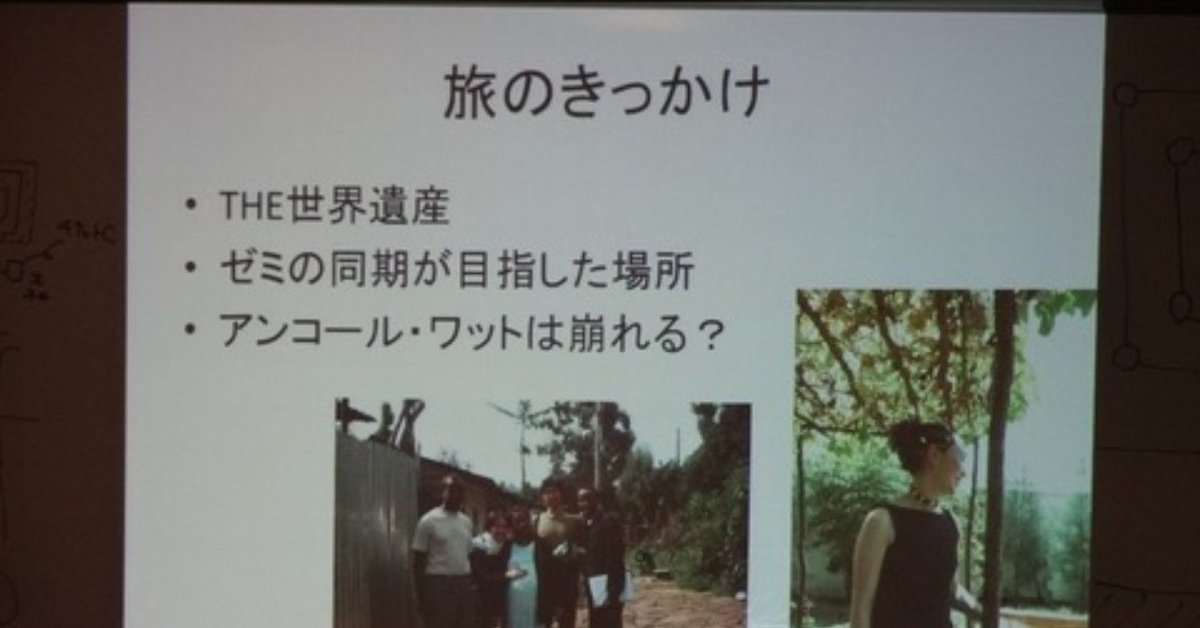
インドシナ陸路ひとり旅報告 〜たったひとつの旅の作り方〜 2015/5/20
2015年5月20日に開催した八丁堀・まなび塾のレポートです。講師は今をときめく上杉惠理子さん。
現在までの変化に驚くかもしれませんが、僕としては「今に通じる」なにかを感じて欲しいと思ってライブドアブログから転載しました。
■73回目の八丁堀・まなび塾
2009年4月から、毎月続けてきている「八丁堀・まなび塾」。
元々仲間内の勉強会で始めたものです。ですから今でも、プロの方をお呼びすることはなく、一般人が(タダの人)が登壇するというスタイルは変えていません。
(2015年)5月20日の開催で73回目を迎えました。7年目に突入したわけで、ここまで続けてくると「継続は力」だと実感できる場面も増えてきます。このまま続けられる限り続けていきたいと思います。またゼロから7年積み上げるのは難儀な気がしますので(苦笑)
■陸路でアンコールワットへ
今回のテーマは
「インドシナ陸路ひとり旅報告 〜たったひとつの旅の作り方〜」
2月にインドシナにひとり旅に行かれた上杉惠理子さんに、その体験レポートと旅から感じたことをお話ししてもらいました。
旅の目的地は「アンコール」です。なぜそこを目指したのか、理由は様々あるようようですが、移動手段として「陸路」で行くということは決めていたそうです。つまり、ホーチミン~プノンペン~シェムリアップとバスで移動するということです。
僕は完全に沢木耕太郎の『深夜特急』世代ですからこの感覚はわかります、というか憧れます。僕より年下の上杉さんが、、、と思ったのですが聞いてみたらやっぱり『深夜特急』を読んでいた(笑)
バス移動ですから、本当の意味で(移動中に)現地の人と身近に接するわけではないかもしれません。たとえばバイクで行くで横断することと比べるるとそういうことになると思います。しかし、ホーチミンからシェムリアップまで飛行機で行くこともできます。(というか普通はそうするし、上杉さんも帰路はそうしたそうです。)
それに比べれば、街の風景を見ながら走り、休憩地点で現地の空気を感じ、なりより陸路で国境を超えるという、日本に住んでいる限り体験できないことをするのは、飛行機で行くのとは違うなにかを感じ取ることができる旅になるのだと思いました。
■歴史の暗部と向き合ってみて
プノンペンでは、キリングフィールドに立ち寄られています。僕が今回のお話しで一番感じることがあったのはこの部分でした。
キリングフィールドとは、、ポル・ポト政権下のカンボジアで、大量虐殺が行われた刑場跡の俗称です。カンボジア全土にあったのですが、一番有名なのは首都プノンペンにあった刑場です。上杉さんはそこに立ち寄られました。
この場所は、人類の負の遺産ととも言える場所です。ここで見つかった2万体の人骨が、ガラスケースに保管されているような場所です。避けて通りたいと思うのが普通だと思います。
だけど僕は、この地に行ったのなら、それは避けて通ってはいけない、と思っています。人間の負の部分をきちんと見ることは必要だと思うのです。臭いものに蓋をし、自分たちのダメな部分に目を瞑っていては、未来で再び同じ過ちを犯すことになると思います。
そこにあえて行った、今回の旅の目的のひとつだったという上杉さんは、さすがだと思ったのでした。
その後、アンコールワットの話の話も興味部深かったです。仏教徒である僕としてはいつかは行ってみたい場所です。なので、自分が行ってから、自分の体験だとして書こうと思います、アンコールワットについては(いつになるやら)
「旅」とはなんなのか。人が旅をするのはなんのためなのか。そんなことを考えさせられるお話しでした。

■アンコールワットを目指した理由
上杉さんはアンコールワットを目指したい理由のひとつに、この本に影響を受けたから、ということがあったそうです。
カンボジアでクメール・ルージュ(ポル・ポト派)により処刑された報道写真家一ノ瀬泰造が残した書簡などをまとめた本です。彼がなぜ危険を冒してまで当時のカンボジアに入ったのか。それが「アンコールワットに魅せられたから」ということらしいです。
「泰造さん」がそこまで魅せられた場所に行かないわけにはいかない、というのも今回の旅の理由だったそうです。彼のお墓にも行って来たらしい。
この本、学生時代に読んだような気がするのですが、話を聞いていると内容がまったく記憶にない。これだけインパクトのある内容をこれほど忘れるのも考えにくいので、読んだという記憶が間違いなんだと思います。
あらてめて読んでみようと思います。
*元記事はこちら
