
妄想:QCサークル活動と世代間格差(43/100)
はじめに
スキマです。note100記事に挑戦しています。
私がやりたいのは課題の解決(カイゼン)
製造業の皆様には大変おなじみのQCサークル活動、「問題解決の手法」として学んだ方も多いと思いますが、問題が発生してから大騒ぎしても遅かったり損害が巨大だったりするので、手法も進化を遂げています。
問題解決型:元祖。不良品を減らすとか納期オーバとか既に発生して困っている問題の解決を目指す奴。
課題達成型:新規業務とか、大幅な現状打破が求められる場合に対応する奴。
施策実行型:問題解決のバリエーションで、対応策をサクッと解決するにはどうしたらよろしいかに着目した奴。
(最近では、課題達成のバリエーションで未然防止ってのが出てきて4種類に増えているらしい)
これもまあ、「なぜなぜ」を部下を詰めるツールにしてしまう誤用が広まってしまったりしていますが、私は「人の困りごとを解決するのが技術で、その技術を社会に実装するのが製造」だと思っているので、基本的には「人間をどうにかして問題を解決する」のはむやみやたらに連発するようなものではない、と考えています
世代間格差について妄想してみる
私は既に製造業で30年以上勤務しており、新入社員の頃から問題解決型の小集団改善活動には触れていたため、慣れてしまっていますが
仮に「今年の新入社員が7つ道具はこうやって使え」と教わったとしたらこんな違和感を抱くのでは?と妄想してみました。
パレート図:こんな図、学校で習ってない。Excelで作るの面倒臭い。
特性要因図:ナニコレ訳わかんね
グラフ:Excelで作れば良いのでまあこれは楽勝楽勝。
ヒストグラム:統計の授業でやった。楽勝。
散布図:Excelで作れば良い。ってか何でグラフと分かれてるんだコレ
管理図:何を管理すればいいかは教えてくれないのが不親切じゃね?
チェックシート:現場猫で見た奴だ・・・
特性要因図がネックになると予想。
裏を返せば、これが伝われば世代間格差も(ある程度)攻略できる。
少なくとも同じものを見て活動ができるのは大きい。
AIに特性要因図書かせてみた
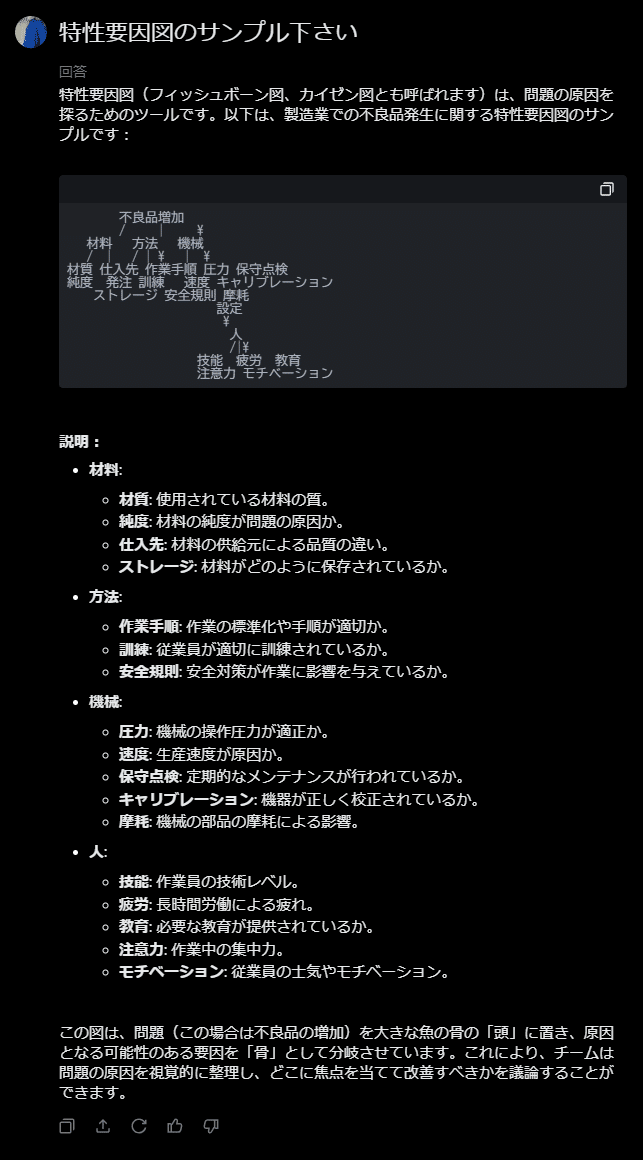
は?何も指示してないのに4M(Man、Machie、Material、Method)出してきたぞGrok。やるな。図は滅茶苦茶だけど。(日本では特性要因図は右から左に書くのが正式らしい)
あれ?製造業の問題解決*AIって超既出では?
さっと検索した結果では「いかがでしたがブログ」や「キラキラ銀の弾丸ソリューション」も出てこない。なんでや。
もしかして、人間性尊重とか自主活動とかとAIの相性が悪いと思われてる?
仮説:コミュニケーションの手段としてAI活用すれば効率化と世代間格差の解消が一度に実現できる
なにせ生成系AIって、思い付きでモノを言う権化なので、若手も老害もAI相手に好きなだけダメ出ししてふるい落とし、残ったものだけを扱えばだれも傷つかないし、考える時間、考えるフリをする時間が無くなれば毎週集まる必要もなくなるし、在宅勤務からでも参加できるし、最後の発表と資料作成なんかそれこそAIに丸投げれば全員がシアワセ
