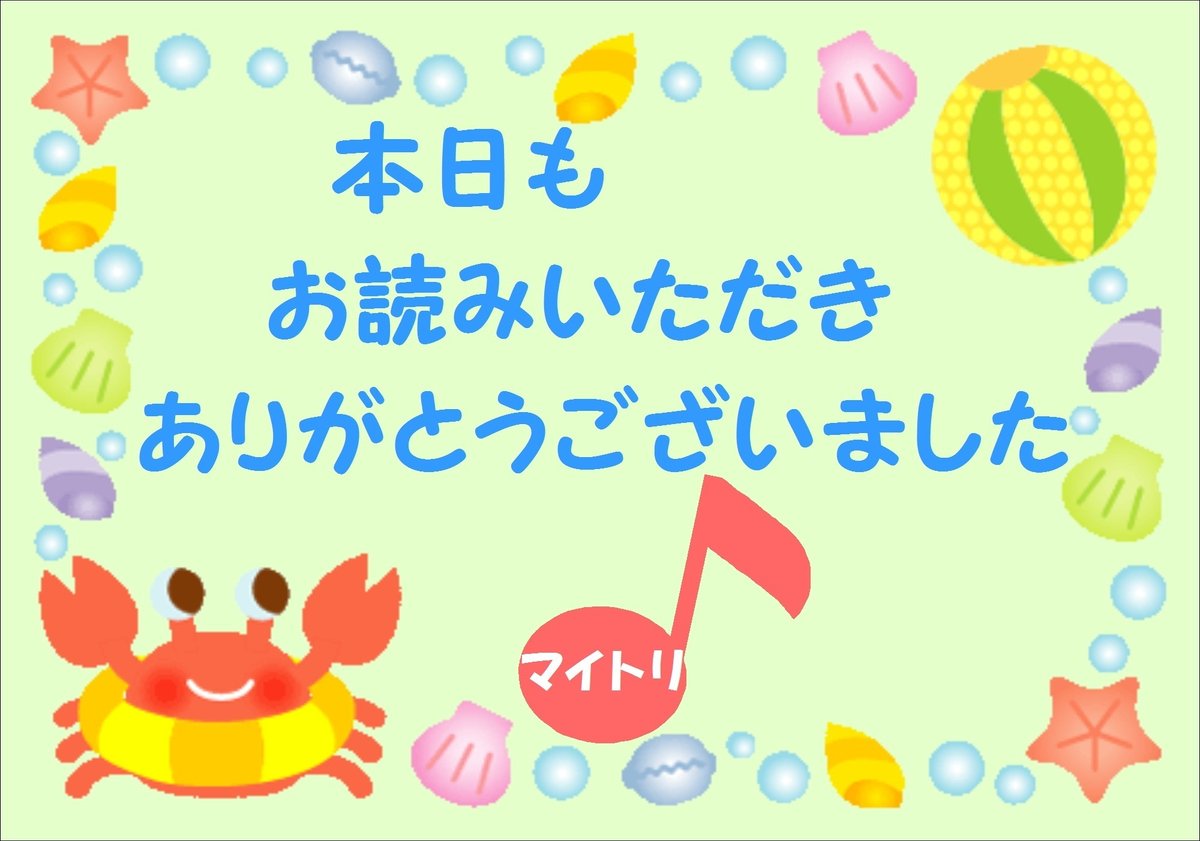音楽トリビア🎵江戸時代の唐辛子売りと曲亭馬琴&小唄「とうがらし」

なんということでしょう。
7月に、あっという間に、7月に・・・なってしまいました💦
唐辛子で暑気払いをして←鰻じゃないの?
猛暑を(猛暑になるかどうかわかりませんが)
元気に乗り切ろう!!
ということで、「唐辛子」の音楽トリビアでございます。

七味唐辛子
老舗の基本的な調合は、唐辛子の他、山椒・麻の実・胡麻が共通。
けしの実・青のり・生姜・柚子など、店により違いがある。
七味唐辛子=上方風の名前
江戸=七色唐辛子
江戸時代、町中でいろいろなものを売り歩く人がいた(社会的弱者のための幕府の救済措置)。
棒手振は、天秤棒の両端に、商品の入った箱や籠を吊り下げ、棒を肩に担ぎ、江戸や大坂で、ありとあらゆるものを売り歩いた。
移動式コンビニのようなものである。
油揚げ・鮮魚・干し魚、貝の剥き身、豆腐・醤油・七味唐辛子・すし、甘酒松茸・汁粉・白玉団子・納豆・海苔、ゆで卵など。
麦湯(麦茶)、冷水、金魚も人気だった。
また、食器、箒といった日用品も売られていた。

ヘッダー画像は、6尺(約180cm)もの巨大な唐辛子のハリボテを背負って売り歩く唐辛子売り。
これ、私の抱き枕に似ている・・・・😓😂
巨大唐辛子のなかには小袋に入った粉唐辛子が収納されており、
「とんとん唐辛子、ひりりと辛いが山椒の粉、すわすわ辛いが胡椒の粉、
七味唐辛子」と言いながら売り歩いた。
📌ひりり=「ぴりり」とも。
それにしても「すわすわ」って、どんな辛さのこと??😓
旋律(メロディ)があるのではなく、「金魚~えぇ~、金魚!」や
「い~しや~き芋~」と同じように、独特の節回しで売り歩いていた。
葛飾北斎も、極貧時代に唐辛子売りをして糊口をしのいでいたとか。

「 近世流行商人狂哥絵図 」は、「南総里見八犬伝」で有名な、
曲亭馬琴(明和4年(1767年) - 嘉永元年(1848年))の作品。。
天保6年(1835年 ) に刊行されたもので、「唐辛子売り」を含む、
江戸時代の行商人の姿と売り声を記している。
曲亭馬琴「著」となっているが、「原画者未詳」とも書かれているので、
説明書きの部分は曲亭馬琴だけど、絵については定かではない??
七色唐がらし売りの売り声
とんとんとん唐辛子
ぴりりと辛いは山椒さんしょの粉(こ)
すわすわ辛いは胡椒の粉
芥子の粉
胡麻の粉
陳皮の粉
とんとんとん唐辛子
そして後々、この唐辛子売りの売り声が、ちょっと変化して、
俗曲・小唄になります。
📌「上方座敷歌集成」に収録されている、
「とんとん、とんがらしはからいね、ひりひり」は別の歌です。
私、小学生の時、小唄・端唄と三味線を習っておりまして。
祖母と母のお稽古を見て、どうしてもやりた~~いと😂
家にお師匠さんがいらしてというシステムの、今で言う出張レッスンです。
あ、この場合、孫悟空が玄奘三蔵法師を呼んだように、
「おししょうさま」、と呼ぶのではなく「おしょさん」と言います。
「しょ」を強く発音します。
山寺のおしょさんみたいな😓←和尚(おしょう)も縮めてますね。

唐辛子売り以外の行商の絵と説明を知りたい方は ↓ こちらへ。
国立国会図書館のデジタルコレクション 「近世流行商人狂哥絵図」
軽快でユニークな小唄(俗曲・端唄)「とうがらし」
ぜひお聴きください。
最後の「葉」が聴かせどころ✨✨
たったの30秒です。