
『DIE WITH ZERO』を読んで、自分の「親孝行」を見直そうと思った
この本を読むまでは、
「仕送り」こそが親孝行なのだ。
と、誤解していました。
最近、ビル・パーキンス(著)『DIE WITH ZERO』を読み終えました。
この本には自分の生活スタイルを変えるインパクトがあったため、書評を残しておきます。
それでは最後までよろしくお願いします。
読むに至った理由
もともとこの本の存在は知っていましたが、読むのを避けていました。
5年前、一人目の子どもが産まれてから、とにかく「家計管理」というテーマで本を読み漁っていた時期がありまして。
で、こうしたお金に関する本って、読んでて疲れません?
やれお金を貯めろ、とか、やれお金を増やせ、とか。
そのときにもう食傷気味になってしまって、本書も気になってはいたものの、いったん読まなくていいか、と思っていました。
そのあと二人目も産まれて、さらに「三人目は産まない」ということを妻と決めたので、先月EXCELを使って家計管理の見直しを行ったんです。
そこで「自分はいつまで働くつもりなのか?」とか「いつどこでどのぐらいお金を使うのか?」といったことを明確に考えないといけないフェーズに来たことを実感しまして。
よし、そろそろ読むか、ということで読みました。
書籍の概要
本書は2020年発売のベストセラーです。

この★でこのレビュー数はかなりのもの。
概要を一言でいうならば、
「死ぬときに貯金を残さない」生き方をしよう。
「ゼロで死ぬ」ことを目指そう。
です。
「そんな必死にお金を貯め続けて、どうするつもりなの?」
「大して意欲も行動力もない老後の自分に大金を送り付けてどうするの?」
「それだったら、今しかできない経験にこそ、お金を使ったらどう?」
という主張を、アメリカの事例を交えて展開してきます。

日本人にも、これグサグサと刺さります。
思わぬ収穫
本書、人生設計についても良い影響があったのですが、今回は「思わぬ収穫」の方を語りたいです。
それは、自分の親孝行について。
私は自分が親にかなりの金銭的負担を強いてしまったことを、うっすらと悔いつつ生きています。
まあ今は、昔ほど深刻には考えていないのですが。
現在は奨学金の返済を終えて、毎年、親に仕送りをしているのですが、本書を読むと「果たして、仕送りが正しい親孝行なのか?」という疑問が沸いてきまして。
というのも両親にとって、今後は、「お金だけあっても困る」という状況になっていくことが分かったためです。
100万円を使わなかったおばあちゃん
本書の第三章には、著者自身のこんなエピソードが出てきます。
著者は昔、70代後半の祖母に1万ドルをプレゼントしたが、そのうち50ドルしか使われなかった。
「何でも好きなものを買ってほしい」と思って100万円を贈ったけれど、おばあちゃんはセーターを一枚買っただけだったそうです。
これ読んで、確かに、と思いました。
80歳近くになって「美味しいもの食べよう」とか「遠くに旅行にいこう」とか、「時短家電を買おう」とか、あまり無いんですね。
「推しのライブに行こう」とか「Switchの最新ゲームを買おう」も、もちろん無い。
今、私の両親は60代なので、まだお金を贈っても多少は使い道があるかもしれません。
でも将来的には、著者が言うように「自力では会いに行けない親戚のもとに行くために、車を出してあげる」とかの方がよっぽど親孝行になり得るのではないか、と考えました。
危なかった。
本書を読んでいなかったら、毎年毎年、お金だけを送り付けて満足してしまいそうでした。
両親の生活が、いま、どのようなものなのか。
何に困っていて、何に喜びを感じるのか。
そうしたことを聞いてみるキッカケになった読書体験でした。
まとめ
今回は『DIE WITH ZERO』を読んで、思いがけず得られた気付きについて書きました。
やっぱり読書のこうした「思いがけない出会い」が、私は好きだなあ。
ただ本書、自身の人生設計にも大きな影響を与えそうな気がします。
海外のベストセラーは伊達じゃないですね。
ちなみに児島修さんの翻訳が本当に素晴らしく、読みづらい読書体験が続いて洋書を敬遠気味だった私でもスラスラ読めました。
一読の価値ありです。
それでは、また。
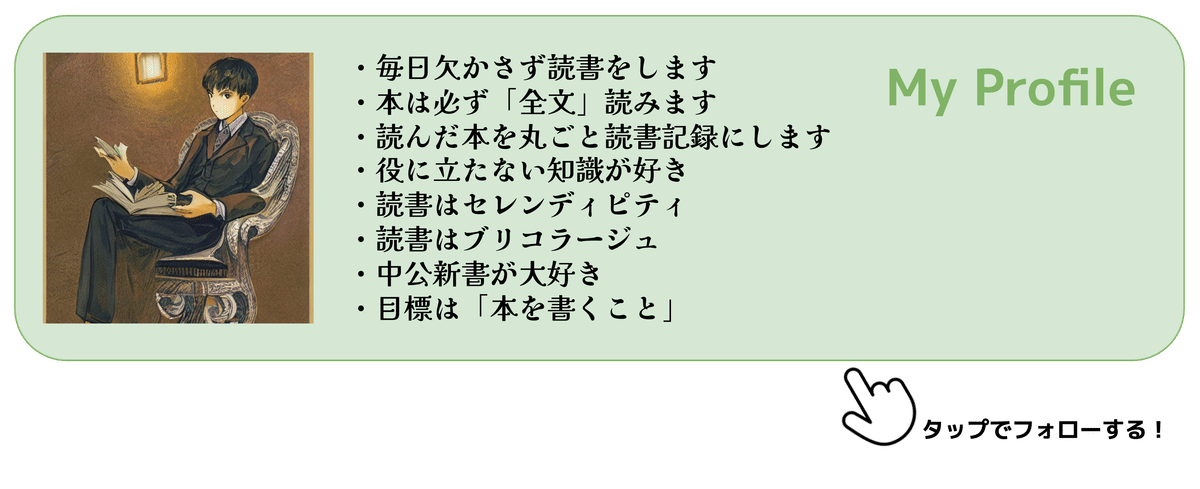
いいなと思ったら応援しよう!

