
山スキーの装備一覧
日帰りの山スキーのギアとウェアを一通り紹介。
ウェアシステム(頭まわり)


アイウェア
ハイクアップのときは TALEX オーバーグラス。国内の偏光サングラスとしては有名らしい。サイト上にもいろんなユーザーボイスがあって情報量が多くて良さそうだったので購入。
フレーム形状的に太陽光が入りづらくて目にやさしい。レンズカラーはエアリーパープル。可視光透過率 25% は、晴れも曇りも対応できている気がする。レンズカラーが寒色系だと雪の景色がキレイにみえるのが良い感じ。


滑走のときは FUJIKAZE のSNG-03電熱ゴーグル。電熱ゴーグルは、モバイルバッテリーを接続することで面発熱するゴーグルで、レンズが絶対に曇らないらしい。定番は SWANS だが4万円以上するので、安い中華ブランドを購入。レンズカラーは可視光透過率がいちばん高くて 45% のレッドを選択。

吹雪のなか、発熱させない状態で装着したがレンズは曇らなかったので、一般ゴーグルくらいのアンチフォグ機能がありそう。モバイルバッテリーを接続すると内部のランプが点滅してたしかに発熱する。いざという時に視界をクリアに確保できる安心感はでかい。
フェイスウェア
faceglove を真似した自作のノーズマスク。顔面・鼻先を冷気や紫外線から守ってくれる。口を塞がないので呼吸がしやすい。
くわえて Finertrack ドライレイヤーウォームバラクラバ。顔周りの冷気・紫外線対策として常に着用。薄い生地なのでハイクアップでも熱がこもりにくい。撥水生地で保水しないので、口に被せても呼吸がしやすい。
鼻下と口周りはほんの少し素肌を露出することになる。無香料の日焼け止めスティックで日焼け対策をしている。口や鼻を布で覆わないのが自分のこだわり。飲食時や、表情によるコミュニケーション、呼吸のしやすさにつながる。
滑走のときや、ハイクアップ時でも稜線で強風に吹かれて寒いと感じたら、Buff メリノウールネックゲイターを顔にかぶる。ふだんは手首に巻いている。
ヘッドウェア
ハイクアップではキャップを愛用。晴れのときは日差しを遮ってくれるし、降雪のときは雪がはいるのをちょっと防いでくれる。
ハードシェルのフードを被ったときに、フードが視界を遮るのも防いでくれる。キャップの頭上に「おへそ」がないので、ヘルメットをレイヤリングできる。
滑走のときは キャップを脱いで、Aoniie のニット帽をかぶる。厚みのあるウール生地で、耳部分はフリース地があてられていて、温かい。
滑走のときはニット帽の上からヘルメットも装着。Black Diamond ビジョン はクライミング用のヘルメットで、スキー用と比べて操作性には劣るが、そのぶん軽量。
ウェアシステム(胴体)


ベースレイヤー
Brynje の スーパーサーモ。通常はノースリーブで、寒いときはロングスリーブを選択。アミアミは温かいし、汗冷えを防いでくれる。Brynje はノルウェーのブランドで、アミアミの生みの親。日本で有名なミレーのアミアミはポリプロピレン約60%だが、Brynje はポリプロピレン100% なのが特徴。編み込まれた繊維は柔らかくて肌触りがいい。

ミドルレイヤー
Patagonia の R1 サーマルジャケット。体にフィットするので動きやすく、冷気に触れずに済む。暑いときはセンタージップで調節。さらっと表面なので雪が付着しにくい。フードは不要。ハードシェルのフードをかぶったときに邪魔になるので。

寒い時は アークテリクスのプロトンLT。アクティブインサレーションなので軽いながらも温かい。そして蒸れにくい。
ハードシェル
The North Face の RTG ゴアテックスシェルを着用。ひとまずメンブレンは GORETEX PRO が良いかなと考えた。胸元の縦ジッパーが2つあるのが便利。バックカントリースキー特化のハードシェルというだけあって、細かいところが使いやすいと感じる。
ダウンジャケット
montbell のプラズマ1000アルパインダウンパーカ。山頂での長時間の休憩や、万が一のビバークのときに着ることになると思う。ふだんはドライバッグに収納。

ウェアシステム(足回り)
タイツ
モンベルのスーパーメリノウールLWタイツを着用。膝部分までまくりあげてソックスと干渉しないようにしている。
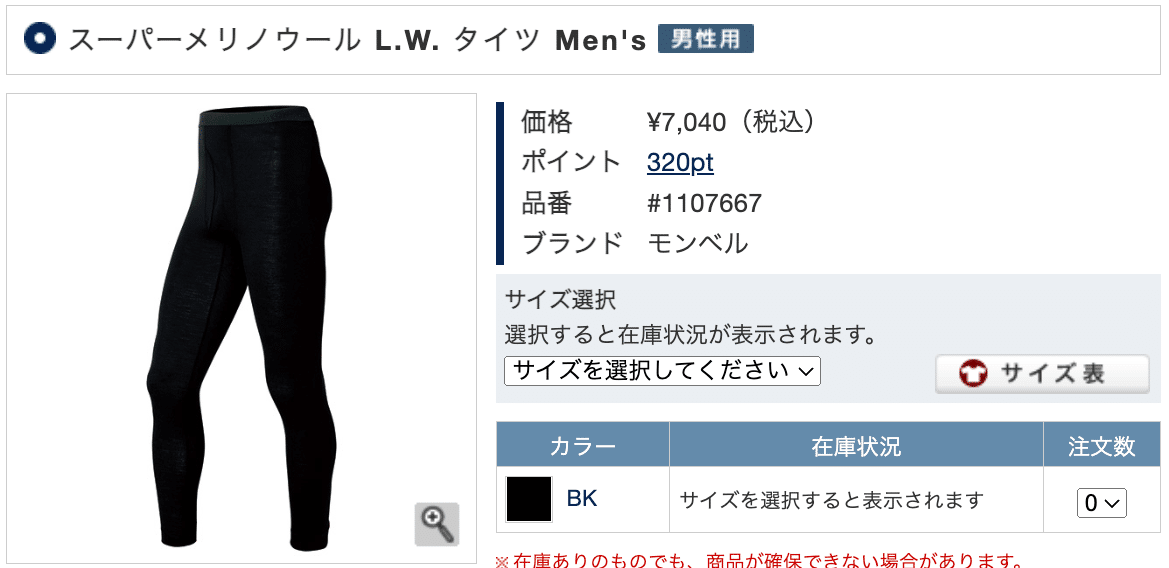
ソックス
DarnTough のスキーソックス。生涯保証なので穴があいたら無償交換してもらえる。スキーブーツ自体の保温性があるので、スキーソックスは薄めでよいと思う。丈の長さがブーツ以上であることもポイント。

ハーフパンツ
TetonBros のハーフパンツ。化繊なので軽くて温かい。ベンチレーションがあるのがあたらしい。ビブパンツと対応しているので、効率よく足回りの熱を逃がせる気がする。ハーフパンツをタイツの上に履いていることで、下山後にビブパンツを脱いでも外を出歩くことができるのが地味に便利。

ビブパンツ
The North Face の RTG ゴアテックスビブ。ひとまずメンブレンが GORE TEX Pro が良いかなと考えて選択。バックカントリー特化というだけあって使い勝手よく感じる。ハイクアップ・滑走の両方でずっと着用していることになるので、ハードシェルよりも活躍の幅が広いのでお金をかけていいところ。
暑いときは、太もものでかいベンチレーションジップが開けられる。胸元もセンタージップがあって開けられる。太ももポケットにはビーコンを収納できる。

ウェアシステム(手)

グローブ
100円ショップのニトリル手袋をまずは着用。手汗を閉じ込めて、グローブを濡らさないようにする目的。いわゆる VBL。

よくわからないブランドのフリースグローブ。スマホタッチができて、ストレッチが効いて、雪が付着しにくければ何でも良いと思う。登山ブランドのグローブが 5000 円以上もするのでスポーツショップで安いものを購入。

スペアとしてファイントラックEXPグローブを常にザックに保持。Sサイズでもフィットがゆるい気がする。高い。撥水生地なので、雪が付着して溶けてもグローブに浸透しない。
ハンドウォーマー
フリースグローブ単体で寒いときにレイヤリングする。ポッサムメリノはケバケバしていて空気を溜め込むので温かく感じる。指先の操作性をのこしつつ、保温性をブーストしてくれる。

オーバーグローブ
ハイクアップで、ハンドウォーマーをレイヤリングしても寒い時に着用。Mammut のシェルミトン。フィッティングが良くて、シーム処理もちゃんとしていて、手のひらグリップが効くのがお気に入り。ペラペラ素材なのでコンパクトに畳んで、ザックのサイドポケットにしまっておける。ミトン形状はやっぱり温かいし、防水生地なので水の侵入の心配もない。
滑走時は防寒テムレスをフリースグローブ、ハンドウォーマーの上から着用。DIYでリストストラップやリーシュをつけることで、かなり使い勝手がよくなった。
ストレージ
バックパック
Osprey の キャンバー32。32Lは日帰りバックカントリーにちょうど良いサイズ。バックカントリー特化のザックは使い勝手が良い。ヘルメットが収納できて、スキー板もアタッチできて、背面アクセスできるのも便利。

ドライバッグ
いろんな容量の詰め合わせのドライバッグ。1Lサイズにはツェルトを収納。2Lサイズにはダウンジャケットを収納。ロールトップはギュッと圧縮できるのが便利。ドライバッグはいろんなサイズがあると使い勝手がいい。
サコッシュ
モンベルの U.L. ショルダーポーチS。シルナイロン製なので軽量コンパクト。車の鍵、家の鍵、財布が常備されている。サコッシュごとバックパックに突っ込む。

ガジェット
スマートウォッチ
Apple watch Ultra。バックカントリーでは頻繁に地図をみたいのでスマホよりもスマートウォッチを好む。Ultra はバッテリー継続時間が長いので安心。画面が大きいので見やすい。

スマホ
iPhone 16 Pro。望遠5倍レンズで遠くの景色を画質良くとれるのが、特に気に入っている。
スマホタッチペン
グローブだとスマホや Apple watch がうまく操作できないのでタッチペンは必須。ザックのショルダーストラップに、コードリールで取り付け。どんなグローブでもレイヤリングでも、すぐに取り出せる位置。
バッテリー
Anker 10000mAh のもの。電熱ゴーグルやスマホやアクションカメラのために。
衛星通信デバイス
バックカントリーは普通の登山に比べてリスクが高いので保持。維持費が高い。さいきんは iPhone の衛星通信もあるから要らないかも思いつつ。
ヘッドライト
Nitecore の NU25。USB-C 充電ができる。ダブルビーム。ボタンワンクリックで光量の強弱を変更するシンプルな仕様。
トランシーバー
複数で滑走するときには無線機があると便利。姿が見えなくても100mくらいなら音声通話ができる。先に滑走した人から雪質や地形について教わったり、滑走のかっこいいシーンをとるための打ち合わせをしたりする。
アクションカメラ
DJI Osmo Action 4。センサーサイズが大きいので、暗闇スタートのバックカントリーでもそれなりに撮影ができるし、やっぱり映像がキレイだと思う。
稜線上は風が強いことが多いし、無風だとしても滑走時のには必ず風の音がする。スポンジカバーは必須。
さいきん発売された視野角を182度まで広げてくれる拡張レンズ。スキー動画は、スキー板の先端を画角にたくさんいれるのが重要だと思う。
マウントはいろいろ試した結果、チェストマウントに落ち着いた。ON/OFFがしやすいし、手元足元がバランス良く撮影できるのがチェスト。
置き撮りしたいときには、ストックに装着して雪のなかに自立させる。セルフィーをしたいときは普通に手持ち。
補給
食べ物
パン・まんじゅう・チョコなど、水分をあまり含んでいなくて高カロリーなもの。
飲み物

ナルゲン500mLとサーモスの山専用ボトル500mLの2本を携行。
ハイクアップ時など水分補給がメインのときはナルゲンから補給。ホットポカリであることが多い。
山頂での休憩時や、滑走の合間の休憩のときは、温かい飲み物がほしくなる。モンベルよりもサーモスのほうが操作性が若干いい気がする。
スキーギア

スキーブーツ
Nordica の Unlimited LT 130。ウォークモードの可動域が広くて歩きやすい。Twitter(X) 界隈でべた褒めされていた気がするので購入した。
スキー板
Elan の Ripstick 106。センター幅が106なのでパウダーシーズンに適しているはず。たぶん残雪期でも問題ない気がする。長さは 172cm で、キックターンなどの取り回しのしやすさ重視。
ビンディング
Marker の Kingpin 10 を装着。ヒールリフターが2段階あり、ブレーキ付きで、機能十分なテックビンディングだと思う。
ストック
Black Diamond Traverse 2 WR ポール。グリップにネジ穴がきってあり、アタッチメント装着できる。片方にはウィペットを装着して、片方にはアクションカメラ用のネジを装着している
シール
POMOCA の クライムプロSグライド。山スキー界隈ではよく見かける水色のシールである。POMOCA のシールはシール面同士をくっつけられるので、チートシートが要らないのがメリットらしい。
ストラップ
G3のスキーストラップ。特にこだわりはないので目立つ赤色を選択。シールがはがれちゃうときに縛り付けるなど、いろんな用途がありえる。ふだんはストックに巻き付けている。

スクレイパーブラシ
山スキー界隈では定番。シールの脱着のときにスキー板に付着した水分や雪をけずりとったり、ビンディングに詰まった雪をブラシで落としたりする。ふだんはコードリールでビブに収納している。
リスクマネジメント
アバランチギア
マムートのプローブ。特にこだわりはない。
MSRのオペレーターDショベル。すでに廃盤。グリップ形状はT字よりもD字が握りやすいときいたので。
マムートのバリボックス。雪崩ビーコンのなかでは定番。雪崩講習の参加者を見渡しても、8割は同じマムートだった。
ツェルト
アライテントのスーパーライトツェルト。万が一のビバークに備えて。特にこだわりはないので、軽さ&コンパクトさを重視。ふだんはドライバッグに収納。
