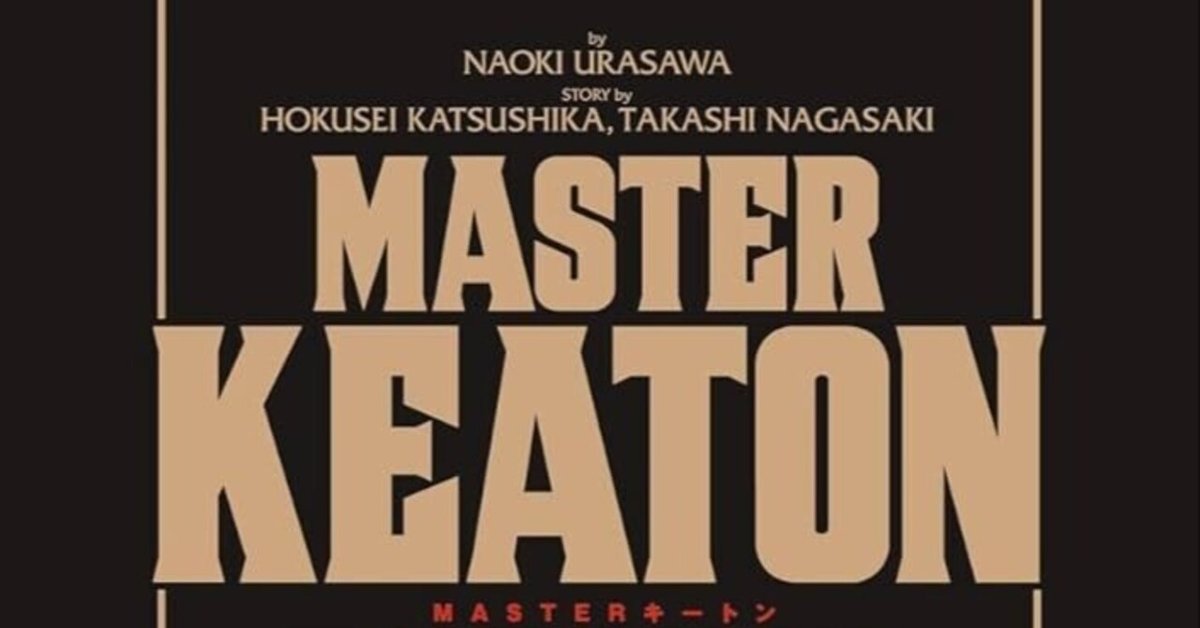
回想・浦沢直樹作画・浦沢直樹・勝鹿北星・長崎尚志脚本『マスターキートン』(小学館、1988~1994年)
『マスターキートン』の主人公は、考古学者の平賀・キートン・太一で、考古学ではメシが食えないので、保険の調査員をして生計を立てている。英国特殊部隊にいた経験も持つ。その主人公の身のまわりに起こる、さまざまな事件や出来事を描いたヒューマンドラマである。
その中に、「屋根の下の巴里」というエピソードがある。私が一番好きなエピソードである。
キートンが考古学の研究を続けたい、と思う大きな理由の1つに、大学時代に人生を変えた師、ユーリー・スコット教授の存在があった。
いつまでたっても大学に就職できない考古学者、キートンは、あるとき、パリの社会人大学の非常勤講師の口を見つける。そこで、社会人たちを前に、考古学を講義することになった。
ところが運の悪いことに、その社会人大学は、もうじきとりこわされることになった。せっかく、意欲のある人たちの前で、自分の好きな専門の講義ができることになった矢先なのに、と、キートンは自分の運の悪さをのろった。
自分は研究者としてはたしてモノになるのだろうか?心が折れそうになったキートンは、ふと、自分の師匠である、ユーリー・スコット先生のことを思い出す。スコット先生は、第二次大戦中のロンドンで、瓦礫と化した大学で、社会人たちを前に、瓦礫からとりだした教科書の土埃をはらいながら、最後の最後まで授業を続けたのである。
第二次世界大戦中の1941年、ロンドンはドイツ軍の空襲にあい、壊滅的な被害を受ける。大学もまた、瓦礫と化してしまう。
大学の瓦礫を片づける1人の男性、その男性のもとに、自分の家の瓦礫の撤去に一区切りをつけた住人たちが集まってきた。
その男性こそが、若き日のユーリー・スコット先生である。
瓦礫の上に立つ先生は集まってきた人たちに言った。「さあそれでは諸君、授業をはじめよう。あと15分ある」
こんな時に授業を?と、いぶかしむ人々。
「敵のねらいは、われわれ英国民の向上心をくじくことだ。そこで私たちが学ぶことを放棄したら、それこそヒットラーの思うつぼだ。今こそ学び、この戦争のような、殺し合い憎しみ合う人間の愚かな性(さが)を乗越え、新たな文明を築くべきです」
先生の言葉は、瓦礫に覆われたロンドンの町にこだました。
ユーリー・スコット先生は、あるとき、当時学生だったキートンに言う。
「人はその意志さえあれば、いつでも学ぶことができる」と。
キートンは、ふと、この師の言葉を思い出し、落ち込んだ自分を奮い立たせるのである。
そして自分もまた、社会人大学がとりこわされる最後の最後まで、授業を続けることを決意する。
キートンは社会人学生たちを前に、講義の最後をこう締めくくる。
「人間は一生、学び続けるべきです。
人間には好奇心、知る喜びがある。
肩書きや、出世して大臣になるために、学ぶのではないのです…
では、なぜ学び続けるのでしょう?
………
それが人間の使命だからです」
そしてこのエピソードは、最後に感動的な場面を迎えて大団円となる。
『マスターキートン』はアニメ化もされている。その中の1つにこの「屋根の下の巴里」のエピソードが含まれている。
私が前職で大学教員をしていた時、1回だけ、授業でこの「屋根の下の巴里」のアニメを見せたことがある。
「今日はアニメ作品をお見せします」とだけ言って、どんな作品かを言わなかった。
30分に満たない作品だが、50名以上の学生が、音も立てずに見入っている。
やがてエンディング。すべて終わって、教室の電気をつけると、すすり泣いている学生が何人かいた。
「では、感想を書いてください。どんなことでもかまいません」と私。
ほとんどの学生が感想を書いてくれた。その感想の一部は写し残しておいた。以下は、そのうちのごく一部である。
「『学ぶところがなくなっても学び続ける』っていう言葉がすごく心に残った」
「一生をかけて向き合っていきたいと思えるようなものに出会えたキートンさんはきっと幸せだと思う。私もそのようなものにこれから出会えたらいいなと思う」
「辞職してまで異端とされた自身の学説を貫き通したユーリー・スコット先生は誇り高い考古学者だと思います。最初は黙って授業を終わらせるしかできなかったキートン先生が、最後の授業で『大臣でも静かにしなさい』と言い放った瞬間に、講師ではなく本物の教師になったのだと感じました」
「“いかなる状況でも学ぶことをやめないでほしい”という主人公やその恩師の言葉が印象に残りました。大学生という思う存分学ぶことができる立場にあるので、そのことに感謝しつつ、しっかりと学んでいきたいと思いました」
「時間がないというのは言い訳でしかなく、学ぼうと思えばいつでも学べる、ということが印象に強く残った」
「キートンの『大臣でも静かにしなさい』というセリフが、とても心に残りました。大学とは異なり、社会人学校は働いている人が多い中、みんな意欲的に授業を受けるという風景にびっくりしました。学ぶ権利は誰にでもあり、そして時間もあるのだと思いました」
「今、私たちが大学で学ぶことができていることがどんなに幸せなことか、あらためて気づかされた。また、どんな状況であっても、自分が学習に対する意欲を持っていたら、いくらでも学ぶことはできるのだなあとユーリー先生から学んだ。大変心が動かされた作品だった」
「『学校がなくても学び続けることはできる』。学ぶというのは、自分の意志ひとつなんだと思う。気持ちさえあれば、すべて勉強になる。不安であっても、やりたいことをやる、ということがあこがれる」
「今の人々は学ぶ場が豊富に与えられていて、自分が学びたいと思わなくても学べる状況にある。学ぶことへの本当の喜びと学べることのありがたさをもっと感じるべきだと思う。また、大学という学ぶのに最も適した場にいることを生かして、意欲的に学びたい」
「自分の知的好奇心に素直になって、学び続けるということが実はすごくむずかしいことで、自分の道を歩み続けるというのは勇気のいることなんだなと感じた」
「私も尊敬する人から将来『立派になったな』と言われたい。学問を追究する姿は胸に迫るものがあった」
「一生学び続けることの大切さを知ったと共に、一生学び続けたいと思いました」
「どんな状況にあっても勉強をやり続けるという教授の言葉は、私の心に響きました。この大学生活の中でも生かせる教訓だと思います」
「学ぶために大学に来たのだということをあらためて感じさせられました。“なぜ学ぶのか”という問いは、いつでも学生について回りますが、この作品を見て、答えの一つを見つけられたような気がします。しかし、その問いの答えは一つではないと思うので、大学での4年間を生かし、自分なりの答えを発見したいです」
「最近レポートとテストに追われていて、いろいろめんどくさいとか思っていたけれど、この作品を見てあらためて「学ぶって面白い、私は勉強するのが好きだから大学に来てるんだ!」って思った。夜、寝る間も惜しんで本を読み、一生懸命興味あるものについて考えるキートンの姿は格好よかった。日々に流されないで、常に向上心を持っていきたいと思った」
「私は最近、勉強がいやで適当になりがちだったのですが、これを見て勉強を楽しいと思っていた時を思い出しました。だから、勉強に対する情熱を取り戻したいと思いました」
15年近く教員稼業をしていたが、学生たちからこれほどのコメントを引き出せる授業は、私にはとてもできなかった。以来自分の無力さを自覚するようになり、それはいまでも続いている。
そんなことより、やはり作品の力って素晴らしい。
