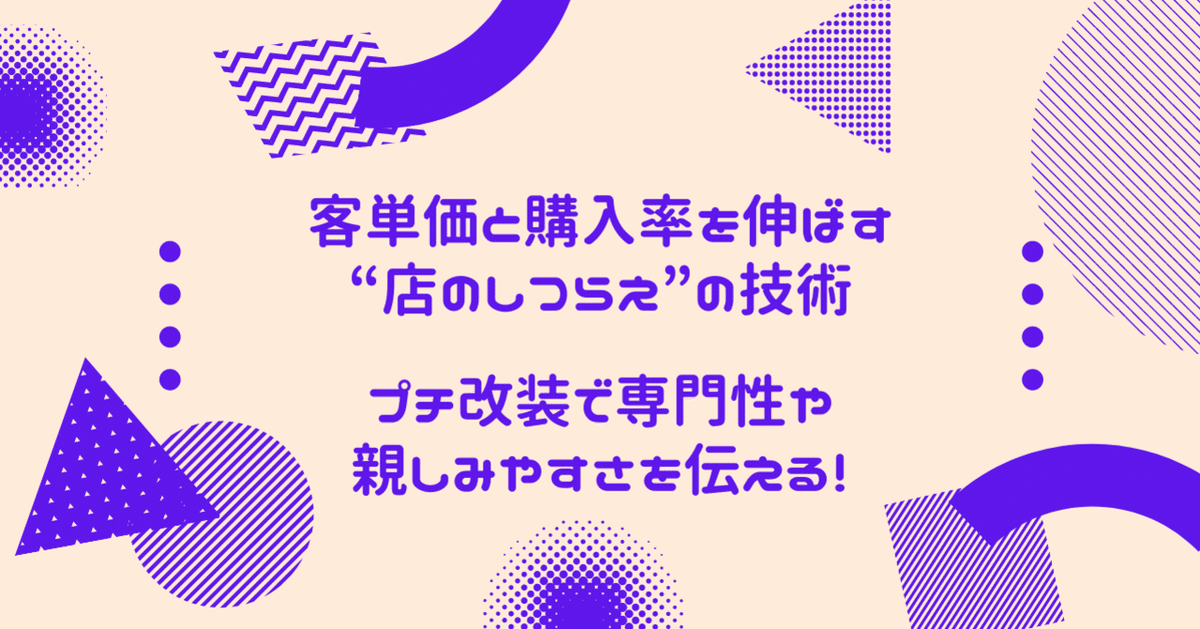
客単価と購入率を伸ばす“店のしつらえ”の技術。プチ改装で専門性や親しみやすさを伝える!
お客視点のちょっとした改善で客単価と購入率を伸ばし、在庫は減らせる
店は、お客に喜びを提供する場所。しかし、毎日そこにいるとお客のためよりも自分の都合を優先し、お客よりも商品を主役とした“しつらえ”になりがちです。儲けをもたらすのは商品ではなく、お客なのだということを忘れてはいけません。お客の心理を捉える「店のしつらえ」を実践し、客単価と購入率、さらには荒利を伸ばしましょう。
店頭のしつらえ 入店客はこれで増える
新規客は、入店するかどうかを、店舗外観と外からうかがえる情報だけで判断して決めます。ここを越えて入店しても、買上率と平均単価は店内空間のつくり方に大きく影響を受けます。集客から購入につながるかは、実店舗の“しつらえ”が鍵になります。
買物方法は成熟して、さまざまな買物方法へと細分化しています(図表①)。実店舗でもネット申し込みから配達までがセットになっていたり、インターネット店舗でも情報の多いサイトで商品決定をしてから最安値検索をして別サイトから購入したり、実店舗に専門家を同行して買物したりと、買物方法が多彩になっています。
そんな中で、実店舗へ来店する人たちには「自分を大切にしてくれる店で買いたい」という共通特徴が強くなりました。お客は日々変化しています。それなのに実店舗はいつ変化させましたか。全面改装ではなく、小さな変化でも人の特性に合っていたら大きく売上に貢献します。
新規客が入店しやすくなる「外観しつらえ」を持たなければ、お金を掛けて集客しても無駄になります。せっかくお客が店頭までやって来ても入店せず、帰ってしまう“店前Uターン客”現象を起こしていませんか。
店のしつらえは気分やセンスではなく、買物多様性時代にわざわざ実店舗に足を運ぶ「非効率を楽しいと感じるお客」に優しいつくり込みをします。
【1】お客にとって危険な外観は無機質・ぞんざい・張り紙
人間にとって自分がどう扱われるかは、生き延びるために重要な案件です。人の気配がしない店頭は無機質で「この店、営業しているのかしら」と不安を覚えます。使わなくなった備品が放置されて掃除もされていないと、見る人に「自分もほったらかしにされるのでは」と恐れを感じさせます。入り口ドアやショーウインドーのガラスに貼り過ぎたポスター類は、お客にとっては「入ってこないで」という遮断として伝わってしまいます。
ある薬局では、店主・従業員の専門性が高く、業界でも評判の商品を取り扱っていましたが、新規客入店が少なく、あってもテレビCM商品の価格の問い合わせばかりでした。この店舗の外観問題点は3つありました。
危険信号①
店頭で一番目立つのはスチール棚で人の気配がない→よく言えばスッキリしているかもしれないが、お客は冷たい感触とドライな扱われ方を想像して身構えてしまう。
危険信号②
古びたスチール三段棚が中心に置かれトイレットペーパーなど無造作に山積み→古びても手入れしてもらえないぞんざいな扱いから、お客は「この店と付き合うと私もぞんざいに扱われそう」と感じて入店しない。
危険信号③
入り口のガラスドアにはメーカー商品ポスターなどがべたべた張られ、店内が見えない。ショーウインドーのガラスは症状などを書いた張り紙がびっしり→お客にとって外から店内がうかがえないのは、お化け屋敷のようなものです。中がよく見えない知らない場所に足を踏み込むには多大な勇気が必要で、気軽に入ってはいけない店だと伝わってしまいます。
この店頭から出ているサインは「この店は冷たく、手入れをしたくない、お客とは接したくない、疲れている店だ」となります。店主は親切で知識も豊富で良い商材を扱っていることなど、まったく伝わらず損をしていました。
【2】外観をプチ改装するだけで入店客が増え、客層が上質に
大掛かりな改装をしなくても、手軽にすぐできる方法があります。高級にするのが目的ではありません。人の気配を出し、お客に手間暇かけたい従業員がいて、あなたを大切に迎える準備ができていると感じてもらうのが目的です。
しつらえを改善するには、まず“引き算”、次に“足し算”、最後に“表情”の順番で進めます。
先の薬局では、まずは古びたスチール棚と張り紙を撤去しました。空いた空間に手書き黒板で「人の気配」を出し、花を寄せ植えした鉢を置くことで「手間暇をかけるのが好きです」と伝え、ベンチを設置して「商品ではなく、このベンチに座る人を待っている」と“しつらえ”を改善しました。
すると店内をのぞき込む人が増え、店の前のお客と目が合う回数が増えました。このときに「にっこり笑顔を返す」と、自然な流れで入店してもらえる回数が増えました。以前のしつらえでは入店しなかった「相談客」が主流顧客となりました。入店しやすい“店のしつらえ”には、店主・従業員という“人”もセットなのです。
人は一人ではなく集団を作り、その中で生活する生き物です。だから「この店は私をどう扱ってくれるのか」が分かる店頭のしつらえが必要なのです。私より商品が大切な店ではなく、私を大切にしてくれる店と付き合いたいのです。
花を枯らさず咲かせるには手が掛かり、掃除も面倒になります。黒板など書き換えるのも手間です。座るためではなく迎えるためにベンチを置くのは非効率です。しかし、お客は自分を効率で扱ってほしくないからこそ効果があります。店の効率化は、お客を大切に扱う余裕を生み出すためにあります。その余裕を生み出す鍵は、店内のしつらえにあります。
店内のしつらえ 客単価はこれで上がる
実店舗の最大リスクは、設営の経費だけでなく維持費も掛かるのに、お客を追い掛けて移動することができないことです。
商売において実店舗は、商品本体以外にも価値を付加できる強みがあります。商品を知った瞬間から、手にして、動機づけされ、購入し、消費され、アフターフォローまでつながる“出合いから使い続ける過程で起こる出来事の質”も価値です。買物する空間と、そこで起こる体験の質が価格に反映できる付加価値となり、それは非効率なことがほとんどです。専門店の実店舗を買物方法に選ぶ人は、非効率を楽しめる特徴を持っています(図表②)。
セルフサービスで買物に販売員が介在しなくても済んでしまう店舗は、効率優先が基本でしょう。物を探しに来る買物方法ですから、当然物が主役です。店側の都合の良いように店はしつらえられます。掃除がしやすい、在庫補充が早い、説明が必要ない、空間にどれだけ多く詰め込めるか、展示と在庫管理が一緒の倉庫兼売場づくりです。接客が基本となる店舗であれば、こうした店都合の売場づくりは逆効果になります。店主・従業員といった人も“しつらえ”に含まれるのですから。信頼性を高める・専門性を感じさせる・集中を邪魔しない店内のしつらえにすると、購入率と客単価が上がります。さらに、無駄な在庫も減らせます。
人は、見る・聞く・触る・嗅ぐ・味わうという五感を使って、一瞬で「なんか好き」とか「なんか嫌い」などと判断します。
外観のしつらえに気を配ると、店とお客の付き合いが「好き」から始められます。好ましさから始まる付き合いは“アバタもエクボ”になり、古いしつらえは歴史を感じさせ、口数の少なさは落ち着きを、絞られた商品数は品質の良さを、限られた空間は近しい距離となります。反対に「嫌い」から始まると、全てがマイナスに感じられてしまいます。人は自分が持った感覚を正当化しようと都合よく物事を捉えます。それが“好き”のもたらす効果です。それを象徴する代表的なものが5つあります。
【1】椅子がたくさんあるとお客と心が通い合う理由
椅子には力があります。座る人を主役にする力です。店内にはできるだけ多く椅子を配置しましょう。商談は価格にかかわらず大切なものです。大切なことは座って対話するのが基本です。自宅に大切な人が訪ねてきたとき、立たせておきますか。座るか座らないかはお客の自由ですが、椅子を勧められるとお客として迎えられたと感じてもらえます。
ある酒販店で、商品の精算や包装をするときに「どうぞ掛けてお待ちください」と椅子を勧めるように変えました。すると、座って待つ人はほぼいませんが、気楽に店内を回遊するようになり追加買いの比率が格段に上がりました。強要ではなく自ら回遊して見つけた商品は、良い物だと正当化されるから買上率が上がるのです。
椅子にはもう一つ力があります。自らが座らなくても荷物置きになることです。人は姿勢によって心の状態が変わります。体の前面にかばんを持つ姿勢だと“販売員とお客の間に荷物がある=販売員とお客の間に障壁がある”となり、心を開いてもらえず寄り添えず、提案が的外れになります。座ると置く、一人に椅子は2脚必要だと覚えてください。
ここから先は
¥ 100
Amazonギフトカード5,000円分が当たる
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?
