
売れるPOPの 書き方・作り方 1 もう一人の腕利き販売員をつくれ!
店頭で商品を売るコツは、売ろうと思わないことです。お客様は追い掛ければ逃げていきます。売ろうと思って必死に商品説明をすればするほど嫌な顔をされます。だからといって、並べて置くだけで売れるほど販売現場は甘くはありません。
ところが、同じ商品説明をしても嫌われないで売れてしまう方法もあります。同じ内容を話しているのに、お客にとって迷惑な販売員を親切な販売貝に変身させてしまう方法です。それは、店頭で販売促進ツールのPOPを使うことです。この記事では、POP に書くべき内容の見つける方法をお伝えします。
POPは「もう一人の腕利き販売員」
POPとは「Point of purchase advertising」の略だと言われます。簡単にいうと、店舗の商品近くにある「商品の特徴やお勧めポイントを価格と一緒に明記してある紙切れ」です。人という販売員ではなく、文字やイラストが書いてある紙切れなのに読むとなぜか欲しくなってしまう紙切れです。よって、私はPOPを「もう一人の販売員」と思っています。どうせなら「腕利き販売員がいいなぁ」と思います。単なる紙切れが、あなたが忙しく働いている時も休憩している時も売上を作ってくれる方法を紹介していきましょう。
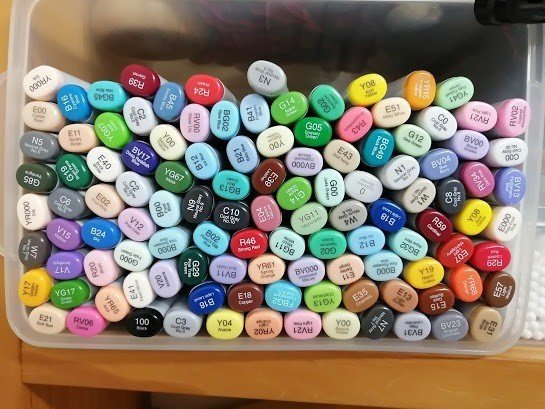
「売れる」という行為を分解してみよう
「売れる=存在を知る×情報が多いものが欲しくなる×今必要だと理解する」
この3つが掛け合わさって初めて商品が売れていきます。
そこには売りつけるという行為は入っていません。だから売ろうと思うと売れないのですね。店頭で商品を売るには、まずは「売れる=存在を知る×情報が多いものが欲しくなる×今必要だと理解する」と行動を分けてみましょう。それぞれに相当する一言をPOPに書くと店頭での販売効率が上がります。
POPで商品を日立たせ、存在そのものを知ってもらうために書く。
↓
お客様の頭の中を商品情報でいっぱいにするために書く。頭の中の情報量が「欲しい」という気持ちを引き起こすからです。
↓
こうして欲しくなったお客様に「今買わなきゃ!」と思わせる。
↓
売れてしまう。
つまり、POPによってお客様と商品のコミュニケーションが取れて売り上げにつながる。忙しいときにも販売貝の分身となり、お客様は勝手に動機付けされて売りげにつながる。これがPOPの持つ力です。
POPを書く行為も分解してみよう
さて、実際にPOPを書こうと思ったときに次のような状態に陥っていませんか。ペンを持って白紙をにらみながら、ろう人形のように固まってしまう。私は「ろう人形の呪い」と呼んでいます。これは売ろうと思ったら売れないのと同じで、上手に書かなくちゃなどと思えば思うほど書けなくなります。こんな時はPOPを書くという行為を分解してみると呪いはとけていきます。
「POPを書く=商品の生い立ちを探す十それをペンで紙に書く」
商品の生い立ちとは、商品ができた理由、商品になるまでの苫労、その苦労を乗り越えるための工夫、原材料・作り方への職人的なこだわり、ライバル商品との違いなどです。これらを探し出さないで、何を書いたらいいか分からないまま書き始めると、商品名と値段だけが書かれているプライスカードになってしまいます。もしくは「おいしいです」「安いです」「カッコイイです」などと具体性のないことを書いてしまいがちです。
そういったPOPは、その商品じゃなくても使えてしまう。商品が変わっても使い回しのできることしか書いていないPOPでは売れません。
プラモデルを作るには部品がいるのと同じことです。カッターとのりだけあっても、部品がないとプラモデルは完成しません。POPも同じです。ペンと紙だけあっても、商品の生い立ちがないと売れるPOPにはならないのです。

POPを書く行為を分解して図にしてみました

POPは感覚で書くものではなく、下調べが必要です。
メーカー・販売員・お客様に質問すると、商品の生い立ちが見つかる15の質問集
そうはいっても、商品の生い立ちをどうやって探したらいいのでしょう。商品の箱には書いてないし、卸問屋の担当者も教えてはくれません。メーカーから説明もありません。本来はメーカーサイドが商品の生い立ちを進んで教えてくれると、店頭側は売るのが簡単になります。でも、メーカーは商品の生い立ちがPOPの大切な部品だとは思っていないのです。
商品の生い立ちを探すときは、メーカーに質問をしてみましょう。何を答えたらよいのか分からない相手に質問をするときには、質問内容が大切です。的外れな答えでは売れるPOPの部品にはならないからです。
質問先を3つに分けます。具体的には、メーカーへの質問が10個、販売現場への質問が1個。お客様への質問が4個。

この質問集の答えは、POPを書くときのネタ帳となります。店頭ではPOP書き以外にもたくさんの仕事がありますが、忙しい店頭でも効率よくPOPが書けるネタ帳になります。すべての質問に答えが出なくても、1つでも2つでも分かれば十分です。分かった答えだけでPOPを書くことが可能です。幸いにもPOPの面積は限られているから、それほど多くの内容を書けませんからね。
商品の代わりにPOPに自己紹介をさせる
POPは作品ではありません。あくまで商品説明のツールです。道具ですよ。主役である商品を知ってもらい、商品情報を読んで動機付けされ購入してもらうためのツール。だから、キレイに作ることよりも何を書くかが大切になります。(もちそん、そのうえ見栄えがキレイなら最高です)
そして、手書きPOPは「整っていない」ために、見る人に「確認したい」という欲求を起こさせます。パソコンPOP のように整っていなからこその利点です。商品は自分で喋ることができません。自分で自己紹介を始めることはありません。だから、売りたい商品にはPOPをつけましょう。商品の代わりにPOPにどんどん自己紹介をさせるのです。
第2話から成功事例を使って、質問集をどうPOPに活かしたかを紹介していきます。手書きPOP中心で紹介していきますね。
