
今が一番美しい 銀座花伝MAGAZINE Vol.33
#今が一番美しい #ひとり時間が許される街 #源氏物語と着物

この街には、世界中の色彩が溢れていて、訪れた人たちの眼を楽しませてくれる。特に銀座中央通りにある海外ブランドのウインドウは、その店でしか生み出せないオンリーワンの色目を商品を通じて発信しているようだ。そして、西洋化した街並みの中に「日本の色」を見つけることも街散策の大きな楽しみだ。
多くの場合、日本の色はこの街を訪れる人々の装いから見出されることが多い。西洋のモダンの中でこそ晴れ晴れと息づく日本の色。それは、「着物」という日本古来の衣装がもたらす文化との出会いから生まれてくる。
夏の晩に秘密裏に開演された「創作能 源氏物語」。銀座老舗店主からのご招待で訪れた能楽堂には、見たこともない王朝文化に彩られた異界が広がっていた。日本文化の文様を克明に切り取った紫式部。彼女の筆を借りて描き上げた創作舞台。文化人M夫人との出会いのひとときは、「ひとり時間の磨き方」を発見するまたとない貴重な機会となった。そのあらましをご紹介する。
銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に人々の力によって生き続けている「美のかけら」を発見していく。

◇Essay 今が一番美しいーひとり時間を誂えるー
プロローグ
人にはそれぞれ好む特別な色があるようで、ヨーロッパ圏を中心に世界の多くの人々にとっては青だと言われる。日本ではどうかといえば、三大色は藍・紅・紫で日本文化を象徴する色とも言われている。特に藍のうち青に近い色は昔から日常着から正装・武具にまで用いられ、人の心を鎮める色として最も日本人に好まれている。
先日、歩行者天国で日本らしい文様をあしらった絹紅梅をまとった母娘に出会った。お母様は大胆な籠目(かごめ)崩しの柄に萩を思わせるドット模様というモダンな着物、娘さんは白く抜かれた撫子(なでしこ)柄に露芝(つゆしば)模様で、藍の色目がお揃い。年齢を重ねた女性が着るモダンは実に格好がいいし、若者が着る夏の季節感を花に求め、そこに水を思わせる露が散るあしらいは、教養を感じる。
銀座3丁目のシャネルのウインドウを背景に微笑みながら語り合う立ち姿は、さながら谷崎潤一郎の「細雪」(ささめゆき)に登場する商家の姉妹のシルエットのようだ。
姉妹たちが帯を選ぶシーンが筆者はとりわけ好きだ。帯柄の「観世水」(かんぜみず)、「露芝」などの文様が会話に出てきて、日常の会話にもかかわらず、そこには眩しさがほとばしる。谷崎のこの作品は、この時局に「帯の文様がどうだ」というようなことに意味があるのか、こんなぜいたくな物語を書くとは何事だ、と批判され「中央公論」は連載中止の処分を受けた。しかし戦争が激化する中でも谷崎は「細雪」を書き続けた。戦争が終わった時、人々はささやかなことにこだわる暮らしの営みの楽しさがここにあると、日常が戻ってきたことを喜んだという。
戦争で被害を受けた方々への鎮魂やその当時に想いを馳せるとき、その中で胸に浮かぶのは、「細雪」にあるような日本の美が宿る日常の尊さについてである。
ひとり時間が許される街
最近コロナの影響もあってか、ひとり時間を楽しむ女性の姿をこれまでに増して見かけるようになった。直近の国勢調査によると30歳代女性の3人に1人が未婚であるというが、既婚未婚にかかわらず、自分だけの時間(ひとり時間)を大切にしたい女性たちがこだわるのは、「自分の美しい」を実感できる時間であることだという。
『「ひとり着物で街を歩く」をやってみたいが、なかなかハードルが高くて実践できないでいる。銀座なら雰囲気的に出来そうだと思うが・・・』と30歳代のOLから相談を受けた。この「ひとりで」という点がとても重要らしい。
以前三人グループで旅行先の京都でレンタル着物を着付けてもらい街を散策してとても楽しかったので、東京でそれも銀座で体験したい。大人の女性としてはひとりでそれができることが相応しいような気がする。しかしながら、仮に着物姿になんとかなったとして、街を散策する時間をどのように過ごしたら良いのかがわからない、というのである。
確かに旅先では勢いもあって、グループでワイワイ着付屋に飛び込み、思い思いの彩を身に纏って街に繰り出すというシチュエーション自体が楽しいし容易であるに違いない。着物初心者にとってはそうした勢いがないとなかなか踏み切れないのだろう。
なぜ、銀座なのかと問うと、
「東京で着物が一番似合うのは、銀座だと思う。それは街の通りがとても美しいこと、そして他に比べて人通りが少ないこと、何より“ひとりを許してくれる”雰囲気があるから」という答えが返ってきた。
そして、ひとりは自由だが、実は場所によっては窮屈な思いをすることが多いというのだ。この窮屈さは、空間からも人からも感じるという。
「ひとり時間」を心地よく過ごすには一人の大人として尊重してくれる街だからこそできる、懐の深さが必要なのだろう。

月夜の源氏物語能
雨がようやく上がった、夏の晩の出来事である。
銀座の老舗店主の招待で、秘密裏に開催された創作能の舞台を鑑賞する機会に恵まれた。非公開のため、観世能楽堂の休場日の夜にそれは開催され200名全ての方が招待客という異例の趣向だった。
テーマは「創作能 源氏物語」である。
冒頭、店主による源氏物語の解説に度肝を抜かれた。その内容の格調の高さは比類なく、博識の香りを漂わせた流麗な語り口は際立って分かりやすく、なんの予備知識もない筆者でもいきなり紫式部の世界に引き込まれてしまった。
銀座の店主というのは生業以外にいろいろ芸事をお持ちだが、その中にあってこの方は、源氏物語の語り部として日本文化の分野では知る人ぞ知る存在であるという。
そしてさらにびっくりしたのは、200名の招待客が全て着物姿だったことである。こんなことがあるとは・・・・・。
店主の話によると、この舞台の主催者は明治期の歌人倶楽部「ホトトギス」に集ったメンバー正岡子規や高浜虚子らの曾孫の皆様で、歴史的な文芸の灯を今に受け継ぎ、新たな文化に編集する活動に励まれているとのことであった。
豆知識:正岡子規(慶応3年〜明治35年)
歌人・俳人。愛媛県松山市に生まれ。一高時代に夏目金之助(漱石)を知り、明治18年ごろから俳句、短歌の実作に入る。明治28年日清戦争従軍、帰国途中に吐血、以後永い病床生活に入った。その壮絶な闘病生活は、随筆「病牀六尺」(明治35年)に詳しい。発病後も文学上の活動は活発化し、明治31年、「歌よみに与ふる書」を発表、短歌革新に乗りだす。芭蕉や古今和歌集についての自説を展開してそれらの全国的な再評価を喚起した。同年、雑誌「ホトトギス」創刊、洋画家中村不折らとの交流により、俳句に自然を描写する写生の重要性を説く。子規の俳句は自筆の稿本『寒山落木』全5巻、『俳句稿』全2巻などに2万近く収められ、短歌は『竹乃里歌』に記され、補遺をあわせて2400首ほど。晩年に近づくにつれて俳句も短歌も境涯を生かした至純な境地に進んだのは、『万葉集』からの摂取、また病苦の深まりによるものであると言われている。彼の俳句・短歌は、高浜虚子、伊藤左千夫に引き継がれる。明治35年9月19日死去、享年34歳。

姫君の装い表現
まずは、物語の概要をご紹介する。
舞台の物語は、光源氏の次の世代、薫の物語で、玉鬘(たまかずら)の二人の娘をめぐる若者たちの葛藤が綴られている巻(源氏物語 竹河二)をベースとする創作である。
「大君、中の君と呼ばれる娘たちはいずれも美しく、求婚者が群がっている。帝や前の帝の冷泉院も大君を望んでいる。また蔵人少将(くろうどのしょうしょう)は特に大君に執心し、薫もほのかに思っているようだ。冷泉院はかつて、玉鬘に思いを寄せ、それを断られたために娘を望んでいるのだった。この巻のクライマックスは、二人の姫君が桜を見ながら碁を打つシーンである。蔵人少将たちがそれをのぞき恋焦がれるが、結局大君は年配の冷泉院にもらわれてゆき、若い求婚者たちを落胆させる。」というあらすじの物語である。
紫式部の筆の見事さ
ここで実に麗しいと感嘆するのは、紫式部の筆による姫君たちの装いとその気高さの表現である。
時は桜の花が咲く頃。
「姫君はいとあざやかに気高ういまめかしきさましたまひて・・・・」
〈姫たちは大変鮮やかで気高く、艶なる装いをしている・・〉
姉の大君は、
「桜の細長、山吹などの、折にあひたる色あひのなつかしきほどに重なりたる裾まで、愛敬のこぼれ落ちるたるやうに見ゆる」
〈桜色の細長(女性の上着)に山吹襲(かさね/表は朽葉色、裏は黄色の色目)など春の季節にふさわしい色合いの重なる裾まで、愛らしさがあふれている〉
中の君の方は、
「薄紅梅に、御髪いろにて、柳の糸のやうにたをたをと見ゆ」
〈表は紅、裏は紫の襲(かさね)で、髪の色は美しく、柳の糸のようにたおやかである〉
姉は華やかで、妹はしっとりと落ち着いているが、ともに桜の花のように咲き出している。式部はその様子を装束を克明に写し、色の変化を際立たせながら描いている。

歌人が語る 源氏物語と着物
舞台の休憩時間になると、暗転していた会場がにわかに明るくなり、200名のお召し物が鮮やかに目の前で露になった。この舞台のテーマを意識してだろうか、王朝文化真っ盛りの色目の鮮やかさが際立つ着物のオンパレード。もちろん夏場なので絽(ろ)の薄物や帯をさりげなく召されている方々も少なからずいらしたが、多くは意匠を源氏物語の衣装や色目に求め装飾化した装いに見えた。
一番前の席をいただいていた筆者は好奇心を抑えきれず、少々緊張しながらぐるりと会場を見渡した。休憩時間でも話し声が聞こえてこないところを見ると、それぞれお一人で足を運んでいらっしゃることがうかがえる。みなさん、凛とした雰囲気を漂わせながらも纏った着物を楽しんでいる、そんな雰囲気が見てとれた。そのうちに同じ列にひとつ離れて座られている女性に目が止まった。その方は薄墨色をベースに有識(ゆうそく)文様(後述)と思しき高貴な柄が見え隠れする着物をお召しだったのである。凛とした座り姿、衣紋(えもん)の抜き方が上品でうなじから教養と艶が同時に香利立つような出立ちである。
失礼を省みず、その美しさに思わず見とれ、眺め入ってしまった。
「初めてでいらっしゃる?」
静かな日本庭園に響く水琴窟の音色にも似て涼やかな声が聞こえた。こちらの驚きを察してか、先方から話しかけてくださったようだ。「こういう世界は不調法で」と申し訳なさそうに言葉を返すと、
「源氏物語の醍醐味はなんだと思われます?」
「装いの仔細な表現でしょうか」
と感じたままを口にしてみた。 すると、にっこり微笑まれて、
「こちらにおいでの皆様はその辺をよく心得て、物語りの世界の一片をご自身の着物の中に取り込み、それを楽しんでいるのだと思います」
筆者の関心を見透かすように、歌人だと自己紹介されたM夫人は、素人にも分りやすく王朝文化と着物についてこんな話をしてくださった。
源氏物語絵巻
11世紀に書かれた源氏物語は、紫式部の描写の克明さにより王朝文化の百科事典だと言われている。それゆえに、その記述はすぐに絵画化されたが、現在残っている最古の絵巻は12世紀のもので、54帖(巻)のうち、4巻だけ。鎌倉時代には、白描きの「源氏物語」の「浮舟」の巻が残っているだけだが、室町時代に入ると、一気に「源氏物語」ルネッサンスが始まり多くの「源氏絵」が描かれ、小袖や意匠として〈源氏〉のイメージがその後の桃山時代、江戸時代にあふれることになる。当時は、女性の婚礼の調度などに源氏物語にちなむ意匠や、物語のことばを装飾化したちらし書きなどが好んで使われたという。
小袖の文様から、源氏物語のどの巻であるかが読み取れるかが問われたりした。そういう意味で、「源氏物語」は当時の女性の教養として重要だったことが分かるそうだ。

https://colbase.nich.go.jp/collection_items/kyohaku/A%E7%94%B216-22?locale=ja#&gid=null&pid=1
豆知識:『源氏物語画帖』「玉鬘」
『源氏物語』「玉鬘」の巻末には、光源氏が紫の上とともに、関係の深い女性たちに、それぞれの個性に最も似つかわしい新年の装束を見立てるという「衣配」(きぬくば)りのシーンがある。それぞれのキャラクターが文様とかさねの色目で表現されるという名場面が絵巻として残されている。
際立つ かさねの色目
王朝人は、色の組み合わせに非常な関心を持ち、さまざまな色目を工夫し、季節や場所によってセンスのいい色目をまるでゲームのように競い合った。
重要なのは、色目によって、色と文様を結びつけ、さらにそれに名前をつけて、ことばと結んだことである。
具体的には次のような方法である。
色の組み合わせを創る。同じ色をだんだん薄くしていき、グラデーションをつける、つまり繧繝(うんげん)彩色という方法だが、それに名前をつける時に〈におい〉という大和ことばで命名するといった具合である。
平安時代に、色と形とことばが一つに結びつき、文様の世界は驚異的に豊かになったのだろう。王朝の女性たちは、袖や裾の色目によって自分の魅力をアピールした。当時は御簾(みす)の陰に身をひそめて全身が見えないために、【打出】(うちいで)という所作を行った。御簾の下から袖や裾の色目を突き出す行為を指すが、これによって男性の気を惹こうとしたのである。
現代でも気があるふりをして誘うことを「色目を使う」というが、この語源がここから来ていると知って、源氏物語に端を発して時代を超えて残る表現の数々にいたく感心した。
最も華やかな配色は
「源氏物語絵巻」各段の場面を通じて、色彩色目の華やかさの点では、「竹河(二)」の段が最も優れていると言われているようです、という。
場面中央の中庭の満開の桜を鍵型に囲んだ簀子(すのこ)の右端に、黄地花菱文の表着の下に裏山吹(うらやまぶき/表皆黄・裏皆濃(うらみなご)山吹)五ツ衣と青き単(ひとえ)を重ねた女房の装束と、場面左端の座敷の端で碁を打っている、銀地に桜をとばした表着の下に山吹の匂襲(においかさね)の五ツ衣、その下に緑色の単をかさねた大君の装束が対照的に配され、その下方には銀地の表着に紅の袴をつけた女房が、また画面右端の下、中庭脇には二藍(ふたあい/赤と藍の中間色:後出)色の直衣(のうし)を来た蔵人少将がバランスよく配置されている。
今回の「創作能 源氏物語」の隠れたねらいがこうした色あわせにもあったことを知り、王朝文化の芸術性の深淵にただただ驚嘆するばかりだった。

この時代の、いくつかの色をずらして重ね、虹のような色のスペクトルを見せるやり方は素晴らしいですよ、とM夫人は続けた。
手元には、手のひらサイズの「日本の伝統色」(長崎盛輝著)なる書物が載っていた。
「いつもこうして、色合わせの源を手繰り寄せながら、鑑賞する」と実に楽しそうに開いて見せてくださった。源氏物語の巻ごとの代表的な色合わせ帖が載っている。
光源氏の愛した 色合わせ
最愛の女性「紫の上」の色
光源氏は、女性のために布や衣装を選んでいる(衣配:前出)が、彼が選ぶさまをみて、それぞれの女性がどのような容貌で、どのような人柄なのかを想像することができたのが紫の上だった。彼は紫の上に自ら似合うものはどれだと思うのか?と尋ねる。紫の上は、鏡を見ただけでは、どうして決められましょうかと恥ずかしそうに答えて、選ぶのを彼に委ねる。
そんな紫の上のために彼が選んだのは、「紅梅のいと紋浮きたる葡萄(えび)染の御小袿(こうちき)、今様色のいとすぐれたる(略)」という組み合わせである。紅梅の模様がくっきりと浮き出た生地を当時流行の最も高価で気品の高い葡萄染したものを選んでいる。「葡萄」は「葡萄葛(えびかずら/山葡萄の古名)のことで、「葡萄」はその山葡萄の実が熟したような、やや黒ずんだ紫色である。
その後もそれぞれの女性の雰囲気に合った衣装を次々と選んでいく光源氏だが、やはり最愛の女性である紫の上には、もっとも高価で気品高い色を選んでいる。贈られた衣装は、元日に着るようにという手紙が添えられ届けられたという。
代表的な色見帖
【紫の上】(むらさきのうえ)
紅梅の模様がくっきりと浮き出た葡萄染(えびぞめ)の小袿(こうちき)、今様(流行)色が見事な配色。
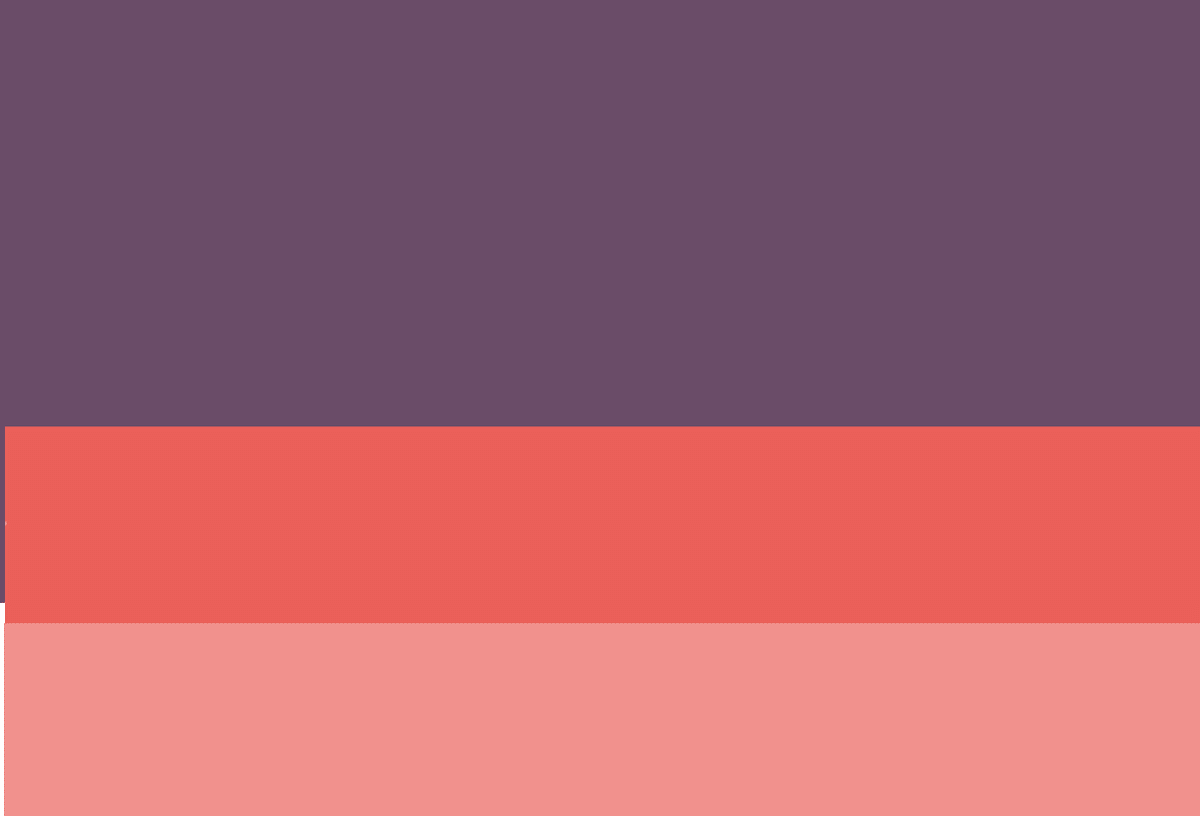
【空蝉】(うつせみ)
青鈍の織物で気の利いたものに、梔子色(くちなしいろ)と聴色(ゆるしいろ)=(紅花染めの淡い紅色)を合わせた配色。

【玉鬘】(たまかずら)
はっきりした赤に、山吹の花の細長

【明石の姫君】(あかしのひめぎみ)
桜の細長(上衣)に、つややかな掻練(かいねり)=(表裏とも紅色系のかさねの色目)

【花散里】(はなちるさと)
浅縹(あさはなだ)の海賦の織物で、織り方は美しいが、華やかでない色にたいそう濃い赤紅掻練。

【末摘花】(すえつむはな)
柳の織物で、由緒ある唐草模様が織り出されたもの。

今が一番美しい
ことばを紡ぐ玄人である歌人が、源氏物語の色彩の妙を語る。実に新鮮な体験だった。きっとM夫人の歌には心の底から湧き出るしみじみとした感情を、濃淡鮮やかな色で彩る妙があふれているに違いない、そんなことが想像できた。
改めて日本文化の代表とも言える着物には、それ自体が備える芸術性の高さとともに、纏う人の教養と想像力でその人間の質までも表出させる、そんな力があるのだと実感した。
終演後、色合わせのにわか知識をもとに、会場を後にする人々の襟合わせや裾の色目を観察してみた。なるほど、「あの方は葵上?」「あの色目は玉鬘?」などとパズルを解くような楽しみを見出すことができたのも貴重な発見だった。
M夫人の帰り際の言葉が胸に残る。
「今が一番美しい、その時間を誂えているんです」
ひとりの時間が「今が一番美しい」と実感できるようにする、そう心がけている方は実にどこか崇高で魅力的な生き方をされています、と言い残された。
その日纏われていたM夫人の着物には、花を菱形にした花菱をつないだ模様が誂えられていた。最初の印象通り、有識文様の幸菱(さいわいびし)文(後出)だった。それは、夏の色「二藍」(前出)に彩られて、真に美しかった。
豆知識:有職(ゆうそく)文様
公家、女房の装束、調度に使われた文様を有職文様という。天皇、皇太子などの地位によって、色や文様の規則性が決められていたが、平安時代になってそれは趣味や遊びの要素を含むようになった。この時代に芽生えた文様への意識や感性が選んだ文様が、それ以降、次第に和柄のスタンダードになっていく。
唐草文、木瓜(もっこう)文、浮線藤(ふせんふじ)文、蛮絵(ばんえ)文、亀甲(きっこう)文、菱(ひし)文、幸菱(さいわいびし)文、襷(たすき)文、立湧(たてわく)文、海賦(かいぶ)文などはその代表である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
凛とした余韻の煌めき
「夏は夜。月のころはさらなり、闇もなほ、ほたるの多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くもをかし。」
舞台がはけて、真夜中の銀座の街に散って行く女性たちの後姿は、清少納言の綴った「枕草子」の一句を思い起こすような、ほたるさながらの光景だった。凛と煌めく後姿は、街灯が落ちた街の中でことのほか眩しく感じられた。
中国古典五経の一つに「大学」という書物がある。その中に、「自分に嘘をつかないための訓練法」として【慎独】(しんどく)が提唱されている。古代より人間の品格を上げる方法として語り継がれてきている。自分が独りの時が“人格の原点”なのだから、独りでいる時こそ見るに堪えないことはしないこと。たくさんの人々が大広間にいるつもりで、その中に今自分がいるのだという心持ちを普段から持ち続けること、それが人間の品格につながるという意味だと聞く。
ひとり時間を磨ける女性(ひと)は美しい。
そうした女性たちだからこそ映える街がここにある。
いつか聞いた「銀座はひとり時間を許してくれる街」の真意を氷解できた気がして、妙に嬉しくなった。

◇editer note
筆者が大切にしているひとり時間は、花を生ける時である。
銀座には多くの生花を揃える店があるが、洋花がほとんどで意外に日本の花の専門店は少ない。特に心惹かれるのは、野の花を専門に扱っている「野の花・司」だ。農家と直結した流通を開拓し、今摘んできたばかりの新鮮そのままの花々の瑞々しさには定評がある。仕事帰りにひと枝、ふた枝とお店のコンシェルジュと会話を交わしながら選ぶのも楽しい時間だ。今日の花は、トラノウと八ヶ岳の麓で採取したというスプレーカーネーションだ。
最近は、京都の末生流の「余白」を生けるシンプルさが気に入っている。「フラワーアレンジメント」と「いけばな」の違いは、余白の違いであると言われる。フラワーアレンジメントが、最高の瞬間をイメージしながら、面いっぱい花空間を作り上げるのに対して、いけばなは、時間の経過を大切にする。長さを変えることで余白を創り、三角形、白銀比を美の基準として、「時の移ろいや命を見届ける」生け方である。
生ける時に植物の「天」と「地」を感じながら、紫色がこぼれ落ちそうなトラノウを真っ直ぐに挿す。さらにひと枝、三角形を意識して挿し込む。この時先達の名人の真似事を倣る(なぞる)ことを心する。
その瞬間に花からこんな声が聞こえてくる。
「水がごちそう・・・」
きっと、八ヶ岳の清流から迸る澄んだ空気を花は思い返しているのだろう。自分との対話、花との対話がひとり時間の醍醐味である。
あなたはどんな「ひとり時間」を紡いでるだろうか?
本日も最後までお読みくださり、ありがとうございます。
責任編集:Ginza Teller 岩田理栄子
〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー ギンザ・テラー / マーケターコーチ
東京銀座TRA3株式会社 代表取締役
著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

