
「街の奇妙な出来事」 後編(完結編) 銀座花伝MAGAZINE Vol.59
#街の人が消える #謎解き #街を救う #希望を取り戻す冒険

「秋の散歩道」という趣を感じるのは、銀座5丁目の並木通りの街路樹に秋の色がつき始める頃だ。そこから、数寄屋橋交差点まで足を伸ばすと、エルメスや東急プラザのガラス建築に挟まれる形で、低層のコンクリート打ちっぱなしの空間が現れてくる。
街に垂直立体型の「公園」を創り出そうという美意識でのプロジェクト、新たなGINZA SONY PARKが2025年1月に完成を迎えようとしている。低層で、地味で、テナントも入れずに、体験空間を創ろうという試み。S0NYの看板さえない工事中のシンプルな建物を見上げながら、そこに銀座らしい美意識を感じるのは、筆者だけだろうか。
いわゆる華美な街の雰囲気とは異なる、土木的な自然を感じる建物に、真の「ぜいたく」を感じるからかもしれない。
完成後は、誰でもが入れる公園とし、のんびり、ゆっくり歩き回り、休憩する場所を目指すのだという。その振り切った哲学に、唸ってしまう。
銀座は、手入れの行き届いた「庭」だといつも感じてきた。街を守ろうとする人々の丁寧な心意気が、その庭を回遊できるビロードのような潤いのある庭に育ててきた。
そこに新しい、庭ができる。自然への回帰を時代の価値観としてそこに注ぎ込もうとしている。
【街の奇妙な出来事】の完結編をお届けする。
街の人々の願いが閉じ込められてしまったために、街から人々が消えて行ってしまったシルバータウン。かつての美しい街並みには、時が止まり暗雲が立ち込めていた。老舗時計店の老職人から「街を救ってほしい」と懇願された主人公(あなた)は、魔女から「願いが閉じ込められた場所の扉を開けて、願いを解放しなければ街がなくなってしまう」ことを告げられる。
わずかに残っていた街の人々の知恵を借りて、謎を解き、ようやく手に入れた鍵。次々に襲いかかる困難に、あなたの心は挫けそうになりながら、街の人々の「願い」の真相に近づいていく。
最後に残された儀式を克服することができるのか。勇気と知恵を絞って立ち向かうあなたは、願いを解放して街を救うことができるのか。
【銀座の文化情報】では、創業145年の天賞堂がお届けする「GINZA TENSHODO CAFE」をご紹介する。
銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に棲息する「美のかけら」を発見していきます。

1. 「街の奇妙な出来事」 後編(完結編)
わずかな希望の先
残された時間はあまりないかもしれない!!!
切迫感が募る一方、あなたは、自分の身に起きている不条理なことを全て受け入れて、ただただ、開放感さえも感じさせるような穏やかで広大に波打つ流れに身を任せていた。
それは一緒に流れに乗っている鯨が安らぎの象徴だと言われているように、あなたの心を妙に落ち着かせていたからだった。あなたの手の中には、確かに「願いが閉じ込められた部屋」を開ける鍵がある。いくつもの謎を解き明かしながら手にしたこの鍵は、この街の人々を救う唯一の残された希望だ。
謎解きの途中で出会った魔法使いからのミッションは次のようなものだった。
「シルバータウンの全ての者の願いが閉じ込められてしまっている。その『願い』は鎖で繋がれ、街の奥深くに幽閉されている。閉じ込められている人々の「思い」や「願い」を解き放つことによって、この街の時間は動き出す。その場所のありかを突き止め、謎を解いて、人々の「願い」を解き放たなければならない」」
鯨の周りには鍵を手に入れるために協力してくれた、街の人々が波間に浮かんでは消えしながら、あなたと同じように鯨が向かう方向へ流れている。叶えられない願いを抱えたまま、あの人たちはきっと、「願いが閉じ込められた」場所に向かおうとしている。
だから、この流れに乗って行きさえすれば、彼らの幽閉されている願いを開放することができる。そんな希望があなたの心を強くしていた。
「まるで羊水の中にいるようだわ」とあなたは感じていた。穏やかな波に揺られどこか遠くから規則正しいリズムのざわめきを聴きながら、子宮壁に響く母の心音を想像している。
そういえば、母から、太古の昔には人間は魚類に酷似した生物だったと聞いたことがある。だから、水の中でもこうして呼吸ができるのだろうか。母は、「私たちの命の中には、三十八億年という進化の流れが人間の無意識の中に、生命記憶として刻み込まれている」という内容の、子供には少し難しい絵本を毎晩読んで聞かせてくれた。幼心に「生命記憶」という言葉を、とても敬虔な思いで受け止めたことを思い出した。
そして、母は困った時にはそれを思い出しなさい、と付け加えた。それはどんなことでも乗り越えられるということだったのか。当時は意味が全くわからなかったが、今は言葉を超えた波動として体に響く気がするから不思議だ。
人間の中に「生命記憶」があるのなら、人間が作る街の中にも「土地の記憶」があるに違いない。それは、街の人々の営みの集積であるのだろう。「営み」は生きることと同じだとすれば、きっと人々の「願い」の結晶として街が出来上がってきたはずだ。自分が最初にこの街を訪れた時に観た街の姿は、実に端正な優美さを伴った「美しい」街だった。美しく築き上げられたシルバータウン、それを支えてきた街の人々の願い、それらを失わせるわけにはいかない!

「願い」はどこへ行ったー美しい街の「異変」
あなたは、仰向けになって閉じていた瞼を開き、上空に瞳を向けた。そこには、人々の笑顔、店の中での語らいが街の風景とともに走馬灯のように流れていた。ところがしばらくすると、映像の中の人々の表情が強ばり、落胆し、無気力へと変貌していくではないか。まるで映画のフィルムがコマ送りされるように、カタカタとした残像とともに、、、、、、
「これは、、、」あなたは瞼を思い切り見開いた。
突然目の前に、街の「土地の記憶」が映像になって映り始めたのだ。始まりは穴が空いた、つながりが欠落した画像の断片として。
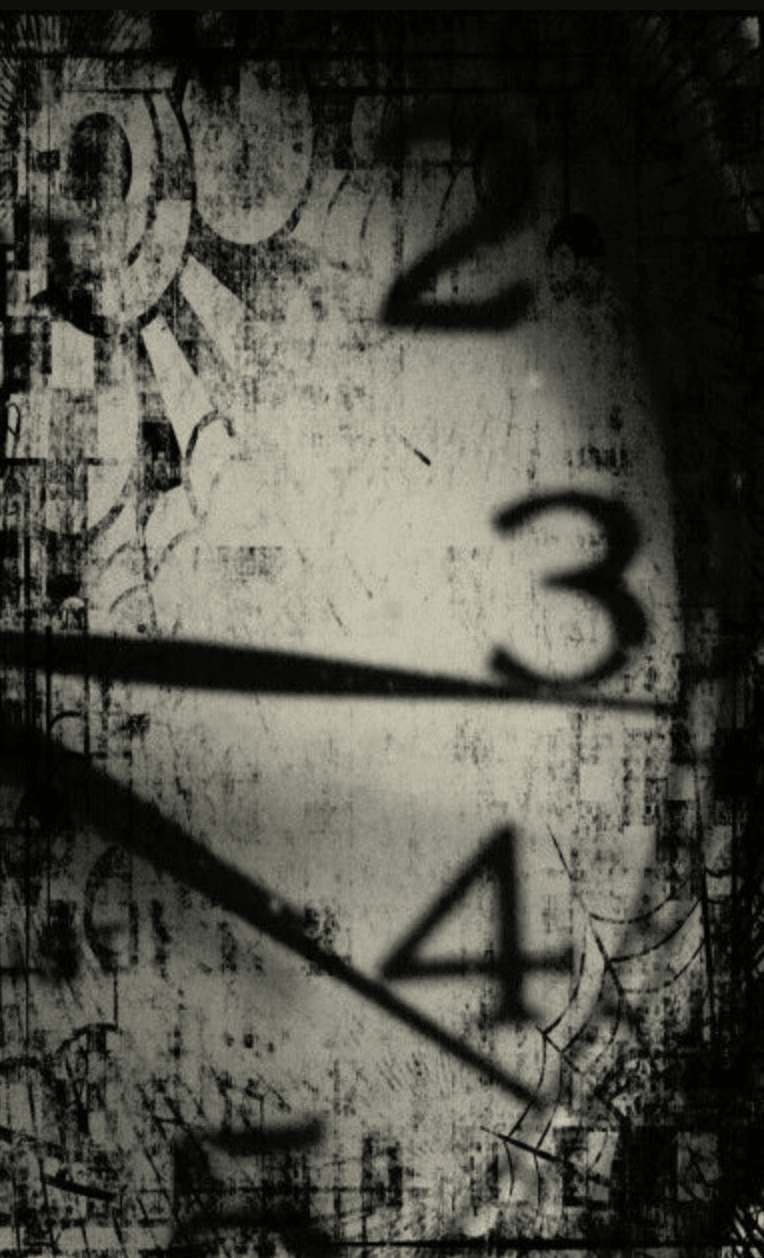
時間を戻してー「紙」屋の願い
「父さん、いいかげんにこんな店止めてくれよ」
「俺が続けないでどうする。この店は100年もこの町で続いて来たんだぞ。大事に守らなきゃご先祖さまに顔向けできない」
老舗の店先では、日常茶飯事の、そんな親子が口論する風景が繰り返されていた。
昔から紙の名産地で創られている伝統的な手漉き和紙を使って、熨斗を作ったり、小さな便箋集に綴じたり、自らの手で作り上げた日常遣いの商品を売って生計を立てていた。店主は店先で、細工をする様子を客に見てもらい、一つ一つ出来上がった作品を店頭に並べた。シルバータウンでは、熨斗には「清めと神幸」の意味があると伝わっていて、この老舗はその所作を伝える店として街の人々が拠り所とする場所にもなっていた。
その手触りの温かい熨斗は、「まるで神様に乗ってお金がやってくるみたいだ」と有難がられ評判となり、街の祝儀や心づけなどには決まって使われるようになった。
シルバータウンには、開業後100年を超える老舗が100以上あって、その店主たちも皆、礼状や手紙を書くときにはこの店の手漉き和紙便箋を使い、心づけにはこの店の手作りの熨斗を用いるのが慣習となっていた。この老舗の手作り商品の遣い手は、シルバータウンの住人であることの証だと人々の間では暗黙の了解になっていたほどだ。
人と人の繋がりを創る手形の役割を果たしていた熨斗は、繁栄したシルバータウンの象徴として、「こころを包む」店といえばこの老舗、と多くの人々が遠方からも足を運んだ。
老店主は時にはシルバータウンに昔から伝わる能や歌舞伎の演目の風物詩や干支を題材に、和紙を重ねた張り子人形を創ることもあった。
店主が和紙を重ねて創る張り子「人形」の手元を何時間でもそばに立って見続けるのを愉しみにしている客も多かった。幅1センチ立方あまりのその小さな人形は、和紙を幾重にも重ねて整形され、その後彩色が施されると、紙製なのに宝石のような存在感を放った。客が出来上がった人形を所望すると、主人は小さな紙の箱を作り、中に人形を入れると可愛い千鳥格子柄の蓋をして、丁寧にカタバミの絵柄のついた和紙の包装紙で包み、赤いビニール紐で器用に手提げ部をくくり上げ、そっと客に手渡した。客は両掌でそれを受け取り、幸せそうな表情で店を後にするのが常だった。
4代目になる主人は、そうした丁寧な仕事をするのが何よりも好きだった。心を込めてする仕事に誇りを持ち愛していた。口下手な彼は、手仕事でしか自分を表現する道を知らなかった。
息子たちから、「金にならない」、「効率が悪い」、「いつまでできる」と罵られ、口論する日が続くようになっても、気持ちを込めて作り続け、店に立ち続けた。
店主が80歳になろうとした時のことだった。手元がおぼつかず、眼も霞んできたことに気付いた彼は、「はて、自分の仕事を継ぐ者はいるだろうか」とふと考え、途方に暮れた。それ以来、もっと私が流暢に語れたら、店を大きくできたのかもしれないのに、と大きくため息をつくことが多くなった。そして、「もっと若いときにその事に気づくことができていたら、、、」と深く後悔をした。
「時を戻して、もう一度やり直せたら、、」と老主人の後悔は、「願い」へと変わって行った。
その頃、黒い服に身を包んだ地上げ屋が店の扉を叩いた。
「この場所にビルを建てて、テナントを入れましょう。儲かりますよ」
息子たちはこの話に飛びついた。父親の意向など無視して、さっさと店を畳んでしまったのだ。
老店主は、なぜこんなことに、、、と心が打ちひしがれた。そして時間を元に戻して、あの日に戻りたい、とまた強く願うようになった時、店の前で深くお辞儀をしながら手を合わせた。
それ以来、店主の姿を見た者はいなくなった。家族も探さなかった。店主の願いは行き場を失い、小さな小箱に詰め込まれ、シルバータウンの空に浮遊するようになった。

話を聞いて欲しいー「糸」屋の願い
この国では、昔は着る物を作る時は、先ず「糸」を作ることから始め、全てを手作りした。衣服の始まりは「糸」だった。170年も前に「糸」商いを始めた老舗「糸」屋は、着物から洋服への時代の移ろいとともに、「糸」を元にして創り上げる小物に商いを移して行った。最も庶民に歓迎され、慕われたのは、「手ぬぐい」だった。
「ほら、ご覧くださいまし。この着物の反物。これは一本の糸から始まっております。昔は反物の端切れを使って、手ぬぐいを創り上げたものです。端切れ、つまり捨てるような部分を使って、ええ、今でいうSDGsですな。え?誰が作り始めたかって? 今から300年くらい前に、このシルバータウンに「山東京伝」という商人がおりましてね。彼は知恵がある上に、実に絵が上手かったもんですから、端切れを手ぬぐいのサイズに裁断してそこに絵を描いて、今の手ぬぐいの原型を作ったってわけです。
今や、手ぬぐいは日本文化の象徴なんて言われますからね、なかなかの才能でしょ。てまえはそのセンスに驚きましたですよ。花鳥風月の柄から、金魚や七夕、西瓜、朝顔、歌舞伎役者や雪の景色、なんでも絵柄にしちまいましてねー」
その熱のこもった楽しげで洒脱な語りが評判で、それを聞きたいがために「糸」屋には、客が押しかけていた。
この男は、長年この老舗を切り盛りする番頭で、店主の顔は拝まないが、この番頭の顔を見に客が訪れるという、シルバータウンでも有名な口上の達者な商人だった。
一年の終わり、大晦日になると、12時の時計塔の鐘が鳴り始めるまで店を開け、鐘がなり終わると店を閉めて、店の前の舗道をブラシで水を流しながら磨く姿もよく知られていた。
屋号の「七」のつく法被を着て、真冬の冷え込みなど感じさせぬ汗だくのその姿に、街を愛する心意気を感じて、シルバータウンの人々は、大晦日になるとその店の前に押しかけて、一年の締めくくりの語らいをするのが慣わしだった。
「街のお陰で商いをさせて貰えてるんでさ。一年の感謝、当たり前のことですわ」
そんな番頭の言葉は、訪れた客の心を温かくして、新年の栄輝を養うのだった。
店の歴史が170年目を迎えるというその日、新しく8代目になり黒い紋付を纏った店主が番頭に告げた。
「もっと現代的な商いに変えないと、ウチは潰れます。あなたの仕事はもう必要ない」
大手のバンカーだったが、先代が急逝してこの老舗を継ぐことになった8代目は、「糸」のことなど知らなくても良い、大事なのは採算、大量に売れる物を作って、老舗の名前・ブランド名をつけて売り尽くす方針に変更すると言い放った。そうすれば、簡単に儲かり商いは継続できる、と考えていた。その経営転換のための、番頭への解雇宣告だった。古くからのやり方に固執する番頭は8代目にとって、目の上のコブだったに違いない。番頭に続いて多くのベテラン社員が辞めていった。
結局、老舗「糸」屋は大量の商品を作ったものの、全く売れず借金を抱えて瞬く間に倒産、店を売り渡すことになった。シルバータウンで大店と言われた老舗が幕を下ろすというニュースを聞いて街の人々は店前に集まった。かつて赤い提灯が店頭に並び、華やかに染め上げられた紫の暖簾がたなびき賑わいが絶えなかった入口は寂れ、ピカピカに磨かれていた舗道は汚れ果てて見る影もなかった。
老舗が取り壊されるのに時間はかからなかった。更地になってしまった跡地の前で店の名残を見出そうとする一人の男がいた。両手に大きな風呂敷包を抱え、悲しい目でその空間を見つめているのは、かつてのあの番頭だった。
彼は、舗道に風呂敷を広げ、中からかつて客に披露した手ぬぐいや糸の小物を取り出し、その上に並べた。そして、行き交う人々に、「七」の屋号の入った法被をまとって、あの日のように語りかけた。
「シルバータウンにお越しの皆さん。こちらは、170年もの間、糸を専門に商ってきた老舗にございます。一本の糸から、反物ができ、その端切れからこの手ぬぐいが出来上がる。この手ぬぐいに洒落た絵柄が描かれるようになると、初めて銭湯でこれを見た人々は、驚きましたね。ただの布切れに、絵柄が描いてあるだけなのに、目立つ目立つ。一気に、街の銭湯は華やぎましたねー。「未知」の世界に触れると、人間は豊かになるんでございますよ。ほれ、ワクワクしてね。
てまえは、ワクワクをお客様にお届けしたいと思うんですよ、作り出した人の知恵に乗せてねーーー、どうぞ触って、広げてくださいましな」
面白い行商がいると次々に人が集まり、あっという間に風呂敷の上の商品は無くなった。番頭は深々と頭を下げ、丁寧に風呂敷を畳み懐に入れた。そして空を見上げて、もう一度店のあった場所に向かってお辞儀をして立ち去って行った。
そして強く願った「もっと話を聞いて欲しい」。
流暢な熱のこもった口上には、番頭の願いが込められていた。その願いは秋が深まる街路樹の色づいた枯葉に乗って、遠く海の方へと漂って消えて行った。
それ以来、番頭の姿を見た者はいない。

心が軽くなる場所ー「囲碁」屋の願い
シルバータウンのメインストリートには、宝石商が軒を連ねる。400年も前にできたこの街には、当時、宝石などを身につける文化はなかったはずなのだが、次第に西洋化が進む中でこういう街の風景が現れた。
この国では宝石はもともと、寺社、仏閣の多い街で仏具や銀器の飾り職人が集まり村を形成して作り始めたことに始まる。その中で、かんざしや帯留め、根付けなどが売られ、その後、武士が世の中を席巻すると、武具や刀に装飾を施す金工細工の技法の基礎ができて宝石と呼ばれる宝飾品になったと言うのがもっぱらの説だ。
因みにこの国の金工作品の最古のものは、もちろん西アジアやヨーロッパや中国には及ばないが、古墳時代の馬具装飾とも言われている。
この街ができた頃には将軍家はじめ大名が、刀剣を作る刀工と共に装飾部分を担当する彫金家を競って育て、代々将軍家にあっては世襲制を持つ彫金家が主に担当したとも言われている。そうして非常に技巧的な人たちが名工として名を残した。しかし武家社会が終わりを告げ、廃刀令(1876年=明治9年))が発せられると、そういった彫金家たちは失業し、職業替えを余儀なくされたが、その一方で、同じく明治政府の方針による、着物から洋装への服飾文化の変化とともに、それに合わせるためにネックレスや髪飾り、指輪などを身につける女性が増えて行くのに伴って、彫金師と言う仕事も生まれてきたのだという。
そんな西洋文化がこの街に入り込んだ時代に、メインストリートの片側の面積のほとんどを所有している大地主がこのシルバータウンで権勢を振るっていた。その大地主は、「玉屋」と言った。先祖は、彫金家だったと言う。まだ宝飾品がこの国に入ってくる少し前から、宝石を扱い一代を成していた。「玉屋」の「玉」は宝石という意味である。軒を連ねるテナントの最上階は、大地主の会社が占有していた。
東側に500メートルも続くメインストリートの片側には、「玉屋」の誘致した時計屋や宝飾店、貴金属店が競うように華やかなショーウインドウを並べていた。そのちょうど中央あたりに、場違いなほど小さく見窄らしい、間口が1間もないような、その半分を占める入り口に長くて白い暖簾を揺らめかせている店があった。白い暖簾には「碁」と立派な墨字で書かれている。
「おお、そうきたか。あんたは、長期戦だから叶わねえな」
「お前さんは、集中力がなくていけねえ。だから肝心なところで、判断を誤るんだよ」
店の奥からは、いつものやりとりが聞こえてくる。
「囲碁というのは、二人それぞれ『白と黒の丸い石を交互に置いて行くことによって、陣地を取り合うゲームだ。伝統的な遊びだが、勝利への道のりが一本筋でなく、相手の応手一つで局面がガラッと変わるのが魅力でもあり、難しさでもある。忍耐強く考える力、想像力を鍛えるといった頭脳ゲームの側面とともに、相手と心を読み合うコミュニケーション能力も大いに身に付く」というのが、ここの囲碁屋(囲碁用品店兼碁会所)の主人の囲碁についての魅力談義のあらましだ。
「おっと、いけねえ。シルバータウンの会合の時間だ。ちょっくら行ってくるから、碁石はこのままにな。いいかい、さわちゃいけねえよ」
そういうと客らしき、その男は、店の奥の障子をすすっと開けて、姿を消した。
「全く、いくらここの大地主だからって、こう毎日来られたんじゃあ、こっちの商売に差し障るってもんさ。」
そうぶつぶつ言いながら、囲碁屋の主人は、さっさと碁盤の上の石を片付けてしまった。
「玉屋」の大地主は、大の囲碁好きで、日を置かずにこの店に通い続けている。一族は、屋号のルーツに従い、元々自らの土地にこれまでは宝石商のみを誘致してきていたが、当代の大地主のたっての希望で、この一等地の狭地に「囲碁屋」を誘致したというわけだ。
この囲碁屋も有に100年を超える歴史を持っている。現在の店主は、元々は棋士だったが、自分で打つより、人に教える方が得意だったので、代々続いている囲碁屋を継いで細々と商いをしている時に、ここの大地主と出会った。大地主は、店主の人柄と粘り強さが気に入って、シルバータウンに囲碁屋を開かないか、と勧めてきた。店主は、そんな華やかな街で碁石屋を商うなんて、身分不相応だと断り続けたが、「シルバータウンには必要な店」だと強く口説かれて、結局店をこの街に移設する事にしたのだ。
店は間口が1間もない、奥に長いうなぎの寝床のようだ。入ると、両方の壁に沿って名器と言われる榧(かや)でできた碁盤がずらっと並んでいる。碁盤の木肌の美しさ、特有の香気が漂い、特有の油分が色ツヤを醸し出している。その奥まった所に置かれている足付碁盤は、とんでもなく渋い飴色の光沢を放っていて、世にいう名器であろうことは素人でもわかるほどだ。小さいながらもこの店の風格を現して余りあった。
両側に碁盤がせり出しているため、奥までの通路は人一人が通れるほどの狭さだ。売り場のさらにその奥には碁盤を挟んで二人がようやく座れるだけのスペースがあって、大地主はいつもそこにたむろしては、店主に対戦をせがむのだった。
店主が開店した時に驚いたのは、奥の障子を開けるとそこには梯子がかかっていて、上の階まで登ることができる仕掛けになっていたことだ。どうもその上の階には大地主の会長室があり、床板をあげてそこにひょっこり顔を出せるようになっているようだ。大地主の会長職と言っても、特別の仕事があるわけではない。娘が6人いて、皆「玉屋」の社長はじめ役職に就いているので、たまに書類にハンコを押すことと、シルバータウンの会合に出かけることくらいだった。
「たまには、碁盤とか、碁石とか買ってもらわないと商売になりませんぜ」
店主がしつこくやってくる大地主に苦情をいうと、
「いいかい、前にも言っただろ。この店はシルバータウンに必要な店なんだ。俺は、お前さんにその場所を提供してんだよ。ただでおいてやってんだ、文句を言いなさんな」
と大地主は反論するのが常だった。
その内に、シルバータウンの会合に出かける時間が惜しいから、この店で会合を開くことにした、ととんでもないことを決めて店に戻ってきた。
シルバータウンの老舗の店主たちが、決まった日になるとこの店に集まり、会議をするようになった。ただでさえ狭い店内に15人もの老舗店主たちが集まるので、狭い通路は丸椅子で埋まった。丸半日かけて会議は続いたが、大抵は結論が出ず、ただ街で起きていることを報告し合って解散するのが常だった。その間ずっとここの店主は大地主の囲碁の相手を務める羽目になった。
その内に顔馴染みになった他の店主が別の日にやってきて、「囲碁を始めたい」とか、「子供に教えて欲しい」などと言いながら、簡易な碁盤や石を買い求めていくようになって行った。
「それにしても、この街も西洋のものばかりになっちまったね。ウチの伝統菓子のあんこなんかを商う店はどんどん減って、ケーキや、パンの店が増えたね。遅かれ早かれこの街の中からこの国のものが消えてなくなっちまうって感じだねえ」
「全くだ。ほら、200年前からある、伝統おもちゃを商ってたあの店も商いをやめるそうだぜ」
「聞いたよ、そこもそうだけど、400年の歴史のあるあの呉服屋も、この間店主と話したら、店をたたむって言ってたからね。」
横で、囲碁屋の店主と対戦しながらその話を聞いている大地主は、口を挟むでなくうんうんと頷いていた。
「それにしたって、大地主さんよ、あんたんとこが西洋から宝飾品を売る店なんかどんどん誘致してくるから、こんな事になっちまってるんじゃないのかい」と水を向けられても、
「そうだな」と、振り向きもせずに答えるだけだった。
ほとんど世界中の宝飾品がこのシルバータウンに集まってくるようになった頃だった。大地主の企業「玉屋」は益々、街に権勢を振るって盤石な時代を迎えていた。
ある日大地主が真っ赤な顔をして、囲碁屋の奥の障子をけたたましい音を立てながら開けて入ってきた。
「どうしたんだい?」
「どうもこうもない。よりにもよって黒い礼服を揃って身につけて、娘6人が急に会長室にやって来た。そして、社長をやっている長女がこう言うんだ。“お父様、そろそろお年ですから、もう会社のことは私たちに任せて、御隠居なさったらいかがです?”だとさ」
ものすごい剣幕で口から泡を飛ばして話を続けた。
「挙げ句の果てに、“あのご道楽はそろそろお辞めになって頂かないと。この国の中で最も高い土地ですのよ、囲碁屋を置いておくなんて、正気の沙汰ではありませんわ”だなんて抜かすから、出てけ!と叫んだんだ」
「確かに、お嬢さんがおっしゃる通りかもしれませんねー」
ボソッと、俯き加減に囲碁屋の店主はつぶやいた。
店主は、“こんな道楽みたいな商売”なのだから、いつかは立退を迫られるだろうし、それもやむを得ないと思っていた。
「おい、一体この会社をここまで大きくしたのは誰のおかげだい?先代がいつも言ってたんだ。商売には、余白がなきゃいけない。金、金、金となった途端に、商いは必ず傾くものだ。この街のメインストリートが西洋の宝石屋ばかりになって行くのを見ていて、なんとかしなきゃならない、この国がこの国である文化を点でもいいから、シルバータウンに残さなけりゃならない、、、、
あんた(店主)に出会った時、ああ、これだ!って思ったんだよ。無駄だと思えるようでも道楽こそが大事だ、街の店主たちが言いたいことを言って、心を和ませる場所を作ろうって決めたんだ。」
店主はその時、初めて大地主が心に秘めていた謀の狙いが分かったような気がした。
数日経って、肩を落とした大地主がやってきた。
「老ぼれが、ガタガタ言ってももうどうしようもないところまで、会社は全部娘たちのものになってしまった。オレの権限なんか、何一つなくなってしまったんだ、、、、」
囲碁を打つ気力も起こらない様子で、がっくりと俯いている背中は、この世の終わりのような暗澹たる気配を漂わせていた。
そして、こう言った。
「最後のお願いだ、頼みを聞いてくれないか。こんな繁栄は長くは続かない。会社はいずれダメになる。そしたら、街の衆と一緒にここに、この場所にみんなが安らげる場所を作ってはもらえないか」
それ以来、大地主の姿を見たものはいなかった。
囲碁屋のビルが取り壊される日が来た。名残を惜しんで集まった街の店主たちに、店に残っていた碁盤や碁石を分け譲りながら、囲碁屋の店主は「大地主の伝言」を伝えた。その日にも、大地主の姿はなかった。
「余白のある街か、、、大地主はそんなことを考えていたのか」
変わりゆく街の中で、店主たちは、決意があれば、今より悪くならないかもしれない、次の人々にこの話を伝えよう、と心に大きな炎を灯した。それから「心が軽くなる、安らぐ街」と願いを込めて皆で声を合わせた。 そして、壊されるビルの前で深くお辞儀をしながら、大地主の願いに向かって手を合わせたのだった。

3つの関門
さまざまな願いが次々に走馬灯のように、目の前を流れて行った。あなたは、そのストーリーを食い入るように見つめた。街の人々の声までが耳に届き、感情を揺さぶった。それは途切れることなく、希望と喪失を繰り返し、徐々に人々から希望と気力が失われていく様子を物語っていた。水の中にいるはずなのに、あなたの頬には涙がとめどなく流れていた。自分が泣いている、その実感にあなたの心は切なさで潰れそうになりながら、「人々の願いが閉じ込められた場所」を開ける鍵をもう一度握りしめた。
打ちひしがれながら、あなたの心には街の人の一つの言葉が残っていた。
「未知」と言う言葉。街の人が待ち望んでいる言葉の象徴のような響きをそこに感じたのだ。これからの冒険の先で問われるキーワードのような気がして、言葉をもう一度胸に刻んだ。
気がつくと、大きなスクリューが回転するような音がずっと下の方から響き渡り出し、あなたの周りの流れは反時計方向に回り始めていた。その音が大きくなるに従って周囲の流れも急速に早まり、あっという間に、目眩がするほどの急流に呑み込まれていた。
そんな状況でも鍵だけは離すまいと握る手に力を込めた。
「凄い回転、しかも上に向かっているわ。この渦の最終地点に何かがあるに違いないわ、、、、、」
遠心力に飛ばされそうになりながら、頂点に達するまで目を閉じ、息を止めたままでこの急流に身を任せようと心に決めた。薄れていく意識の中で、さっき目の前を流れて行った街の人々の心が折れ行く情景をを思い出していた。
「希望を失った街の人々の心のエネルギー源、それを取り戻して、とあの人々の思いを映し出したあのフィルムは伝えているのではないかしら?でも、私たち人間の“体”は、食物を与えればエネルギーを蓄えさせることができるけれど、“心”にはどうやってエネルギーを蓄えさせたらいいの?」」
渦の頂点に達するまでには時間はかからなかった、その瞬間、ギョワン!という奇妙な爆音とともに、あなたは空中高く放り上げられた。
気がつくと、海と空の間の不思議な空間を漂っている。遠くに太陽と月が同時に上がっている。ここは異界のようだ。
「鯨が見えない!!」
あなたは、道標を無くしてしまったことにひどく動揺して、両手で自分の頭を抱え込んだ。
「どうしよう!どこに向かったらいいの?」
次の瞬間、進んでいる方向に紅い鳥居のような門が2つ現れた。どちらに進むかを今すぐに決めなければ通り過ぎてしまいそうだ。一つの門にはその先に道がない。もう一つの門の先には道があり、しかもその先には見慣れた街の風景が回転しながら浮遊している。
「どちらの門をくぐったら、例の場所へ辿り着けるのかしら。確かに「道がある」門の方が確実な気がする。見知った街の風景も見えるんですもの。でも、ちょっと待って。」
あなたは、じっと心に聞いてみた。
「見知った街に戻ること、かつてのシルバータウンになることが本当の願いかしら。それは、違う。
そして、私が受け取ったメッセージは「未知」だった。これは、新しい道へ向かえ、と言っているような気がする。」
幼い頃に母に言われた「行き詰まったら、反対へ行け」と言う言葉に従うなら、そう、道のない方に行くのがいいんだわ!」
あなたは、躊躇なく、先に道のない紅い門をくぐった。

最後の儀式
あなたの勇気ある選択は、正しかったようだ。
門をくぐり抜けると、その先には、目を疑うような数の紫色をした惑星が散在している空間が広がっており、身体は留まることなくそれらに向かって漂い続けていた。何気なく右に顔を向けてみると、そこにはなんとあの鯨が仰向きに横たわった街の人々を抱き抱えるようにしながら同じ方向へと進んではないか。
「あ〜」。あなたはこれまで経験したことのないような安堵感を覚えた。
やがて行手のまるで宇宙の最果てのような暗くて遠い場所に、街の時計塔と同じ形をした石塔が見えてきた。
「あそこが、みんなの願いが閉じ込められている場所に違いないわ」
鯨と街の人々は、石塔にいとも簡単に近づき、あっという間に石塔の下にぶら下がっている小さな箱の扉の中に吸い込まれて行ってしまった。
あなたは、手で周りの空気をかくような動作をしながら、ようやく石塔に近づいた。その石塔は、アメジストのような紫水晶でできていて、浄化と再生のエネルギーを放っているように見えた。水晶の塔に掴まるようにして下の方に移動してみると、塔にくくりつけられている、さっき鯨と人々が吸い込まれて行った小さな箱が目に入った。
近づいてよくみると、小さな箱の扉には鍵穴がある!!!
「これで何もかも終わるわ」
そう独り言を言って、握っていた「鍵」をその鍵穴に突きさして回した。
「?」
なぜか、鍵は回らなかった。
なぜ、開かないの?こんなに苦労をして手に入れた鍵、、、、、この鍵で開けられないなんて、そんなはずないわ!と何度も鍵を入れ直し、回そうとするが、全く動かない。誰かに尋ねることもできない、一体どうしたらいいの?
あなたは驚きと失望感で途方に暮れ、膝を抱えてうずくまってしまった。
紫色の小さな惑星があなたの横を通り過ぎていく。
どれくらい、時間が経っただろうか。それはあなたには永遠のように長く感じられていた。
「そうだ、これには、何か仕掛けがあるはずだわ」
突然そう閃いて、「未知」というキーワードを掴むことのできた人々の想いが、走馬灯のように流れるシーンを思い返してみた。きっと、あそこに鍵を開ける際の儀式のようなもの、そのヒントがあるはずだわ。店主や番頭たちの行為、仕草に共通したものはなかったかしら。紙細工をしている時の仕草、手ぬぐいを売る口上の所作、囲碁を打つ手の動き、、、、どれも、違う。いえ、そう言うことではないんだわ。
「彼らが、心を込めて願う時、行っていた仕草、、、、、、、、、」
「そうだわ! お辞儀!、そうよ、全員願い事をしながら、お辞儀をしていたわ!」
そう確信して、握り拳を胸に押しつけ、ガッツポーズをした。
あなたは、おもむろに、石塔にぶら下がっている箱の扉の前に立ち、祈るような気持ちで、深くお辞儀をした。
それから、もう一度鍵を出して、その扉の鍵穴に深く差し込んで回した、、、、、

エピローグ
気がつくと、あなたはシルバータウンの街の石畳の舗道に仰向けに横たわり、真上に広がる夜空を見上げていた。
「何が起きたの?」
「星がきれい・・・・」
願いが解き放たれた瞬間に、それまで街の空を覆っていた暗雲が消え去り、深い紫の夜空に、これまで見えなかったものまでもが明るさを取り戻した星たちが集まって、大輪の星座を作っている。そして、空いっぱいに大きな美しい星座が現れた。
白く輝く円が少し傾き、中央に小さな星たちが集まり宇宙の奥へと螺旋を描くように、ゆっくりと穏やかに動いている。ため息をつくほどの美しさに、あなたは安堵の表情を浮かべて再び瞼を閉じた。
遠くから、人々の歓声が聴こえて来る。シルバータウンの人々がその星座に見入りながら、歓喜の声を上げているようだ。街に人が戻ったのだ!時計塔からは、12時の鐘の音が響いていた。時間も動き始めたらしい!
「皆んなが希望を取り戻したんだわ。本当によかった。」
重い身体を起こしてゆっくりとシルバータウンの中央通りを歩きながら、もう一度美しく、神秘性を孕んだ星座に目を向けたその時だった。
「君の勇気のおかげじゃ」 空から聴き慣れた声がした。
「知ってるかい?これは「ポータル座」という星座じゃが、現実の宇宙では認識されていない、想像上の星座なんじゃ。君だけに教えておこう、この星座の意味を」
あなたは、ゴクンと音を出して唾を呑み込んだ。
「これは、新たな世界への入り口や、未知の領域への通路を象徴してるんじゃ。」
「と言うことは、、、、」
「そうじゃ、この星座は、人々の心に新たな可能性や希望を与えてくれる存在じゃ。これを、羅針盤に街の人々の願いを込めた新たなシルバータウン作りが始まると言うことじゃ」
「いいかい。これから未知の街が始まると言うことじゃ」
「未知の街、、、、、いつだって、未知こそがワクワクさせる道」
あなたは、大きく空に向かって頷いて、
「私にとっても、新たな人生の始まり、って言う気がします」
あなたは深呼吸を一つして、踵を返して、初めてこの街に降り立った場所に向かって、大きく一歩を踏み出した。
後編(完結編) 了

2.銀座文化情報
◆GINZA TENSHODO CAFE
春海通りとレンガ通りの街角には、こっそりとレンガ通りを覗き込む仕草がいかにも愛らしい、エンジェルが佇んでいる。頭を撫でると「恋が実る」という言い伝えが都市伝説になって、銀座の名所として愛されている。
銀座天賞堂がこのエンジェルの生みの親である。創業145年、時計、宝石など貴金属を提供してきたこの老舗の美意識には定評がある。
筆者が初めて、先代の新本秀章社長にお目にかかった際に、何を販売していらっしゃいますか?とお尋ねした際に、
「手前どもは、“審美眼”を売っております」
と答えられた。
言葉通り、世界中の時計を販売しながらも、自社独自の時計「メイド イン ギンザ」を開発し、おしゃれで独創的なウインドウに並べた。その時計はまさに、長年時計と深い付き合いをしてきた先代社長の「時計屋が欲しくなる時計を作りたい」という夢の実現だった。
銀座は常に「日本初」「日本一」と冠がつく老舗の多い街だが、中でも天賞堂は、オリジナルの時計を開発している点、ウインドウを初めて設置した老舗として、夏目漱石はじめ多くの文化人に愛されてきた。
「GINZA TENSHODO CAFE」は、2024秋に、開業した。場所は、エンジェルが見つめるレンガ通りのちょうど先、銀座2丁目にある。
螺旋階段を上がると、気品が漂うTENSHODO BLUEの空間が広がっている。イタリア北部の世界遺産の街、ヴィチェンツァのゆったりした「パッラーディオ様式」をイメージしたデザインだという。ソファの近くには、あのエンジェルも鎮座している。おすすめは、1,300円で楽しめるランチの他に、何と言っても天賞堂プレミアムアフタヌーンティ。ブリニ、スコーン、マフィン、キッシュ、抹茶ブラウニー、ジェラート、など軽食・デザートと共に、プレゼンテーションBOXからテースティング・オーダーできる各種お茶の数々は、一度お試しいただきたい香り満載である。



3.編集後記(editor profile)
銀座の街から、老舗が消えていくドラマをこれまでどれほど見てきたことだろうか。そこには、いつも銀座人の志と家族との葛藤があった。そして、激動の日本経済の歴史、商売の歴史と無関係ではなかった。
筆者がこれまで応援してきた老舗の中で、市場が衰退して需要が落ち込む状況においても歯を食いしばって、「志」を守り続けた呉服屋がある。希望を見失わないために、心掛けていることについて、長年店を支えてきた番頭が話をしてくれた。
「一日一日を違って生きること。そこが大事じゃないですか。それが結局“新しさ”を作ることだと思うんです。世の中の不景気がどうのこうの、お客さんの嗜好が変わったどうのこうの、いろんなこと言いますけどね、関係ありません。問題は、自分自身にとって「未知」であることに毎日挑戦してるかってことです。
『未知の世界』はワクワクしますでしょ。生きることと一緒です。
私は、もう86歳になりますけど、社長に雇ってもらって今でも現役です。毎日、銀座の店には12時に出勤、その前にやることがあるからです。原宿に立ち寄って、若者の着てるもの、話していること、、、つまり彼らの文化に触れてから出勤してます。〈新しい自分〉に出会うことは、〈未知の新しい物を生む〉原動力だと思ってます。」
その話を聞きながら、驚愕と尊敬の念が込み上げた。と同時に、いつも細胞が生まれ変わり続けている、人間の体(生命)と重なっていることにも想い及んだ。話をしてくれた番頭は、生命と同質という意味で真に「生き抜いている人」だと唸ったことを思い出す。
そういえば、ゲーテは「ファウスト」という作品を23歳で描き始め、何度も休止期間を経ながら、82歳で亡くなる直前まで描き続けていたという話は有名だ。生涯を通じて60年間も、この作品に取り組んでいた事になる。「ファウスト」を描き続けることは、世の中の誰かのためだけではなく、ゲーテ自身にとって今日を新しく「生きること」だったに違いなかったのだろう、という気がしてくる。
世の中が、また大きく変わろうとしている。
私たち一人一人が、毎日を違って生きることによって、自分自身の中に希望が生まれ、人間も街も社会も希望に向かって動き出すのではないか。そう確信している。
本日も最後までお読みくださりありがとうございます。
責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子
〈editorprofile〉 岩田理栄子:【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ
東京銀座TRA3株式会社 代表取締役
著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

