【河川砂防専門キーワード】流域治水プロジェクト
背景
気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理等の取り組みだけでなく、流域に関わる関係者が主体的に治水に取り組み社会を構築する必要がある。

流域治水とは・・・?
河川・下水道管理者等による治水に加え、あらゆる関係者(国・都道府県・市町村・企業・住民)により、流域全体で行う治水
主な考え方は以下の3つの軸で構成される
①氾濫リスクの最小化
【雨水貯留浸透機能の強化】(集水域)
⇒調整池や透水性舗装等の雨水貯留浸透施設整備
⇒田んぼやため池の治水利用、グリーンインフラの活用

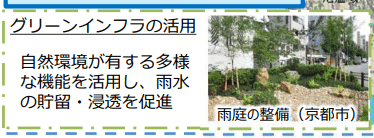
【河川流量や氾濫水の抑制】(河川区域)
⇒利水ダムの治水への活用等による洪水調整機能強化
(事前放流、堤体嵩上げ、危機管理型ハード対策)
⇒河床掘削、砂防堰堤、排水施設整備等による流下能力向上
⇒粘り強い堤防構造による氾濫水の抑制
(天端舗装、堤脚保護工等の法尻強化、危機管理型ハード対策)
②被害対象の減少(集水域、氾濫域)
⇒土地利用規制、移転促進等による、低リスクエリアへの誘導
⇒二線堤整備等による、被害対象範囲の減少
③被害の最小化(氾濫域)
⇒水災害リスクなどの土地利用リスク情報の充実
⇒河川水位予測やリアルタイム情報発信による避難体制強化
⇒工場や建物の浸水対策やBCP(事業継続計画)策定による経済被害の最小化
⇒不動産取記時の水害リスク情報提供等による住まい方の工夫
⇒官民連携によるTEC-FORCE体制など、支援体制の充実
⇒排水樋門の整備等による排水機能強化

流域治水プロジェクトとは・・・?
7水系で実施された「緊急治水対策プロジェクト」と同様に、全国の一級水系で流域全体で早急に実施すべき対策の全体像

今後の予定
「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト(※別記事で詳しく説明)」のとりまとめを踏まえ、今後、各一級河川において、国・都道府県・市町村等との協議会を設置し議論を進め、流域治水プロジェクトを策定する予定
