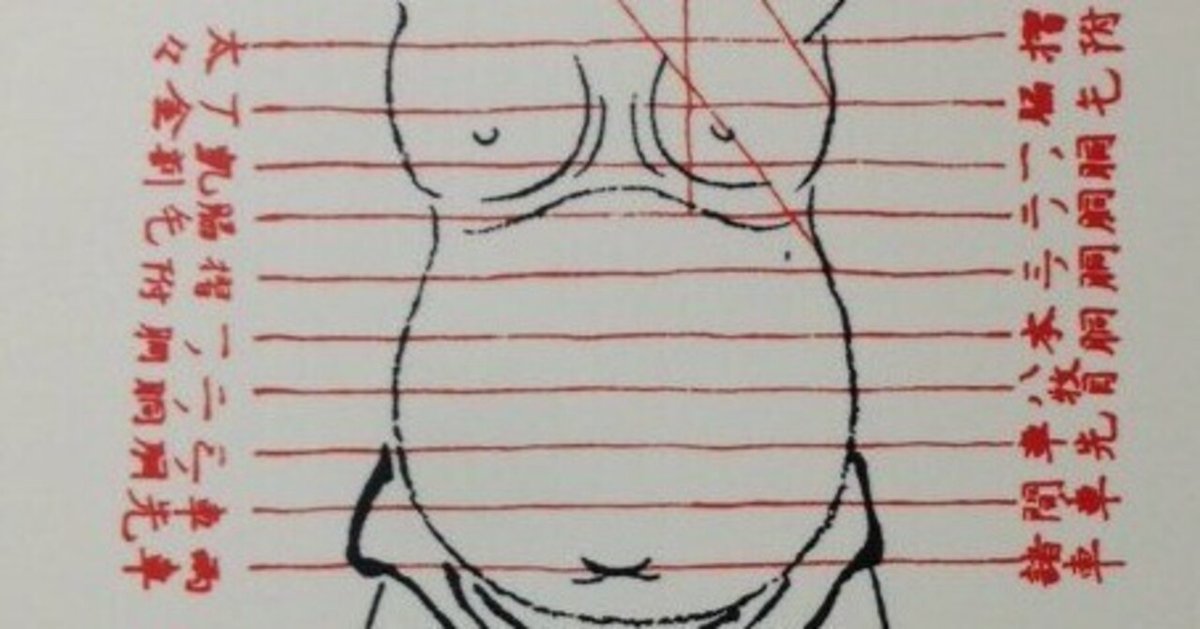
魔斬
第5話 安政奇譚⑤
この季節、暮れ六つになると、すっかり辺りも暗くなる。温め酒でもひっかけなけりゃあ、こんな仕事はやってられないと、山田浅右衛門は屋台で一心地就いていた。となりに座る助六は顔面蒼白だ。
「だめだ……全然酔えねえ」
何度も、独り言を呟いていた。
よく味の染みた大根を頬張りながら、浅右衛門は美味そうに酒を干していった。三杯も呑めば少しは気分も落着いてくる。
「さてと、助六」
浅右衛門は勘定を済ませて立ち上がった。
「だ……旦那、あっしはここで旦那の帰りを」
助六は声を震わせた。
「往生際の悪い野郎だな」
「へへへ」
「おら、ぐずぐずしねえで、とっとと来やがれ」
浅右衛門は助六の耳たぶを掴んで引っ張った。あまりの痛さに、助六は引っ張られるままに歩き出した。
昼間の喧騒が嘘のように、浅草寺仲見世界隈はひっそりとした闇に閉ざされた。この界隈は、新吉原を除けば闇のなかである。
浅草伝法院は、雷門を潜って暫らく行った左手にある。生人形はここに納められ人形番もいた。もっとも怪異ののちは、山門傍らの詰所に彼らは一晩中籠もって、決して堂内には入らない。ここには浅草弾左衛門の言伝が届いていた。細やかな手際である。浅右衛門が来ると、人形番は大喜びでこれを迎えた。
「浅草の親分から聞いておりやす。どうぞ、お入りくだせえ」
「浅の旦那。よう来てくだされた。このままじゃ、あっしらは気が狂っちまいます。生人形は本堂の隅に置いてあるんで、あとは頼んまさあ」
口々に喚く人形番は騒々しい。
「案内せい」
「案内は勘弁してくだせえ」
「それじゃあ、困る」
「すぐそこに見える、それ、そこに。あれが本堂でさあ」
人形番たちは震えながら、正面の建物を指さした。
大太刀を腰帯に挟み、浅右衛門は本堂へと近付いた。恐々とした屁っぴり腰で、助六もついてきた。近付くにつれて、やがて何やら人の声らしきものが耳に留まった。
「悲鳴……でしょ、旦那?」
助六の声が震えた。
浅右衛門は構わず進んだ。
ゆっくりと、本堂の扉を開いた。中は真っ暗で、薄らと妖気が漂っていた。これくらいの気は、夜にもなれば何処の寺社にも漂う。
(別段変わったところは……)
と、右手の隅に目が止まった。
三体の生人形が、確かにそこにあった。一体は妖艶なお初人形、そして二体が鬼婆と、それに腹を裂かれる女である。
(これは……まるで生きてるような)
浅右衛門は感動した。なんと見事な造りであろう。
(喜三郎と申す者、ほんに名人よな)
もっとよく見ようと、浅右衛門は生人形に近付いた。
と、弾かれたような感覚に、浅右衛門はふと足を止めた。
「……ぐ……ぐうう……ぐぐ……」
鬼婆が呻いた。
耳を疑った。が、紛れもなく、それは生人形から聞こえてきた。
浅右衛門は更に近付いた。
「……誰じゃ」
途端、鬼婆は肉声を発した。助六は奇声を上げて蹲ったが、浅右衛門は些かも動じることなく
「人に訊ねるときはまず名乗れ。そして、この生人形に宿った理由を申せ」
一瞬、間が空いた。
「……そなた、恐ろしくないのか?」
「いいから名乗れ!」
鬼婆は一言
「とら」
と名乗った。次いで人形に宿る理由を、浅右衛門は鋭い口調で正した。
「……この婆は向島に住んでいた者。喜三郎と申す者は生人形をつくる折、この婆を手本にしたのじゃ。そのためか、死した婆は、この人形に閉じこめられてしもうた」
「それだけか?」
「……」
「それくらいで、人は人形に封じ込まれぬ」
鬼婆は戸惑いながら、それでも吐き出すように
「……生前、不義密通の嫁をなぶり殺した」
浅右衛門は目を丸くした。
これは婆の怪異ではない。殺された嫁が婆を封じ込め、生人形に怪異をもたらしているに違いない。恐らく嫁は、死してなお婆を恨み、成仏させまいと生人形へ魂を縛り付けているのだろう。
「して、嫁は?この分では嫁も成仏していまい。どこへ埋めた」
浅右衛門は問うた。
「その嫁が成仏せねば、そなたもここを出られまい。嫁の呪縛から、そなたを救ってやろうぞ」
「……」
「嫁は、何処に埋まっておる?」
「……浄閑寺、豕(いのこ)塚」
「浄閑寺豕塚だな?」
「……成仏させてくだせえ。引導を渡してくだせえ」
鬼婆の生人形の両目から、一筋、血の涙が流れ落ちた。
「そちが嫁を殺したのは、いつだ?」
「……七日前」
「そちは死して浅いのか?」
「……御裁きが恐ろしゅうて、嫁を埋めた直後に首を縛りました」
やれやれと、浅右衛門は呟いた。
「助六。お頭にこのことを伝えてくれ。浄閑寺豕塚に元凶ありとな」
「へい」
「待っていろ。すぐに成仏させてやる」
浅右衛門はそう呟いて、本堂から出ていった。
浄閑寺は新吉原の遊女たちが投げ込まれる〈無縁寺〉である。吉原大門を左に折れて土手通りを真っすぐ進めば、この浄閑寺に行き当たる。
稀だが、吉原では遊女が己の身を憂い、自ら生命を断つ。客と心中をする者もいる。その死体処理を任されたのが、車善七である。車善七は江戸の非人社会を束ねる〈四人の非人頭〉のひとりとして、裏社会でもその名が知られていた。そんな彼も、浅草弾左衛門の前では子供同然なのだ。
「あっ旦那、先程はどうも」
車善七が大門から出てきた。また、遊女が死んだ。年期明けまで二十年、その歳月の長さに失望し、首を吊ったのだという。
「旦那は、何方へ」
「ああ、ちと浄閑寺へな」
「同じだ、御一緒しますぜ。道に慣れてるあっし等でも、どうにも夜道は、怖くていけねえや」
「投げ込みは、昼間でもいいんだろ」
「死体に一間を使うより、生きた女で稼ぎたいんだとさ」
「人間って、惨いな」
車善七の子分が三人係りで、遊女の棺桶を担いでいる。大八車を用ないのは、小回りが利くからである。それほど手早く片付けることを、善七の仕事は要求されていた。
さて。
吉原大門を左に折れて土手通りを真っすぐ進めば、すぐに浄閑寺に行き当たる。豕塚は、浄閑寺の一郭にあった。天保八年の吉原大火ののち、新吉原では防火のまじないとして、大門の脇に豚を飼うようになった。豚は十二支の末尾・亥を表し、五行思想では北に配置される。北の亥は水のシンボルで、すなわち防火のまじないなのである。この寺の豕塚は、吉原大火ののちに
(遊女の墓所も火災から守ろう)
という主旨から、死した豚の骸を埋めて建立されたものである。
ただし、こういう畜生塚は、いわゆる獣の浮遊霊を呼び寄せ、そこへ宿らせるとも云われる。そういう意味では、かなり厄介な塚だ。畜生と人の骸を同じくするのは、かなりの問題がある。低級な動物霊が成仏できぬ人間霊に憑依融合すれば、それは怨霊ではなく妖怪になるからだ。
(急がねば、いかんな……)
賑やかな大門は不夜城の如く闇のなかに煌々と輝き、その灯の下では、様々な人生が交差していた。この大門を、遊女は出ることは許されない。任期を終えて半病人として出ていくのか、骸と化して出ていくのか。そして、大半の遊女はこの大門を生きて出ることがない。
「さて、行こうか」
浅右衛門は車善七を促した。
大門から浄閑寺までは四半刻、彼らは提灯ひとつで夜道を急いだ。死体投込みのため、車善七は浄閑寺門前の手前で浅右衛門と別れた。山田浅右衛門はそのまま境内へと進んだ。
そのときである。
「ギャアア!」
悲鳴が、響いた。聞き覚えのある声……助六の声だ。
(まさか……!)
