
家族葬の費用はいくら?流れとマナーをわかりやすく解説
「親が亡くなったけど、葬儀費用っていくらするのかな?」
「なるべく少人数で、費用も安く切り上げたいけど・・・」
家族を亡くすと最後は優しい気持ちで見送りたいですよね。
一方で経済的な余裕や人間関係が理由となって、家族だけで済ませたい気持ちにもなります。
家族葬や小規模な葬儀は徐々に広がっており、選択肢も様々あります。
家族葬にした場合の費用や流れ・マナーなど、知りたいことを分かりやすくまとめました。
家族葬の費用はいくら?
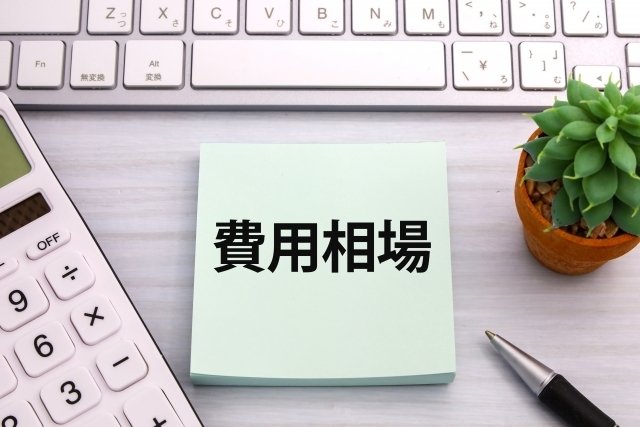
親族だけでの10人程度で行う家族葬の相場は100万円ほどです。
僧侶へのお布施や飲食代などにより150万円になる事もあります。
基本的な葬儀費用だけで収めようとすれば50万円程度まで下げることも可能です。
どのような家族葬にするのか、僧侶へのお布施はいくらにするのかにより変動します。
家族葬の基本料金の内訳
葬儀を行うので最低限の葬儀費用は必要になります。
安置費用
搬送費用
葬儀場の利用料
葬飾用品
火葬費用
葬儀進行費用
上記の費用は必要になり、さらに僧侶へのお布施・お車代、仏壇や位牌、お墓の費用は別途必要です。
葬儀をしないという選択肢
葬儀をしないという選択肢もあります。
法律では故人の葬儀は義務付けられておりません。
法律で決められているのは、故人が亡くなったことでの行政上の手続きと火葬だけです。
あとは関係者への連絡などです。
保険会社や契約関係の名義変更や解約を家族がしなければいけません。
ただし故人の遺体を放置しておくと、悪意がなくても「死体遺棄罪」に問われます。死体遺棄罪について(出典 WIKIBOOKS)
葬儀をしない場合、火葬費用だけになりますので市区町村によって差がありますが、8万円〜10万円で済ますことができます。
費用を抑えるポイント
故人への弔いの儀式ではありますが、家庭の経済状況で安く済ませたい場合はいくつかのポイントがあります。
生前予約での割引きがある葬儀社と契約しておく
葬儀のプランで祭壇や棺、葬飾品などのグレードを下げる
僧侶への依頼をやめる
葬儀社との相談や打ち合わせで相見積もりを取る事も有効的です。
保険や助成金の活用方法
葬祭費補助金制度という給付金制度があります。
加入している健康保険によって名称や給付金額に違いがあります。
社会保険、または共済組合に加入している場合
加入先が社会保険、または共済組合の場合は「埋葬費」または「埋葬料」が支給されます。
勤め先を通じて、葬儀の領収書や住民票・死亡診断書などが必要です。
被扶養者(配偶者や子供など)の死亡時にも支給されます。
金額はおよそ50,000円です。
国民健康保険に加入の場合
加入している本人が死亡した場合に、葬儀を執り行った喪主などに支払われる給付金です。
「葬祭費」という名目で支給されます。
申請は加入している国民保険の自治体に申請します。
申請時に必要なものは以下の通りです。
故人の保険証
葬儀の領収書
印鑑
振込先の口座を証明できるもの
申請者の本人確認書類(免許証・保険証など)
給付金額は自治体によって違いますが、ほとんどの場合50,000円です。
お坊さんへのお布施の目安は?

僧侶へのお布施等は特に決まってはいないですが、10万円〜30万円を見込んでおきましょう。
僧侶に依頼する内容は主に下記のような内容です。
葬儀全般での読経
戒名の授与
初七日などの法要
故人への葬儀ではありますが、無宗教や諸事情により僧侶なしで進めることは可能です。
ただしお寺、特に菩提寺のお墓に納骨する場合は僧侶に依頼する方がよいでしょう。
遺族が勝手に戒名の作成や納骨をすることはできませんので注意が必要です。
家族葬のできる葬儀屋
葬儀を執り行う葬儀屋さんは、大きなメモリアルホールを持つ葬儀会社でも電話で相談すれば、対応してくれることも多いです。
近年は特に家族葬が増えているので、ほとんどの葬儀会社で執り行ってもらえます。
複数の葬儀社に生前に連絡などして見積もりを取って比較しておくのもいいでしょう。
家族葬の流れ

家族が亡くなった場合、悲しみに暮れることとなるでしょうが、特に家族葬の場合は家族がメインで動くことが多くなります。
混乱のない葬儀でお見送りするためにも、生前に一度確認しておくことが大事です。
死亡の確認と葬儀の準備
家族が亡くなった時は、他の家族への連絡と並行して葬儀に向けた行動が急がれます。
死亡の確認
死亡診断書の受け取り
遺体の搬送と安置
葬儀社の手配
死亡の確認
家族が亡くなった場合は必ず家族による、ご遺体と死亡の確認が必要です。
特に不慮の事故で亡くなった場合は必ず確認する必要があります。
亡くなった直後に故人を見るのは精神的につらいでしょうが、様々な問題を抑えるためにも家族・親族の誰かが確認しなければなりません。
死亡診断書の受け取り
入院や搬送先の病院の臨終に立ち会った医師や遺体の検死を確認した医師に書いてもらいます。
葬儀社への手配や給付金の申請の時に必要です。
ほとんどの場合は、遺族の気持ちを察して病院側から案内されて受け取ることが多いです。
遺体の搬送と安置
亡くなった時は葬儀まで病院の霊安室に安置することが多いです。
葬儀場が遠く離れている場合はすぐに搬送して、葬儀場で安置することもあります。
葬儀社または病院と連絡をして搬送の手配が必要です。
注意しなければいけないのは、法律上、故人の遺体は24時間以内の火葬は禁止されていることです。
「墓地、埋火葬に関する法律」はこちら
葬儀社の手配
遺体の安置や葬儀の日程を決めるために自分たちから葬儀社へ依頼します。
生前予約している場合は、事前に渡されたガイドに従って行動しましょう。
不慮の事故などの場合は想定外なので慌ててしまいますが、ネットで「家族葬 〇〇市 安い」などで検索するとよいと思います。
検索結果の中から金銭的、または内容で判断されるのがいいです。
お通夜から告別式までの一般的な流れ
病院から葬儀場へ搬送されるとすぐに葬儀社により、葬儀の準備が始まります。
大きな葬儀の場合は関係者への連絡などで、故人の仕事関係、友人などを調べるのに時間を要しますが、家族葬の場合は家族・親戚だけになるので連絡はすぐにできると思います。
納棺
棺に納める前に故人の身支度をします。
ほとんどの場合は葬儀社が行いますが、家族も立ち会うことができます。
直接触れる機会なので最後の時間を共有しましょう。
最後に葬儀社によって故人は棺に納められます。
お通夜
納棺後にお通夜が始まります。
僧侶による読経が始まり、途中から僧侶の指示があればお焼香を始めます。
お焼香は喪主から始め、その後は故人の配偶者、親、兄弟、子供世代、孫世代の順で行うのが一般的です。
僧侶による勤行が終われば、葬儀社のスタッフから次の葬儀の打ち合わせがあります。
スタッフの誘導にてお通夜が終わり、葬式の時間までの休息と判断してください。
お焼香

お焼香は宗派によって違いがありますが、間違えたからと言って特に問題はありません。
僧侶・遺族に一礼をする
焼香台の前に行き遺影に一礼する
数珠を左手に持つ
右手の三指(親指・人差し指・中指)で抹香をつまんで目の高さまで持ち上げる
指で抹香をすりつぶすようにしながら、香炉の中央に置く
真言宗は3回、他宗は1回でも問題ありません
遺影に合掌後、下がって遺族に一礼する
抹香を高い位置から落とすような行為はマナー上、良くありません。
きちんと香炉の中に置くように入れましょう。
葬式
お葬式は翌日に行われることが一般的です。
流れはお通夜と同じで、僧侶による読経、焼香を行います。
家族葬なので弔問者は来ないと思いますが、もしどこかから聞きつけて弔問に訪れた方に対しては丁重に受け入れましょう。
弔問者からのお言葉には、特に難しい返事は必要ありません。
いつも通りの言葉で、弔問してくださったことに感謝をお伝えすればよいです。
香典をいただいた場合は、後日香典返しをお持ちしましょう。
告別式
お葬式の後、喪主のご挨拶や追悼のお時間を設けます。
故人に触れる最後の機会です。
棺にお花などを入れます。
お酒やたばこ、お札を入れる方もいますが、燃えにくい物を入れるのは控えておきましょう。
追悼文を読まれる方がいましたら、静聴します。
出棺
告別式の最後に棺の蓋を閉めて遺族により「釘打ち」をします。
その後で火葬場へ向かいます。
棺は可能な限り親族で持ちましょう。
故人に関係の強かった人から故人の頭部付近を持ちます。
分からない場合や人が足りない時は葬儀社のスタッフが手伝ってくれます。
棺を乗せた霊柩車には位牌を持った喪主が乗ることが一般的です。
遺影は他の参列者とともにマイクロバスや自家用車に乗る人の中で、喪主の次に故人に近い人物が持つのがよいでしょう。
火葬
火葬場へ着くと火葬場の担当者の指示で火葬場内へ運びます。
ここで棺のお顔部分から見えるお顔が、本当に最後の顔合わせになります。
火葬が始まると終わるまで控室で待ちます。
火葬中の撮影などはマナー上よくないのでやめましょう。
骨上げ・収骨
火葬後に故人様の遺骨を骨壺に入れます。
骨上げには作法があります。
喪主が遺骨の頭付近に立つ
2人1組で行う
長さの違う竹の箸と木箸を使う
骨上げは喪主、遺族、親族などお焼香と同じ順でよいでしょう
骨は足の部分から順に骨ツボに入れていきます
最後に故人と最も縁の深かった人物が喉仏を納めます
初めてだったり緊張したりしますが、係の人が案内してくれるので安心できます。
帰路
骨上げ後は骨壺を火葬場の係の人が持ちやすいように包んでくれます。
遺骨は喪主が持ち、他の遺族が位牌や遺影を胸の前に持って帰ります。
お骨を家に持ち帰ったら祭壇に安置してお線香をあげます。
その後僧侶によって「環骨法要」として読経と焼香を順に行いお葬式は終わりです。
納骨
四十九日法要の後、お墓や納骨堂に骨壺を納骨します。
四十九日でなくても関係者が集まれる日でも問題ありません。
お墓がない場合や遺骨を管理できない場合は、引き取りを拒否することもできます。
火葬場で引き取ってもらう場合は0~3万円程度が目安です。
海洋散骨などは自治体の許可を取れば、自分で遺骨を粉砕してばら撒けば無料で済みます。
ただし、家族の遺骨を粉砕するので精神的に耐えられないことが多いです。
また、散骨するためには遺骨を2㎜以下のパウダー状にしなければなりません。
遺骨が2㎜以上の大きさの場合は、「死体遺棄罪」の問われます。
死体遺棄罪について(出典 WIKIBOOKS)
葬儀社に依頼すれば粉砕、散骨で3万円~10万円が目安です。
遺族のマナー

家族葬の場合は近親者だけになりますので、特に厳格に服装に気を付けることはしなくても問題ありません。
しかし喪主の方をはじめ、ある程度の節度は必要です。
家族だけとはいえ弔いの席ですので最低限のモラルを知っておきましょう。
服装
正喪服としては紋付き袴やモーニングスーツがありますが、家族葬では費用の点から見ても正喪服でなくても問題はありません。
喪主の方であれば準喪服と呼ばれる黒のスーツとネクタイに白いワイシャツでよいでしょう。
生地に光沢や柄がない方が望ましいです。
タイピンなども外しておきましょう。
女性の場合もフォーマルスーツで飾りもパールなどのシックな物がいいです。
お化粧も薄化粧にしておきましょう。
他の遺族や親族は自分たちで決めていいですが、なるべく落ち着いた色柄の生地のスーツ、ネクタイがおすすめです。
濃紺や濃いグレーなどでいいと思います。
髪型
故人との思い出があるかもしれませんが、基本的には清潔感のある髪型にしてファッション性は減らしておくのがいいでしょう。
女性も髪を束ねて垂らしておくなど、派手にならないような注意が必要です。
髪の毛が極端に明るい茶髪の場合はウイッグを付けるか、カラースプレーなどで一時的に黒くする方法があります。
家族だけの場合は特に問題はないでしょう。
鞄
男性はなるべく軽装で鞄はない方が望ましいです。
女性は布製で落ち着いた柄の鞄にしましょう。
皮のバッグ、特にワニ皮、ヘビ柄などは僧侶による儀式のために避ける必要があります。
色は黒か黒に近い紺、グレーがいいでしょう。
その他
指輪やピアスなどの装飾品は外しましょう。
女性の場合も真珠のネックレス以外の装飾はしない方が無難です。
ネイルもなるべく何も付けずに、口紅もシックな色にしましょう。
男性は夏場でもスーツの上着付きが基本になります。
女性の場合はノースリーブなどは控えた方がいいです。
出棺の時には上着を着る習慣があるためです。
これも家族葬では許されるかもしれませんが、葬儀の習慣として守ることをおすすめします。
葬儀になくてもいいものは?

家族葬にしようとする場合、金額だけでなく内容も削減できるものはないか気になりますよね。
故人様への思いを大切にするために必要な葬儀や法要、または付随する物は絶対に必要なのか見てみましょう。
無くても良い物であれば費用を抑えることができます。
戒名
戒名とは極楽浄土での故人の名前です。
仏教の世界の決まり事です。
法律的にはつけなくても問題はありません。
しかし葬儀にて戒名なしでは僧侶の読経以外の勤行はできなくなるでしょう。
また菩提寺のお墓に納骨されるときに菩提寺から拒否される可能性もあります。
戒名をお寺で付けてもらうには目安として10万円〜100万円必要です。
納骨
納骨も戒名と同じく法律的にはしなくても問題ありません。
実際に骨壺を家で保管している家庭もあります。
納骨をしない理由にはいくつかの理由があるようです。
お墓がない
自分の身近に置いておきたい
納骨のタイミングが分からない
お金がない
自宅で管理する分には問題ないですが、供養はきちんとした方がいいでしょう。
遺骨を納骨しない方法もあります。
散骨(遺骨を砕いて海などの自然界に撒く)
火葬の後、遺骨を受け取らないで火葬場に処理してもらう
納骨堂に納める(共同の施設)
ただし、自宅などで管理していた遺骨をごみとして廃棄すると罪に問われます。
死体遺棄罪について(出典 WIKIBOOKS)
お墓
お墓は故人や先祖との繋がりの証であり、中には故人の骨があるので家族内の歴史的な意味を持ちます。
しかし必ず持たなければならないということはありません。
墓石や墓地の区画などで100万円以上の費用が掛かり、管理費も必要です。
将来的にお墓を管理する子や孫の負担をなくすために、お墓を作らない人も増えています。
また墓を移動させたり、処分したりする場合にも様々な手続きがあります。
費用だけでも10万円ほど必要で、手続きにはお寺だけでなく行政にも届け出が必要です。
費用軽減だけでなく将来的な展望を含めて家族や親戚で考える必要があります。
家族葬のメリット

家族葬は一般的な葬儀と比較して主に4つのメリットがあります。
費用を少なく済ませられる
参列者が近親者だけになるので気遣いが減る
葬儀内容に見栄を張る必要がなくなる
故人の希望に合わせやすい
葬儀は婚礼のようにミスがあっても笑って済ませることが難しいですが、弔問客なしで気兼ねなくお行えるのが最大のメリットです。
家族葬のデメリット

近親者だけで行う葬儀にはデメリットも存在します。
葬儀に呼ばない人への対応
故人への思い入れのあった人への対応
香典などがない分、出費は自分たちで用意する必要がある
信仰心として周囲から非難される可能性がある
故人の仕事先や友人への連絡はご理解いただけるような配慮が必要です。
また葬儀後に仕事関係者や友人による仏壇やお墓参りへの対応が必要になる事があります。
故人の友人や仕事関係者などには、葬儀に参列して一目見たかったという人もいます。
なぜ葬儀に呼ばなかったのかと問い詰められることもあります。
葬儀前に故人の人間関係を調べて、家族葬を行う意向を伝えましょう。
また葬儀後に弔問希望者が分かった場合は、家族葬で済ましたことと連絡が遅くなったことのお詫び文として連絡しましょう。
まとめ

家族葬の最大のメリットは料金削減とその後の維持管理の簡素化です。
しかしそれは故人や葬儀に呼ばれなかった人への想いを尊重して行わなければなりません。
また葬儀後の遺骨や遺影、位牌、お墓などの管理も含めて無理できないのであれば周囲も賛同してくれるでしょう。
一般的な葬儀よりも簡素化し、和やかに進められるメリットを理解してのお別れであれば故人もよい人生だったと偲ばれることでしょう。
(執筆者 大田恵三)
